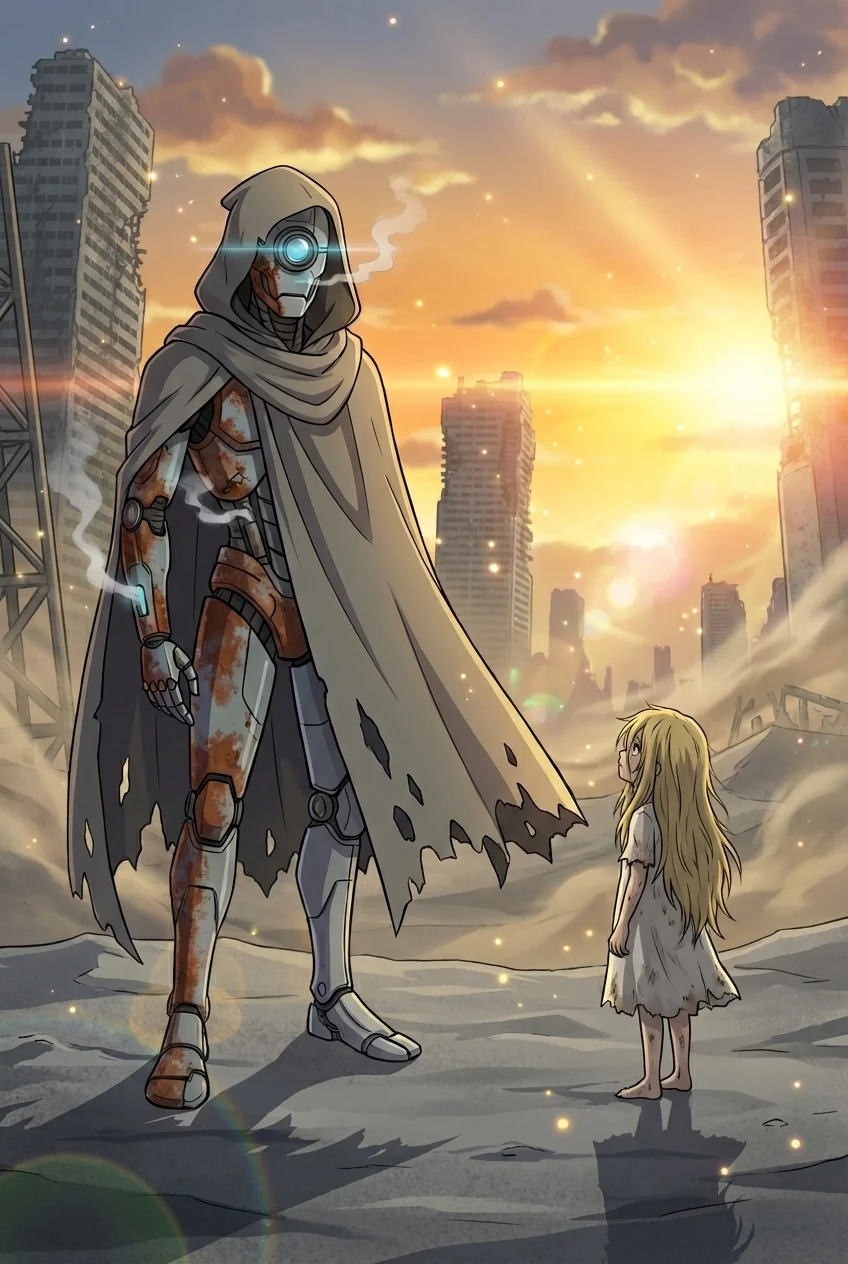第一章 色褪せた港の歌
霧雨が、カイの外套の肩を静かに濡らしていた。
彼が立つ港町「アズール」は、今まさに周期的な「存在希薄化期間(フェード期間)」の只中にあった。石畳は半ば透け、向こう側の景色がゆらりと滲んで見える。建物の輪郭は曖昧で、まるで水彩画が水に溶けていく過程を、スローモーションで見ているかのようだ。触れようと手を伸ばせば、確かな抵抗はなく、冷たい霞を掴むような心許なさが残る。
カイの耳には、この色褪せた風景とは不釣り合いなほど鮮やかな音が届いていた。
──ああ、光よ、届け。海の向こう、あの人の元へ。
それは喜びと、切ないほどの希望に満ちた男の声。幻聴だ。カイは、今はもう存在しない場所の「感情の残響」を聞くことができる。この港の沖合、百年前に大津波で沈んだという「旧市街の灯台」から発せられる、最後の灯台守の感情だった。その純粋な祈りがカイの鼓膜を震わせ、胸の奥を温かく締め付ける。彼は一時的に、その見ず知らずの灯台守と感情を共有する。
ふと、カイは自身の手のひらを見下ろした。指先が、街の景色と同じように透け始めている。彼自身もまた、フェード期間に入りやすい体質だった。存在が希薄になる感覚は、冷たい水に全身をゆっくりと沈められていくのに似ている。記憶も、自己も、世界の縁から滑り落ちていくような、静かな恐怖。
彼はポケットから、古びた木枠の小さな砂時計を取り出した。中には白銀の砂が封じられている。彼の指先が透けるにつれて、その砂時計は内側からぼんやりと青白い光を放ち始めた。失われた場所の声を拾うための、彼の唯一の道標。「無音の砂時計」だった。
第二章 無音の砂時計と管理者
世界のどこを探してもフェードすることのない場所が、いくつか存在する。カイが向かった「アルカの書庫」もその一つだった。天を突くようにそびえる白亜の塔は、周囲の希薄化した世界の中で、絶対的な存在感を放っていた。
重厚な樫の扉を開けると、古い紙とインクの匂いが彼を迎えた。無限に続くかのような書架には、古今東西の記録が眠っている。カイは、フェード現象の起源について何か手がかりがないか探しに来たのだ。
「あなたですね。失われた場所の声を聞く、という方は」
凛とした声に振り返ると、そこに一人の女性が立っていた。黒いドレスに身を包み、銀色の髪をきつく結い上げた、氷の人形のように美しい人だった。彼女はシズクと名乗った。
「我々は、あなたのような方を捜していました」
「我々…?」
「この世界の秩序を維持する者。『記憶の管理者』です」
シズクの瞳は、カイの能力も、彼が持つ砂時計のことも全て見透かしているようだった。彼女は静かな口調で語り始める。カイの聞く「残響」は、世界の調和を乱す不安定なノイズであり、彼自身がその発生源になりかねない危険な存在なのだと。
「その砂時計は、あなたを過去の幻影に縛り付ける呪いの道具。我々に預けていただけませんか。そうすれば、あなたの存在も安定するでしょう」
彼女の言葉は理路整然としていたが、カイの心には冷たい不信感が芽生えた。この人は、何も感じていない。彼が聞く声の温かさも、その奥にある切なさも。
第三章 褪せる記憶、灯る光
カイのアパートの大家である老婆が、深いフェード期間に入ったのは、その数日後のことだった。いつも陽気にお茶を勧めてくれた彼女の姿は、陽炎のように揺らめき、声も遠くなった。カイは焦燥に駆られた。彼女と交わした言葉、彼女が焼いてくれたクッキーの味、その記憶そのものが、自分の内側から砂のようにこぼれ落ちていく。
存在が忘れ去られるとは、こういうことなのか。
カイ自身のフェードも急速に進んでいた。半透明になった腕が震える。このままでは、老婆も、自分も、誰の記憶にも残らずに消えてしまう。彼はたまらず、シズクが「呪い」と呼んだ無音の砂時計を強く握りしめた。
その瞬間、砂時計がこれまでになく強い光を放った。そして、新たな残響が彼の脳髄を貫いた。
──許さない。我らの森を奪った、その傲慢を。
それは燃え盛るような怒り。何世紀も前に焼き払われたという「忘れられた大森林」の、木々やそこに生きた生命すべての絶叫だった。肌が粟立ち、呼吸が浅くなる。だが、その激しい感情の奔流は、カイの薄れかけていた自己の輪郭を、逆説的に強く意識させた。
彼は決意した。シズクの言葉の裏にある真実を、この世界の歪みの根源を、自らの手で探り当てなければならない。
第四章 アルカの書庫、偽りの年代記
再び訪れた「アルカの書庫」で、シズクはカイを待っていた。彼女は何も言わず、彼を禁断の領域である書庫の最深部へと導いた。そこは、冷たい空気に満たされた巨大な円形の広間だった。壁一面に、水晶のような板が埋め込まれ、その一つ一つに淡い光が明滅していた。
「これが、この世界の真実です」
シズクが壁に触れると、水晶板に様々な情景が映し出された。蒸気機関で空を飛ぶ都市、魔法が文明の中心だった王国、そして、カイが聞いた灯台のある港町が津波に飲まれず、さらに百年繁栄を続けた歴史。それらは全て、起こり得たかもしれない「可能性の物語」だった。
「フェード期間は、自然現象ではありません」
シズクの告白は、カイの世界を根底から覆した。
「あまりに多くの可能性が分岐し、互いに矛盾し、争いを生んだ結果、世界そのものが崩壊しかけたのです。我々『管理者』は、その混沌を収拾するために、無数の歴史を剪定し、安定した唯一の物語へと世界を再構築するシステムを作り上げました。それがフェード期間の正体です」
フェードしない場所は、管理者たちが定めた「正史」を固定するための楔(アンカー)。そして、カイが聞く残響は、彼らによって切り捨てられ、消された無数の「もしも」の歴史、その分岐点で生まれた最も強い感情の断末魔だったのだ。
第五章 語り部の岐路
「あなたの力は、消え去ったはずのノイズを拾い上げる。それは、完成間近の物語に不協和音を投げ込む行為に他なりません」
シズクはカイの目を見据え、最後の提案を持ちかけた。
「あなたの力で、最後の残響を鎮めてください。そうすれば、この世界は矛盾のない完全な物語として完成し、フェード現象も終わりを迎える。あなた自身の存在も、もう二度と揺らぐことはありません」
安定した、一つの未来。だが、それは無数の犠牲の上に成り立つ、都合の良い歴史。カイは激しく葛藤した。消された物語にも、喜びや愛があったはずだ。それを無かったことにしていいのか。
その迷いが、彼の存在をさらに希薄にした。体がほとんど見えなくなり、意識が遠のいていく。消滅の恐怖が彼を襲う。
彼は無意識のうちに、震える手で「無音の砂時計」を逆さにした。
白銀の砂が、静かに、しかし確かな速度で落ちていく。シズクが息を呑むのが、遠くに感じられた。
砂が、全て落ちきった。
第六章 沈んだ灯台の追体験
カイの意識は、肉体を離れ、時を遡った。
彼は百年前の港町、嵐が吹き荒れる夜の灯台の最上階に「いた」。いや、彼が灯台守そのものになっていた。窓の外では荒れ狂う波が街を飲み込もうとしている。だが、彼の心は不思議なほど穏やかだった。彼は、この光が港に残した妻と幼い息子への最後の道標になると信じていた。
「ああ、光よ、届け。海の向こう、あの人の元へ」
それは絶望の中の祈りではなく、未来へ託す、純粋で絶対的な愛の光だった。
津波が灯台を飲み込む瞬間、彼は愛する家族の顔を思い浮かべ、微笑んでいた。
その圧倒的な感情の追体験の中で、カイは全てを悟った。
自分は、あの時、灯台守が未来を託した幼い息子だった。本来なら、母と共にあの港で波に飲まれ、物語から退場するはずの存在。だが、管理者の歴史剪定システムの歪みが、消えるはずだった彼を「別の物語の語り部」としてこの世界に弾き出してしまったのだ。彼の能力は、同じように消されていった無数の物語たちの声を聞くためのものだった。
意識が、急速に現在へと引き戻される。目の前には、彼の選択を待つシズクと、今は光を失い、ただのガラスと木片に戻った砂時計があった。彼の体は、ほとんど完全に透明になっていた。
第七章 残響の夜明け
「ありがとう」
カイは、目の前の管理者に静かに微笑みかけた。彼の声は、風の音のようにか細かった。
「でも、物語は、誰か一人が書くものじゃない」
彼はその透けた手で、輝きを失った砂時計をそっと床に置いた。
それは何かの合図だったのかもしれない。
「たとえそれが不確かで、悲しい結末を孕んでいても……そこに生きた人々の声は、消えちゃいけないんだ」
カイの言葉が響き終わると同時だった。
世界中から、声が溢れ出した。アルカの書庫を震わせ、空気を揺さぶり、カイが今まで聞いてきた何百、何千倍もの感情の残響が、一斉に世界に解き放たれたのだ。それは焼き払われた森の怒り、沈んだ街の愛、空飛ぶ都市の希望、滅びた王国の哀しみ。無数の失われた可能性が、混沌のままに、しかし力強く奏で始めた新しい世界の交響曲。
悲鳴か、あるいは産声か。シズクの整った顔が、初めて驚愕に凍りついた。
その壮大な音の奔流の中で、カイの体は最後の輪郭を失い、完全に光の中へ溶けていった。
彼がいた場所には、もう誰もいない。
ただ、夜明けの光が差し込む床に、微かな温もりと、全ての始まりを告げるような、新しい風が吹き抜けていくだけだった。
世界がこれからどんな物語を紡いでいくのか。その答えは、まだ誰にも分からない。