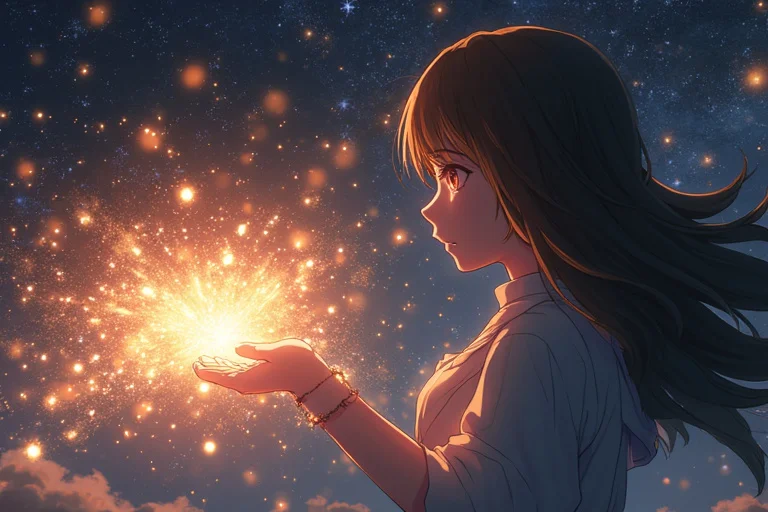第一章 記憶の香水師
僕の仕事は、いわば調香師だ。ただし、僕が扱うのは花や香木ではない。この街、クリプトシティを構成する無数の「情報結晶」から、未読のまま眠る感情の残滓を嗅ぎ分け、それを「記憶の香水」として掬い取ること。それが僕、カイの生業だった。
クリプトシティの街並みは、決して昨日と同じ姿をとどめない。世界中から送信され、誰にも開かれなかった電子メッセージが、ここでは物理的な結晶となって大地から生まれ、壁となり、塔を築く。誰かがメッセージを開封すれば、その結晶は音もなく崩壊し、新たな道や広場が生まれる。人々は、さながら流動するサンゴ礁に住まう魚のように、この絶え間ない変化に適応して生きていた。
僕の鼻は、この街では少しばかり特別だった。結晶に込められた送信者の想いを、「匂い」として感じ取れるのだ。十年前に送られた初恋の告白は、熟れたベリーと朝霧が混じり合った甘酸っぱい香りを放つ。喧嘩別れしたままの友人への謝罪は、錆びた鉄と湿った紙の匂いがした。僕はそれらの匂いをガラスの小瓶――「感情のボトル」に集めては、過去を求める人々に届けていた。
だが、この数ヶ月、街は明らかに異常だった。成長速度が狂ったように加速し、新しく生まれる結晶壁が、古い街区を無慈悲に飲み込んでいく。そして何より不可解なのは、その元凶となっている新しい結晶が、ことごとく「無臭」であることだった。
その日も、依頼を受けて向かった馴染みの路地が、一夜にして巨大な乳白色の結晶壁に塞がれていた。僕は壁にそっと手を触れる。ひんやりと滑らかな感触。しかし、そこからは何の匂いもしなかった。喜びも、悲しみも、怒りさえも。まるで感情そのものが死に絶えたかのような、完全な沈黙。
背筋を冷たいものが走り抜ける。この無機質な沈黙が、やがて街のすべてを覆い尽くしてしまうのではないか。そんな得体の知れない恐怖が、僕の胸を締め付けた。腰に提げた空の「感情のボトル」が、カランと虚しい音を立てた。
第二章 無臭の迷宮
街の異常を解明するため、僕は「無臭の結晶」が最も密集している新興地区へと足を踏み入れた。そこは、僕が知るクリプトシティとは全くの別世界だった。
陽光を乱反射させ、常にどこかでキラキラと輝いていたはずの街並みは、ここでは光を鈍く吸収する乳白色の壁に置き換わっていた。結晶と結晶の隙間は狭く、まるで巨大な迷宮に迷い込んだようだ。何より奇妙なのは、音のなさだった。人々の話し声も、風が結晶の角を撫でる音も、すべてが分厚い壁に吸い込まれていくかのように静まり返っている。ここには、記憶のざわめきが存在しない。
僕は迷宮の奥深くへと進んだ。誰かが意図的に、何か巨大な感情を隠蔽しているのではないか。あるいは、感情を伴わないメッセージ――システム通知のような無機質な情報――が、何らかの理由で大量に結晶化しているのか。様々な仮説が頭をよぎるが、どれも確信には至らない。
壁に囲まれた小さな広場に出ると、数人の住民が途方に暮れた顔で座り込んでいた。
「また道が変わっちまった」
老人が一人、力なく呟く。
「昨日まで、ここから市場へ抜ける近道があったんだがね」
別の女性が、生まれたばかりの赤ん坊を抱きしめながら不安そうに空を見上げる。その視線の先では、天を突くように新しい結晶の塔が、今もなおゆっくりと成長を続けていた。
このままでは、街は自らの重みで崩壊する。人々は生活空間を失い、過去から切り離され、ただ変化に押し流されるだけになってしまう。僕は唇を噛みしめた。この沈黙の侵食を、止めなければならない。だが、匂いのない結晶の前では、僕の能力はあまりに無力だった。
第三章 ボトルが映すもの
自室に戻った僕は、無臭地区から持ち帰った結晶の欠片をテーブルに置いた。それは手のひらに収まるほどの大きさで、やはり何の匂いも発しない。僕は最後の望みをかけて、一番精巧な作りの「感情のボトル」を取り出した。透明なガラスの中で、捕集した光の粒子が渦を巻く特殊な小瓶だ。
ボトルを結晶の欠片にかざし、意識を集中する。
「匂いを、気配を、何でもいい、捕まえろ」
しかし、ボトルの中は静かなままだった。やはり無駄なのか。僕が諦めかけた、その時だった。
ふと、机の隅に置かれた古い写真立てが目に入った。そこには、幼い僕と、僕より少し年上の、よく似た笑顔の少女が写っている。姉の、エルマ。僕がこの能力に目覚めるきっかけとなった、遠い日の記憶。彼女の笑顔を思い出した瞬間――テーブルの上のボトルが、微かに、しかし確かに反応した。
「……え?」
ボトルの中に、インクを垂らしたような黒い染みが、じわりと広がっていく。それは僕が今まで見たことのない色だった。喜びの金色でも、悲しみの青でも、怒りの赤でもない。それは、光を一切拒絶するような、底なしの闇の色。染みはゆっくりと渦を巻き、まるで何かを必死に内側へ押し留めようとしているかのように、激しく蠢いていた。
脳天を殴られたような衝撃が走る。
これは、送信者の感情じゃない。
僕はずっと勘違いしていた。無臭の結晶は、送り手の感情が「無い」のではない。これは……これは、受け取る側の「強い拒絶」の感情だ。見たくない、知りたくない、開きたくない。その硬い意志が、メッセージ本来の匂いを完全に封じ込め、自らが結晶を形成していたのだ。
街を歪めているのは、未読のメッセージそのものではない。メッセージから目を背け続ける、誰かの「心」だったのだ。そして、ボトルが僕の記憶に反応したということは……。
ぞっとするような予感が、僕の全身を貫いた。
第四章 開封
僕は走り出した。向かう先は、クリプトシティの中心。街が生まれた時からそこにあると言われる、最も巨大で、最も頑強な結晶の塔、「始まりの尖塔」だ。誰もがその存在を知りながら、誰もその正体を知らない、街の象徴。僕は、幼い頃からずっと、無意識にあの場所を避けて生きてきた。
尖塔の麓にたどり着く。乳白色の巨大な結晶は、天を突き刺すように聳え立ち、その表面は氷のように冷たく滑らかだった。僕は震える手を伸ばし、その壁に触れた。
瞬間、忘却の底に沈めていた記憶が、奔流となって蘇る。
両親が乗った乗り物の事故。けたたましいサイレンの音。大人たちのひそひそ話。そして、病院の白いベッドで、か細い呼吸を繰り返していた姉のエルマ。僕は、ただただ怖かった。現実を知ることが、あまりにも恐ろしかった。
数日後、僕の元に一通のメッセージが届いた。エルマからだった。でも僕はそれを見ることができなかった。開けば、きっと、耐えられないほどの悲しみが記されている。永遠の別れが、そこにある。だから僕は拒んだ。「見ない」。そう強く念じ、意識の蓋を閉じた。それ以来、僕はそのメッセージの存在すら忘れていた。
目の前の巨大な結晶の表面に、光の粒子が揺らめき、微かに文字が浮かび上がる。
『カイへ。エルマより』
ああ、そうだ。この街の異常な成長は、他の誰のせいでもない。この巨大な拒絶の塊は、僕自身が生み出したものだったのだ。僕の恐怖が、僕の悲しみが、この街を沈黙の迷宮に変えてしまった。
僕は目を閉じ、深呼吸する。もう、逃げない。
「開くよ、エルマ」
僕が心の中でそう呟くと、巨大な尖塔は内側から眩い光を放ち始めた。ゴウ、と地響きのような音がして、結晶の表面に無数の亀裂が走る。それは破壊ではなかった。硬く閉ざされた蕾が、長い時を経て花開くような、荘厳な解放だった。
光が収まった時、尖塔のあった場所には、暖かな光に満ちた広大な円形の広場が生まれていた。街を圧迫していた重苦しい沈黙は消え去り、心地よい風が吹き抜けていく。そして、僕の鼻腔を、今まで嗅いだことのない、優しくも切ない香りが満たした。
それは、雨上がりの土の匂いに混じる、小さな白い花の香り。深い悲しみの奥底に、確かに残されていた、僕への揺るぎない愛情の香りだった。
エルマのメッセージは、絶望だけを綴ったものではなかったのだ。
僕はその場に膝から崩れ落ち、初めてその香りを胸いっぱいに吸い込んだ。涙が、後から後から溢れて止まらなかった。未読だった僕の心に、十数年分の姉の想いが、ようやく届いた。
生まれ変わった街の空は、どこまでも青く澄み渡っていた。