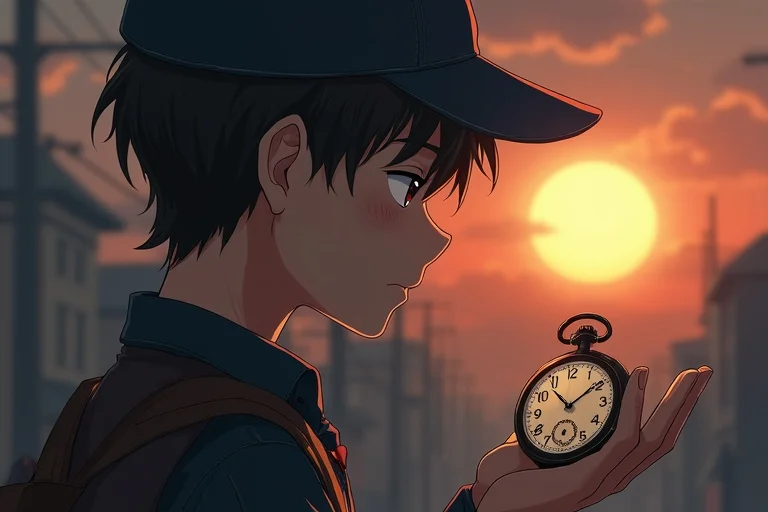第一章 色褪せた絵本
カイの瞳には、世界が常に一冊の絵本として映っていた。それは比喩ではない。彼が出会う全ての存在の頭上には、その生涯を締めくくる『最後の物語』が、数ページの簡素な絵本となって浮かんで見えるのだ。
土埃と鉄錆の匂いが混じる風が、瓦礫の街を吹き抜ける。カイは、痩せこけた兵士の横を通り過ぎた。兵士の頭上には、赤黒く塗りたくられた絵本が浮かぶ。最後のページは、名も知らぬ敵の刃に貫かれ、泥水に顔を沈める姿。その隣で施しを乞う老婆の絵本は、凍える夜に誰にも看取られず、息絶える場面で終わっていた。
変えることのできない、確定された結末。カイはただの傍観者だ。この呪いにも似た力は、彼の心を静かに、しかし確実に蝕んでいた。感情はとうに摩耗し、他者の悲劇を見ても、胸にさざ波ひとつ立たなくなって久しい。人々が血眼になって求める『概念石』の輝きも、彼にとっては新たな悲劇の絵本を生み出す、忌まわしい光でしかなかった。
『自由』を掲げる者は圧政者の首を刎ね、『正義』を謳う者は異教徒を火刑に処す。概念の力が強大であればあるほど、その結末の絵本は皮肉に満ちた鮮血の色を濃くした。
そんな色褪せた世界の中で、カイはひとつの小さな村にたどり着いた。そこで彼は、リラと名乗る少女に出会う。彼女は、砲弾の痕が生々しい広場の片隅で、瓦礫の隙間から芽吹いた一輪の白い花に、大事そうに水をやっていた。
カイは思わず息を呑んだ。
彼女の頭上に浮かぶ絵本は、これまで見てきたどの物語とも違っていた。淡い水彩で描かれたような、柔らかな光を放つ絵本。ページをめくる風の音すら聞こえそうなほど穏やかで、その最後のページには、成長した彼女が、満開の花畑の中で、あの最初の一輪を胸に抱きしめ、安らかに眠りにつく姿が描かれていた。悲しい結末には違いない。だが、そこには絶望も憎悪もなかった。ただ、静かで満ち足りた時間が流れていた。
「お兄さんも、このお花、綺麗だと思う?」
屈託のない声に、カイは我に返る。リラの瞳は、世界の汚濁を知らない湖のように澄んでいた。彼女の胸元で、小さな石の欠片が陽光を弾いてきらめく。おそらくは、砕け散った『希望』の概念石の、ほんの小さな名残だろう。
カイは、何年ぶりかに、自分の心が微かに震えるのを感じていた。この少女の穏やかな結末だけは、誰にも汚させたくない。その衝動が、灰色の世界の中で、唯一の色を持つ道標のように思えた。
第二章 鏡に映るもの
カイとリラの奇妙な旅が始まった。リラはカイの能力について何も知らなかったが、彼の瞳の奥に宿る深い孤独を感じ取っていた。彼女は鳥のさえずりを教え、道端の草花の名前を語り、焚き火の前で拙い歌を歌った。カイは黙ってそれを聞き、彼女の頭上に浮かぶ優しい絵本を時折盗み見ては、凍てついた胸の内に小さな灯火がともるのを感じていた。
ある雨の日、二人は苔むした古い遺跡で雨宿りをしていた。その奥で、カイは埃をかぶった手鏡を見つける。黒曜石の枠に銀の細工が施された、『概念の写し鏡』。古の時代、概念の本質を識るために使われたという伝説の品だ。
「わあ、綺麗な鏡! ねえ、何か映してみてもいい?」
リラが胸元の『希望』の欠片を手に取り、鏡にかざす。すると、鏡面が淡い光を放ち、いくつもの情景を映し出した。それは、絶望の淵から立ち上がる兵士の姿であり、不治の病に侵されながらも明日を夢見る子供の笑顔だった。しかし、光が強まるにつれ、鏡には無数の影が滲み始める。叶わなかった無数の願い、届かなかった祈り、希望の光の裏側で消えていった者たちの慟哭。
鏡面にかすかな亀裂が走り、リラの瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。
「……悲しい。希望って、こんなにたくさんの悲しみを乗り越えて、やっと光るものなのね」
カイはリラの肩をそっと抱いた。『希望』という概念が持つ、残酷なまでの重さを突きつけられた気がした。この世界にある全ての概念が、光と影を内包している。ならば、争いの連鎖を断ち切るには、概念そのものを消し去るしかないのではないか。
その考えは、伝説の『究極概念:終焉の無』へと彼を導いた。誰もその具現化を見たことがなく、カイの能力をもってしても、その結末はただの『空白のページ』としてしか見えない謎の存在。それは完全な破壊か、それとも真の平和か。
「リラ。俺は行くよ。『終焉の無』が具現化するという、『沈黙の谷』へ」
「……うん。カイが行くなら、私も行く」
リラの穏やかな結末を守るため。その一心で、カイは世界から全ての物語を消し去る覚悟を、静かに固め始めていた。
第三章 空白の頁の真実
『沈黙の谷』は、その名の通り、不気味なほど静かだった。かつてここで、最強の『憎悪』と『慈愛』の概念石が激突し、互いを霧散させたという。谷底には巨大なクリスタルの祭壇がそびえ立ち、周囲には様々な概念の力が渦巻いて、空気を奇妙に震わせていた。
静寂は、すぐに破られた。『終焉の無』の力を我が物にせんと、武装したいくつもの勢力が谷になだれ込んできたのだ。剣戟の音、怒号、そして概念石が放つ破壊の光が、静謐な谷を瞬く間に戦場へと変えた。
「やめて!」
リラの悲鳴が響く。カイは彼女を庇いながら、兵士たちの頭上に次々と浮かび上がる、おぞましい結末の絵本に歯を食いしばった。仲間だと思っていた男に背中を刺される騎士、暴走した自らの力に飲み込まれる魔術師。無数の悲劇が、彼の脳裏を焼き付けていく。
彼は奔走した。誰かを助けようとしたわけではない。ただ、これ以上、悲しい絵本が生まれるのを見たくなかった。その強い想いが引き金になったのか、カイの身体に異変が起きる。戦場で砕け散る概念石の力――『怒り』『絶望』『狂気』――そのエネルギーが、まるで磁石に吸い寄せられる砂鉄のように、彼の身体へと流れ込み始めたのだ。
「ぐっ……あああああっ!」
全身を焼かれるような激痛に、カイは膝をついた。頭が割れそうだ。無数の物語の断片が、彼の意識の中で濁流となって渦巻く。
その時、懐から『概念の写し鏡』が滑り落ちた。震える手でそれを拾い上げ、カイは鏡を自分自身へと向けた。知りたかった。『終焉の無』の正体を。そして、自分の頭上に浮かぶ、この忌まわしい『空白の絵本』の意味を。
鏡が映したのは、苦悶に顔を歪めるカイ自身の姿。
だが、その背後には、信じがたい光景が広がっていた。彼がこれまで見てきた、全ての『物語の結末』。兵士の無残な死も、老婆の孤独な最期も、そして、リラの穏やかな眠りさえもが、巨大な渦となってカイの背中に吸い込まれていく。
ピシリ、と音を立てて鏡面に大きなひびが入った。
カイは悟った。自分は傍観者などではなかった。出会う全ての存在の物語を、その結末を、無意識のうちに喰らい続けてきたのだ。あらゆる概念の争いのエネルギーを吸収し、終焉へと導くための器。
彼こそが、『終焉の無』を世界に具現させる、最後の媒体だったのだ。
頭上の空白の絵本は、まだ何も描かれていない、世界の最後のページそのものだった。
第四章 物語のいない世界
カイが真実を悟った瞬間、世界が応えた。『沈黙の谷』の祭壇が甲高い音を立てて砕け、世界中に存在する全ての概念石が、一斉に光の奔流となってカイを目指し始めた。空を裂き、地を走り、光の川が彼へと注ぎ込む。
「カイ!」
リラが叫ぶ。だが、その声すらも、絶対的な力の奔流の前では意味をなさなかった。
カイは、薄れゆく意識の中でリラを見た。彼女の頭上には、あの優しい水彩画の絵本が、まだ静かに浮かんでいる。この世界から物語が消えれば、彼女の穏やかな結末も、彼女が生きてきた証も、全てが『無』に帰す。それで、本当にいいのか。
一瞬の逡巡。だが、彼はすぐに首を振った。争いが続く世界では、彼女のあの結末すら、いつか血の色に塗り替えられてしまうかもしれない。ならば。
それが、カイが自らの意志で選んだ、最初で最後の『結末』だった。
彼は静かに目を閉じた。リラの名を心の中で呟きながら。
カイの身体は眩い光に包まれ、やがて粒子となって霧散していく。それと同時に、世界中の概念石は光を失い、ただの冷たい石ころへと変わった。人々は、振り上げていた剣を、何故持っていたのかも忘れたかのように、ぽとりと地面に落とす。憎しみも、愛も、喜びも、悲しみも、その概念を支えていた輝きが消え、人々の中から急速に色を失っていった。
世界は、完全な静寂に包まれた。それは、究極の『平和』だった。
リラは、カイが消えた場所をじっと見つめていた。頬を伝う涙の理由も、胸を締め付ける喪失感の意味も、もう彼女には分からなかった。ただ、風が吹き抜けていく。その風に、匂いも、音も、温度もなかった。
世界から、全ての『物語』が消え去った。
それは、魂の安寧か、それとも緩やかな死か。答えを知る者は、もうどこにもいない。かつてカイの頭上にあった空白の絵本。その最後のページが、誰にも読まれることなく、静かに閉じられた。