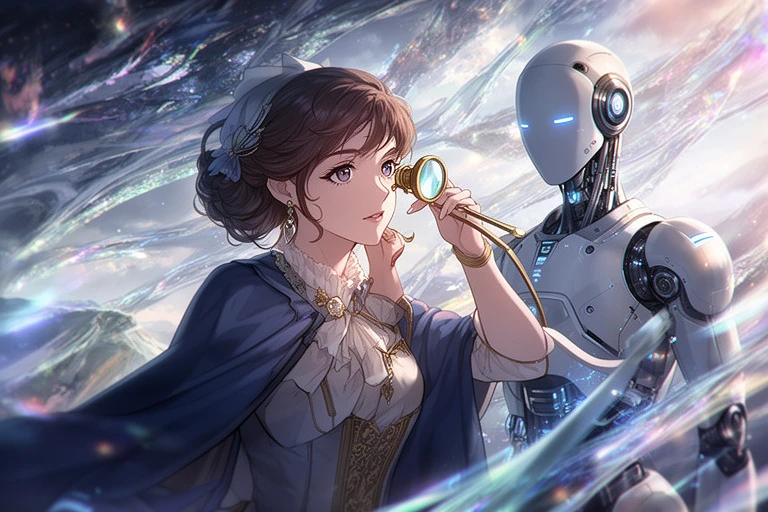第一章 灰色の点滅
エララにとって、窓の外の世界は壊れたストロボライトのように見えた。
明滅する光と闇。
人間たちが呼ぶ「昼」と「夜」は、彼女の網膜には高速で切り替わる灰色のグラデーションとしてしか映らない。
彼女は、古びた時計塔の最上階に住む修復師だ。
種族はエルフ。
樹齢三千年の大樹の如く、彼女の心臓は緩やかに、しかし重厚に時を刻んでいる。
「ごめんください」
鐘の音と共に、店内に色彩が飛び込んできた。
人間の少年だ。
エララが手元のルーペを置き、ゆっくりと瞬きをする間に、少年はカウンターの前まで移動していた。
彼らの動きは、いつもコマ送りのようにぎこちなく、そして速い。
「この時計、直せますか? 死んだじいちゃんの形見なんだ」
差し出されたのは、真鍮製の懐中時計。
歯車が悲鳴を上げ、ゼンマイが肋骨のように歪んでいる。
エララは長い指でそれに触れた。
金属の鼓動が聞こえる。
――痛い、痛い、と。
「直せるわ」
エララは答えた。
言葉を発するだけで、肺の中の空気が重く澱む。
「本当!? ありがとう、お姉さん!」
少年は満面の笑みを浮かべた。
その笑顔の残像が消える前に、彼は「じゃあ、頼んだよ!」と言い捨てて、疾風のように店を出て行った。
残されたエララは、ふぅ、と息を吐く。
紅茶を淹れよう。
湯気が立ち上るその優雅な揺らぎだけが、この部屋で唯一、彼女と同じ速度で動くものだった。
一口、琥珀色の液体を喉に通す。
芳醇な香りが鼻腔をくすぐる。
さて、仕事に取り掛かろうか。
彼女は懐中時計を分解し始めた。
極小のピンセットで、砂粒のようなネジを摘まむ。
この作業には、呼吸を止めるほどの集中力が必要だ。
窓の外で、灰色の点滅が繰り返されている。
彼女の意識は、金属の微細な溝、その深淵へと沈んでいった。
第二章 早回しの幻影
カラン、コロン。
再び鐘が鳴った。
エララは顔を上げた。
「やあ、エララさん。どう? 進んでる?」
そこに立っていたのは、背の高い青年だった。
精悍な顔つき。
骨格がしっかりとして、声も太い。
エララは首を傾げた。
(さっきの少年のお兄さんかしら?)
服装の趣味は似ている。
「もう少しよ。今、主要なテンプを調整しているところ」
彼女は微笑んだ。
ほんの少し、考え事をしながらネジを回していただけだ。
体感では、まだ数十分しか経っていない。
「はは、相変わらずのんびり屋だなあ」
青年は苦笑して、カウンターに肘をついた。
「俺さ、来月結婚するんだ」
「あら、おめでとう」
エララは作業の手を止めずに答える。
人間の流行り廃りは早い。
昨日まで半ズボンを履いていた子供が、今日は結婚の話をする。
そういう「遊び」なのだろうか。
「彼女に見せたいんだ、その時計。じいちゃんの自慢だったからさ」
「わかったわ。急ぐわね」
「頼むよ。……じゃあ、また来る」
青年は手を振って出て行った。
エララは再びルーペを覗き込む。
急ぐ、とは言ったものの、この歪んだヒゲゼンマイを修正するには、慎重な力加減が必要だ。
彼女は歌を口ずさんだ。
森の故郷に伝わる、星の巡りを称える歌。
一小節を歌い終える頃には、窓から差し込む光の角度が変わっていた。
美しい夕焼けだ。
いや、違う。
これは季節が変わる際に見える、太陽の傾きだ。
まあいい。
彼女はピンセットの先についた微量の油を拭き取った。
あと少し。
あと、ほんの少しの調整で、この時計は再び命を吹き返す。
心地よい微睡(まどろみ)のような集中。
それは、エルフにとっての至福の時間。
第三章 刹那の約束
カラン、コロン。
ドアベルの音が、どこか錆びついて聞こえた。
「……できましたか、エララさん」
掠れた、低い声。
エララは最後の裏蓋を閉め、パチン、という小気味よい音と共に顔を上げた。
「ええ、完璧よ。まるで新品のよう……に」
言葉が途切れた。
そこに立っていたのは、杖をついた老人だった。
白髪が薄く頭を覆い、顔には深い皺が刻まれている。
けれど、その瞳。
琥珀色に輝く、好奇心に満ちたその瞳だけは、見覚えがあった。
あの少年の瞳だ。
そして、あの青年の瞳だ。
「……レオ?」
エララは初めて、その顧客の名前を呼んだ。
老人は、くしゃりと顔を歪めて笑った。
「覚えていてくれましたか。私の名前」
「どうして……?」
エララは混乱した。
ついさっき、彼から預かったばかりだ。
お茶を飲み、歌を一曲歌い、ネジを締めた。
それだけの時間だったはずだ。
「待っていましたよ。ずっと」
老人は震える手で、カウンターの上に硬貨を並べた。
古びた、今はもう流通していない硬貨も混じっている。
「あなたの『急ぐ』を信じて、毎日ここへ通いました」
「毎日……?」
「ええ。あなたはいつも、石像のように固まって、真剣な顔で作業をしていましたから」
老人の言葉に、エララは戦慄した。
彼女が集中して「数分」と感じていた時間は、彼にとっての「数十年」だったのだ。
彼女が瞬きをする間に、彼は成長し、恋をし、老いていった。
窓の外の点滅。
あれはただの昼夜のサイクルではなかった。
彼女が作業に没頭している間に、幾千もの太陽が昇り、沈んでいったのだ。
「ごめんなさい……私、そんなつもりじゃ……」
エララの目から、涙が溢れた。
「謝らないでください」
老人は優しく言った。
「この店の中だけ、時間が止まっているようでした。あなたの変わらない美しを見るのが、私の人生の楽しみだったのです」
彼は懐中時計を受け取った。
耳に当て、チク、タク、という音を聞く。
「ああ……いい音だ。じいちゃんに聞かせたかった」
老人は満足げに頷き、そして、ゆっくりと床に崩れ落ちた。
最終章 永遠の秒針
「レオ!」
エララはカウンターを飛び越え、彼を抱き起した。
軽い。
枯れ木のように、軽い体。
「ありがとう……エララさん……」
老人の瞳から、光が消えていく。
それは、エルフの感覚でも捉えきれないほど、あまりにも早い消失だった。
ろうそくの火が吹き消されるように、命が消える。
エララの腕の中で、彼は動かなくなった。
手には、直ったばかりの懐中時計が握りしめられている。
チク、タク、チク、タク。
無慈悲なほど正確に、時計だけが時を刻み続けている。
「早すぎるわ……」
エララは彼の白髪を撫でた。
人間の命は、朝露のように儚い。
彼女がほんの少し微睡む間に、彼の一生は過ぎ去ってしまった。
ただ、時計を直すのを待つためだけに費やされた人生。
罪悪感と、名状しがたい愛おしさが胸を締め付ける。
彼女はレオの手から懐中時計を取り上げた。
そして、裏蓋を開け、細い指先でテンプを弾いた。
キチチチ……。
異音がして、秒針が止まる。
「これでいい」
彼女は呟いた。
「あなたの時間は、もう進まなくていい」
エララは動かなくなったレオの亡骸の横で、冷めた紅茶を一口飲んだ。
苦い。
窓の外では、相変わらず世界が目まぐるしい速度で点滅している。
けれど、この店の中だけは。
レオと彼女のいるこの空間だけは、永遠に止まっていた。
埃が舞う。
夕陽が射す。
それは一枚の絵画のように、静寂に満ちていた。
エララは目を閉じる。
次の瞬きを開ける頃には、この街の形すら変わっているかもしれない。
それでも、彼女はこの一瞬の記憶を、琥珀の中に閉じ込めるように抱きしめていた。
長い、長い、エルフの孤独な夜が始まる。