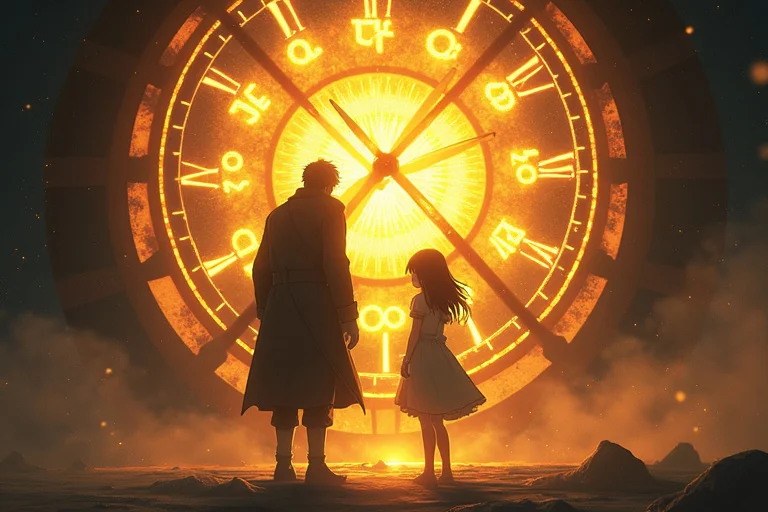第一章 廃棄場の鑑定士
リヒトの世界は、灰色がかった埃と、忘れ去られた感情の澱(おり)でできていた。彼が働く「記憶晶工房」の地下室は、街中から集められた廃棄記憶晶で満たされている。人々が眠るたびに、その日の記憶の一部は磨かれた宝石――記憶晶となって体外に現れる。幸福な記憶は虹色に、悲しい記憶は深い藍色に輝き、人々はそれを交換したり、飾ったり、あるいは不要な記憶として捨てたりする。
リヒトの仕事は、その「捨てられた」記憶晶を鑑定し、魔力炉で溶かして無に還すことだった。彼は生まれつき、奇妙な呪いとも祝福ともつかない能力を持っていた。持ち主が大切にしている記憶晶に触れても何も感じないが、持ち主自身が忘れたいと強く願い、放棄した記憶晶にだけは、触れることでその記憶を鮮明に追体験できるのだ。
「またか」
リヒトはピンセットで、泥に汚れた黒ずんだ結晶をつまみ上げた。嫉妬、裏切り、後悔。彼が日々目にするのは、人間の心の最も醜い部分ばかりだった。指先でそっと触れると、脳内に友を騙す男の卑しい笑い声と、良心の呵責が濁流のように流れ込んでくる。リヒトは顔をしかめ、それを無感情に「廃棄」の箱に放り込んだ。他人の心のゴミ処理。それが彼の日常であり、彼が人間という存在に冷めた視線を向ける理由だった。
そんなある日のことだ。いつものように廃棄記憶晶の山を仕分けていると、彼の指先に、ひときわ冷たく、そして清らかな感触が伝わった。それは、他の汚れた結晶とは明らかに異質だった。泥を拭うと、夜明け前の空の色を閉じ込めたような、深く澄んだ紫色の記憶晶が現れた。あまりに美しく、完璧なカットが施されている。こんな極上の記憶晶が、なぜ廃棄場に?
好奇心に抗えず、リヒトはそれに指を触れた。瞬間、彼の全身を甘く切ない旋律が駆け巡った。満月の光が降り注ぐ広場。大勢の聴衆がうっとりとステージを見上げている。その中心で歌っているのは、街一番の歌姫、エララだった。彼女の銀色の髪が月光にきらめき、その声は人々の心を震わせ、涙を誘う。それは、彼女が最も喝采を浴びた、栄光の夜の記憶だった。幸福そのものを結晶にしたような、眩いばかりの記憶。
だが、リヒトには分かった。この記憶晶は、確かに「捨てられた」ものだった。記憶の奥底から、言葉にならないほどの深い悲しみと、諦観の冷たさが染み出してくる。
なぜだ? なぜ、誰もが羨む歌姫エララは、こんなにも輝かしい記憶を、心のゴミ溜めに捨てたのだろうか。リヒトは紫色の記憶晶を握りしめた。その滑らかな表面の奥に、これまで彼が見たどんな醜い記憶よりも、深く暗い謎が潜んでいる気がしてならなかった。
第二章 歌姫の影
あの日以来、リヒトはエララのことが頭から離れなかった。昼休みになると、彼は工房を抜け出し、彼女が歌うという中央広場へ足を運んだ。噂に違わず、彼女の周りにはいつも人だかりができていた。
エララの歌声は、たしかに魔法のようだった。澄み渡る高音は春の陽光のように暖かく、人々を笑顔にする。かと思えば、物悲しいバラードは秋の霧雨のように聴く者の心に静かに沁み込み、知らず知らずのうちに涙を流させる。誰もが彼女の歌に魅了され、幸福な溜息をついていた。リヒトもまた、その歌声の力に圧倒された。
だが、彼は見てしまった。一曲歌い終え、喝采を浴びる彼女の笑顔の裏に、ほんの一瞬だけよぎる、深い疲労と哀しみの影を。それは、あの紫色の記憶晶から感じ取ったものと、同じ種類の感情だった。
「彼女は、何を隠しているんだ?」
リヒトは、鑑定と偽って街の宝飾店を巡り、エララの記憶晶について聞き込みを始めた。誰もが口を揃えて彼女の記憶晶を「至高の芸術品」と褒めそやす。彼女の記憶晶は市場にはほとんど出回らず、手に入れた者は幸運になれるとまで言われていた。だが、誰もその「捨てられた」記憶晶の存在は知らない。
ある雨の日、リヒトは広場の片隅で雨宿りをしているエララを見かけた。いつも彼女を取り巻いている人垣はなく、一人きりで俯く彼女は、まるで迷子の子供のように見えた。衝動的に、彼は声をかけた。
「……素晴らしい歌でした」
エララは驚いたように顔を上げた。その瞳は、ステージの上で見せる自信に満ちた輝きはなく、どこか怯えているようだった。「ありがとうございます」と彼女はか細い声で答えた。
「あなたの記憶晶は、きっと素晴らしい輝きなのでしょうね」リヒトは核心に触れる言葉を投げかけた。
その瞬間、エララの顔から血の気が引いた。彼女はリヒトを警戒するように一歩後ずさる。「記憶晶のことなど、あなたに何がわかるのですか」
「俺は、記憶晶鑑定士の助手で……」リヒトは慌てて身分を明かした。「ただ、あなたの歌を聴いていると、どんなに美しい記憶が結晶になるのかと、気になっただけで」
エララはリヒトの目をじっと見つめた。その瞳の奥で、激しい葛藤が渦巻いているのが見て取れた。しばらくの沈黙の後、彼女は小さな声で呟いた。「私の記憶は、美しくなどありません。……呪われているんです」それだけ言うと、彼女は雨の中に駆け出していった。
呪われている。その言葉が、リヒトの胸に重く突き刺さった。彼はポケットの中の紫色の記憶晶を握りしめる。この美しい結晶に秘められた呪いとは、一体何なのか。彼女の苦しみの正体を知りたい。いつの間にか、単なる好奇心は、彼女を理解したいという強い願いに変わっていた。他人の心に踏み込むことをあれほど嫌っていたはずの自分が、信じられなかった。
第三章 幸福の代償
数日後の夜更け、工房の扉を叩く音がした。リヒトが訝しげに扉を開けると、そこに立っていたのはずぶ濡れになったエララだった。彼女は震える手で、小さな布袋を差し出した。
「お願いです。私の記憶を、見てください」
袋の中身を手のひらに広げると、そこには色とりどりの、しかしどれもが溜息の出るほど美しい記憶晶が十数個、きらめいていた。そのどれもから、あの紫色の記憶晶と同じ、深い悲しみの気配がした。これら全てが「捨てられた」記憶だというのか。
リヒトは彼女を工房の地下室に招き入れた。埃っぽい、忘れられた記憶の墓場で、二人は向かい合って座る。
「なぜ、こんなに美しい記憶を捨てるんですか?」リヒトは静かに尋ねた。
エララは顔を覆い、嗚咽を漏らした。「あれは、私の記憶ではないのです」
絞り出すような彼女の告白は、リヒトの想像を絶するものだった。
エララの歌声には、特殊な力があった。それは、聴いた者の心から、最も幸福な記憶を一つ、吸い出してしまうという力。彼女が歌えば歌うほど、人々は一時的な幸福感に満たされるが、その代償として、自らの大切な思い出を一つ失うのだ。そして、吸い出された幸福な記憶は、夜、彼女が眠る間に、美しい記憶晶となって体外に排出される。
「私には、選べないのです。歌うことをやめれば力は暴走し、周りの人々の記憶を無差別に奪ってしまう。だから歌い続けるしかない。毎日、誰かの幸せを奪い、それを宝石として生み出し続けている……。私が捨てていたのは、私自身が見たくもない、他人から盗んだ幸福の残骸なんです」
彼女自身には、歌の力を得てからの幸福な記憶が、ほとんど残っていなかった。人々の笑顔を見るたびに、その笑顔の裏にある失われた記憶を思って罪悪感に苛まれる。彼女の記憶は、その痛みと苦しみだけで満たされていた。
リヒトは愕然とした。目の前にある美しい記憶晶は、誰かが大切にしていたはずの、恋人との初めての口づけや、子供が生まれた日の喜び、亡き母との温かい思い出だったのだ。彼がこれまで見てきた、人々が自ら捨てたかった醜い記憶とは、正反対のもの。人間の醜悪さの果てを見てきたと思っていた。だが、最も美しい結晶の中にこそ、最も残酷で、深い悲劇が隠されていた。
彼の価値観が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。記憶とは何だ。幸福とは、不幸とは何だ。彼は、言葉を失ったまま、手のひらの上で輝く小さな結晶を見つめていた。それは、誰かの失われた幸福であり、目の前の女性が一人で背負い続けてきた、途方もない重さの罪の証だった。
第四章 君のための物語
長い沈黙が、二人を包んでいた。リヒトはゆっくりと顔を上げ、エララの涙に濡れた瞳を見つめた。彼の胸を占めていたのは、驚きでも同情でもなく、静かで、しかし烈しい怒りだった。こんなにも優しい人間が、なぜこれほどの重荷を背負わなければならないのか。運命に対する、どうしようもない怒りだった。
そして、彼は気づいた。自分の能力の、本当の意味に。
「エララさん」リヒトは震える声で言った。「俺は、持ち主が捨てた記憶晶しか見ることができない。……あんたが捨てたその記憶は、本来の持ち主にとっては、決して捨てたくない大切な宝物だったはずだ。でも、あんたがそれを『自分のものじゃない、捨てたい』と強く願ったから……だから、俺には見えるんだ」
それは、呪いのような能力が、初めて誰かのために役立つと確信した瞬間だった。
リヒトは、テーブルに広げられた記憶晶の中から、ひときわ暖かなオレンジ色に輝く一つを手に取った。彼はそれにそっと指を触れ、目を閉じた。
「……夕暮れのパン屋だ。焼きたてのパンの匂いがする。小さな女の子が、初めてお使いを頼まれて、誇らしげにパンを抱えている。彼女の母親が、店の外で心配そうに、でもとても嬉しそうに彼女を見守っている……」
リヒトが見た光景を、訥々と語り始める。それは、彼が追体験している、誰かの失われた、ささやかで温かい幸福の記憶だった。エララは、息をのんでその言葉に耳を傾けていた。彼女の頬を、新しい涙が伝っていく。だが、それは先ほどまでの絶望の涙とは色が違っていた。
「俺に、手伝わせてほしい」リヒトは目を開け、真剣な眼差しで彼女に言った。「これから、君が捨ててしまう記憶を、俺が一つずつ見て、物語にして君に聞かせよう。君自身の記憶にはならなくても、君がその歌で、人々に与えた幸福の代償として生まれた物語だ。君が誰かの心を温めた証として、君の中に残るように」
それは、あまりにささやかな救いだったかもしれない。だが、エララにとっては、暗闇の中に差し込んだ一筋の光だった。彼女は何度も頷き、子供のように声を上げて泣いた。
その日から、二人の奇妙な夜が始まった。リヒトは廃棄記憶晶の鑑定を続けながら、夜ごとエララのために、彼女が生み出した記憶晶の物語を紡いだ。彼はもはや、他人の記憶を心のゴミだとは思わなかった。どんな記憶にも、たとえそれが忘れ去られたものであっても、持ち主だけの物語と、かけがえのない価値があることを知ったのだ。
ある晩、リヒトが一つの物語を語り終えると、エララは窓の外の月を見上げながら、静かに微笑んだ。
「ありがとう、リヒト。私の歌も、少しだけ、暖かくなった気がする」
その笑顔は、リヒトが今まで見たどんな記憶晶よりも美しく輝いて見えた。彼は自分の手の中に、まだ見ていない小さな水色の記憶晶を握りしめる。それは、誰かの失われた幸福のかけらであり、これから彼が愛する人のために紡ぐべき、新しい物語の始まりだった。彼らの物語は終わらない。ただ、こうして静かな夜の中で、優しく続いていくだけなのだ。