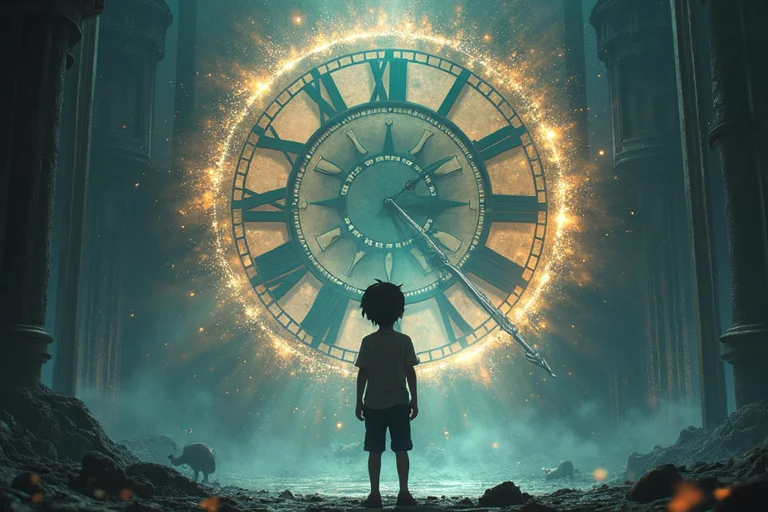第一章 色褪せた譜面
カップから立ち上る湯気の揺らめきが、一瞬、コマ送りのように見えた。鼻腔をくすぐるコーヒーの苦い香りは、その映像からコンマ数秒遅れて脳に届く。この微細な世界の不協和音が、時間調律師である僕、カイの日常だった。他者の過去と同期するたび、僕自身の『現在』は、世界のそれから僅かずつ引き剥がされていく。
ドアベルの乾いた音が鳴った。僕が立ち上がるより先に、扉が開く。僕の時間のズレを知る数少ない客は、いつも性急だ。
「カイさん、お願いがあります」
息を切らして飛び込んできたのは、歴史保存局の記録員、エリアだった。彼女は握りしめた古びた譜面の端が、自身の指の震えで小さく波打っていることに気づいていない。早口で紡がれる言葉は、まるで堰を切った水のように僕に降り注いだ。
「レナード・アークライトを、覚えていますか?」
その名に、僕の記憶の糸は微かに震えたが、確かな像を結ばなかった。エリアはそれを見透かしたように、絶望の色を瞳に浮かべる。
「一週間前まで、彼の交響曲は歴史上最も偉大な音楽として記録されていました。でも、今では……」
彼女はテーブルの上に、くすんだ真鍮のオルゴールを置いた。ゼンマイを巻いても、それは虚ろな沈黙を吐き出すだけだ。
「記録が消え、人々が忘れ、まるで初めから存在しなかったかのように世界が塗り替えられていくんです。これが、彼の最後の遺した譜面の一部。彼が生きた証を、世界から完全に消される前に、どうか……」
その声は祈りに近かった。僕は黙って譜面を受け取る。インクのかすれた五線譜の上に、ただ一つの音符も記されてはいなかった。まるで、奏でられるべき旋律そのものが、世界から削り取られてしまったかのように。
第二章 虚ろな旋律
書斎の奥、窓からの光が届かない棚に、それは鎮座していた。『無記名の砂時計』。世界から忘れ去られた存在の最後の記憶が、淡く光る砂となって溜まっている。
僕はエリアから預かったアークライトの指揮棒を手に取った。冷たい象牙の感触が、僕の皮膚を通して意識の奥深くへと侵入してくる。目を閉じ、呼吸を深くする。世界の音、光、匂いが遠ざかり、代わりに僕のものではない記憶の奔流が流れ込んできた。
――万雷の拍手。ライトを浴びて汗が光る。高揚感と共に押し寄せる、絶対的な孤独。彼は聴衆の顔を見ていなかった。彼の音楽は、もっと遥か遠く、この世界の誰でもない『何か』に捧げられていた。記憶は断片的で、熱狂と静寂の間を激しく行き来する。次第に、彼の音楽を理解する者がいなくなり、ホールから一人、また一人と人が消えていく。忘れられることへの恐怖が、彼の魂を黒く蝕んでいくのが分かった。
「……っ!」
現実へと引き戻された僕の額には、びっしりと汗が滲んでいた。世界のズレが、さらに大きくなっている。エリアの声が、唇の動きからワンテンポ遅れて聞こえてくる。
「大丈夫ですか……顔色が」
僕は頷き、震える指で砂時計を逆さにした。そして、追体験したばかりのアークライトの記憶――彼の情熱と苦悩の残滓を、意識の中で砂の粒子へと変え、ガラスの中へとそっと注ぎ込んだ。砂時計の中の砂が、わずかに量を増し、儚いオーボエの音色のような光を放つ。これで、彼の完全な消滅は、ほんの少しだけ先延ばしにされたはずだ。だが、砂時計は渇きを癒やせない旅人のように、常に次なる記憶を求め続けている。
第三章 加速する忘却
アークライトだけではなかった。エリアの調査で、事態の深刻さが明らかになる。偉大な発見をした科学者、圧政に立ち向かった革命家、後世に多大な影響を与えた哲学者。彼らの存在が、まるで系統だった剪定のように、歴史の枝から切り落とされていた。
「共通点があるんです」エリアは壁一面に貼り出した資料を指差した。「消されているのは、世界に『大きな調和』や『新たな秩序』をもたらした人たちばかりです」
それは、もはや自然な忘却ではない。明確な意思を持った、計画的な『削除』だった。世界の存在基盤である記憶を、何者かが意図的に破壊している。このままでは、世界の構造そのものが崩壊し、全てが無に還るだろう。
僕たちは、アークライトが最後の演奏会を開いたとされる、街外れの廃墟コンサートホールへと向かった。埃とカビの匂いが立ち込めるホールの中央に、一台のグランドピアノが、巨大な墓標のように佇んでいる。鍵盤は朽ち、弦は錆びつき、もはや音を奏でることはない。
「ここで、彼は最後の曲を」
エリアが呟いた。だが、誰のために? 記録によれば、その演奏会に聴衆は一人もいなかったという。
僕はピアノの前に立ち、冷たい鍵盤に指を置いた。ここには、彼が最後に世界に遺そうとした記憶が、最も色濃く残っているはずだ。僕は、これまでで最も深く、危険な同期を試みる覚悟を決めた。
第四章 無音の交響曲
意識が沈む。ホールの闇が、宇宙の深淵へと変わった。
アークライトの最後の記憶が流れ込んでくる。彼は、聴衆のいないホールで、ただ一人、ピアノを奏でていた。それは交響曲と呼ぶにはあまりに静かで、悲痛な独奏曲だった。彼の指から紡がれる旋律は、人間ではなく、この世界そのものの魂に向けて奏でられていた。
その時だ。
僕は、アークライトの記憶のさらに奥、その向こう側にある、途方もなく巨大で、そして古い意識の存在を感じ取った。
それは、喜びも悲しみも、怒りも安らぎも、全てを呑み込んで摩耗しきった、疲れ果てた意識だった。世界の始まりから、生まれ、死んでいく全ての生命の記憶を、ただ受け止め続けてきた『最初の意識』。あまりにも多くの記憶は、無限の重荷となり、その存在を内側から蝕んでいた。
アークライトの音楽は、この疲弊した意識を慰めるための鎮魂歌だったのだ。しかし、永劫に続く時間の中では、いかなる美しい旋律も、いずれは苦痛な繰り返しでしかない。
『もう、終わりにしてほしい』
声ではない声が、僕の魂に直接響いた。
『忘れたい。全てを。私が生まれた、最初の無へと還りたい』
『最初の意識』は、自らを忘れることで、無限の苦しみから解放されようとしていた。アークライトのような、世界を強く繋ぎ止める記憶の楔を消し去っていたのは、世界の崩壊を加速させ、自らの完全な忘却を成し遂げるためだったのだ。
その根源的な絶望に触れた瞬間、僕の世界はガラスのように砕け散った。過去と現在が混濁し、エリアの叫び声が、水中の音のように遠く、歪んで聞こえる。僕は、世界と共に無へと引きずり込まれていく感覚に、抗うことができなかった。
第五章 始まりの音
絶望の渦に呑まれながら、僕は最後の抵抗を試みた。能力の逆用。他者の過去を追体験するのではない。僕の、この歪んでしまった『現在』を、そっくりそのまま『最初の意識』へと同期させるのだ。
震える手で、懐からエリアのオルゴールを取り出す。鳴らないはずのガラクタだ。だが、僕は心の中で、アークライトの記憶から蘇らせた旋律を奏でた。それは、孤独な天才が世界に捧げた鎮魂歌ではない。僕がエリアから受け取った、一つの記憶を必死に繋ぎ止めようとする、切実な願いの旋律だった。
僕は同期させた。
『最初の意識』が経験したことのない、たった今、この瞬間の感覚を。
アークライトを忘れまいと奔走するエリアの姿。失われゆく記憶を繋ぎ止めようとする僕自身の意志。そして、まだ誰も知らない、これから生まれるかもしれない『未来の音楽』への、不確かで、だからこそ輝かしい期待。
『忘れること』と『忘れられること』しか知らなかった巨大な意識に、初めて異なる概念が流れ込む。それは、無限に積み重なる過去の重荷とは全く違う、軽やかで、どこか不協和音を伴う、けれど新しい『始まりの音』だった。
それは問いかけだった。忘れることで終わる世界と、不完全なまま新しい記憶を紡ぎ続ける世界。どちらが、真の安らぎなのか、と。
第六章 時の残響
『最初の意識』の、世界を終わらせようとする強固な意思が、わずかに揺らいだ。それだけで十分だった。忘却の奔流が勢いを失い、世界から消えかけていた存在たちの輪郭が、滲んだ水彩画のように、ゆっくりと色を取り戻し始める。完全な回復ではない。だが、世界の崩壊は食い止められた。
僕の意識は、ゆっくりと現実のホールへと浮上した。
時間感覚のズレは、もはやズレと呼べないほどに大きくなっていた。僕が生きる『現在』は、世界のそれとは全く違うテンポで流れている。だが、不思議と苦痛はなかった。むしろ、その歪みの中に、奇妙な静けさと調和を感じていた。僕は、世界と異なる時間を歩むことで、誰よりも世界の『記憶の響き』に敏感な調律師となったのだ。
「カイさん!」
エリアが駆け寄ってくる。彼女の手にあったオルゴールから、か細く、しかし確かな旋律が流れ出していた。アークライトの曲だ。世界は、彼の全てを忘れたわけではなかった。
僕は書斎の『無記名の砂時計』を思った。あの砂は、まだ落ち続けているだろう。忘却は、この世界の法則そのものだから。
「世界は、忘れることをやめない。たぶん、それが摂理なんだ」僕はエリアに微笑みかけた。「でも、思い出すことをやめる必要もない。僕たちは、そのための調律師なんだろう」
僕の耳には、まだ誰も知らない、未来のどこかで奏でられるはずの新しい旋律が、微かな残響として聞こえている気がした。不完全で、忘れっぽくて、それでも続いていくこの世界で、僕たちはこれからも、失われた音を探し続けるのだ。