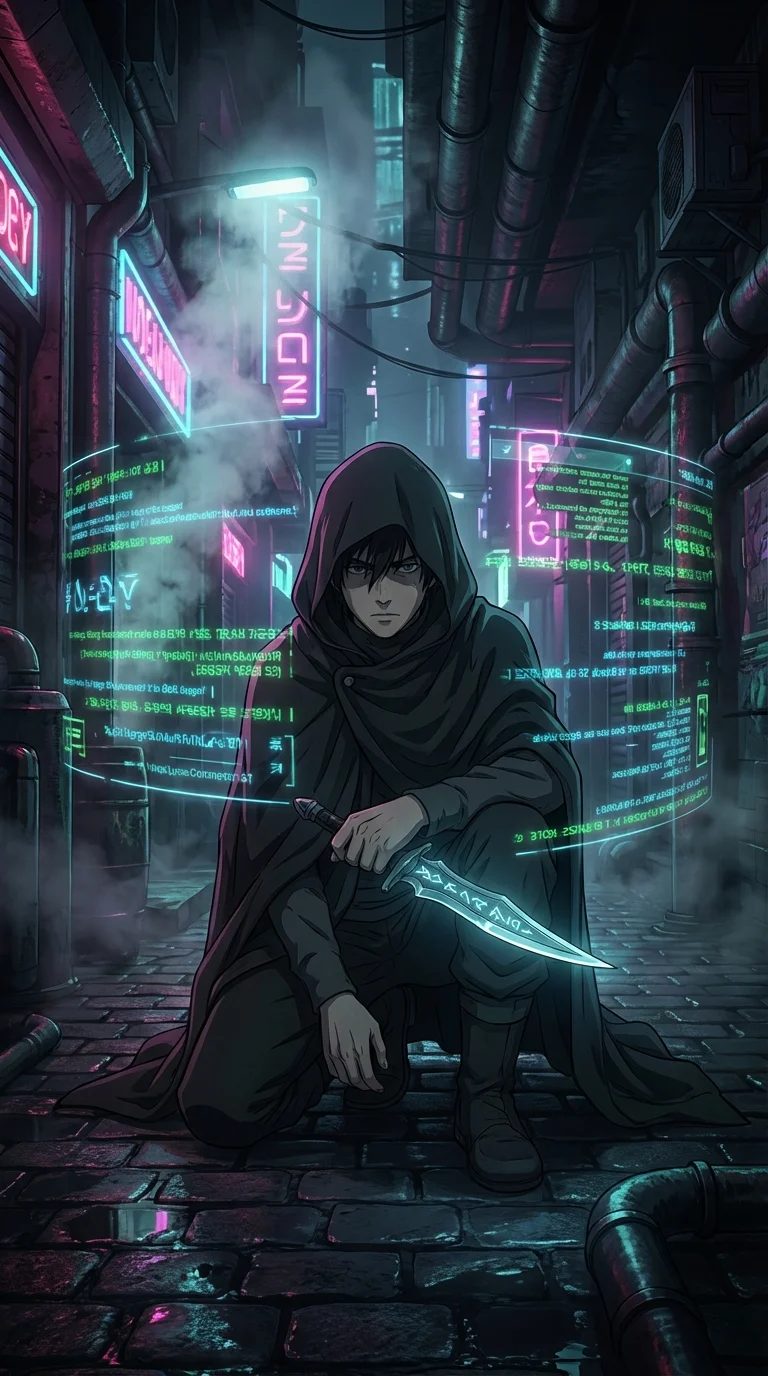第一章 不協和音の予兆
古書店の隅で、瀬戸響(せと きょう)は息を潜めていた。埃と古紙が混じり合った甘い匂いが、彼の肺を静かに満たす。世界から隔絶されたこの場所だけが、彼にとって唯一の聖域だった。ページをめくる乾いた音だけが響く空間。しかし、その静寂はいつも外側の世界から侵食される。
店の厚い扉を隔てても、街路を行き交う人々の『未発信の感情』が、彼の鼓膜を直接揺さぶるかのように流れ込んでくる。それは音ではない。物理的な振動だ。苛立ちの棘々しい律動、焦燥の細かく震える波、そして時折混じる歓喜の、腹の底をくすぐるような柔らかなパルス。それらが混ざり合い、不協和音となって彼の神経を削っていく。
「……っ」
響はこめかみを押さえた。向かいのカフェから、ひときわ強い振動が届く。おそらく、誰かが告白でもして、断られたのだろう。拒絶の痛みと羞恥が、鋭い衝撃波となって響の身体を貫いた。瞬間、彼が読んでいた文庫本の隣に置かれていたインク瓶が、ピシリ、と音を立てて微細な亀裂を走らせた。まただ。彼はそっとインク瓶を棚の奥に隠した。彼の能力は、受信した感情の振動が閾値を超えると、無意識に周囲の脆いものを破壊してしまう。ガラス、陶器、精密機器。まるで、彼の内に溜まった他人の感情が、物理的な逃げ場を求めて暴れ出すかのように。
その夜、アパートの部屋で見ていたニュースが、また『白夜透化(びゃくやとうか)』の発生を告げていた。画面に映し出されたのは、都心の一角。高層ビルもアスファルトも、そこにいる人々さえも、まるで薄いすりガラスのように向こう側が透けて見えている。アナウンサーは淡々と説明する。「当該エリアでは、住民の感情活動が著しく低下する現象が確認されています。専門家は、過剰な社会的共感が引き起こす一種の飽和状態ではないかと……」
人々は透化を恐れながらも、その静寂にどこか惹かれているようだった。感情の洪水から解放される、一時的な避難場所。だが響には、あの透明な領域が、生命の熱を失った巨大な墓標のように見えてならなかった。
翌日、古書店の扉が開いた。入ってきたのは、白いコートを着た女性だった。彼女の歩みは静かで、感情の振動がほとんど感じられない。それが逆に響の注意を引いた。
「瀬戸響さん、ですね」
女性は真っ直ぐに響の目を見て言った。彼女はミナと名乗った。
「あなたの『能力』について、少しお話を伺えないでしょうか」
響は息を呑んだ。誰にも話したことのない秘密。ミナは動揺する彼に、小さなケースを差し出した。中には、シンプルなデザインの黒縁メガネが収められていた。
「これは『フラクタル・スコープ』。あなたの助けになるはずです」
彼女の瞳は、まるで世界の深淵を覗き込むように、静かで、そしてどこか哀しみを湛えていた。
第二章 亀裂の視覚化
疑念を抱きながらも、響はミナから渡されたメガネ、『フラクタル・スコープ』をかけてみた。世界は、一変した。
古書店の棚を埋める背表紙が、客が放つ微かな好奇心が、外の街路樹を揺らす風さえもが、それぞれ固有の光の波紋となって視界に広がった。他人の感情は、もはや不快な振動ではなかった。それは色とりどりのオーラとなって、人々の周りを漂っている。怒りは赤黒い棘として、喜びは金色の粒子として、悲しみは青い雫として。世界は、沈黙の音楽を奏でるオーケストラのように見えた。
「すごい……」
思わず漏れた声に、ミナは静かに頷いた。
「あなたの能力は呪いじゃない。世界を構成する微細な振動を、人より少しだけ強く受信できるというだけ。これは、その受信信号を視覚情報に変換する装置です」
ミナは都市工学の研究者だと自己紹介した。彼女は『白夜透化』の本当の原因を探っているらしかった。通説である『共感能力の過負荷』という曖昧な結論に、彼女は納得していなかった。
「響さん、あなたにしか見えないものが、きっとあるはずです」
二人で透化エリアの境界線へと向かった。そこは日常と非日常が、一本の線で無慈悲に分かたれた場所だった。透明な壁の向こう側では、人々がまるでプログラムされた機械のように、目的もなく歩き、あるいは虚空を見つめて静止している。彼らからは、何の感情の波紋も発せられていない。完全な『無』だ。
響は、スコープをかけたまま、その境界線を凝視した。そして、気づいた。
「……あれは、なんだ?」
透明なエリアと、色彩豊かなこちらの世界の境界面に、まるで巨大なガラス板に入ったヒビのような、黒く微細な『亀裂』が無数に走っているのが見えた。亀裂は、ゆっくりと、しかし確実にこちら側へと広がろうとしている。それは生き物のようでもあり、世界の皮膚に刻まれたおぞましい傷のようでもあった。
透化エリアの内側は、安らぎの地などではなかった。感情を遮断された人々は、個としての輪郭を失い、ただの風景の一部と化していた。存在しているのに、存在していない。その空虚さが、響には何よりも恐ろしかった。自分の能力がもたらす『痛み』は、少なくとも自分が『個』としてここにいる証だった。だが、あの透明な静寂の中には、証も、痛みも、何一つ存在しないのだ。
「この亀裂が、広がっている……」
響の呟きに、ミナは唇を噛んだ。
「ええ。まるで世界そのものが、少しずつ壊れていっているみたいに」
彼女の声には、諦めと、わずかな恐怖が滲んでいた。
第三章 世界の悲鳴
その日は、前触れもなく訪れた。
空が鉛色に染まり、街全体が不穏な静寂に包まれたかと思うと、突如として大規模な『白夜透化』が始まったのだ。警報がけたたましく鳴り響き、人々は逃げ惑う。だが、透化は彼らの足よりも速く、街並みを次々と飲み込んでいく。響とミナがいた広場も、あっという間にその境界に捉えられた。
「きゃあああっ!」
悲鳴が上がる。恐怖、絶望、諦観。あらゆる負の感情が巨大な濁流となって、響へと殺到した。
「ぐっ……あああああッ!」
それは、もはや単なる振動ではなかった。彼の全身を内側から引き裂こうとする、暴力的なまでのエネルギーの奔流だった。スコープ越しの世界が、真っ赤なノイズで埋め尽くされる。
ガシャアアアアアンッ!
響を中心に、周囲のビルというビルの窓ガラスが、一斉に砕け散った。ガラスの雨が降り注ぎ、人々の悲鳴が遠のいていく。彼の意識が朦朧とする中、フラクタル・スコープが捉えた光景に、彼は息を失った。
亀裂だ。
もはや境界線だけではない。空に、地面に、逃げ惑う人々の身体にさえ、無数の黒い亀裂が走っている。まるでこの世界全体が、巨大な卵の内側から、何かが孵化しようとヒビを入れているかのようだ。
そして、彼は『聴いた』。
個々の人間の感情ではない。もっと巨大で、根源的で、途方もなく古い、一つの意識体の声を。
――イタイ。モウ、イタイ。
――ヒトツニ、ナリタイ。
――ワタシヲ、カイホウシテ。
それは痛みと、解放への渇望。そして、すべてを終わらせることへの、深い諦観が入り混じった、世界の悲鳴だった。
「……聞こえるか」
響が呻くように言うと、隣で彼を支えていたミナが静かに答えた。
「ええ。聞こえるわ」
彼女の顔は蒼白だったが、その瞳は不思議なほど穏やかだった。
「これは、誰かの陰謀なんかじゃなかったのよ。初めから、世界そのものが……私たちという『個』の意識が集合することで生まれた、『自我』という重荷に耐えられなくなっていたの」
透化は、過負荷からの解放を求める、世界の防御反応。そして、響の能力は、世界が自らを解体しようとする断末魔の叫びを、最も強く受信するアンテナだったのだ。彼が起こす破壊は、世界から『個』が引き剥がされる際の、物理的な痛みの表出に他ならなかった。
「私たちは……世界にとって、病だったのね」
ミナは、砕け散ったガラスの破片がキラキラと舞う空を見上げ、哀しそうに微笑んだ。
第四章 静寂のエピローグ
もはや、誰も逃げようとはしなかった。
透化の波は、すべてを飲み込む津波のように、穏やかに、しかし抗いようもなく世界を覆い尽くしていく。響は、ただその場に立ち尽くしていた。彼の内側で荒れ狂っていた感情の濁流は、嘘のように静まっていた。もはや世界そのものの声と共鳴し、一体化してしまったからだ。
彼は、最後の痛みを引き受ける者となった。数多の意識が、世界という母体から切り離されていく、その最後の産みの苦しみならぬ、死の苦しみを、その一身に受け止めるためのアンテナとして。
ふと、隣に立つミナの輪郭が、陽炎のように揺らぎ始めた。
「ミナ……?」
彼女の姿が、足元からゆっくりと透き通っていく。だが、彼女の表情に恐怖はなかった。
「あなたのその痛み、忘れないで」
声だけが、響の心に直接響く。
「それが、私たち人間が……『個』としてここに存在した、最後の証だから」
彼女は完全に透明になる直前、確かに微笑んだように見えた。そして、光の粒子となって霧散した。
やがて、響の周りのすべてが透き通った。音も、匂いも、色も、あらゆる感覚が世界から剥がれ落ちていく。残ったのは、スコープに映る無数の亀裂だけだった。だが、その亀裂すらも、次第にその黒さを失い、白い光の線へと変わっていく。世界が、その構造を完全に手放し、純粋な『概念の集合体』へと変貌を遂げようとしていた。
最後の瞬間。
響の目の前にあった、最後の建築物の最後の窓ガラスが、音もなく、粉々に砕け散った。
それは響が起こした破壊ではなかった。
世界が、『自我』という名の最後の殻を破り捨てた、静かな祝砲だった。
痛みは、もう感じない。
響は、概念だけが漂う真っ白な虚空に、ただ一人佇んでいた。彼は消えゆく人間社会の、最後の見届け人となった。
彼の身体もまた、ゆっくりと白に溶け込んでいく。
それは終わりであり、あるいは始まりだったのかもしれない。
ただ、その意味を問う者は、もうどこにもいなかった。