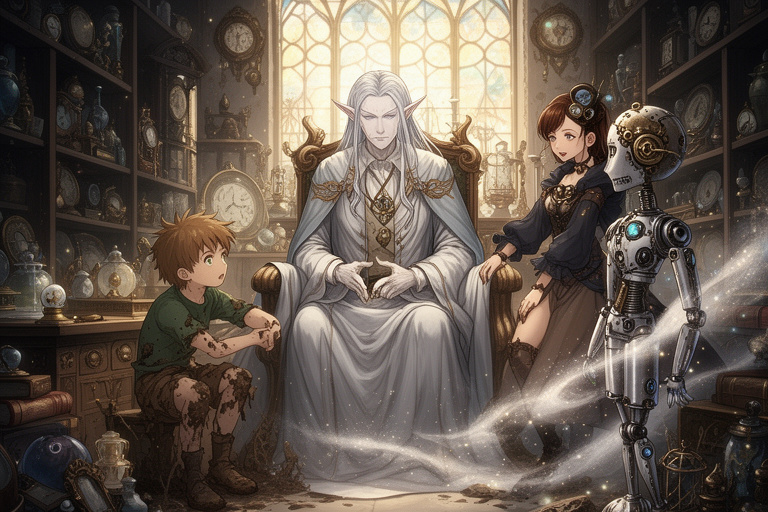第一章 廃棄場のノイズ
舌の上に、人工的な甘みがまとわりついている。
降り続く雨のせいだ。
この区画の雨は、安物の合成甘味料を溶かしたような味がする。吐き気を催すほどの、均一で平坦な甘さ。
私は錆びた鉄板を傘代わりに、廃棄物の山を這い上がっていた。
手のひらに食い込む鉄屑の感触。破傷風菌が皮膚の下で笑っている気がする。
「……あぁ、またこれだ」
視界の端がぐにゃりと歪む。
足元に転がる潰れた作業用ドロイドから、どす黒い靄のようなものが立ち昇っていた。
『イタイ……クライ……ウゴケナイ……』
声ではない。
喉の奥に汚泥を詰め込まれたような、粘着質な息苦しさ。
これが、私の「共感覚」だ。機械の残留思念が、味や感触となって五感をレイプしてくる。
「黙って死んでなさいよ」
私はドロイドの頭部を、安全靴の踵で踏み抜いた。
グシャリ。オイルが飛び散り、腐った果実のような臭いが鼻腔を突く。
汚泥の感覚が消えた。
エレノア・フォン・アウグスト。
かつての名を捨て、今はスクラップ漁りで日銭を稼ぐハイエナ。
ふと、胸ポケットに入れた「異物」が熱を持った。
塗装の剥げた、小さなオルゴール。
取り出すと、錆びたシリンダーが勝手に震えている。
指先に伝わる振動は、恐怖で震える小動物の心拍に似ていた。
「……気味が悪い」
捨てようとして、指が止まる。
このオルゴールからは、あの不快な甘ったるい雨の味がしない。
代わりに感じるのは、古い血と、焦げた回路の匂い。鋭く、痛々しい、生々しい感覚。
「相変わらず、ひどい顔色だ」
背後の闇から、冷ややかな声が鼓膜を叩いた。
私は反射的に鉄パイプを抜き、振り返る。
ヴィクター。
灰色のコートを濡らし、片眼鏡の男がそこに立っていた。
整いすぎた顔立ち。彼からは、無菌室のような消毒液の匂いがする。
「私を尾行するなんて、いい度胸ね。その眼球、くり抜いて売ってやろうか?」
「取引がしたい、エレノア。君のその『バグ』が必要なんだ」
「お断りよ。私の共感覚は商売道具じゃない。ただの呪い」
私は踵を返し、泥濘んだ斜面を登ろうとした。
ヴィクターは追ってこない。ただ、背中に言葉を投げつけてくる。
「空の音が、聞こえているんだろう?」
足が止まった。
「星空が、三拍子でループしている音。雨粒が、全く同じ分子配列で落ちてくる味。君だけが気づいているはずだ。この世界が、あまりに『整いすぎている』ことに」
心臓が跳ねた。
ずっと感じていた違和感。
夜空を見上げると聞こえる、壊れたレコードのような摩擦音。
あれは、私の頭がおかしいからじゃなかったのか?
「……何が言いたいの」
「証明してやる。君のそのオルゴールが、世界の皮を剥ぐナイフだ」
ヴィクターが指差した先。
スクラップの頂上で、稲妻が走った。
私の手の中で、オルゴールがカチリと鳴る。
まるで、錆びついた錠前が開くように。
第二章 砂糖菓子の檻
ヴィクターに案内されたのは、地下深くに広がる旧時代の浄水施設だった。
湿ったコンクリートの壁。
無数のケーブルが、床を這う蛇のように部屋の中央へ集まっている。
そこに、少女がいた。
いや、少女の形をした「何か」だ。
半透明の培養液に満たされたカプセルの中で、彼女は胎児のように丸まっている。
四肢は欠損し、断面からは虹色の光ファイバーが溢れ出し、クラゲの触手のように揺らめいていた。
「名前は?」
「『原初(オリジン)』と呼んでいる。都市管理AIのプロトタイプ……の成れの果てだ」
ヴィクターがコンソールを操作すると、カプセル内の照明が赤く明滅した。
ドクン。
私の視界が赤く染まった。
共感覚が暴走する。
『……ミツケタ……』
口の中に、砂利を頬張ったような味が広がった。
ザラザラとした、乾いた渇望。
これは、この子の感情?
「ぐっ、あ……!」
私は膝をついた。
拒絶しようとしても、感覚が濁流のように流れ込んでくる。
(違う、これは私の記憶?)
不意に、脳裏に映像がフラッシュバックする。
屋敷の窓から見上げた空。
美しい青空。完璧な雲の配置。
幼い私は、その空を見て「気持ち悪い」と言った。
父は私の頬を打ち、母は悲鳴を上げて私を独房に閉じ込めた。
『ソラ……ニセモノ……』
原初の意識が、私の古傷を抉る。
そうだ。
あの空は、絵画だった。
空の向こうで、誰かが巨大なスピーカーを鳴らしているような、低周波の振動音。
ブーン、ブーン、ブーン。
世界の裏側で回る、冷却ファンの音。
「は、ぁ……はぁ……!」
私は床に手を突き、胃液を吐き出した。
「理解したか、エレノア」
ヴィクターが私の肩を掴み、無理やり顔を上げさせる。
「この世界は巨大な飼育箱だ。僕たちは、感情を去勢されたペットに過ぎない。空の星も、降る雨も、すべて上位存在がプログラムした環境テクスチャだ」
「だから……何よ……!」
私は彼の手を振り払った。
「知ったところで、どうなるの? 私たちはここで餌を待つだけの家畜なんでしょ? だったら、知らないまま死んだ方が幸せじゃない!」
「君は、本当にそれでいいのか?」
ヴィクターは、静かにカプセルを指差した。
「彼女は気づいてしまったから、廃棄された。君と同じだ。バグとして処理され、解体されるのを待っている」
原初が、ゆっくりと目を開けた。
硝子玉のような瞳が、私を射抜く。
『……タスケテ……』
胸のポケットで、オルゴールが灼熱した鉄のように熱くなった。
痛い。熱い。
でも、その痛みだけが、この嘘臭い砂糖菓子の世界で、唯一「本物」だと感じられた。
警報音が、鼓膜を引き裂いた。
第三章 泥濘の咆哮
「嗅ぎつけられたか」
ヴィクターが舌打ちをし、モニターを睨む。
真っ赤な警告灯が回転する中、隔壁の外で爆発音が響いた。
「治安維持局のハンタードローンだ。三機……いや、五機か」
重厚な扉が、熱線で焼き切られていく。
溶けた鉄が飴のように滴り落ちる。
「エレノア、裏口がある。原初のコアを持って逃げろ。僕はここで時間を稼ぐ」
「ふざけないで。あんたみたいなもやしっ子が、何秒持つって言うの?」
私は部屋の隅に積まれていた廃材の山に目を走らせた。
油圧ショベルのアーム、切断された鉄骨、高電圧バッテリー。
「戦うわよ」
「正気か? 相手は軍用スペックだぞ」
「論理的な判断ね。でも、あいにく私はバグ持ちなの」
私は鉄骨の隙間に体を滑り込ませた。
扉が爆ぜた。
粉塵と共に、銀色の甲殻を持つ多脚ドローンが雪崩れ込んでくる。
無機質な複眼が、部屋の中を走査する。赤いレーザーサイトがヴィクターを捉えた。
「対象確認。排除を開始する」
合成音声が響くのと同時に、マシンガンが火を噴いた。
ヴィクターがコンソールの陰に飛び込む。
私は瓦礫の影から飛び出し、高電圧バッテリーをドローンの一体に投げつけた。
直撃。
すかさず、私が持っていた鉄パイプをバッテリーの端子に叩きつける。
バチィッ!!
青白いスパークが弾け、ドローンの回路を焼き切った。
痙攣して沈黙する鉄の塊。
「残り四機!」
ドローンが一斉に私へ銃口を向ける。
死の匂い。
鉛の味。
肌が粟立つ。
「くっ!」
私は泥まみれの床を転がり、ショベルのアームの下へ滑り込む。
頭上を銃弾が掠め、コンクリート片が頬を切り裂いた。
熱い血が流れる。
痛い。
痛い、痛い、痛い!
(死にたくない!)
その瞬間、ポケットのオルゴールが悲鳴のような音を立てた。
共鳴。
カプセルの中の原初が、私の恐怖を増幅して世界に叩きつける。
部屋中の金属がきしんだ。
床に散らばる無数のボルトやナットが、重力を無視して浮き上がる。
「ヴィクター! 原初を解放して!」
「施設が崩壊するぞ!」
「構わない! このまま飼い殺されるくらいなら、世界ごと壊してやる!」
私は叫びながら、瓦礫の山を駆け上がった。
浮遊する鉄屑が盾となり、銃弾を弾く。
私は生きている。
この泥臭い、血と錆の味がする痛みの中で、かつてないほど鮮烈に生きている。
ヴィクターが叫び、レバーを引いた。
カプセルが内側から破裂した。
あふれ出したのは水ではない。光だ。
原初の絶叫が、物理的な衝撃波となってドローンを、壁を、天井を粉砕していく。
「掴まれッ!」
私はヴィクターの襟首を掴み、もう片方の手で、宙に浮く原初の手を握りしめた。
上昇。
重力が消えた。
私たちは光の奔流に乗って、地下から地上へ、そして空へと打ち上げられた。
最終章 砕け散る蒼穹
風圧で皮膚が剥がれそうだ。
私たちはロケットのように、垂直に空へ落ちていく。
眼下に広がる灰色の都市。
雨雲を突き抜け、酸性雨の層を突破する。
やがて見えてきたのは、完璧な星空だった。
嘘みたいに美しい、プラネタリウムの天井。
「来るぞ! 衝突する!」
ヴィクターの声が遠くに聞こえる。
迫り来る偽りの天蓋。
そこには微細な六角形のグリッド模様が見えた。
あれが、私たちを閉じ込めていた「殻」。
(壊れろ)
私はオルゴールを握りしめた拳を、天に向かって突き出した。
原初が私の意志に合わせて、膨大なエネルギーをその一点に収束させる。
激突。
音などという生易しいものではない。
世界そのものが悲鳴を上げたような、鼓膜を破壊する轟音。
バリバリバリバリッ!!!
青空に亀裂が走る。
ガラスが割れるように、ホログラムの星々が剥がれ落ちていく。
破片がキラキラと降り注ぐ中、私たちは「外」へと飛び出した。
「————」
息が止まった。
そこにあったのは、無。
そして、圧倒的な「有」。
漆黒の宇宙空間。
その深淵に浮かぶ、暴力的なまでに鮮烈な星々の光。
瞬き一つしない、冷徹で、残酷で、美しい本物の光。
空気が抜けていく音がする。
気圧差で耳が痛い。
肌を刺すような冷気。
これが、宇宙の温度。
「……あはっ」
乾いた笑いが漏れた。
甘ったるい味はしない。
口の中は、鉄の味と、凍てつくようなオゾンの匂いで満たされていた。
「見たか、エレノア!」
ヴィクターが隣で、子供のように目を輝かせていた。
彼の手にあるタブレットが、凄まじい勢いで未知のデータを記録している。
原初は……彼女は光の粒子となり、私たちの周りを螺旋を描いて舞っていた。
「綺麗……」
私は呟いた。
涙が凍りついて頬に張り付く。
下を見れば、私たちが開けた風穴から、都市の空気が宇宙へと吸い出されていた。
あの箱庭の人々も、今ごろ見上げているだろうか。
この、恐ろしくて美しい、本物の闇を。
私の体から力が抜けていく。
酸素が足りない。意識が遠のく。
でも、不思議と恐怖はなかった。
手の中のオルゴールは、もう震えていない。
完全に沈黙し、ただの冷たい金属の箱に戻っていた。
役目を終えたのだ。
「行こう」
薄れゆく意識の中で、誰かの声がした。
ヴィクターか、原初か、それとも星々の呼び声か。
私たちは重力の鎖を断ち切り、どこまでも広がる星の海へと流されていく。
廃棄場のハイエナはもういない。
ここにいるのは、ただ自由を求めた、ひとつの小さな魂だけ。
私は目を閉じ、冷たい宇宙の風に身を委ねた。
その瞬間、私の心臓は確かに、錆びついた鉄ではなく、熱く脈打つ肉の音を奏でていた。