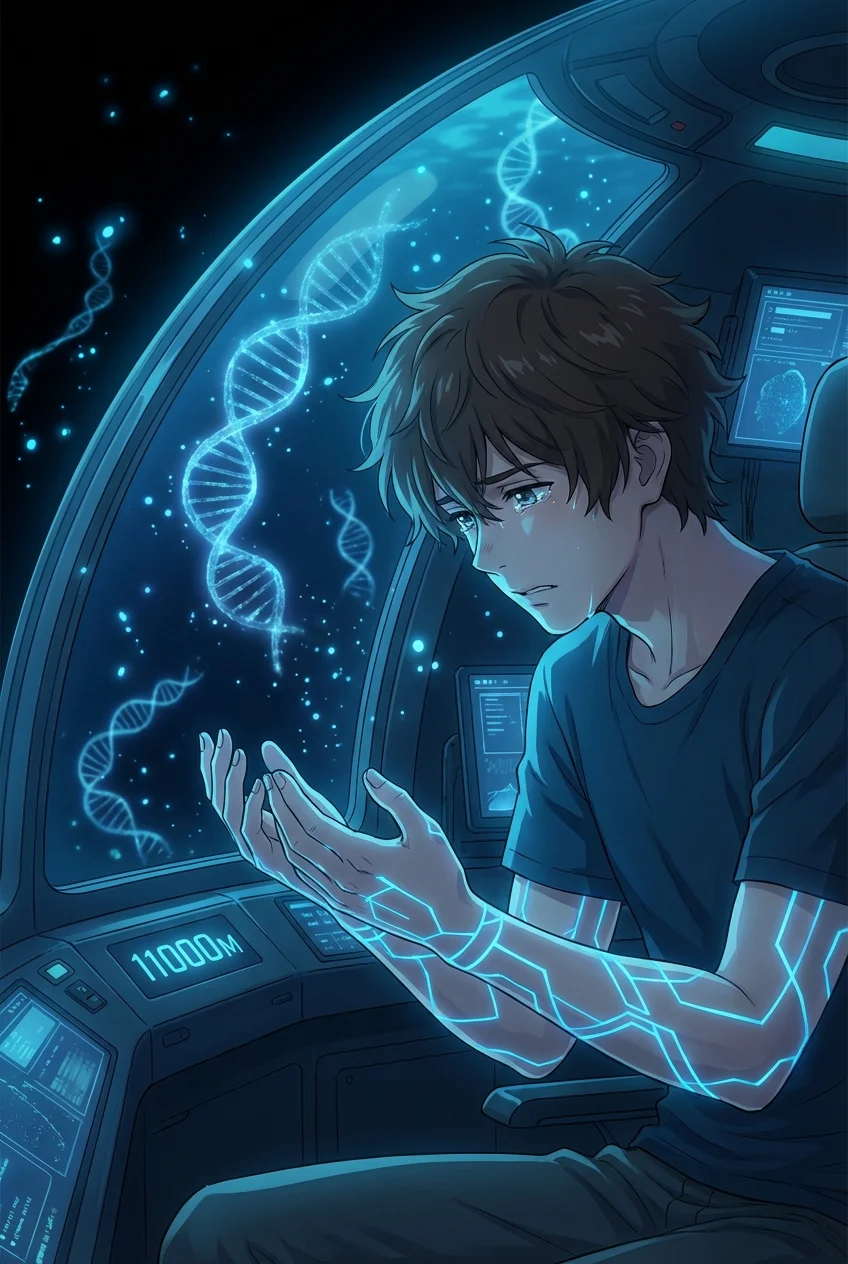第一章 歪んだプロフィール
深夜二時。ワンルームの静寂を、スマホのブルーライトだけが切り裂いている。
星野縁(ゆかり)の親指は、死んだ魚のような目で画面を左へ弾き続けていた。
《タカシ/32歳/商社マン/週末はキャンプ》
「……無理」
写真を見た瞬間、胃液が逆流しそうな嫌悪感がこみ上げる。
日焼けした肌、白い歯、自信に満ちた瞳。
間違いなく『人間』だ。
言葉の裏を読み合い、マウントを取り合う、あの泥臭い生態系。想像するだけで掌がじっとりと湿る。
縁は画面をスワイプした。指が止まる。
《レン/28歳/経営者/夜の散歩が好き》
黒髪の青年。だが、縁の網膜には別の情報が焼きついた。
写真の輪郭が、夏の日の陽炎(かげろう)のように揺らめいている。
画面越しなのに、雨に濡れた犬のような、あるいは古びた神社の縁の下のような、湿った匂いが鼻腔をくすぐった。
「……あ、こっちは大丈夫」
縁の強張った肩から力が抜ける。
こいつは人間じゃない。
人の皮を被って、孤独な魂を啜(すす)りに来た『あちら側』の住人だ。
人間相手なら「嫌われないか」と震える声も、相手が化け物ならどうでもいい。喰われるか、喰わせるか。それだけのシンプルな関係。
『マッチングしました!』
画面にポップな文字が躍る。縁は躊躇なくフリック入力した。
「はじめまして。写真、素敵ですね。人間の皮、被るの上手ですね」
送信ボタンを押した瞬間、スマホが熱を帯びたように脈打った。
ホーム画面のアイコン――ピンク色のハートマークに、血管のような、あるいは蜘蛛の糸のような赤黒い線が、また一本、絡みついた。
第二章 蜜の味、砂の記憶
「来月は、君の好きな紫陽花を見に行こう」
レンはそう言って、小さな包みを差し出した。
カフェのテラス席。夕陽が彼の影を長く伸ばしているが、その影は二つに分かれ、一つは獣の尾のように揺らめいている。
「気が早いのね、レン」
縁は苦笑しながら、包みを開けた。中には、紫陽花の色をしたガラスのピアスが入っていた。
胸の奥がじんわりと温かくなる。
誰かに気にかけてもらう喜び。明日への約束があるという安堵。
その感情が湧き上がった端から、レンの瞳が掃除機のようにそれを吸い上げていく。
「君の寂しさは、甘いね。……もっと、頂戴」
レンの手が、縁の手を包み込む。
指先から、私の中の「孤独」が、そして「彼を愛おしいと思う心」が、泥のように流れ出していく。
心地よい痺れ。
私の魂の一部が、彼を構成する肉(にく)になる。
ドクン、とレンの喉仏が大きく動いた。
その瞬間だった。
世界から、音が消えた。
縁の指先から、先ほどまで感じていた温もりが急速に冷えていく。
目の前に座る男の顔色が、蝋人形のような白さから、生々しい血色を帯びた肌色へと変わる。
ガラス玉のようだった瞳に、人間らしい理性の光が宿る。
それと引き換えに。
(……え?)
縁は、自分の手にあるガラスのピアスを見下ろした。
ただのガラスだ。
なぜ、こんな物を持っているのだろう。
直前まで胸を満たしていたはずの「愛おしさ」が、スプーンで抉り取られたようにゴッソリと消えている。
「縁、ありがとう。これで僕は……」
男が何かを言いかけた。
縁は口を開こうとした。名前を呼ぼうとした。
けれど、声帯が凍りついたように動かない。
喉の奥で「誰?」という言葉だけが空回りする。
目の前の男が、急激に知らない他人になる。
彼と交わしたはずの「紫陽花を見に行く」という約束の意味が、脳のシナプスから物理的に切断される。
ただの音の羅列になり、砂のように崩れ落ちていく。
寒い。
心臓の真ん中に風穴が開いたように寒い。
縁が瞬きをした次の瞬間、対面の椅子は空っぽだった。
飲みかけのコーヒーと、意味のわからなくなったガラスのゴミだけが、テーブルに残されていた。
第三章 最後の糸
季節が三つ、過ぎ去った。
縁のスマホのアイコンは、もはや元のハートマークが見えないほど、赤黒い糸で雁字搦(がんじがら)めになっていた。
極彩色の曼荼羅。けれどその中心だけが、底なしの井戸のように黒くぽっかりと空いている。
「待たせたね」
待ち合わせ場所に現れた男は、くたびれたジャケットを羽織っていた。
名前は「ケイ」。
匂わない。歪んでいない。影も一つしかない。
(人間……?)
縁が警戒して一歩退くと、ケイは困ったように眉を下げた。
「風が冷たい。中に入ろう。……君は、窓際の席が好きだろう?」
ケイは縁の返事も待たず、迷いなく店の奥にある、死角になった窓際の席へと歩き出した。
まるで、縁がいつもそこを選んで座ることを知っているかのように。
席に着くと、彼はメニューも見ずに店員を呼んだ。
「ブレンド二つ。片方はミルクなし、砂糖二つで」
縁の心臓が、早鐘を打った。
それは、誰にも言ったことのない私の黄金比だ。
「……あなた、何者?」
震える声で問うと、ケイは静かにポケットから何かを取り出した。
それは、縁がいつか失くしたと思っていた、お気に入りの万年筆だった。
キャップには、小さな傷がついている。縁が昔、落としてつけた傷だ。
「よく文字が掠れるんだったね。修理に出しておいたよ」
ケイは慈しむような手つきで、それをテーブルに置いた。
縁の視界が、滲む。
知らない。
この人が誰なのか、私は知らない。
いつ万年筆を預けたのか、どんな会話をしたのか、記憶の図書館は空っぽだ。燃え尽きた跡すらない。
けれど、体が覚えている。
彼がカップを持ち上げる仕草。
笑うと目尻に寄る皺。
そのすべてに、魂が共鳴して震えている。
理由のわからない涙が、頬を伝って止まらない。
(ああ、そうか)
縁は悟った。
私の記憶がないのは、忘れたからじゃない。
全部、彼にあげてしまったからだ。
私が彼を「人間」にするために、私たちが過ごした日々の全てを、彼という存在の核(コア)として埋め込んだのだ。
ケイは何も説明しなかった。
ただ、テーブル越しに手を伸ばし、縁の涙を親指で拭った。
その指は温かく、わずかにインクの匂いがした。
「行こうか、縁」
ケイが立ち上がり、右手を差し出す。
縁はその手を見つめた。
この手を取れば、私は「過去」を持たないまま、「未来」へと歩き出すことになる。
空っぽの記憶の器を、これから二人で作る新しい時間で満たしていくのだ。
縁はスマホを取り出し、テーブルに置いた。
画面の中で、赤黒い糸の塊がほどけ、光の粒子となって消えていく。
彼女は、ケイの手を強く握り返した。
無機質なプラスチックの筐体が取り残されたテーブルの上で、スマホの画面がスリープモードに入る。
暗転した黒い鏡面には、寄り添って歩き出す男女の姿が、一瞬だけ映り込んでいた。