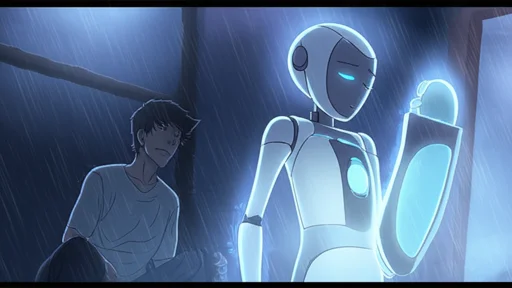第一章 硝子の心臓
「ねえ、エオス。きみ、また忘れたでしょ」
風が、乾いた砂の匂いを運んでくる。
少女の声に振り返ると、栗色の髪が茜色の空に溶けるように揺れていた。
エララだ。
彼女の瞳が、どこか縋るように僕を見つめている。
「忘れたって、何を?」
僕は首を傾げた。
右手に握りしめた真鍮製の筒――『記憶の万華鏡(アムネシア・スコープ)』が、ひどく冷たい。
まるで死人の指を握っているような錯覚を覚え、僕は慌てて持ち直した。
「昨日の晩ごはんよ。あんなに美味しいって、二人で笑いながら食べたじゃない」
エララは唇を尖らせて笑ってみせたが、その表情はすぐに崩れそうだった。
喉の奥がつかえる。
「ああ……そうだったかな。ごめん」
思い出せない。
昨日の夕食の味も、香りも。
それどころか、昨日という一日が丸ごと、黒いインクをぶちまけたように塗りつぶされている。
胃の中に、鉛のような重たい空白だけがある。
「……次のお客さん、待ってるよ」
エララが視線を逸らし、顎で前方を示した。
崩れかけた石壁の陰に、一人の老婆がうずくまっている。
肌はひび割れた陶器のように白く、瞳からは光が失われていた。
この世界は『黄昏』に停滞している。
空には物理的な太陽はなく、地平線から湧き上がる光の粒子が、世界をかろうじて照らしていた。
記憶こそが光源であり、生命線だ。
忘却は、すなわち死を意味する。
僕は老婆の前に膝をついた。
「おばあさん。大切なものが、見えなくなってしまったんですね」
老婆は緩慢な動作で顔を上げた。
その目は、深い井戸の底のように暗い。
「夫の……顔が……。あんなに愛していたのに、思い出そうとすると、顔のパーツが泥のように溶けてしまうのじゃ……」
「大丈夫です。僕が、ピントを合わせます」
僕は万華鏡を構えた。
冷たい接眼レンズを右目に押し当てる。
左目を閉じ、呼吸を止める。
世界から音を遮断する。
カチリ。
万華鏡の先端にあるダイヤルを回す。
指先に伝わる微細な振動。
暗闇の中に、無数の光の破片が舞い上がった。
老婆の脳内にある記憶の残滓だ。
多くは煤け、灰色に濁っている。
僕はさらにダイヤルを回す。
指先が擦り切れるほど繊細に、焦点を探る。
瓦礫の山のような記憶の奥底。
そこに、今にも消え入りそうな、琥珀色の小さな灯火があった。
「……見つけた」
僕は万華鏡の焦点を、その一点に固定する。
言葉はいらない。
ただ、強く念じるだけだ。
この灯火を、燃え上がらせろと。
僕は筒を握る手に力を込め、一気に魔力を流し込んだ。
万華鏡から光の粒子が噴き出し、老婆を包み込む。
音のない旋律が響く。
空間に、鮮やかな『過去』が結像した。
一面のひまわり畑。
夏の草いきれ。
土の匂い。
若い頃の老婆と、照れくさそうに笑う大柄な男性。
男性の太い指が、不器用に小さな指輪を差し出している。
老婆の瞳に、色が戻る。
ひび割れた肌に赤みが差す。
「ああ……あなた……! そうじゃ、その笑い方……」
老婆が震える手で、虚空の映像に触れようとする。
目尻からこぼれ落ちた涙が地面に吸い込まれ、そこから小さな青い花が芽吹いた。
記憶という名のエネルギーが、世界を潤していく。
「ありがとう、旅人さん……ありがとう……」
老婆が僕の手を握りしめる。
温かい。
節くれだった指の感触。
生きている人間の熱。
その瞬間だった。
僕の頭の芯で、何かが濡れた音を立てて千切れた。
「ぐッ……」
激痛ではない。
もっと根源的な喪失。
脳みそをスプーンでひとすくい、ごっそりと抉り取られたような感覚。
吐き気がこみ上げる。
視界が歪む。
今さっきまで鮮明だった母の顔が、突然、のっぺらぼうに変わった。
母が作ってくれたスープの温かさが、冷たい泥水の感触へと変質する。
僕という人間を形成していたピースが、また一つ、永遠に欠落した。
「エオス!」
エララの悲鳴のような声。
彼女の腕が僕を支える。
その体温だけが、僕を現実に繋ぎ止める楔(くさび)だった。
「だい……じょうぶだ、エララ」
僕は荒い息を吐き、万華鏡を胸ポケットに押し込む。
脂汗が頬を伝う。
「何が大丈夫なもんか! 顔色が紙みたいに白いじゃない!」
「平気さ。慣れてる……」
僕はふらつく足で立ち上がり、エララの胸元で揺れる青い石を見た。
綺麗なペンダントだ。
あれは、どこで手に入れたものだったか。
「ねえ、エララ。その石……いい色だね。いつ買ったんだっけ?」
何気ない問いかけのつもりだった。
けれど、エララの表情が凍りついた。
彼女は胸元の石をきつく握りしめ、泣きそうな、それでいて僕を責めるような目で睨みつけた。
「……これは、あなたがくれたのよ。先月の誕生日に。『きみの瞳と同じ色だ』って言って」
「あ……」
思考が停止する。
自分が選んだ贈り物。
彼女にかけた言葉。
その瞬間のときめき。
すべてが、僕の中から消え失せていた。
ただの空洞がそこにあるだけだった。
「ごめん……」
自分の手が、ひどく薄汚れたものに見える。
僕が世界を救うために支払っているのは、僕自身そのものだ。
「謝らないでよ……バカ」
エララは涙をこらえ、僕の手を強く引いた。
「行こう。日が暮れちゃう。この世界が、闇に飲まれる前に」
彼女の掌は熱く、痛いほど強かった。
僕が僕でなくなっていく恐怖を、その痛みだけがかき消してくれた。
第二章 忘れられたノイズ
旅は続く。
灰色の荒野を、僕たちはただ歩く。
会話が途切れるたび、僕は自分が何者かを確認するように、エララの横顔を盗み見た。
「ねえ、エオス」
エララがぽつりと呟く。
「この旅が終わったら、どこに住もうか」
「え?」
「だから、家よ。海の見える丘がいいな。毎日、潮風が入ってくるような窓辺で、あなたが本を読んで、私がシチューを作るの」
彼女は努めて明るく振る舞っている。
それが逆に、胸を締め付けた。
「……そうだね。海がいいな」
僕は同意する。
だが、僕の中にある『海』の概念は、すでにぼやけていた。
青いのか、黒いのか。
しょっぱいのか、甘いのか。
言葉としての知識はあっても、感覚としての記憶がない。
やがて、僕たちは奇妙な廃墟にたどり着いた。
地図にも、誰の記憶にもない場所。
巨大な鉄の墓標のようなビル群が、傾きながら空を突き刺している。
だが、おかしい。
通常の廃墟なら漂っているはずの『生活の匂い』がない。
人々の想いや未練といった残留思念が、ここには一切存在しなかった。
あるのは、完全な無機質と、耳鳴りがするほどの静寂。
「気味が悪いわ……」
エララが身を震わせ、僕の腕にしがみつく。
足元の瓦礫を蹴ると、乾いた音が虚しく響いた。
僕は万華鏡を取り出し、周囲を覗き込む。
レンズ越しに見える世界に、戦慄が走った。
美しい幾何学模様を描くはずの光の粒子が、ここでは黒く濁り、ノイズのように激しく明滅している。
まるで、傷んだフィルム映像のように。
「うぐっ……!」
万華鏡を覗いた右目に、焼けるような痛みが走った。
反射的に手を離そうとしたが、万華鏡が手に吸い付いたように離れない。
「エオス!?」
「見るな、エララ! 目を閉じろ!」
叫ぶと同時に、僕の視界が黒い奔流に飲み込まれた。
『エラー……データ破損……』
『強制消去(パージ)を開始します』
機械的な音声が脳内に直接響く。
続いて、網膜に焼き付けられる惨劇のフラッシュバック。
白い塔。
無機質な実験室。
並べられたガラスケースの中で眠る、数えきれないほどの人間たち。
白衣を着た男たちが、無表情にスイッチを押す。
『不要な記憶データを削除。容量を確保』
次の瞬間、ガラスケースの中の人間たちが、音もなく崩れ落ちた。
血の赤さはない。
ただ、データの塵となって霧散していく。
彼らの絶望、恐怖、生きた証が、「ゴミ」として処理されていく光景。
「は、ぁ……ぁ……!」
僕は膝をつき、嘔吐した。
胃液と共に、恐怖が逆流してくる。
見えた。
見てしまった。
瓦礫の陰に、半透明の子供の幻影が立っている。
その顔には目も鼻もなく、ただ黒い穴が開いているだけだ。
『ボクタチハ、ココニイタ』
『ケサナイデ』
子供の影が、僕に向かって手を伸ばしてくる。
その手は焼け爛れ、指先からノイズが滴り落ちていた。
「いやだ……来るな……!」
「エオス! しっかりして! 何が見えてるの!?」
エララが僕の肩を揺さぶる。
現実と幻覚の境界が曖昧になる。
「違うんだ……エララ……この世界は……」
僕は震える唇で、言葉を紡ぎ出す。
推測ではない。
確信だった。
内臓の底から湧き上がる、おぞましい真実。
「ここは楽園なんかじゃない。……ここは、巨大な『処分場』だ」
黒いノイズが、ついに実体を持って襲いかかってくる。
無数の腕が、僕の足首を掴む。
冷たい。
絶対零度の冷気が、骨まで凍らせる。
「くそっ!」
僕は万華鏡を構え直す。
癒やすんじゃない。
戦うんだ。
彼らの『無念』を、光に変えて焼き払うしかない。
僕はダイヤルを、軋むほど強く回した。
自身の魂を削り、燃料にする。
僕の中の『幼少期の記憶』が、音を立てて崩落していく。
父の声が消える。
初めて自転車に乗った日の風が消える。
友人の名前が消える。
「消えろぉおおおおッ!!」
万華鏡から放たれた閃光が、黒い影を薙ぎ払う。
断末魔のようなノイズを残し、影は霧散した。
静寂が戻る。
僕は地面に倒れ込んだ。
万華鏡のレンズに、亀裂が走っていた。
「エオス……」
エララが僕を抱き起こす。
彼女の涙が、僕の頬に落ちた。
熱い。
この熱さだけが、唯一の真実だ。
「……ねえ、エララ」
僕は虚ろな目で空を見上げた。
「僕たちが守ってきた『綺麗な記憶』は、誰かの都合で選別されたデータに過ぎなかったんだ。都合の悪い悲劇を消去して、美しい嘘だけで塗り固めた……」
「もういいわ。喋らないで」
「そして僕は……その『削除機能』を端末化しただけの存在なんだろうな」
だから、僕には過去がない。
だから、僕の記憶は簡単に上書きされる。
僕は人間じゃない。
ただのシステムの一部だ。
「違う!」
エララが叫んだ。
彼女は僕の顔を両手で挟み、正面から見つめた。
「あなたの手は温かいわ。あなたは泣いたり、笑ったり、怒ったりする。それが人間でなくて何なのよ! たとえ世界が偽物でも、私とあなたが過ごした時間だけは本物よ!」
彼女の瞳に、僕の顔が映っている。
ひどく疲れ切った、しかし確かに生きている男の顔が。
「……エララ」
「行こう、エオス。最後まで。あなたが誰でも構わない。私はあなたと一緒にいたいの」
彼女の声が、凍りついた心臓を溶かしていく。
僕は彼女の手を握り返した。
強く、指が白くなるほどに。
第三章 最後の夜明け
世界の崩壊は、音もなく加速していた。
空の茜色が剥がれ落ち、その向こう側に広がる『無』の暗黒が露出している。
地面からは黒いノイズが湧き出し、村々を、森を飲み込んでいく。
記憶の限界容量(オーバーフロー)。
世界というサーバーが、悲鳴を上げている。
僕たちは、世界の中心に聳える『記憶の塔』の前に立っていた。
光の粒子が螺旋を描いて空へと昇る、この世界の心臓部。
「エオス、待って」
塔へ続く橋のたもとで、エララが立ち止まった。
彼女の顔は蒼白で、唇が震えている。
「ここから先へ行ったら……もう戻れないんでしょう?」
彼女は感づいていた。
僕が何をしようとしているのか。
「僕が行かなきゃ、世界は完全に崩壊する。きみも、きみの家族も、あのお婆さんも……みんな消えてしまう」
「でも、あなたが消えちゃう! 全部忘れて……自分自身がなくなって……そんなの死ぬより辛いじゃない!」
エララが僕の胸に縋り付く。
彼女の涙が、僕のシャツを濡らす。
「あなたがいなくなる世界なんて、私には意味がないわ! 世界なんか救わなくていい、逃げようよ、ねえエオス!」
「エララ……」
僕は彼女の背中に腕を回し、一度だけ強く抱きしめた。
彼女の匂い。
柔らかさ。
鼓動の音。
これを記憶に残すことはできない。
だから、魂に刻み込む。
「ごめんね」
僕は万華鏡を取り出した。
ボロボロで、真鍮のメッキは剥げ、レンズはひび割れている。
僕のボロボロの心そのものだ。
「これを……」
僕は万華鏡を彼女に渡そうとした。
いや、渡すべきだと思った。
これさえなければ、僕はただの男として、彼女と最期の瞬間まで一緒にいられるかもしれない。
エララの手が伸びる。
だが、その指先が万華鏡に触れる直前、僕は手を引っ込めた。
「エオス?」
「……やっぱり、これは僕が持っていくよ」
僕は万華鏡を強く握りしめた。
これは僕の呪いであり、僕の存在証明だ。
僕が僕であるための、最後の欠片。
「嫌よ! 置いていかないで!」
エララが僕の腕を掴む。
僕は歯を食いしばり、彼女の手を振りほどいた。
「行け、エララ! 離れるんだ!」
「エオスッ!!」
僕は彼女に背を向けた。
振り返ってはいけない。
振り返れば、決意が揺らぐ。
僕の足は、意思とは裏腹に鉛のように重い。
「ねえ、エオス! 大好きよ! ずっと、ずっと大好きだったのよ!」
背後から聞こえる、悲痛な叫び。
その言葉が、僕の胸を貫く。
『大好き』。
その言葉の意味を、感覚を、僕はまだ覚えているだろうか。
「……僕もだ」
声にならなかった。
風だけが、僕の呟きをさらっていく。
僕は塔の光の中へと足を踏み入れた。
眩い光が視界を覆う。
身体が軽くなる。
指先から、足先から、光の粒子になって解けていく感覚。
ああ、これが消滅か。
意外と、怖くない。
ただ、少し寒い。
僕の名前は……なんだっけ。
ああ、思い出せない。
大事な人の名前があったはずだ。
栗色の髪の……笑顔が素敵な……。
思考が白に染まる。
最後に残ったのは、ただ一つの温もりだけ。
誰かの手を握った時の、確かな熱。
それもやがて、白い光の中に溶けて消えた。
最終章 名もなき旅人
あれから、どれくらいの季節が巡ったのだろう。
世界は生まれ変わった。
空は抜けるように青く、雲がゆっくりと流れている。
かつての『黄昏』も、崩壊の危機も、今では遠い昔のお伽噺だ。
風の吹く丘の上の広場で、一人の旅人がベンチに腰掛けていた。
使い古したローブを纏い、フードを目深にかぶっている。
彼は何も持っていない。
名前も、過去も、行く当ても。
ただ、ふらりと現れ、子供たちの遊ぶ姿を遠くから眺めては、また何処かへ去っていく。
自分が何者かを知ろうともせず、ただ『何か』の気配を探すように。
「あ、旅人さん!」
広場を走り回っていた子供たちが、旅人の周りに集まってきた。
彼らの手の中には、小さなガラス玉がある。
「これ見て! すっごく綺麗なんだよ!」
一人の少女が、旅人の目の前にガラス玉を差し出した。
それは太陽の光を吸い込んで、内側から温かな輝きを放っている。
「……綺麗だね」
旅人は掠れた声で呟いた。
言葉を発するのは久しぶりだった。
喉が渇いているような、不思議な感覚。
「これね、昔、世界を救った英雄さんが残してくれた光なんだって!」
少女は目を輝かせて言う。
「英雄さんはね、自分の記憶を全部ぜーんぶあげて、僕たちを守ってくれたの。だから僕たちは、英雄さんのことを忘れないように、みんなで少しずつ、英雄さんの思い出を持ってるんだよ」
「……思い出を? 他人の?」
旅人は首を傾げた。
意味がよくわからなかった。
だが、そのガラス玉の光を見た瞬間、胸の奥底で何かがドクリと脈打った。
古傷が疼くような、それでいて懐かしい痛み。
少女が、旅人の手を取り、そっとその光の玉を乗せた。
「あげる。旅人さん、なんだか泣きそうな顔してるから」
掌に、光が触れる。
その瞬間。
世界が震えた。
映像ではない。
言葉でもない。
圧倒的な『温度』が、空っぽだった彼の器に奔流となって流れ込んでくる。
『大好きよ』
『ありがとう』
『また会おうな』
『元気でね』
無数の声。
無数の感謝。
そして、栗色の髪の少女が、くしゃくしゃの泣き顔で笑っている姿。
それは、彼自身が失い、世界へと捧げたはずの欠片。
世界中の人々が、彼の代わりに大切に守り続け、語り継いできた、彼自身の『一番大切な思い出』。
「あ……」
旅人の目から、大粒の涙が溢れ出した。
頬を伝い、光の玉に落ちて弾ける。
なぜ泣いているのか、彼にはわからない。
自分が誰なのかも、思い出せない。
あの栗色の髪の少女が誰なのかも。
けれど、愛おしくてたまらない。
胸が張り裂けそうなほど、温かい。
「泣いてるの?」
少女が心配そうに覗き込む。
旅人は、濡れた顔を袖で拭い、静かに微笑んだ。
それは、かつて世界を癒やした、あの優しい笑顔だった。
「いいや……ただ、とても温かいんだ」
彼は光の玉を、胸のポケットにそっとしまった。
そこには、ボロボロにひび割れた、しかし今や黄金色に輝き始めた、真鍮の筒が眠っていた。
いつの間にか、彼の手はその筒をしっかりと握りしめていた。
「ありがとう」
旅人は立ち上がり、風の吹く方角を見つめた。
どこか遠くで、誰かが呼んでいる気がした。
海が見たい、とふと思った。
彼は一歩を踏み出す。
その足取りは、もう孤独ではなかった。
世界中が、彼を覚えている。
彼が彼を忘れても、愛だけは、決して消えずに巡り続けるのだから。