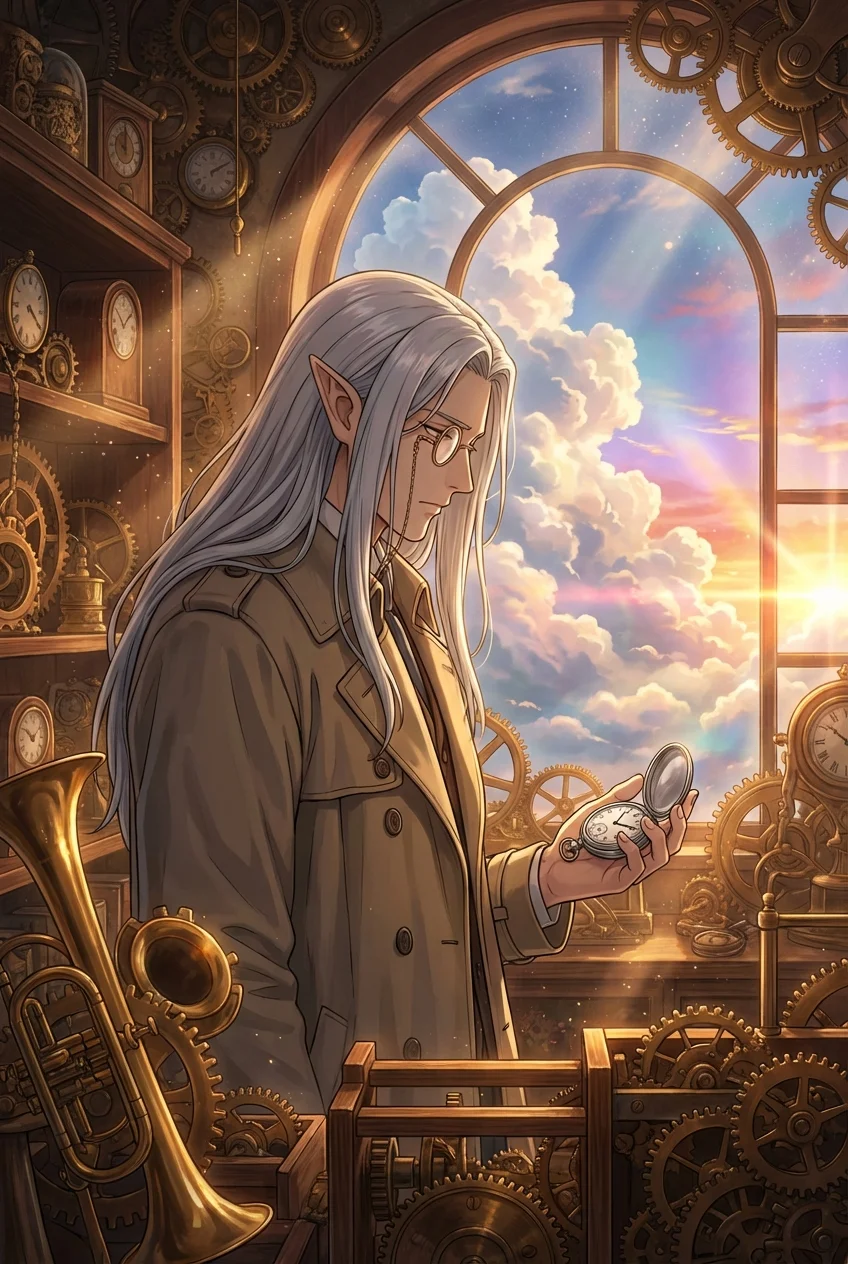第一章 条件反射と震える指先
背中に張り付く冷たい岩肌の感触で、意識が浮上した。
鼻腔を刺すのは、腐った雑巾のような湿気と、鉄錆の臭いだ。
「ッ……」
佐野悟は咳き込みながら上体を起こした。
スーツの生地が擦れる音だけが、やけに大きく響く。
視界が悪い。天井には蛍光灯などなく、青白い粘液を垂らす苔が、墓標のようにぼんやりと列を成しているだけだった。
左手首に、冷ややかな締め付けを感じた。
黒い樹脂製のバンド。安っぽいデジタル表示。
かつて『アビスコンサルティング』で全社員に強制支給されていた、「無限残業タイマー」だ。
だが、表示がおかしい。
液晶のバックライトが、不吉な赤色に明滅している。
『SAN値:限界突破』
『現在の幸福度:E-(供給不足)』
「なんだ、これ……」
ズズッ、ズリッ。
闇の奥から、何かが床を擦る音がした。
佐野は息を呑み、目を凝らす。
緑色の肌。子供ほどの背丈。
汚れた腰布を巻いたそれは、ファンタジー映画の「ゴブリン」そのものだった。
だが、怪物は襲ってこなかった。
佐野の足元まで這いずると、持っていた欠けたツルハシを取り落とし、その場に崩れ落ちたのだ。
「ギ……、ギギ……」
ゴブリンが顔を上げる。
佐野の背筋が凍りついた。
その瞳には、焦点がなかった。
白く濁り、乾いた目ヤニがこびりつき、眼窩は骸骨のように窪んでいる。
痙攣する唇からは、涎が糸を引いていた。
その顔が、鏡の中の自分と重なる。
三日連続の徹夜明け、駅のトイレで見た、あの死人のような自分の顔と。
「おい、立てよ!」
佐野の口から、怒声が迸った。
思考するより先に、身体が動いていた。
ブラック企業で十年かけて骨の髄まで染み付いた「管理職の条件反射」だ。サボっている部下を見れば、怒鳴るように回路が焼き付けられている。
「まだノルマが終わってないだろ! 休憩時間はとっくに――」
ビクッ、とゴブリンが肩を跳ねさせた。
細い腕で頭を抱え、床に額を擦り付けて震え始める。
怯えきった獣のような、その仕草。
「あ……」
佐野の喉で、言葉が詰まった。
俺は、何をしている?
こいつはモンスターだ。だが、その震えは、かつて上司の革靴の前で縮こまっていた、俺そのものじゃないか。
吐き気がした。
自分自身への嫌悪感で、胃液が逆流しそうになる。
佐野は震える手で、手首のタイマーを掴んだ。
側面に小さなボタンがある。
これを押せば何が起こるか分からない。警報が鳴り、自分が処分されるかもしれない。
恐怖で指先が強張り、うまく力が入らない。
それでも、佐野は目の前の惨状から目を逸らせなかった。
ゴブリンの、痩せこけたあばら骨が上下している。
「……休憩だ」
掠れた声が出た。
「業務命令だ。休め」
カチリ。
脂汗の滲む指で、ボタンを押し込む。
液晶の文字が高速でスライドした。
《福利厚生モード:強制執行》
《休憩室ランク:S》
ブォン、と低い音が空間を揺らす。
天井の青白い苔が、一瞬にして暖かなオレンジ色へと変化した。
冷え切っていた空気が、柔らかな陽だまりのような温度を帯びる。
「ギ?」
ゴブリンが顔を上げた。
濁っていた瞳に、オレンジの光が映り込む。
強張っていた緑色の肩から、ふっと力が抜けていくのが見えた。
その瞬間、タイマーが軽快な音を立てた。
『システム通知:良質なエネルギーを回収』
『ダンジョン評価:微増』
佐野はへたり込んだ。
心臓が早鐘を打っている。
だが、温かな空気の中で深呼吸をしたとき、肺の奥に溜まっていた黒い澱が、少しだけ薄れた気がした。
「……ここでは、俺がルールだ」
佐野は、まだ微かに震える拳を握りしめた。
-----
第二章 カップの縁を叩く音
「ボス! タナカさんがまた過呼吸です!」
「なんでだよ! 有給休暇をとれって言っただろ!」
佐野は岩窟の回廊を走り抜けた。
あれから三ヶ月。
このダンジョンの改革は、困難を極めていた。
当初、佐野が週休二日制を導入しようとした際、モンスターたちはパニックに陥ったのだ。
『休む=不要な存在として処分される』という恐怖が染み付いており、ツルハシを取り上げると泣き叫び、隠れて採掘を始める始末だった。
佐野は、一から教え込まなければならなかった。
休むことは罪ではないこと。
温かいスープを飲み、ふかふかの苔ベッドで眠ることで、翌日のパフォーマンスが上がること。
「タナカ! しっかりしろ!」
休憩室に駆け込むと、巨躯のハイオークが、真新しいソファの上で震えていた。
「ブモォ……(申し訳ナイ、申し訳ナイ……)」
「謝るな。お前が昨日掘り当てたレアメタルのおかげで、今期の目標値は達成済みだ。だから、今はスープを飲め」
佐野はオークの分厚い手に、湯気の立つマグカップを握らせた。
岩塩と香草の香りが漂う。
タナカは恐る恐るそれを口にし、やがて、その豚のような瞳から大粒の涙をこぼした。
「ブモォ……(美味イ……)」
「ああ、そうだ。美味いんだよ」
佐野はタナカの背中をさすった。
その温もりが、佐野自身の手のひらをも癒やしていく。
効率化の果てにあったのは、数字の羅列ではなく、この笑顔だったのだ。
その時だった。
休憩室の入り口に、ゆらりと黒い影が現れた。
新人の『シャドウストーカー』だ。
言葉を持たず、漆黒の霧のような身体を持つ不定形のモンスター。
一週間前に配置されたばかりだが、その動きに、佐野はずっと違和感を抱いていた。
シャドウストーカーは、支給されたコーヒーのカップを手に取ると、飲む前に必ず、人差し指でカップの縁を二回叩くのだ。
カツ、カツ、と。
佐野の脳裏に、記憶がフラッシュバックする。
残業続きの深夜のオフィス。
自販機コーナー。
泥水のようなコーヒーを飲む前に、必ずカップを二回叩いて「よし」と呟く男。
入社三年目の佐藤。
佐野の隣の席で、誰よりも真面目に働き、そしてある日突然、「実家に帰る」と言って姿を消した男。
まさか。
佐野はゆっくりと影に近づいた。
「……佐藤、なのか?」
影が揺らぐ。
のっぺらぼうの顔が、こちらを向いた。
カツ、カツ。
シャドウストーカーは、もう一度カップを叩いた。
そして、闇の中から絞り出すような音が響く。
『サ……ノ……サ……ン……』
ドクン、と心臓が跳ねた。
佐野の手首で、タイマーがけたたましい警告音を発する。
『警告:従業員リソースの元データを検知』
『識別ID:アビスコンサルティング元社員・佐藤健二』
『現在の状態:魂の搾取率 98%』
「ふざけるな……っ!」
佐野は愕然として膝をついた。
視界が赤く染まる。
このダンジョンは、異世界などではなかった。
現実世界のブラック企業が、使い潰した社員の精神(リソース)を再利用し、最後の滴までエネルギーとして吸い上げるための、地獄の最下層だったのだ。
タナカも、あのゴブリンも。
みんな、どこかで死ぬほど働かされた誰かだったのか。
「こんな……こんなことが許されてたまるかよ!」
佐野の叫びに呼応するように、タナカが立ち上がる。
シャドウストーカーが、その闇の腕を佐野の肩に置いた。
そこには、確かな体温があった。
「ブモッ!(やるぞ、ボス)」
『コワ……ス……』
彼らの目には、もう恐怖はなかった。
あるのは、理不尽に対する静かな怒りと、覚悟だ。
佐野は涙を拭い、タイマーを睨みつけた。
画面には、皮肉にもこう表示されている。
『幸福エネルギー充填率:限界突破間近』
「……そうか。このシステムは、俺たちの『絶望』をちびちび吸い上げるように設計されている」
佐野はニヤリと笑った。
それはもう、死んだ魚の目をした社畜の顔ではなかった。
「なら、喰わせてやろうぜ。回路が焼き切れるほどの、特大の『幸福』を」
-----
第三章 ハッピー・オーバーフロー
最深部「コア・ルーム」。
巨大な水晶体が、不気味な紫色の光を放ちながら回転している。
ここが、現実世界のアビス本社へエネルギーを送る心臓部だ。
佐野はタイマーのダイヤルを最大まで回した。
「総員、聞け! これより特別ボーナスを支給する!」
佐野の声が、集まった数百のモンスターたちに響き渡る。
「残業代の未払い分、全額精算! 有給消化率200%! さらに、退職金代わりの『感謝』を上乗せだ!」
佐野はタイマーの「福利厚生リミッター」を解除した。
禁断の全開放。
『警告:幸福度が許容値を逸脱しています』
『警告:エネルギー過多。コンデンサが耐えきれません』
「知るか! 受け取れぇぇぇ!!」
佐野がボタンを叩き込む。
瞬間、ダンジョン全体が黄金の光に包まれた。
それは、タナカがスープを飲んだ時の喜び。
佐藤がコーヒーを飲んだ時の安らぎ。
そして、彼らが互いに交わした、労りと信頼の温もり。
「ブモォォォォォオオオオ!!(ありがとう、ボスゥゥゥ!!)」
モンスターたちの咆哮が、歓喜の波動となって水晶体に殺到する。
紫色の光が、黄金の輝きに飲み込まれていく。
「搾取」のために作られた細いパイプに、「幸福」という名の濁流が押し寄せたのだ。
バチバチバチッ!
水晶体に亀裂が走る。
空間が悲鳴を上げた。
『システムエラー:幸福過多によりシステムダウン』
『強制シャットダウン……不可……崩壊……』
「いけええええええ!!」
カッッッ!!!
鼓膜を突き破るような破砕音と共に、水晶体が粉々に砕け散った。
強烈な閃光が視界を白く塗り潰す。
地面が消える。天井が溶ける。
佐野の身体も、光の粒子となって分解されていく。
隣を見ると、佐藤の姿をした影が、人間の姿に戻りかけていた。
眼鏡をかけた、気の弱そうな青年が、泣きながら笑っている。
タナカも、ゴブリンたちも、光の中で穏やかな顔をして空へ昇っていく。
(ああ……やっと、定時上がりだ……)
佐野は光の中で目を閉じた。
不思議と、恐怖はなかった。
ただ、温かいスープの味が、口の中に残っていた。
***
「……ん」
風の音で目が覚めた。
アスファルトの冷たさと、排気ガスの臭い。
佐野は、新宿の高層ビル街の片隅で倒れていた。
スーツはボロボロで、何日も風呂に入っていないような臭いがする。
だが、身体は羽のように軽かった。
左手を見る。
あの忌々しいタイマーは消滅していた。
代わりに、掌には微かな熱が残っている。誰かと固く握手をしたような、確かな感触。
通りの向こうにある巨大なビル――アビスコンサルティングの本社ビルから、黒い煙が上がっているのが見えた。
サイレンの音が近づいてくる。
スマホを取り出すと、ニュース速報が画面を埋め尽くした。
『アビスコンサルティング、メインサーバーが謎の熱暴走』
『全データ消失、粉飾決算の証拠が流出か』
『意識不明だった社員たちが、一斉に意識を取り戻す奇跡』
「ざまあみろ」
佐野は呟き、ネクタイを引き千切った。
空を見上げる。
ビルの隙間から覗く空は、ダンジョンの天井なんかよりずっと高く、突き抜けるように青かった。
「さてと」
佐野は立ち上がり、ポケットに入っていたくしゃくしゃの名刺を破り捨てて、風に放った。
紙片が、桜の花びらのように舞い上がる。
世界はまだクソみたいに厳しいかもしれない。
けれど、もう怖くはない。
見えないけれど、背中を押してくれる手がたくさんあるのを感じるから。
タナカの分厚い手、佐藤の細い指。
「新しいシステム、作りに行くか」
佐野は雑踏の中へ歩き出した。
その足取りは力強く、二度とあのような場所へは戻らないという、確固たる意志を刻んでいた。