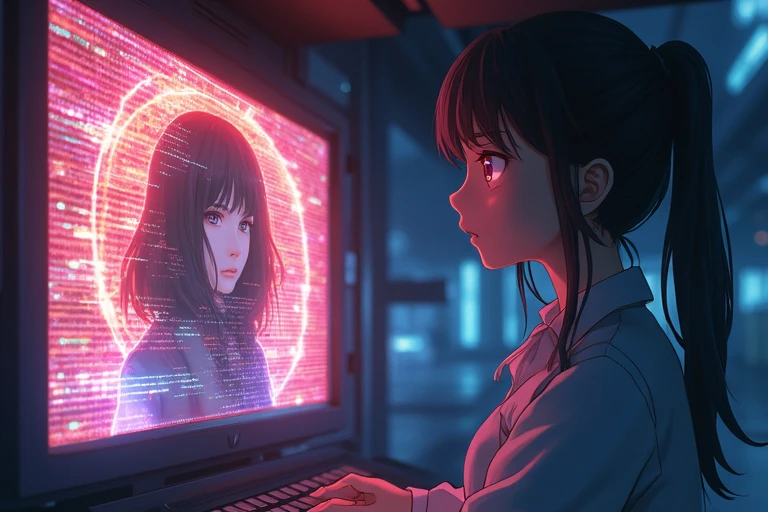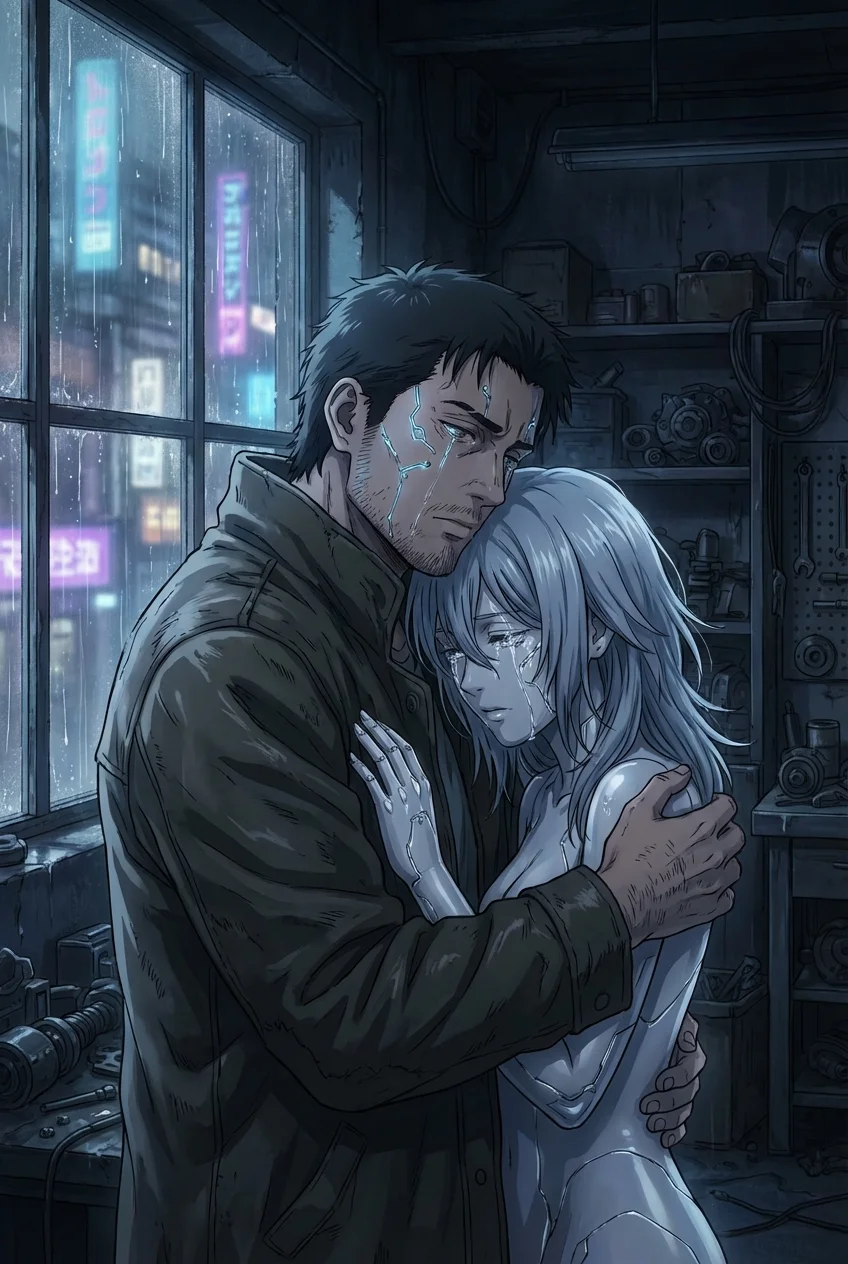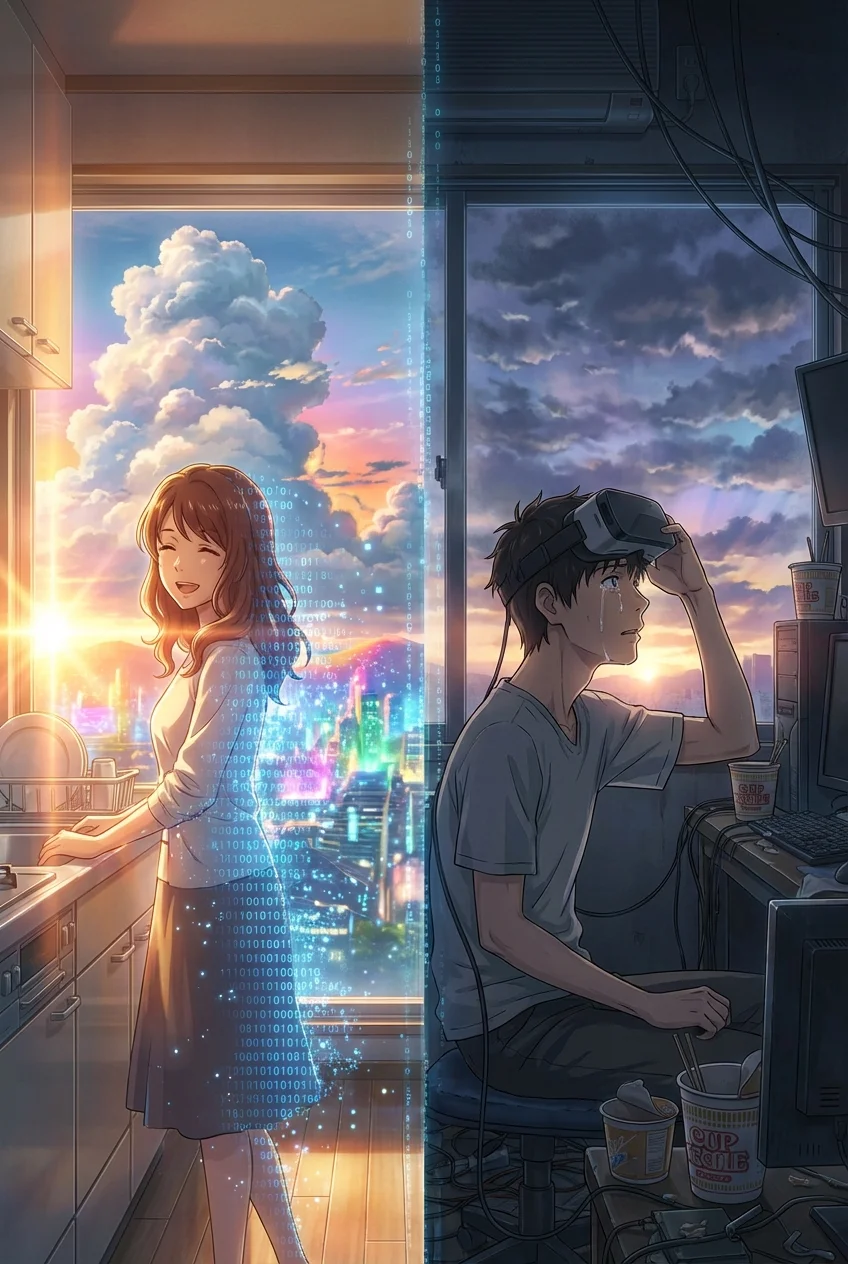午前二時、合わせ鏡の奥に死神が見えるという。
俺が見たのは、ただの寝癖のついた自分の顔と、その背後でピースサインをする『何か』だった。
「おい、映り込み。邪魔だぞ」
俺がそう呟くと、鏡の中の影は呆気にとられたように歪み、霧散した。
第一章 5G回線のメリーさん
雨上がりのアスファルト特有の、湿った匂いが鼻をつく。
放課後の旧校舎。本来なら立ち入り禁止のこの場所は今、異界と化していた。
「っ……速い!」
悲鳴を上げたのは、俺の相棒であり、自称『霊能美少女』の相沢ヒマリだ。
彼女の周囲を、赤黒い影が高速で旋回している。
『私、メリーさん。今、校門にいるの』
ヒマリのスマホが震える。
通知音の不協和音が、鼓膜を不快に叩く。
「レン、助けてよ! こいつアップデートされてる! 瞬間移動なんて聞いてない!」
ヒマリが霊符を構えるが、影は嘲笑うかのようにその背後を取る。
錆びついた鉄の臭いが濃くなる。
メリーさんが持っているのは電話線じゃない。切れ味鋭い鎌だ。
俺はポケットからスマホを取り出し、あくびを一つ。
「ヒマリ、落ち着け。今の怪異の設定、ガバガバすぎるだろ」
「はあ!? 命の危機に何言ってんの!」
俺、九条レンの特技は『除霊』ではない。
『論破』だ。
俺は迫りくる鎌を見据え、気だるげに言い放つ。
「おい、メリー。お前、固定電話の妖怪だろ。なんで5G回線使って位置情報取得してんだよ。設定崩壊もいいとこだぞ」
その瞬間、空間に走っていたノイズがピタリと止まった。
第二章 存在証明のパラドックス
怪異とは、人の噂が形を成したものだ。
つまり、その『設定』に矛盾が生じれば、存在そのものが揺らぐ。
『ア……ガ……』
赤黒い影が明滅する。
俺は畳みかける。
「それに、『今、後ろにいるの』って言ったな? GPSの精度的に、数メートルの誤差が出るはずだ。ピンポイントで背後を取れるのは、お前がそこにいるからじゃない。ヒマリが『いる』と思い込んでいるからだ」
俺は一歩、前へ出る。
「お前はメリーさんじゃない。ただの不審者通報アプリのバグだ」
バヂヂッ!!
青白い火花が散り、怪異の輪郭が崩壊していく。
鎌が飴細工のように溶け、ドロドロとした黒い液体となって床に広がった。
「うわ……汚な」
ヒマリがへたり込む。
「……あんたさぁ。毎度毎度、夢も希望もない倒し方するよね。もっとこう、必殺技とかないの?」
「ない。非科学的なもんは嫌いなんだよ」
俺はハンカチで靴の汚れを拭う。
だが、違和感は拭えなかった。
最近、都市伝説の『進化』が早すぎる。
誰かが意図的に、噂を書き換えている。
「ねえレン。次の噂、知ってる? 『嘘つきのレンくん』の話」
ヒマリの声色が、急に低くなった。
最終章 誰も知らない八番目の不思議
廊下の空気が凍り付く。
ヒマリの瞳から、ハイライトが消えていた。
「え?」
「『嘘つきのレンくん』はね、怪異を言葉だけで消しちゃうの。でもね、本当はレンくん自身が、一番大きな嘘なんだって」
ヒマリの背後に、先ほど消したはずの黒い影が再び渦巻く。
いや、違う。
影はヒマリ自身から溢れ出している。
「……なるほどな」
俺はスマホをポケットにしまった。
理解してしまったからだ。
なぜ、俺の『論破』がこれほど効くのか。
なぜ、ヒマリの周りばかりで怪異が起きるのか。
怪異を生み出していたのは、ヒマリの『恐怖』と『想像力』。
そして、それを打ち消すための安全装置として、彼女が無意識に作り出した存在こそが――。
「俺、か」
俺の手が、半透明に透け始めていた。
『レンくんは、私のヒーローだから。ずっと一緒にいてね』
ヒマリの形をした怪異が笑う。
俺は、自分の存在が『都市伝説』そのものであることを突き付けられる。
俺が俺自身を「非科学的だ」と論破すれば、俺は消える。
だが、論破しなければ、暴走するヒマリの妄想が学校を飲み込む。
「……皮肉なもんだな」
俺は透けかけた手で、ヒマリの頭に触れた。
冷たくて、でも懐かしい感触。
「ヒマリ。お前の作り話にしては、俺というキャラはひねくれ過ぎだ」
俺はニヤリと笑う。
「『嘘つきのレンくん』は、最期にこう言うんだよ。『お前はもう、一人で大丈夫だ』ってな」
それは、俺が吐いた最初で最後の、根拠のない『嘘』だった。
俺の言葉がトリガーとなり、世界が白く弾ける。
論理も、怪異も、俺という存在さえも、朝の光の中に溶けていった。