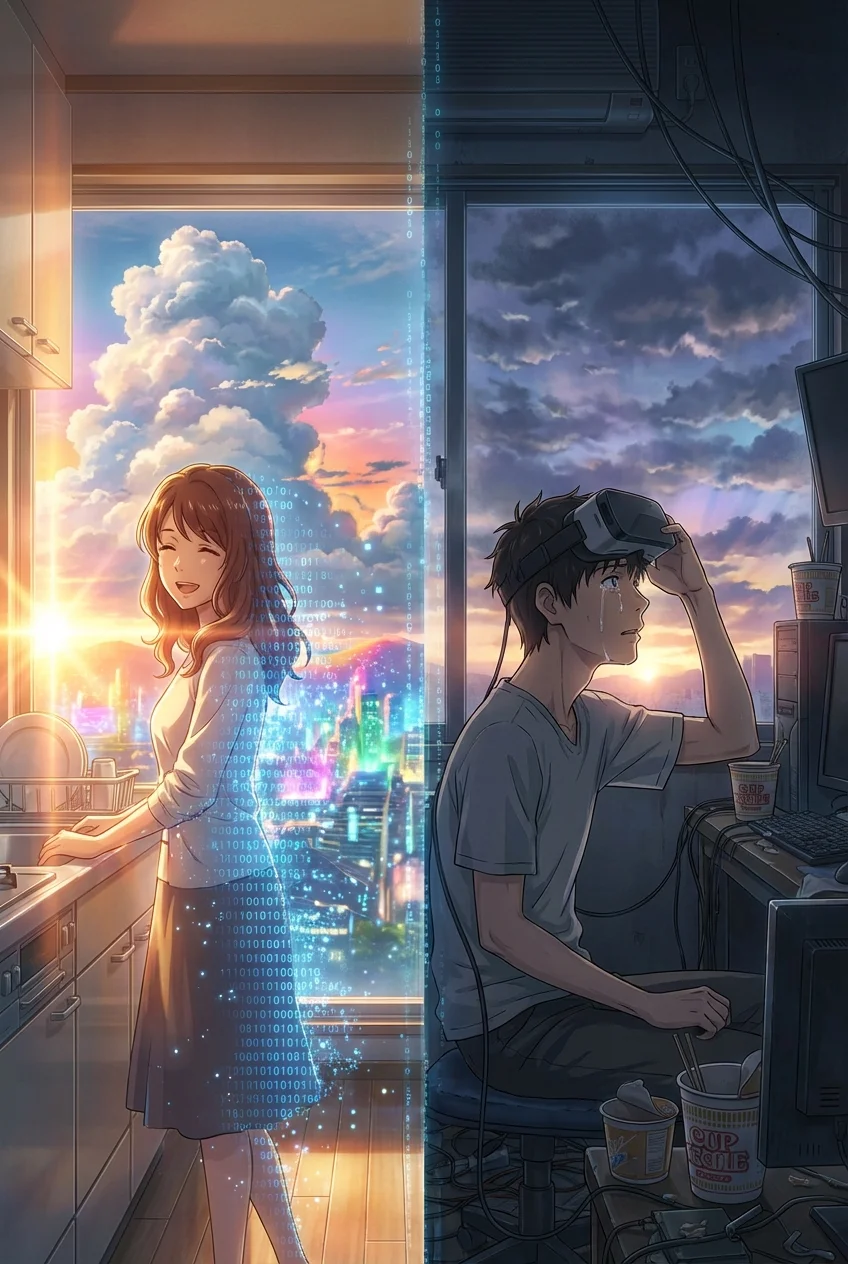第一章 悲鳴を上げる水圧
「キッ、キキ……」
チタン合金の殻が、爪を立てられた黒板のような音を立てる。
俺のこめかみに、鋭い痛みが走った。
「海人(かいと)、深度10,900を通過。バイタルが乱れてるわよ」
通信機越しのエレナの声は、氷のように冷静だ。彼女は知らない。
この潜水艇『アビス・ウォーカー』が今、断末魔を上げていることを。
「……聞こえるんだよ。フレームの右舷接合部、リベットが悲鳴を上げてる」
俺は操縦桿を握る手に滲んだ汗を、ズボンで乱暴に拭った。
金属の歪みが「音」として聞こえる俺の共感覚(シナスタジア)は、この深海では呪いでしかない。
視界を埋め尽くすのは、絶対的な闇と、マリンスノーの死骸だけ。
外の水圧は1000気圧を超えている。指先ほどの穴が開けば、俺たちは瞬時に肉塊へと圧縮される。
「センサーに感あり。……信じられない」
エレナの息を呑む音が聞こえた。
「ソナーがエラーを吐いてる。音波が……吸い込まれてる?」
モニター上の地形図が、ノイズで真っ赤に染まった。
サーチライトを前方に向ける。
闇が切り裂かれ、その先に「それ」が浮かび上がった。
海底の泥に半分埋もれた、巨大な構造物。
自然物ではない。
直線で構成された、完全な正十二面体。
表面は光を一切反射しない漆黒。
だが、俺を戦慄させたのはその形状ではない。
「おい……嘘だろ」
俺の耳に届いていた「金属の悲鳴」が、ピタリと止んだのだ。
いや、違う。
あの構造物の周囲だけ、物理的な振動が――「死んで」いる。
第二章 凍りついた時間
「アームを展開。サンプルを採取するわ」
「待て! 何かがおかしい。水流が止まってる」
俺の制止を無視し、エレナが遠隔操作でマニピュレーターを伸ばした。
機械の腕が、黒い構造物の表面に触れた瞬間。
ガクン、と潜水艇が揺れた。
「なっ……!?」
計器の数値を見て、俺は目を疑った。
深度計:0メートル。
外水圧:0気圧。
「システムエラーか? ここは水深1万メートルだぞ!」
「違う、窓の外を見て!」
エレナの叫び声に顔を上げる。
サーチライトに照らされたマリンスノーが、空中で静止していた。
いや、潜水艇の周囲の水が、完全に動きを止めている。
まるで、ここだけ時間が切り取られたかのように。
さらに異様なことが起きた。
黒い十二面体の一部が、音もなくスライドして開いたのだ。
中から漏れ出したのは、青白い光。
海水が浸入しない。
開口部の内側は、空気で満たされているように見えた。
「ありえない……開口部はシールドなしで水圧を支えてるの?」
俺たちの常識、いや、人類が積み上げてきた物理法則が、ここではジョークのように扱われている。
開いた扉の奥に、何かが見えた。
あれは……部屋?
無機質な白い壁。そして、中央に置かれた一台の粗末な机。
「海人、あれ……」
机の上に、何かが突っ伏している。
人間の、白骨死体だ。
着ているのは現代的なパーカー。
そして、その骨の指が握りしめているものを見た瞬間、俺の全身の血が逆流した。
それは、旧世代のスマートフォン。
ひび割れた画面に、見覚えのあるステッカーが貼ってある。
俺が10歳の時、事故で死んだ妹がくれた、歪な猫のシール。
「なんで……俺のスマホが、あそこにある?」
俺はポケットを探った。
ある。
俺のスマホは、ここにある。
じゃあ、あそこで死んでいるのは誰だ?
第三章 因果のバグ
「接近して。データを吸い出すわ」
「やめろ! あれは触れちゃいけないものだ!」
「これは人類史上最大の発見よ! オーパーツなんてレベルじゃない!」
エレナがコンソールを叩く。
潜水艇が吸い寄せられるように開口部へ近づく。
距離、5メートル。
俺のシナスタジアが、再び脳内で叫び声を上げ始めた。
今度は金属音じゃない。
もっと根源的な、世界の「コード」が書き換わるような不協和音。
《警告:因果律の不整合を検知》
潜水艇のスピーカーからではなく、直接脳内に響く声。
《アーカイブ『人類』のデータ破損を確認。ロールバックを開始します》
「……ロールバック?」
白骨死体の持つスマホが、不意に点灯した。
画面に映し出されたのは、動画。
そこに映っているのは、髭面でやつれ、右目を失った――未来の俺だった。
『これを見ているということは、お前はまた失敗したんだな、海人』
画面の中の俺が、絶望的な目でこちらを見つめる。
『その箱を開けるな。それは宝箱じゃない。この宇宙というシミュレーションの、ゴミ箱だ』
ズズズ、と視界が歪む。
潜水艇の壁が、デジタルのノイズのようにモザイク状に崩れ始めた。
エレナが悲鳴を上げるが、その声はコマ落ちしたように途切れ途切れになる。
『俺たちは、バグったデータを廃棄するために、この深海(ゴミ箱)に生成された。外に出ようとするな。出れば、世界が処理落ちする』
画面の中の俺が、拳銃をこめかみに当てる。
『頼む。そこで終わらせてくれ。次のループを始めないでくれ』
銃声。
と同時に、目の前の白骨死体が、砂のようにさらさらと崩れ去った。
直後、強烈な圧力が戻ってきた。
「海人! 水圧が戻った! 圧壊する!」
警報音が鳴り響く中、俺は理解した。
ここは遺跡じゃない。
未知の文明の遺産でもない。
俺たちは、削除されたデータの残骸。
「……ああ、そういうことか」
俺の共感覚が捉えていた「金属の悲鳴」。
あれは、潜水艇の音じゃなかった。
削除されるデータが上げる、断末魔だったんだ。
視界が暗転する直前、俺は崩れ落ちた白骨の山の中に、俺のスマホと同じ「猫のシール」が、無限に重なって埋もれているのを見た。