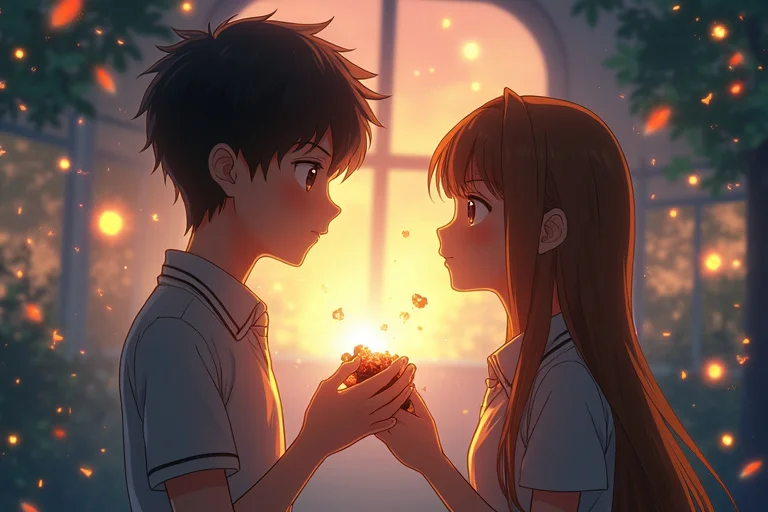第一章 紫色の空
退屈だった。世界は褪せた写真のように、どこか色味を失っているように見えた。高校二年の秋、水野蓮(みずの れん)の世界は、そんな灰色の濃淡で構成されていた。所属する写真部も、惰性でシャッターを切るだけの時間。被写体に心惹かれることもなく、ただ構図と光の計算だけが頭を占める。そんな日々は、これからも続くのだと信じて疑わなかった。
その日も蓮は、授業が終わると真っ先に屋上へ向かった。立ち入り禁止の札は形骸化しており、そこは蓮だけの聖域のはずだった。冷たい風が頬を撫で、街の喧騒が遠くに聞こえる。いつものようにフェンスに背を預け、空でも撮ろうかとカメラを構えた時、視界の隅に、ありえないはずの人影を捉えた。
イーゼルの前に立つ、小柄な少女。同じクラスの、佐伯唯(さえき ゆい)だった。彼女は、クラスでもほとんど誰とも話さず、窓の外を眺めているか、本を読んでいるかのどちらかだった。その影の薄さは、まるで風景に溶け込むための術を心得ているかのようだった。
彼女が、こんな場所に。好奇心よりも先に、自分の聖域を侵されたような苛立ちが蓮の胸をかすめた。だが、次の瞬間、蓮の足は縫い付けられたように動かなくなった。彼女がキャンバスに描いている「空」に、目を奪われたからだ。
それは、青ではなかった。夜空に揺らめくオーロラのように、淡い紫と翠の光が渦を巻き、星々が宝石のように瞬いていた。非現実的で、しかしどうしようもなく美しい、幻想の空。蓮は思わず息を呑んだ。現実の空は、雲ひとつない、ありふれた秋晴れの青だというのに。
「……何、描いてるんだ」
気づけば、声が漏れていた。びくりと肩を揺らし、唯が振り返る。大きな瞳が驚きに見開かれ、慌ててキャンバスを自分の体で隠した。
「水野、くん……」
「その絵……」
蓮がキャンバスを指さすと、唯は気まずそうに視線を逸らした。小さな声が、風に乗り、かろうじて蓮の耳に届く。
「……あなたには、見えませんか?」
その問いの意味が、蓮には分からなかった。見えているのは、褪せたコンクリートと、どこまでも広がる平凡な青空だけだ。蓮が黙っていると、唯は寂しそうに微笑み、こう付け加えた。
「これは、本当に大切なものを見つけた人にだけ見える、特別な空なんです」
その言葉が、蓮の灰色の世界に、初めて色のついた楔を打ち込んだ。
第二章 ファインダー越しの嘘
その日を境に、蓮は屋上で唯と顔を合わせるようになった。最初はぎこちない沈黙が流れたが、蓮が彼女の描く幻想的な空について尋ねるうちに、少しずつ言葉を交わすようになった。
唯が語る物語は、いつも詩的で、どこか切なかった。彼女には幼い頃に亡くした兄がいて、「いつか二人で、世界で一番綺麗なオーロラを見に行こう」と約束していたのだという。兄を失って以来、彼女は空を見上げ続けてきた。そしてある時、兄との約束を強く心に念じた瞬間、目の前の空が、あの日の約束の色に染まったのだと。
「兄が、私にだけ見せてくれる景色。だから、私はこれを描き続けなきゃいけないの」
そう語る唯の横顔は、儚く、そして強い光を宿しているように見えた。蓮は、自分が今まで出会った誰とも違う彼女の存在に、強く惹かれていくのを感じていた。退屈だった写真部の活動にも、目的が生まれた。
「佐伯を、撮らせてくれないか」
蓮の申し出に、唯は一瞬戸惑ったが、静かに頷いた。ファインダーを覗くと、世界は切り取られ、意味を持つ。蓮は、幻想の空を描く唯の姿を、夢中で撮り続けた。絵の具の匂いが混じる風。キャンバスに向かう真剣な眼差し。時折、こちらに気づいてはにかむ、あどけない笑顔。
カシャリ、とシャッター音が響くたび、蓮の心に温かい何かが満ちていく。これは、誰かのために撮る写真だ。初めて抱くその感情は、蓮の世界を少しずつ色鮮やかなものに変えていった。
彼の写真の中で、唯はいつも少し寂しそうに、けれど誇らしげに笑っていた。まるで、自分だけが知る秘密を抱えた、物語の主人公のように。蓮は、彼女の語る「紫色の空」の物語を、いつしか疑うことなく信じていた。いや、信じたかったのだ。この退屈な世界にも、そんな奇跡が存在するのだと。
「水野くんの写真、好きだな」ある日、唯がぽつりと言った。「なんだか、本当の私じゃないみたいに、綺麗だから」
「そんなことない。佐伯は、そのままで綺麗だよ」
思わず口から出た言葉に、蓮自身が驚いた。唯は顔を赤らめ、嬉しそうに俯いた。その瞬間、二人の間に流れる空気は、夕焼けの空のように甘く、切なく色づいていた。蓮は、この時間が永遠に続けばいいと、本気で願っていた。
第三章 ありふれた奇跡
秋が深まり、学園祭の季節がやってきた。美術部の友人から、校内絵画コンクールの結果が出たと聞き、蓮は真っ先に展示ホールへ向かった。金賞の札がかけられた作品の前に、人だかりができていた。その中心にあるのは、間違いなく佐伯唯の作品だった。
蓮は胸を高鳴らせながら、人垣をかき分けて絵の前に立った。そして、絶句した。
そこに描かれていたのは、蓮が焦がれた、あの幻想的な紫色のオーロラではなかった。
描かれていたのは、どこにでもある、平凡な青空だった。澄み渡り、白い雲がいくつか浮かんでいるだけの、何の変哲もない、青い空。タイトルには、こう記されていた。
『ありふれた奇跡』
頭が真っ白になった。どういうことだ?あの特別な空は?彼女の物語は?観衆の「綺麗だね」「心が洗われるようだ」という賞賛の声が、耳障りな雑音のように聞こえる。蓮は、いてもたってもいられず、ホールを飛び出した。
屋上に、唯はいた。イーゼルも立てず、ただ一人、フェンスの向こうの空を見つめていた。
「どういうことだよ、佐伯!」
蓮の荒々しい声に、唯の肩が震える。ゆっくりと振り返った彼女の瞳は、赤く潤んでいた。
「あの絵は、なんだ。お前が見ていた空は、紫のオーロラじゃなかったのか」
問い詰める蓮を、唯は悲しげな目で見つめ返した。やがて、ぽつり、ぽつりと真実を語り始めた。堰を切ったように、涙と共に。
「……見えなかった。一度も」
「え……?」
「紫色の空なんて、最初から見えなかったの。全部……私が作り出した、嘘だったんです」
唯は、兄を失った深い喪失感から、自分を特別な存在だと思い込みたかったのだという。特別な力があると思えば、孤独に耐えられる気がした。幻想の空の物語は、他者を遠ざけ、自分の殻に閉じこもるための、か弱くも頑丈な鎧だった。
「でも、水野くんに出会って……あなたが、私の写真を撮ってくれて……」
唯は、蓮が撮った自分の写真を見つめるうちに、気づいたのだと嗚咽交じりに語った。写真に写っているのは、特別な力を持つ少女ではなかった。ただ寂しさを抱え、それでも必死に前を向こうとする、等身大の自分。その「ありのままの自分」を、蓮のファインダーは、とても優しく見つめてくれていた。
「特別な何かがなくたって、いいんだって……。こうして、あなたと話したり、笑ったりする、ありふれた毎日が、本当は奇跡みたいに大切なんだって、気づいたの。だから……もう、嘘はつけなかった」
嘘を捨て、彼女が最後に描いた「本当の空」。それが、あの青空だったのだ。
蓮は、ハンマーで頭を殴られたような衝撃を受けていた。自分が惹かれたのは、一体何だったのか。彼女の語る幻想的な物語か。それとも、嘘をついてでも必死に自分の世界を守ろうとしていた、彼女自身の健気さだったのか。自分の感情の正体が分からなくなり、蓮はただ立ち尽くすことしかできなかった。
第四章 君が見つけた空
自室に戻った蓮は、これまで撮りためた唯の写真を、一枚一枚、見返した。紫色の空を背景にした、幻想の少女。そう思って撮っていたはずの写真の中にいたのは、紛れもなく、現実を生きる佐伯唯だった。風に髪を乱し、少し困ったように笑い、時折、遠い目をする少女。
蓮は、気づいた。
自分が本当に撮りたかったのは、幻想などではなかった。この、不器用で、嘘つきで、それでもひたむきな一人の少女の、その存在そのものだったのだ。彼女の嘘ごと、彼女の痛みごと、すべてを美しいと感じていたのだ。
翌日の放課後、蓮はカメラを持たずに屋上へ向かった。あの日と同じように、唯が一人で空を見上げていた。蓮は何も言わず、彼女の隣に並んで立つ。気まずい沈黙が流れる。先に口を開いたのは、蓮だった。
「俺には、やっぱり紫の空は見えないや」
唯の肩が、小さく震える。
「でも」と蓮は続けた。まっすぐに前を見つめたまま。「佐伯の描いた青空、すごく綺麗だと思った。俺が今まで見てきた、どんな空よりも」
唯が息を呑む気配がした。彼女の方を見ると、大きな瞳から、ぽろぽろと涙がこぼれ落ちていた。それは、後悔や悲しみの涙ではなかった。蓮には、それが分かる。やがて彼女は、泣きながら、花が綻ぶように微笑んだ。
その笑顔は、蓮がファインダー越しに追い求めてきた、どんな表情よりも輝いて見えた。
時は流れ、二人はそれぞれの道を歩み始めた。蓮は写真家を目指して東京の大学へ進み、唯は地元の大学で美術を学んでいる。頻繁に会うことはなくなったが、二人の心には、あの屋上で見つけた「本当の空」が、ずっと広がっていた。
数年後、都内の小さなギャラリーで、水野蓮の初の個展が開かれた。様々な風景や人物が並ぶ中、一枚だけ、ひときわ多くの人の足を止める写真があった。
それは、高校の屋上で撮られた一枚。ありふれた青空を背景に、少しはにかみながら、でも晴れやかに微笑む少女の姿。
写真の傍らには、小さなプレートが置かれていた。
『君が見つけた空』
その青は、どんな幻想のオーロラよりも鮮やかで、見る者の心に、温かくも切ない、静かな感動を呼び起こしていた。会場のどこかで、同じ空を見上げているであろう彼女のことを思いながら、蓮はそっと目を閉じた。褪せていたはずの世界は、今、数えきれないほどの色彩に満ち溢れていた。