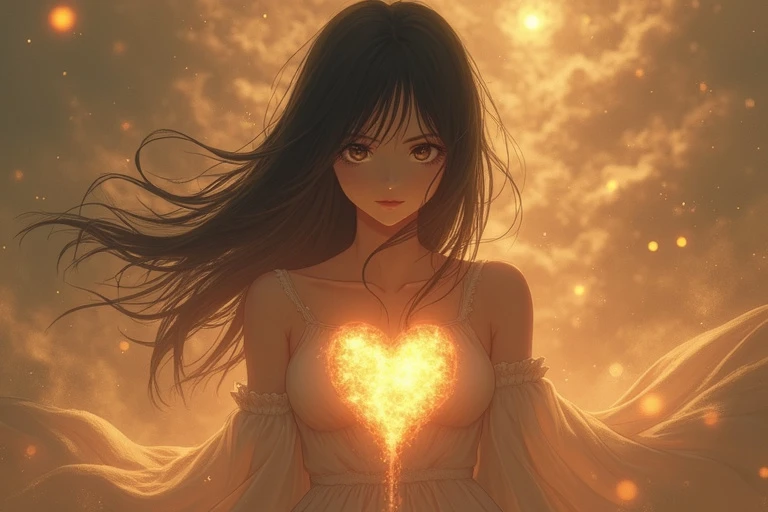第一章 雨上がりの森と、焼きたてのパン
橘陽(たちばな はる)が何かを真剣に語っている。彼の唇は確かに動いているのに、俺、水島湊(みずしま みなと)の耳には、何の音も届かない。その代わり、ふわりと鼻腔をくすぐる豊かな香りが、彼の言葉のすべてだった。
最初は、雨上がりの深い森の匂い。湿った土と、苔むした樹皮、そして若葉の青々しい香りが混じり合っている。これは、陽が何かを心配している時の香りだ。おそらく、俺が昨日から寝ずに仕上げたレポートのことだろう。次に、香りはがらりと変わる。香ばしく、温かい、焼きたてのパンの香り。バターがじゅわりと溶けるような、甘やかで優しい匂い。これは、彼が提案をしている時の香りだ。きっと、「少し休めよ」とでも言っているに違いない。
俺は頷き、スマートフォンのメモ帳に『わかってる。これが終われば寝る』と打ち込んで見せた。陽はそれを見て、安心したように微笑む。彼の笑顔とともに、今度は陽だまりのような、乾いたリネンの香りがした。
これが、俺と陽の日常だった。
物心ついた頃から、俺には陽の言葉だけが「香り」として届いた。他の人間の声は、ごく普通に音として聞こえるのに、陽の声だけがこの奇妙な現象の対象だった。医者にも、専門家にも原因は分からなかった。いつしか俺たちは、この不便で風変わりなコミュニケーションに慣れていった。
陽の感情は、香りとなって俺の脳に直接流れ込んでくる。嘘も、誤魔化しも一切ない。嬉しい時は柑橘系の弾けるような香り、悲しい時は錆びた鉄のような冷たい匂い、怒っている時は焦げ付いたスパイスの刺激臭。それはある意味、言葉よりもずっと雄弁だった。
しかし、俺はこの関係を手放しで喜んでいたわけではない。具体的な情報を伝えるには、どうしても筆談やテキストが必要になる。周りから見れば、俺たちはいつもスマートフォンを介して会話する、奇妙な二人組に映っていただろう。その視線が、時々、ひどく息苦しかった。陽の優しさに甘えながらも、心のどこかで、この不完全な繋がりを疎ましく感じていたのだ。
そして最近、俺はその「香り」に、新たな異変を感じ始めていた。
陽が放つ香りが、明らかに薄くなっているのだ。以前なら部屋中に満ちるほど鮮やかだった香りが、今は彼のすぐそばにいなければ感じ取れないほど微かになっていた。まるで、色鮮やかな絵画が、長い年月を経て少しずつ褪色していくように。
「何かあったのか?」
そうテキストで尋ねても、陽はいつも決まって、穏やかなラベンダーの香りを漂わせながら、『何でもないよ』と返すだけだった。その香りに嘘はない。だが、その香りの奥に、まるで薄いヴェールに隠されたような、嗅ぎ取れない何かがある気がしてならなかった。雨上がりの森の香りの奥に、枯れ葉の匂いが混じるように。焼きたてのパンの香りの奥に、冷えた石のような硬質さが潜むように。
その正体不明の気配が、俺の胸に言いようのない不安の染みとなって、じわりと広がっていた。
第二章 色褪せる世界と、記憶の断片
陽の香りが薄れていくにつれて、俺の世界から少しずつ色彩が失われていくようだった。これまで当たり前のように俺の感情を揺さぶっていた豊かな香りの奔流が、か細い流れに変わってしまった。それは、俺が思っていた以上に、深刻な喪失だった。
大学のキャンパスで、陽が他の友人たちと談笑している姿を見かけた。彼は楽しそうに笑い、身振り手振りを交えて何かを話している。友人たちも、彼の言葉に耳を傾け、声を上げて笑っていた。彼らの間には、ごく当たり前の「音」によるコミュニケーションが成立している。俺だけが、その輪の外にいる。
その光景が、ガラス一枚隔てた向こう側の出来事のように見えた。嫉妬、だろうか。いや、違う。もっと複雑な感情だ。陽が、俺といる時だけ特別な負担を強いられているのではないかという、鉛のような罪悪感。そして、その特別な関係が失われつつあることへの、身勝手な焦り。
俺は無意識に、陽との幼い日々を思い出していた。
初めてこの現象に気づいたのは、確か七歳の夏だった。公園のジャングルジムから落ちて頭を打った俺に、駆け寄ってきた陽が何かを叫んだ。その時、彼の言葉は音ではなく、強烈なミントの香りに変わった。ツンと鼻を突き、涙が滲むほどの鮮烈な香り。パニックになった俺は、「気持ち悪い!」と叫んで彼を突き飛ばしてしまった。
それでも、陽は俺のそばから離れなかった。彼はすぐに状況を理解し、小さなスケッチブックを取り出して、たどたどしい文字で俺と対話し始めた。彼のそばにいると、いつも心地よい香りがした。母親に叱られた日には、甘いミルクティーの香りが俺を慰めてくれた。テストで良い点を取った日には、弾けるソーダのような爽やかな香りが、共に喜んでくれた。
いつしか、陽の放つ「香り」は、俺にとっての世界そのものになっていた。言葉よりも深く、確かで、疑うことのできない真実だった。その世界が今、ゆっくりと崩れ始めている。
「本当に、何もないのか?」
その夜、俺は再びテキストで問い詰めた。返ってきたのは、いつものラベンダーの香り。だが、あまりにも弱い。まるで、遠くで焚かれた香炉から、風に乗ってやっと届いた一筋の煙のようだ。
『湊こそ、最近顔色が悪いよ。俺のことは気にしないで』
陽からの返信。そこには、微かに、本当に微かに、雨上がりの森の匂いが混じっていた。俺を心配する香り。その優しさが、今はかえって俺の胸を締め付けた。俺は、この関係の本質について、何も知らないのかもしれない。陽が、その穏やかな香りの裏で、何を抱えているのか。俺は、それを知るのが少し怖かった。
第三章 空っぽの部屋と、香りの真実
その日は、突然やってきた。
朝、目を覚ますと、世界から完全に香りが消えていた。いつもなら、隣のアパートに住む陽の気配が、朝食を作るベーコンの香りや、コーヒーの香ばしい匂いとなって微かに届くはずなのに、今日は何も感じない。ただ、無機質な空気がそこにあるだけだった。
胸騒ぎがして、陽にメッセージを送る。既読はつかない。電話をかけても、呼び出し音が虚しく響くだけ。嫌な予感が全身を駆け巡り、俺は部屋を飛び出した。
陽のアパートのドアは、鍵がかかっていなかった。
「陽!」
呼びかけに応えはない。がらんとした部屋は、まるで抜け殻だった。家具も、本も、彼の生活の痕跡がすべて消え去り、ただ四角い空間だけが広がっている。その部屋の中心に、ぽつんと置かれたローテーブルの上に、一通の封筒と、古びた一冊のノートだけがあった。
震える手で封筒を開ける。そこには、見慣れた陽の、丁寧な文字が並んでいた。
『湊へ。急にいなくなってごめん。少し遠くへ行くことにした。探さないでほしい』
短い文面。そこからは何の感情も読み取れない。俺は、手紙を握りしめ、隣のノートに目をやった。表紙には、マジックで『香りの日記』と書かれている。
ページをめくると、そこには俺の知らない陽の世界が広がっていた。それは、陽の視点から綴られた、俺たちの関係の記録だった。
『七月十日。湊がジャングルジムから落ちた。頭を打って、少しの間、言葉が出なくなった。お医者さんは、ショックによる一時的なものだと言うけど、すごく心配だ。僕の声も、聞こえていないみたいだった』
『七月十五日。湊が僕を避けるようになった。僕が話しかけると、嫌な顔をする。どうしてだろう。でも、僕が心の中で「大丈夫だよ」って強く念じたら、湊が少しだけこっちを向いた気がした。もしかして……』
読み進めるうちに、俺は呼吸を忘れていた。
ノートに綴られていたのは、衝撃的な真実だった。
俺が陽の言葉を「香り」として感じていたのではない。逆だった。
陽は、自分の感情を「香り」という形で相手に伝えることができる、特殊な能力の持ち主だったのだ。
幼い頃、事故の後遺症で一時的に失語症になった俺を励ますため、彼は必死にこの能力を磨いたらしい。言葉を失った俺に、何とかして想いを届けたい。その一心で、彼は「言葉の代わり」として、俺にだけ香りを送り続けていたのだ。俺が普通に話せるようになってからも、それが俺たちのコミュニケーションの形として定着したから、彼は能力を使い続けた。
日記の最後の方は、インクが掠れていた。
『最近、湊に香りを送るのが少し辛くなってきた。この力は、僕の命を少しずつ削っているのかもしれない。でも、後悔はない。湊はもう、僕がいなくても大丈夫だ。たくさんの友達がいて、自分の世界をちゃんと持っている。僕がいつまでも、彼の特別でいてはいけない。彼が本当の意味で自立するために、僕は消えるべきなんだ』
最後のページには、こう書かれていた。
『湊。君の世界が、これからもたくさんの素晴らしい香りで満たされますように』
ノートが、手から滑り落ちた。
ああ、そうか。香りが薄れていたのは、彼の力が尽きかけていたからなのか。俺を心配していた雨上がりの森の香りは、俺のためであると同時に、消えゆく自分自身への悲しみの香りでもあったのだ。
俺が疎ましくさえ感じていたこの関係は、陽の命を賭した、あまりにも大きくて、痛々しいほどの友情の証だった。自分がどれだけ彼に守られ、甘え、そして無自覚に彼を追い詰めていたかを知り、俺はその場に崩れ落ちた。空っぽの部屋で、初めて声を上げて泣いた。陽がいない世界は、無味無臭で、あまりにも寂しかった。
第四章 君の言葉になるために
陽がいなくなってから、三年が経った。
俺は大学を卒業し、今は小さな香水工房で調香師見習いとして働いている。あの日以来、俺の世界から香りは失われたままだ。食事の味は分かるし、花の匂いも嗅ぎ分けることはできる。だが、かつて陽がくれたような、感情を揺さぶる豊かな香りはどこにもなかった。世界は平板で、奥行きを失っていた。
陽の行方は、依然として分からない。彼が姿を消した後、俺は必死で彼を探した。だが、彼の一族は、その特殊な能力を隠すように、静かに暮らしているらしく、足取りは全く掴めなかった。
それでも、俺は諦めていない。
工房の片隅にある俺の作業台には、数えきれないほどの香料瓶が並んでいる。ローズ、ジャスミン、サンダルウッド、ベルガモット。俺は毎日、陽が遺してくれた『香りの日記』を道標に、香りを調合している。
『嬉しい時は、シチリアのレモンの香り』
『悲しい時は、雨に濡れたアスファルトの匂い』
『優しい気持ちは、カモミールティーみたいに』
彼が俺に与えてくれた香りを、今度は俺自身の手で再現する。それは、途方もなく困難な作業だった。だが、俺にはやらなければならない理由があった。
陽、お前は言ったな。俺が自立するために消える、と。馬鹿野郎。お前がいない世界で、俺は本当の意味で独りになった。お前がいたから、俺は世界を豊かに感じることができたんだ。
だから、今度は俺の番だ。
いつか、必ずお前を見つけ出す。そして、再会した時に伝えるんだ。言葉でじゃない。俺が作った、この香りで。
「ありがとう」でも「ごめん」でもない。
「今度は俺が、君の言葉になる」と。
その日の夕方、俺は一つの新しい香水を完成させた。霧雨に濡れた森の静けさと、焼きたてのパンの温かさ、そして陽だまりの優しさを閉じ込めた香り。それは、俺が最も愛した、陽の香りだった。
小さなガラスの小瓶に、そっとラベルを貼る。
『陽(ハル)』
窓の外を見上げると、茜色の空がどこまでも広がっていた。まるで、あの日の陽の穏やかな微笑みのように。
不意に、風が窓から吹き込んできて、試香紙に染み込ませたその香りを、ふわりと俺の鼻先へ運んだ。
その瞬間。
ほんの一瞬だけ、懐かしい彼の声が聞こえたような気がした。
「……湊」
俺は目を閉じ、その余韻を深く吸い込む。
ああ、そうだ。きっとどこかで、君もこの空を見ている。
俺はこれからも、君を探し続ける。君が俺にしてくれたように、この世界のすべての香りを集めて、君に届けるために。
「大丈夫だよ、陽」
俺は、誰もいない空に向かって、静かに呟いた。
「今、君の香りがしたんだ」