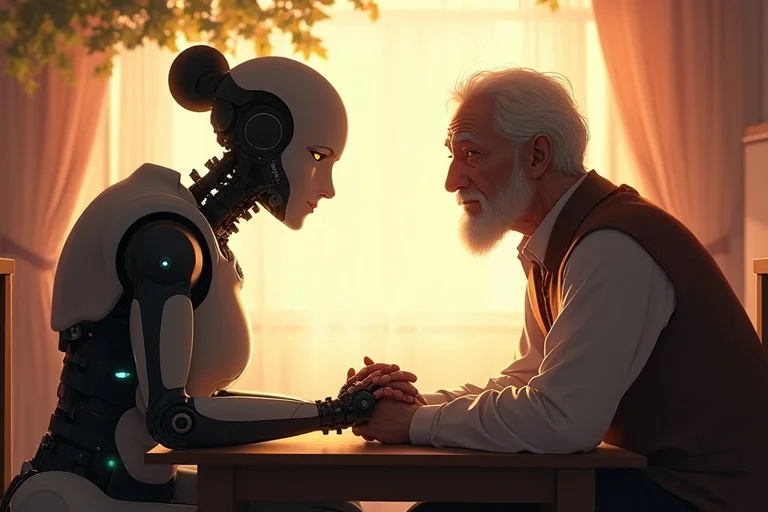第一章 空白のオルゴール
俺の指先は、呪われている。
そう本気で思うようになったのは、いつからだったか。古物修復師という仕事柄、俺は日々、他人の人生が染みついた品々に触れる。そのたびに、意図せずして流れ込んでくるのだ。持ち主の、人生で最も輝かしかったであろう、幸福の記憶が。
初めてのデートの甘酸っぱいときめき。我が子が生まれた瞬間の、世界が祝福に満ちたかのような歓声。長年の努力が実を結んだ、誇りに満ちた一瞬。それらは眩い光のように俺の意識を貫き、数分間、他人の人生を強制的に追体験させる。人々はそれを奇跡と呼ぶかもしれないが、俺にとっては毒だった。他人の完璧な幸福に繰り返し触れるたび、俺自身の平凡で色褪せた日常が、より一層みすぼらしく感じられるのだ。だから俺は、人と深く関わることをやめた。他人の幸福を覗き見るだけで、自分の幸福を築くことから逃げ続けていた。
そんなある雨の日、店のドアベルが寂しげな音を立てた。入ってきたのは、背を丸めた小柄な老婆だった。千代と名乗った彼女は、古びた布に大切に包まれた木製のオルゴールを、震える手でカウンターに置いた。
「これを、直していただけないでしょうか。祖母の、唯一の形見なんです」
オルゴールは、長年の歳月を感じさせる深い飴色をしていた。細やかな彫刻は摩耗し、蓋の蝶番は錆びついている。俺は仕事として、ごく自然にそれに指を伸ばした。ひんやりとした木の感触が指先に伝わる。そして、いつものように記憶の奔流が押し寄せるのを待った。
しかし、何も起こらなかった。
シン、と静まり返った意識の中、ただオルゴールの冷たさだけがそこにある。何度か角度を変え、彫刻の溝をなぞるように触れてみても、結果は同じだった。空白。完全な無だ。こんなことは初めてだった。
俺の能力が感知するのは、その人物の人生における「最も」幸せだった記憶、たった一つのハイライトだ。まさか、このオルゴールの持ち主には、その記憶が一つもなかったとでもいうのだろうか。そんな空虚な人生が存在するのか?
「……分かりました。お預かりします」
俺は動揺を悟られぬよう、努めて事務的な声で答えた。千代は深々と頭を下げ、何度も礼を言いながら店を出ていった。雨に濡れる彼女の背中を見送りながら、俺は手の中のオルゴールに再び目を落とす。
沈黙する木箱は、俺がこれまで触れてきたどんな曰く付きの品よりも、不気味で、そしてどこか悲しい謎を秘めているように思えた。この空白のオルゴールとの出会いが、俺の灰色の日々を根底から揺るがすことになるなど、その時はまだ知る由もなかった。
第二章 沈黙との対話
オルゴールの修復作業は、静寂との戦いだった。
精密ドライバーを手に、錆びついたネジを一つひとつ慎重に外していく。蓋を開けると、埃と微かな樟脳の匂いがした。櫛歯は何本か折れ、シリンダーのピンも所々摩耗している。予想以上に状態は悪い。
俺は作業に没頭した。指先に神経を集中させ、金属の冷たさ、木のささくれ、油の粘り気を感じる。普段なら、これらの感触と共に、持ち主の温かい記憶が流れ込んでくるはずだった。しかし、このオルゴールはどこまでも沈黙を貫いている。まるで、固く心を閉ざした老人のように。
時折、俺の心に冷たい疑念が湧き上がる。この持ち主は、本当に不幸なだけの人生を送ったのだろうか。生涯、一度も心からの幸福を感じることなく、このオルゴールを虚しく撫で続けていたのだろうか。そう考えると、自分の仕事がひどく虚しいものに思えた。失われた音色を取り戻したところで、その先に待っているのが空白だけだというのなら、一体何の意味があるというのだ。
数日後、千代が様子を見に店を訪れた。
「祖母は、とても無口な人でした」
カウンターの隅で、湯気の立つハーブティーを両手で包みながら、彼女はぽつりぽつりと語り始めた。
「戦争で夫を亡くし、女手一つで母を育てて。贅沢もせず、いつも黙々と畑仕事か編み物をしていました。笑った顔なんて、ほとんど記憶にありません。だから……このオルゴールが鳴らなくなってしまった時、祖母の人生そのものが、音もなく終わってしまったような気がしたんです」
彼女の言葉は、俺の胸に小さく突き刺さった。俺は他人の幸福の記憶を覗き見ては、自分の人生を嘆く。だが、目の前にいるこの女性は、愛する祖母に幸福な記憶がなかったのではないかと、本気で心を痛めている。俺の傲慢さが、不意に恥ずかしくなった。
「……必ず、直します」
俺は、ただそれだけを告げた。それはもはや単なる仕事の請負ではなく、千代と、そして名も知らぬ彼女の祖母に対する、俺からの約束だった。
それからの日々、俺は能力に頼ることをやめた。代わりに、オルゴールそのものと対話するように、丁寧に修復を進めた。シリンダーのピンの摩耗具合から、どの曲を特に好んで聴いていたのかを推測する。蓋の裏に残された、爪で引っ掻いたような小さな傷を見つけ、どんな気持ちでこれを開け閉めしていたのかに想いを馳せる。
それは、記憶の奔流に身を任せるのとは全く違う、静かで、しかし豊かな時間だった。俺は初めて、物に残された物理的な痕跡を通して、持ち主の生きた証に触れているような気がしていた。沈黙は、もはや空虚ではなかった。それは、語られなかった無数の物語を内包した、深い静寂なのだと思えるようになっていた。
第三章 幾重にも響き合う旋律
一ヶ月後、オルゴールの修復は完了した。
折れた櫛歯は寸分違わぬ形に作り直し、摩耗したシリンダーのピンは繊細な手つきで補強した。古びたゼンマイを巻き上げると、カチ、カチ、と心地よい張力が指に伝わる。俺は息を呑み、ストッパーをそっと外した。
その瞬間、澄み切った、それでいてどこか懐かしい音色が店内に響き渡った。それは、有名なクラシックでもなければ、流行りの歌でもない。素朴で、子守唄のように優しい、ただ静かに心を慰めるような旋律だった。
俺は鳴り響く音色に聴き入りながら、最後の仕上げとして、丁寧に磨き上げた蓋にそっと触れた。
その時だった。
稲妻が落ちたような衝撃と共に、記憶が、ついに流れ込んできた。
だが、それは俺が知っているような、一つの鮮烈な光景ではなかった。それは、光の奔流。無数の記憶の欠片が、オルゴールの旋律に乗って、万華鏡のように俺の意識の中で明滅を繰り返したのだ。
縁側で、柔らかな春の日差しを浴びながら、膝の上の猫を撫でる温かい手のひらの感触。
まだ幼い千代の寝顔を覗き込み、その小さな寝息に安堵する、月の静かな夜。
亡き夫の写真を磨きながら、二人でこっそり食べた甘い饅頭の味を思い出し、小さく笑みをこぼす午後。
編み棒を動かす指先と、窓を打つ優しい雨音だけが響く、満ち足りた静寂。
芽吹いたばかりのジャガイモの小さな緑に、生命の力強さを感じて胸が熱くなる朝。
それらはどれも、人生のハイライトと呼ぶにはあまりにささやかで、日常的な光景だった。しかし、その一つひとつが、確かな幸福の輝きを放っていた。一つが消えると、また次の幸せが生まれ、それらが幾重にも重なり合い、美しいタペストリーのように連なっている。
俺は、雷に打たれたように立ち尽くしていた。
分かった。なぜ、これまで記憶を読み取れなかったのか。
このオルゴールの持ち主にとって、「最も幸せな記憶」は一つではなかったのだ。彼女の人生は、たった一つの輝かしい瞬間で定義されるものではなかった。雨粒の一つひとつがやがて大河を成すように、彼女の人生は、数えきれないほどの小さな、けれど確かな幸福の積み重ねによって、豊かに満たされていたのだ。
俺の能力は、あまりに強力な光しか捉えられない、不器用なレンズのようなものだった。彼女の人生に満ちていた、淡く、しかし無数にきらめく光の粒を、これまで捉えることができなかったのだ。
オルゴールは、その無数の幸福が溶け合い、結晶化した魂そのものだった。だからこそ、修復が完了し、すべての記憶が調和して一つの旋律を奏でた瞬間に、俺はようやくその全貌に触れることができたのだ。
俺は、自分がこれまで見てきた他人の「完璧な幸福」が、いかに人生の断片的な一面に過ぎなかったかを思い知った。人生の価値は、輝かしい一瞬にあるのではない。平凡な日々の営みの中に、愛おしむべき無数の瞬間が隠されているのだ。俺は、その真実を、音の鳴らないオルゴールから教えられた。
第四章 祝福の指先
千代がオルゴールを受け取りに来た日、店には穏やかな西日が差し込んでいた。
俺はカウンター越しに、修復されたオルゴールを彼女に差し出した。彼女はそれを受け取ると、まるで宝物に触れるかのように、優しくその表面を撫でた。
「……鳴らしてみて、いただけますか」
俺は頷き、ゼンマイを巻いてストッパーを外した。あの優しい旋律が、再び店を満たす。千代は目を閉じ、じっと聴き入っていた。やがて、その目尻から一筋の涙が静かにこぼれ落ちた。
「ああ……おばあちゃんの音だ……」
彼女の呟きを聞きながら、俺は初めて、自分の能力について話す決心をした。
「千代さん。あなたのお祖母さんの人生は、決して不幸なものではありませんでした」
俺の唐突な言葉に、彼女は驚いて顔を上げた。
「俺には、物に触れると、持ち主の記憶が少しだけ見えるんです。このオルゴールからは、最初は何も感じられませんでした。でも、今なら分かります」
俺は言葉を選びながら、ゆっくりと続けた。
「あなたのお祖母さんの人生は、数えきれないほどの幸せで満ちていました。日向ぼっこの暖かさ、あなたの寝顔を見る喜び、静かな雨音の安らぎ……。あまりにたくさんの幸せがあったから、そのどれか一つを『最も幸せ』だなんて、選ぶことができなかったんです。このオルゴールは、そのすべての幸せの響きが詰まった、宝箱だったんですよ」
俺の言葉を聞き終えると、千代は声を上げて泣き始めた。それは悲しみの涙ではなかった。安堵と、喜びと、祖母への深い愛情が溶け合った、温かい涙だった。
「よかった……本当によかった……。おばあちゃん、幸せだったんだ……」
何度もそう繰り返す彼女を見て、俺の胸にも、これまで感じたことのない熱いものが込み上げてきた。他人の幸福に触れても、そこにあったのはいつも焦燥と孤独だけだった。だが今は違う。彼女の喜びが、まるで自分のことのように嬉しかった。
千代が感謝の言葉を残して帰った後、俺は一人、夕日で橙色に染まった店内に佇んでいた。カウンターの上に置かれた、自分用の、何の変哲もないコーヒーカップに目が留まる。
俺は、おそるおそる、そのカップに指先でそっと触れてみた。
流れ込んできたのは、特別な記憶ではない。
ただ、少し前に自分で淹れたコーヒーの温かさと、その香りがもたらす、穏やかな安らぎの感覚。そして、千代の涙を見て、心がじんわりと温かくなった、今の、この瞬間の気持ち。
それは、誰かの人生を照らすような、眩い光ではなかった。けれど、自分の足元を確かに照らしてくれる、小さく、しかし確かな灯火だった。
俺は、ふっと笑みをこぼした。
呪われていると思っていたこの指先は、もしかしたら、人生に満ちている無数の小さな祝福を見つけ出すためにあるのかもしれない。俺はまだ、自分の人生の旋律を奏で始めたばかりなのだ。
窓の外では、一日が終わろうとしていた。だが俺にとっては、新しい何かが始まる、美しい夕暮れに思えた。