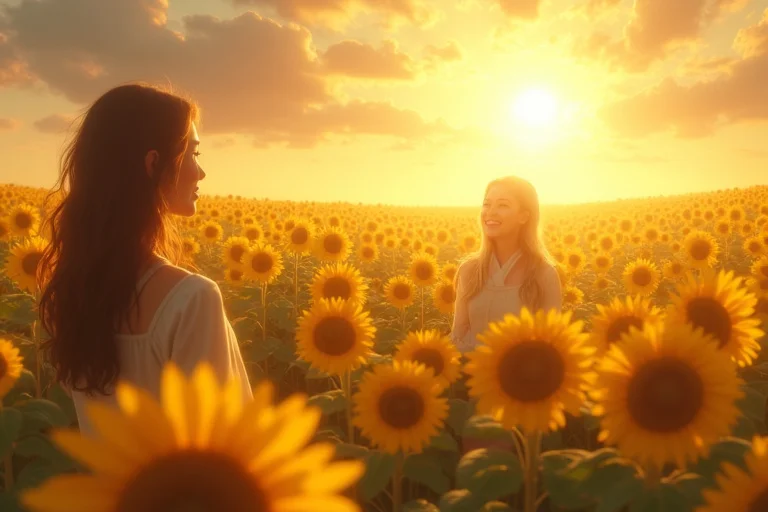第一章 幸福の対価
古い商店街の路地裏、忘れられたように佇むその店は「喪失買取処 忘れな草」という奇妙な看板を掲げていた。店主である私、霧島朔(きりしま さく)の仕事は、人々が手放したいと願う「喪失」を買い取ることだ。客が持ち込むのは、辛い記憶、失った才能、あるいは呪いのような恋心。私はそれらを特別な対価と引き換えに受け取り、アンティークのガラス瓶に封じ込めてきた。
その日、店のドアベルが告げた来客は、降りしきる五月雨の匂いを連れていた。現れたのは、傘から滴る雫で床に小さな水たまりを作る、線の細い女性だった。年の頃は二十代半ばだろうか。その瞳は、まるで深い湖の底のように静かで、一切の光を拒絶しているように見えた。
「いらっしゃいませ。何か、お売りになりたいものでも?」
私はいつものように、カウンターの内側から静かに問いかけた。店内には、乾燥させた薬草と古い木材の香りが混じり合って漂っている。彼女――水瀬唯(みなせ ゆい)と名乗った――は、濡れたコートの裾を気にしながら、震える声で言った。
「あの……ここが、喪失を買い取ってくださるお店で、間違いありませんか」
「ええ、その通りです。どのような喪失を?」
客の多くは、この問いに躊躇いを見せる。心の最も柔らかな部分に触れる痛みや恥辱を、言葉にして差し出すのだから無理もない。だが、彼女の答えは私の予想を、そしてこの店の常識を根底から覆すものだった。
「私から、幸福だった記憶を買い取ってください」
一瞬、時が止まったように感じた。カウンターに並ぶ、様々な色合いの「喪失」が詰められたガラス瓶たちが、静かに私を見つめている気がした。紫紺の悲嘆、鉛色の絶望、錆びついた赤の嫉妬。しかし、そのどれとも違う。幸福。それは、この店が扱うべき商品ではなかった。
「申し訳ありませんが、当店では幸福の類は買い取れません。買い取れるのは、お客様にとって重荷となる喪失だけです」
「これが、今の私にとって一番の重荷なんです」
唯の言葉は、雨音に溶け込むようなか細さでありながら、決して折れない芯を持っていた。
「彼との思い出が、輝いていればいるほど、今の私を殺していくんです。この光を消してください。どうか、お願いします」
彼女の瞳から、ついに一筋の涙がこぼれ落ちた。それは床に落ちて小さな染みを作る。私はその染みを見つめながら、初めて扱う「幸福」という名の喪失が、どれほどの絶望から生まれるのかを、静かに測りかねていた。
第二章 褪せない面影
それから唯は、雨の日も晴れの日も、飽きることなく店に通ってきた。私はその度に、丁重に、しかし断固として彼女の依頼を断り続けた。店の掟は絶対だ。負の感情や記憶がその人を蝕む前に引き剥がし、魂の平穏を取り戻させるのが私の仕事。幸福は、人が生きるための糧であり、それを奪うことは魂の殺人に等しい。
「彼と初めて会ったのは、海辺の小さな図書館でした」
ある日の午後、西日が店内に長い影を落とす中、唯はぽつりぽつりと語り始めた。彼女が売ろうとしている「幸福」の正体を、私は聞かずとも知ることになった。彼の名前は陽太(ようた)。笑うと目尻に優しい皺が寄る、太陽のような人だったという。
彼女が語る記憶の断片は、どれも眩い光に満ちていた。古書のインクの匂いがする静かな図書館での語らい。真夜中の公園で、二人で分け合った自動販売機の温かいココアの味。彼がプロポーズの言葉を探して、不器用に口ごもった日の、照れくさそうな横顔。それらはまるで、上質な絹織物のように緻密で、色鮮やかだった。
「その全てが、今は鋭いガラスの破片なんです。息をするたびに、胸に突き刺さる」
彼女はそう言って、きつく胸元を押さえた。陽太は、一ヶ月前の交通事故で、あっけなくこの世を去った。あまりに突然の、理不尽な喪失だった。
彼女の話を聞くたび、私の胸の奥深くで、固く閉ざしていた扉が軋む音を立てた。私自身もまた、かつて大切な光を失った人間だったからだ。その喪失感から逃れるようにして、私はこの「喪失買取処」を始めた。他人の痛みを受け入れることで、自分の痛みを麻痺させてきたのだ。唯の憔悴しきった姿は、鏡のように過去の私を映し出し、忘れたはずの疼きを呼び覚ました。
「もし、その記憶がなくなったら、あなたは何を頼りに生きていくのですか」
ある日、私はたまらずにそう尋ねた。
「頼るものなんて、もう何もいらないんです。ただ、空っぽになりたい。楽になりたい。それだけです」
彼女の瞳は、もはや涙すら浮かべていなかった。渇ききった湖底のようだった。その虚無に満ちた眼差しを見て、私はついに、店の掟を破る決意を固め始めていた。このまま彼女を放置すれば、彼女自身が記憶と共に消えてしまいかねない。それは、私が最も恐れる結末だった。
第三章 交叉する時間
「分かりました。あなたの『幸福な記憶』を、買い取りましょう」
数日後、再び店を訪れた唯にそう告げると、彼女の顔に初めて安堵と呼べる表情が浮かんだ。だが、その奥には深い哀しみが影を落としており、私の胸を締め付けた。
買い取りの儀式には、客の記憶が強く宿った「縁(よすが)」となる品が必要だ。唯が差し出したのは、彼から贈られたという小さな砂時計だった。ガラスの中で、星屑のようにきらめく銀色の砂が、さらさらと落ちていく。永遠に繰り返される、束の間の時間。
私はカウンターの上に、白檀の香を焚き、銀の匙と空のガラス瓶を用意した。儀式は単純だ。私が「縁」の品に触れ、記憶をたぐり寄せ、銀の匙で掬い取るようにして瓶に封じ込める。記憶を抜き取られた客は、その出来事自体は覚えていても、それに伴う一切の感情を失う。
「準備はよろしいですか。一度買い取った喪失は、二度とお返しできません」
最終確認の言葉に、唯は静かに、しかしはっきりと頷いた。
私は覚悟を決め、冷たいガラスの砂時計にそっと指を触れた。
その瞬間だった。
私の脳裏に、奔流のように映像が流れ込んできた。それは唯の記憶ではなかった。もっと生々しく、鮮烈な、死にゆく者の最後の視界。
―――雨の夜。車のヘッドライトが乱反射する濡れたアスファルト。ハンドルを握る若い男。助手席には、小さなベルベットの箱が置かれている。彼の顔は希望に満ち、少し緊張している。彼は唯に会いに行く途中だった。プロポーズするために。
次の瞬間、けたたましいクラクションと衝撃音。視界が激しく回転し、フロントガラスに広がる蜘蛛の巣状の亀裂。そして、最後に映ったのは、交差点の信号機だった。それは、故障して明滅を繰り返していた。
全身から血の気が引いていくのが分かった。あの信号機。あの交差点。私は知っている。
数年前、まだ私が電気工事士として働いていた頃のことだ。あの日、私は豪雨の中、あの交差点の信号機のメンテナンスを担当していた。急ぐあまり、私は一つの重要な確認作業を怠った。ほんの僅かな気の緩み。それが原因で、制御システムに致命的な欠陥が残ってしまったのだ。会社はミスを隠蔽し、私は罪悪感に苛まれて職を辞した。
巡り巡って、私の過去の過ちが、陽太という若者の命を奪い、目の前にいる唯から幸福を根こそぎ奪い去ったのだ。
私は、彼女の痛みに寄り添う資格などない、ただの加害者だった。彼女が忘れたいと願うほどの幸福は、私が引き起こした悲劇の裏返しに過ぎなかった。砂時計を持つ指が、氷のように冷え切っていく。
第四章 忘れ得ぬもの
「……できません」
絞り出した声は、自分でも驚くほどにかすれていた。唯が怪訝な顔で私を見つめる。
「買い取りは、できません」
私は砂時計から手を離し、カウンターに両手をついた。隠し通すことはできない。いや、してはならない。私は観念して、震える唇で全てを打ち明けた。あの日の豪雨、私の犯したミス、そしてそれがこの悲劇に繋がってしまったこと。
「あなたの恋人を殺したのは、間接的に……私なんです」
告白は、私自身に突き立てた刃でもあった。長年、心の奥底に封じ込めてきた罪悪感が、堰を切ったように溢れ出す。他人の喪失を買い取ることで、自分自身の罪から目を背けていただけだったのだ。その卑劣さに、吐き気がした。
唯は、ただ黙って私の話を聞いていた。その表情は能面のように動かず、何を考えているのか読み取れない。やがて、長い沈黙を破って彼女が口を開いた。
「そうだったんですね……」
その声には、怒りも、憎しみもなかった。ただ、深い、深い疲労と諦めが滲んでいた。
「もう、いいんです。誰のせいでもない。……ううん、誰かのせいにしたかったのかもしれない。でも、あなたが憎いとは、思えません」
彼女は立ち上がると、カウンターの上の砂時計をそっと手に取った。
「この記憶を売るのは、やめます」
その言葉に、私は顔を上げた。
「彼が生きていた証まで、消したくなくなりました。この痛みも、苦しみも、全部が彼と過ごした時間の一部なんです。忘れるんじゃなくて……この思い出と一緒に、生きていくことにします」
そう言った唯の顔には、吹っ切れたような、淡い微笑みが浮かんでいた。それは、雨上がりの空にかかる虹のように、儚くも美しい光を放っていた。
彼女が店を去った後、私は一人、地下の保管庫へと降りた。ひんやりとした空気の中、棚には無数のガラス瓶が並んでいる。私が人々から買い取ってきた、様々な形の喪失。その一番奥に、一つだけ、私自身の「喪失」を封じ込めた瓶があった。
埃をかぶったその瓶を、私は手に取る。ラベルには、私の拙い字でこう書かれていた。
『希望』
大切な人を守れなかった絶望の中で、私は自ら未来を信じる心を捨てたのだ。
私は瓶のコルク栓に、ゆっくりと指をかけた。固く閉ざされていたそれが、乾いた音を立てて抜ける。瓶の中から、目には見えない何かがふわりと解き放たれ、私の心に染み込んでいくのを感じた。それは暖かくも、切なくもある、微かな光だった。
喪失がなくなることはない。罪が消えることもない。だが、それらを抱えたままでも、人は再び前を向けるのかもしれない。
窓の外では、いつの間にか雨が上がっていた。濡れた路地を照らす夕日が、忘れな草の看板を黄金色に染めていた。