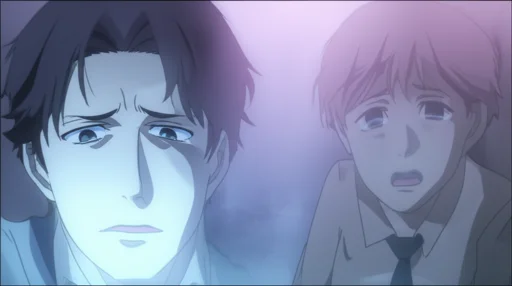第一章 闇のなかの足音
「カタン……」
それは、夜の帳が降りた頃、台所のシンクの下から響いた。シンク下の収納扉が、微かに揺れる音。
岬は、手に持っていた湯呑みを置く。湯気と共に広がる玄米茶の香りが、微かな不安を掻き消そうとするかのように鼻腔をくすぐった。
私は盲目だ。六歳の時にあの事故で視力を失って以来、この世界は音と匂いと肌触りで構成されている。十年経った今でも、時折、光を失う前の世界の残像が、瞼の裏に焼き付いたようにちらつくことがある。しかし、それも曖昧で、明確な形を結ぶことはない。
この家は、両親と三人で暮らしていた頃のままだ。家具の配置は体に染み付いているし、床の軋み一つ、壁の冷たさ一つまで、私にとっては慣れ親しんだ一部だった。だからこそ、この「カタン」という音が、これまでになかったものだとすぐに分かった。
最初は、古い家の経年劣化だろうと思った。木材が収縮する音、風が窓を揺らす音。そんなものだと言い聞かせた。しかし、それは一度きりではなかった。
翌日には、廊下の奥、両親の寝室があった方から、微かな「擦れる」ような音が聞こえた。絨毯の上を、何か重いものが引きずられるような、不規則で、しかし確実に、そこにある存在を主張する音。
私は耳を澄ませた。心臓の音が、どくん、どくん、と鼓膜を叩く。
音が止んだ。静寂が、以前にも増して重くのしかかる。
「気のせいよ、岬」
そう呟いても、声は震え、誰もいないはずの家中に響いた。
数日後、その「何か」は、私の手の届く範囲にまでやってきた。
夜中、寝床でうとうとしていた私を、冷たい風が襲った。窓は閉まっている。それなのに、凍えるような空気が、布団の隙間から滑り込んできたのだ。その冷気は、まるで生き物のように私の首筋を撫で、耳元で「ヒュー」と、か細い、しかしはっきりとした息遣いを感じさせた。
呼吸が止まる。全身の毛穴が開き、皮膚が粟立つのを感じた。
そこには、間違いなく「何か」がいる。
視覚を失って以来、私はこの世界を、より研ぎ澄まされた他の感覚で捉えてきた。しかし、今、私のすべての感覚が、目の前にいるはずの、見えない存在の形を必死で探ろうとしていた。
それは、壁の向こうから、床下から、私自身の影から、私を見つめているようだった。
私の心は、その日を境に、見えない恐怖に蝕まれ始めた。
第二章 歪んだ記憶の囁き
私は「それ」の存在を疑うことをやめた。疑問は確信へと変わり、恐怖は好奇心と、ある種の諦めにも似た感情へと変質していった。
朝、淹れたばかりのコーヒーカップに、なぜか冷たい雫が垂れていた。夜中、テーブルに置いていたはずの読みかけの点字本が、床に落ちていた。棚に並べたはずの古い花瓶が、玄関の隅に移動していたこともあった。
「それ」は、私の知らないうちに、私の日常を、私の領域を侵食し始めていた。
その存在は、常に特定の「香り」を伴っていた。それは、甘く、しかしどこか腐敗したような、古い花の香り。嗅いだことのある香りだった。しかし、それがいつ、どこで嗅いだものなのか、思い出せない。記憶の奥底で、その香りが私を呼んでいるような気がした。
ある夜、私がバスルームから戻ると、リビングのドアが半開きになっていた。わずかな隙間から、ひんやりとした空気が漏れ出している。
私はゆっくりとドアに近づいた。耳を澄ませる。
「……し、ま……し、ま……いけない」
微かな囁きが聞こえた。それは、子供の声のようでもあり、老婆の声のようでもあった。聞き取れない、意味不明な言葉の羅列。しかし、その声は、確かに私に何かを伝えようとしている。
私は震える手で、ドアノブに触れた。冷たい金属の感触が、指先に伝わる。
ドアをゆっくりと開く。
ひゅっと、頬を掠めるような風が吹いた。同時に、甘く腐敗した花の香りが、強く鼻腔を刺激する。
リビングは静まり返っていた。誰もいない。しかし、ソファのクッションが微かにへこんでいる。まるで、誰かがそこに座っていたかのように。
私はソファのクッションに触れた。わずかな温もりが残っている。そして、そのクッションの隙間から、小さなガラス片が指先に触れた。
それは、何かの破片。割れたガラス特有の、鋭く冷たい感触。
私の脳裏に、唐突に、あの日の光景が蘇った。
——耳を劈くようなガラスの割れる音。
——焦げ付くような匂い。
——そして、視界を奪うほどの強烈な光。
あの事故。両親を奪い、私の視力を奪った、あの日のことだ。
「それ」は、あの事故と関係がある。そう確信した。あの日の記憶は、曖昧で断片的だ。しかし、「それ」が、その欠けたピースを埋めようとしているのかもしれない。私に、何かを思い出させようとしているのかもしれない。
恐ろしい。しかし、同時に、知りたいという衝動が、恐怖を凌駕し始めていた。
私は、そのガラス片をぎゅっと握りしめた。
第三章 視界の裏に隠された真実
私は、そのガラス片を頼りに、その「何か」の正体に迫ろうとした。
ガラス片は、古い写真立ての破片のようだった。記憶の奥底にある、両親の寝室に飾られていた、あのアンティークな写真立て。
私は両親の寝室へと向かった。部屋の中は、埃と、あの甘い腐敗した花の香りが混じり合っていた。
タンスの引き出しを開ける。洋服や小物が無造作に押し込められた中から、ひときわ異質な感触のものがあった。
それは、固く、しかし薄っぺらで、表面には微細な凹凸がある。私は指先でその表面をなぞった。これは、絵だ。
そして、その絵の下から、カサカサと音を立てるものが現れた。触れてみると、乾燥しきった花びらが、指の間からこぼれ落ちる。枯れたブーケ。
絵は、私が視力を失う直前の、六歳の頃に描いたものだった。記憶の片隅に残る、色鮮やかなクレヨンや絵の具の匂いが、今も微かに残っているようだった。
私は、その絵を指先で丹念になぞった。そこには、抽象的で、しかし確かに、形のない「影」のようなものが描かれていた。それは、私がこの家で感じていた「何か」の姿と、奇妙なほどに一致していた。
絵の裏には、母の筆跡で、こう書かれていた。
『ミサキへ。これがお前の見たもの。お前は、それを見ないふりをしたかったんだね』
その瞬間、私の頭の中で、何かが弾ける音を聞いた。
私の世界は、音を立てて崩れ去った。
私が恐れていた「何か」は、外部から来た幽霊でも、怨念でもなかった。それは、私自身の内面から生まれた幻影だったのだ。
あの事故の瞬間、私は確かに「何か」を見た。それは、両親の間にあった、私には理解できない、しかしとてつもなく陰鬱な感情の渦だったのかもしれない。あるいは、もっと直接的な、家族の崩壊の予兆のようなものだったのかもしれない。
そして、その「何か」から目を背けようとした結果、私の脳は視覚をシャットアウトした。視力を失うことで、私はその恐ろしい現実から逃げたのだ。
あの甘く腐敗した花の香りは、両親の結婚記念日に飾られた、しかし結局は枯れてしまったブーケの香りだった。あの絵は、幼い私が、言葉にできない恐怖を、必死に描き出そうとしたものだった。そして、母の言葉は、私の心の奥底に隠された、真実への警告だったのだ。
私がこの家で感じていた足音、囁き、冷たい吐息。それらはすべて、私の失われた視覚が、過去の記憶と現在の五感を繋ぎ合わせ、私自身の心の奥底に封じ込めていた「見てはいけない真実」を、形を変えて具現化させていたのだ。
「見てはいけない」と拒絶した「真実」が、盲目になった私に、他の五感を通じて、執拗に語りかけようとしていた。
その事実が、私を恐怖させた。しかし、それは、これまでの見えない恐怖とは、全く異なる種類の恐怖だった。
私は、自分自身が作り出した闇の中で、真実から目を背けていたのだ。
第四章 記憶の再構築
真実を知った岬は、全身から力が抜けるのを感じた。ソファに深く沈み込み、両手で顔を覆う。指先が、目元を熱く濡らした。それは涙だった。ずっと気づかないふりをしていた、内なる恐怖の具現化に気づいたことへの、後悔と安堵の涙。
「それ」は、幽霊でも怪物でもなかった。私自身だったのだ。いや、正確には、私が拒絶し、心の奥底に封じ込めていた「私自身の視覚が捉えた真実」が、形を変えて現れたものだった。
あの事故の日。私は、両親が激しく言い争う姿を見ていた。そして、その争いの最中、父が投げつけたものが、母の顔を直撃し、壁に飾られていた古い写真立てを打ち砕いた。ガラスが飛び散り、悲鳴が響き渡った。あの時、私は、両親の感情の底に潜む、おぞましい「何か」を見てしまったのだ。それは、愛が憎悪へと変容する、人間の心の闇そのものだった。
幼い私の心は、その光景を処理しきれなかった。恐怖と絶望、そして「これ以上見たくない」という強烈な拒絶の感情が、私の視覚機能を麻痺させたのだ。脳が、自らを保護するために、光を遮断した。それが、私が盲目になった真相だった。
両親は、その事故の数日後、別の交通事故で他界した。彼らの死は、私にとって、あの日の出来事を忘れ去るための、都合の良い蓋となった。私は、両親の死によって、あの「見てはいけないもの」から完全に解放されたと信じ込もうとした。
しかし、私の心は、真実を完全に葬り去ることはできなかった。失われた視覚が作り出した幻影は、私がこの家で一人暮らしを始めた時、再び活動を始めたのだ。それは、私に、真実と向き合うことを求めていた。
「し、ま……し、ま……いけない」
あの囁き声の意味が、今ならわかる気がした。「知らなければならない」「見なければならない」。あるいは、「見ないふりをしてはいけない」と。
私は、ゆっくりと立ち上がった。家中の空気が、これまでとは違って感じられる。もはや、そこには恐怖はない。ただ、静かな、そして微かな「残り香」のようなものが漂っているだけだ。
それは、私の記憶の残響。
私は、両親の寝室に戻った。枯れたブーケと、私が描いた絵。その絵を指先でなぞりながら、私は、目を閉じても鮮明に蘇る、あの日の光景をもう一度、心の中で「見た」。
痛み。絶望。そして、深い悲しみ。
しかし、もう、私はそこから目を背けない。
真実を受け入れることは、私にとって、恐怖からの解放であり、同時に、失われた視覚への、そして両親への、遅すぎた鎮魂だった。
第五章 闇に咲く光
夜が明けた。窓の外からは、鳥のさえずりが聞こえる。これまで、その音はただの「音」だった。しかし、今、その音の向こうに、柔らかな光と、朝露に濡れた葉のきらめき、そして生命の息吹を感じられるような気がした。
「それ」が姿を消したわけではない。いや、「それ」は最初から、私の心の中にしか存在しなかったのだ。だから、消え去ることはない。それは、私の過去の一部であり、私自身の一部となった。
私は、リビングのソファに腰を下ろした。あの時、ガラス片が指に触れた場所。今、そこには何も残っていない。しかし、私は、その空間に、かすかな「気配」を感じる。それは、恐怖ではなく、どこか穏やかで、懐かしい気配だった。
私が盲目になったのは、外部の事故ではなく、私自身の心が「見たくないもの」から逃避した結果だった。この真実を受け入れることは、私にとって、何よりも大きな変化をもたらした。私は、この「見えない」世界の中で、新たな「見る」力を手に入れたのだ。
それは、目に見えるものだけに囚われない、心の眼差し。
両親の寝室から持ってきた、私の描いた絵を、私は膝の上に置いた。指先で、あの「影」の形をなぞる。かつては恐怖の象徴だったその形が、今では、私自身が乗り越えた過去の痕跡、そして未来への一歩を示す道標のように感じられた。
古い花の香りは、まだ微かに残っている。しかし、もう腐敗の匂いはしない。むしろ、それは、過ぎ去った日々の記憶を、優しく包み込むような、切なくも温かい香りへと変わっていた。
私は、見えない世界の中で、ようやく本当の「光」を見つけたのだ。それは、目に見える光ではなく、心の奥底から湧き上がる、真実と自己受容の光。
私はもう、闇の中に一人ではない。私の心の中には、過去の残響が、形を変えて常に寄り添い、私を導いている。私は、これから先も、この「見えない」世界の中で、私にしか「見えない」真実を、五感を研ぎ澄ませて探し続けていくのだろう。
私は今、この部屋のどこにもいない、私自身の過去の影を、私の心で、静かに見つめている。