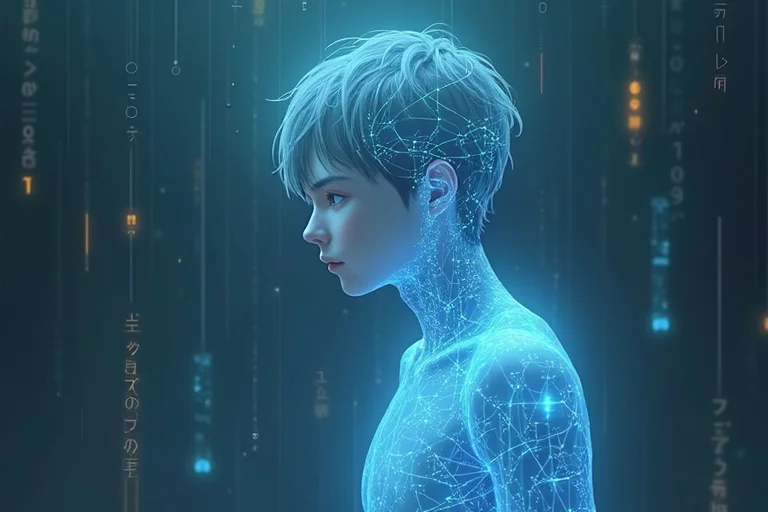第一章 色喰らいのカイ
俺の肌は、他人の絶望を吸って生きている。
路地裏の湿った石畳に腰を下ろすと、背を預けた壁の冷たさが染みた。人々が俺を避けて通る気配が、空気の微かな揺らぎでわかる。彼らの視線は、俺の肌を覆う毒々しい紋様に一瞬だけ触れ、すぐに嫌悪と恐怖に曇る。それは緋色、藍色、鬱金色が複雑に絡み合った、呪いのような色彩のタトゥー。誰かが人生を諦めたとき、その心の澱みが俺の身体に流れ込み、新たな模様を刻むのだ。痛みはない。ただ、孤独が深まるだけだ。
この世界では、『存在値』という尺度が人のすべてを決める。社会的貢献度が高い者ほど、その肉体は透明度を増していく。街を行き交う人々は皆、おぼろげなガラス細工のようだ。彼らの目標はただ一つ、完全な透明となり、物理的干渉すら受け付けない『無形の存在』として、この世界の頂点に君臨すること。それは、最も価値ある生き方だと誰もが信じて疑わない。
俺のような、他人の負の感情を吸収して色を濃くする存在は、そのシステムの底辺に位置する出来損ないだ。色濃く、不透明な肉体を持つことは、すなわち無価値の証明だった。
ポケットから古びた真鍮製の羅針盤を取り出す。繊細なガラスの下で、針だけが異様な色彩を放っていた。俺が吸収した絶望の色を凝縮したような針は、震えながら常に同じ方角を指し示している。都市の中央に聳え立つ、天にも届かんばかりの『天頂の塔』。そこに、『無形の存在』がいるとされていた。
第二章 羅針盤の囁き
市場の片隅で、俯く老婆がいた。彼女の周りだけ、空気が重く淀んでいる。手にした空っぽの籠を見つめる瞳は、もう何も映してはいなかった。その背中から立ち上る、深い深い諦めの匂い。それは、長年連れ添った夫を失い、誰からも忘れ去られた孤独の色だった。
俺がそばを通り過ぎた瞬間、その感情が奔流となって流れ込んできた。ぞわり、と肌が粟立つ。右腕に、深い紫色の蔓が伸びるように、新たな紋様が鮮やかに浮かび上がった。老婆は小さく息を吐くと、少しだけ顔を上げ、ふらりと歩き去っていった。彼女の絶望は、今や俺の肉体の一部だ。
その時だった。
胸のポケットで、羅針盤が熱を帯びて激しく震え始めた。ただ塔を指すだけだった針が、狂ったように回転し、今までとは比較にならないほどの強い光を放っている。俺は弾かれたように空を見上げた。天頂の塔の、その頂。完全に透明であるはずの空間に、ほんの一瞬、俺の腕に刻まれたばかりの、あの深い紫色が閃光のように揺らめいたのだ。
『無形の存在』が、色を帯びた?
彼らは、世界の理そのもの。絶対的な価値の化身。そんな彼らが、なぜ絶望の色を? 俺が吸収するこの忌まわしい色と、同じものを? 謎が、冷たい鉤爪のように俺の心を掴んだ。羅針盤の針は、まるで「来い」と囁くように、塔の頂を指して止まっていた。確かめなければならない。この身体に刻まれた無数の絶望の意味を、そして、あの頂で微かに煌めく色の正体を。
第三章 天頂への道
天頂の塔へ向かう道は、透明な壁に阻まれているようだった。物理的な障害はない。ただ、俺の色彩豊かな肌を見た人々が、まるで汚物でも見るかのように道を空け、囁き合う。その無数の視線と侮蔑が、見えない壁となって俺の歩みを鈍らせた。
「見て、あんなに色が濃い…」
「きっと、誰かの価値を吸い取って生きているのよ」
彼らの声は、乾いた風のように俺の耳を通り過ぎていく。俺はただ、羅針盤の針が示す一点だけを見つめて進んだ。
塔に近づくにつれて、人々の透明度は増していく。輪郭すら曖昧な彼らは、まるで陽炎のようだ。彼らが纏う空気はひどく希薄で、その存在に触れることすらできない。彼らは高め合った『存在値』の果てに、体温も、匂いも、人間らしい手触りさえも失っていた。俺はふと、自分の肌を覆う紋様に触れた。ざらりとした感触はないが、そこには確かに肉体の熱が宿っている。どちらが、本当に生きていると言えるのだろうか。
塔の麓に辿り着いた時、俺は同じように紋様を背負った男とすれ違った。彼の背中には、燃えるような朱色の鳥が描かれていた。俺たちは互いに視線を交わしたが、すぐに逸らした。慰めも、共感もない。ただ、同じ呪いを背負う者同士の、静かな諦めだけがそこにあった。俺たちは、この世界で互いの存在を肯定することさえ許されないのだ。
第四章 無形の心臓
塔の内部へは、驚くほど簡単に入れた。警備など存在しない。なぜなら、価値のない者がこの神聖な場所に足を踏み入れるなど、誰も想像すらしないからだ。
しかし、そこに広がっていたのは、俺が想像していたような物理的な空間ではなかった。床も壁も天井もない。ただ、無数の光の粒子が渦巻き、沈黙の音が満ちる、概念の海が広がっていた。人々の「価値を高めたい」という純粋な祈りと欲望が凝縮され、結晶化したような場所。歩を進めるたびに、足元で誰かの願いがさざ波のように砕けた。
羅針盤は、この空間の中心を指して、かつてないほど強く輝いている。俺はその光に導かれるように、渦の中心へと泳いでいった。
そして、最深部に辿り着く。
そこには、玉座も、祭壇も、そして『無形の存在』そのものもなかった。ただ、空間そのものが心臓のようにゆっくりと脈動し、その鼓動に合わせて、あの微かな色が明滅しているだけだった。俺が今まで吸収してきた、ありとあらゆる絶望の色。悲しみの青、怒りの赤、諦めの灰色。それらが混ざり合い、美しいとは到底言えない、濁った虹色となって空間の歪みから漏れ出していた。
羅針盤の針が示すもの。それは特定の誰かではなかった。この塔そのもの。いや、この世界を支配する『存在値』という概念、そのものだったのだ。人々が崇め奉る「価値」の頂点、その心臓部が、人々から切り捨てられた「絶望」によって蝕まれていた。
第五章 砕け散る神
俺がその濁った虹色に手を伸ばした瞬間、世界が軋む音がした。
俺の身体に刻まれた紋様と、空間に満ちる絶望の色が激しく共鳴する。今まで吸収してきた数え切れないほどの諦めや悲しみが、俺の内部で咆哮を上げた。それは個人の感情ではなかった。『存在値』という不条理な物差しによって人生を歪められ、価値がないと断じられた全ての人々の、声なき声の集合体だった。
『無形の存在』とは、個人ではなかったのだ。それは、人々が透明になる過程で切り捨ててきた人間性――喜び、怒り、そして悲しみ――その全てを受け止め、封じ込めるための巨大な器。人々が価値を高めるほどに、その対価として切り捨てられた絶望がこの塔に蓄積され、システムの根幹を成していた。
そして今、その器が、溜め込みすぎた絶望の重さに耐えきれず、限界を迎えようとしていた。
空間の歪みから、ピシリ、とガラスに亀裂が入るような音が響き渡る。一度入った亀裂は瞬く間に全体に広がり、濁った虹色の光が内部から溢れ出す。人々が神と崇めた絶対的な価値の概念が、自らが切り捨てたはずの感情によって、内側から崩壊していく。それはあまりにも皮肉で、そして荘厳な光景だった。
第六章 黎明の肌
天頂の塔が、砕け散った。
巨大なステンドグラスが粉々になるように、「価値」という概念は無数の光の破片となって世界中に降り注いだ。その一つ一つが、かつて誰かが切り捨てた絶望の色を宿した、優しく輝く粒子だった。
色彩の雨が、地上に降り注ぐ。それは俺の身体にも触れた。すると、まるで長年こびり付いていた古いインクが洗い流されるように、肌を覆っていた紋様が淡く溶け、剥がれ落ちていく。緋色も、藍色も、鬱金色も、全てが光の粒子に還り、空へと昇っていく。紋様が消えた跡には、生まれたままの、温かい肌が残されていた。
見渡せば、街の至る所で同じ奇跡が起きていた。紋様を背負い、俯いて生きてきた人々が、驚きと戸惑いの表情で自らの腕や顔に触れている。同時に、半ば透明になりかけていた人々も、失っていたはずの肉体の輪郭と色彩を徐々に取り戻していた。頂点が消えた世界で、『存在値』という呪いはその力を失ったのだ。
人々は初めて、ありのままの姿で互いを見つめ合った。そこにはもう、価値の優劣も、羨望も、侮蔑もない。ただ、同じ肌の色と体温を持つ、等しい人間がいるだけだった。
俺は、もう何も指し示さなくなった羅針盤を空に放った。それは小さな光の弧を描き、雑踏の中へと消えていく。
自らの、色のない、しかし確かな熱を持つ手のひらを見つめる。この手で、これから何を掴み、誰に触れるのだろう。答えはまだない。だが、絶望の色ではなく、希望の色を、この世界はこれから紡いでいくのだろう。
空には、色彩の雨が降らせた、美しい夜明けが広がっていた。