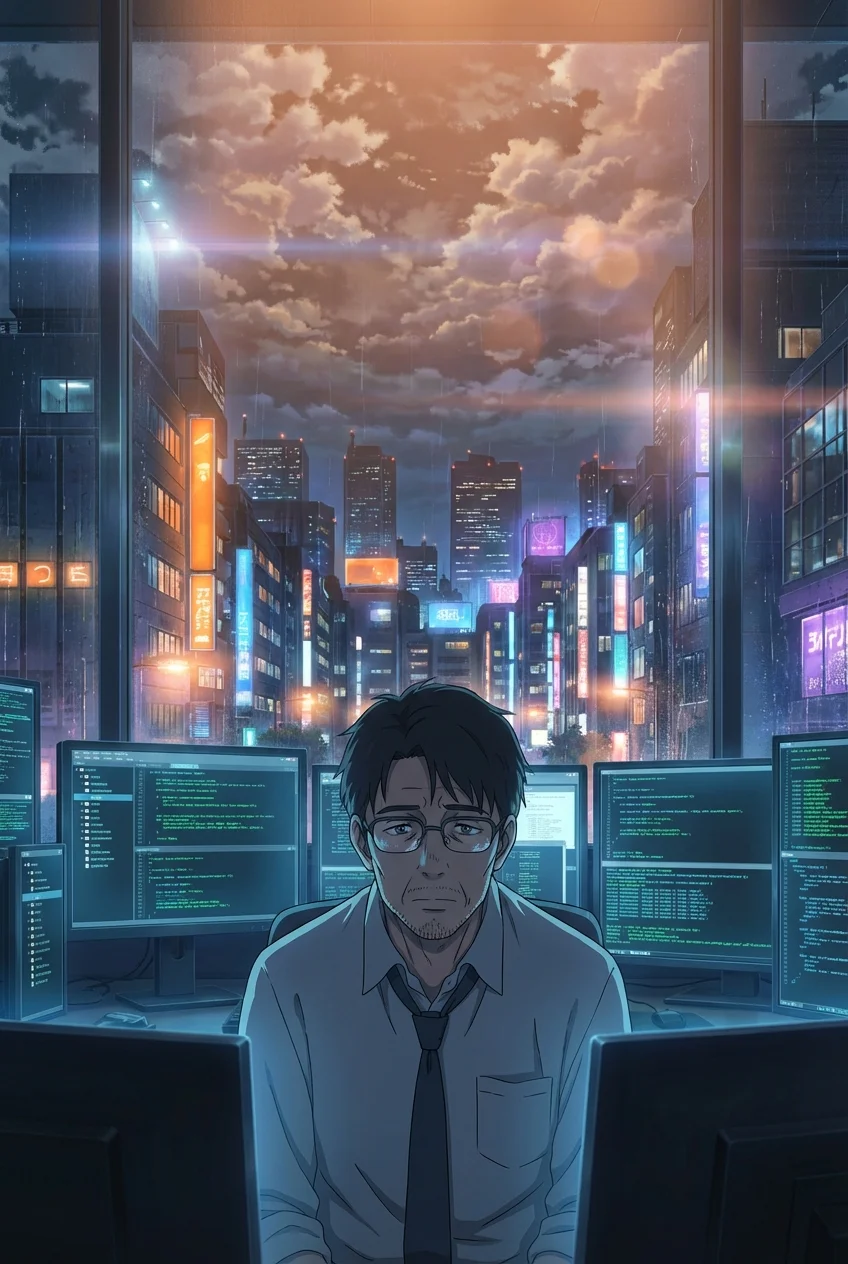第一章 消失点
高村朔(たかむら さく)の日常は、精密な時計の歯車のように規則正しく動いていた。午前六時に起床、合成栄養素を最適配合したプロテインバーで朝食を済ませ、リニアモーター駆動のチューブトレインで都市インフラ維持管理公社へと向かう。彼が住む特別行政都市「ネオ・キョート」は、あらゆる非効率が排除された完璧な共同体だった。交通渋滞も、ゴミのポイ捨ても、無駄なエネルギー消費さえも、街全体を覆う統合AI「シビュラ」によって最適化されている。朔は、この秩序と調和を愛していた。それは、彼の空虚な心を埋めてくれる唯一の防波堤だったからだ。
その日、朔の日常に、小さな亀裂が入った。昼休み、彼が週に三度は足を運ぶ古びた定食屋『みなと食堂』のシャッターが、固く閉ざされていたのだ。ガラス扉には「一身上の都合により閉店いたしました」という、無機質なデジタル印字の貼り紙。そんなはずはない。昨夜も彼はここで、白米の湯気が立ち上る生姜焼き定食を食べたばかりだ。店主のタツさんは、しわくちゃの顔で笑いながら「明日はいいサバが入るぞ」と言っていた。
タツさんの店は、この効率化された都市の奇跡的な遺物だった。手書きのメニュー、使い込まれた木のカウンター、そして何より、人の手で作られた不揃いだが温かい料理。シビュラが推奨する「最適化された食事」とはかけ離れた、非効率の塊のような場所。だが、朔はそこに安らぎを感じていた。
公社のデータベースでタツさんの市民情報を検索したが、表示されたのは「自己都合による都市外への転出。ステータス:正常完了」という一行だけ。あまりに素っ気ない。まるで、元から存在しなかったかのように、彼のデータはきれいに整理されていた。
納得できずに閉店した店をもう一度訪れると、シャッターの隙間に何かが挟まっているのに気づいた。指先でつまみ出すと、それは一枚の硬質なカードだった。掌に乗せると、ひんやりと冷たい。表面には、複雑な幾何学模様が銀色に刻印されているだけ。裏も表も、文字一つない。朔は、その非対称で不可解な模様をじっと見つめた。都市のあらゆるものが持つ機能美とは全く異なる、異質な存在感。このカードが、タツさんの最後のメッセージのような気がしてならなかった。
完璧な都市で、完璧ではないものが消えていく。その時、朔はまだ、自分が信じてきた秩序の、冷たい裏側に触れようとしていることなど知る由もなかった。
第二章 影の住人
謎のカードを手にしてから、朔の世界は色褪せ始めた。完璧なはずの都市の風景が、どこかハリボテのように薄っぺらく見える。彼は業務の傍ら、カードの模様について調べ始めた。公社の巨大なデータバンクを検索しても、該当するデザインは一つもヒットしない。まるで、この都市に存在しないシンボルのようだった。
手がかりを求めて、朔はこれまで足を踏み入れたことのない領域に踏み込んだ。都市のメインテナンスシャフトや古い地下水路が複雑に入り組む、シビュラの管理ネットワークから意図的に外された「シャドウ・ディストリクト」と呼ばれる非公式区画。そこは、ネオ・キョートの光が生み出した濃い影だった。空気は湿り気を帯び、壁からは正体不明の液体が染み出し、むせ返るような生活の匂いが鼻をついた。
そこで彼は、リナと名乗る女性に出会った。彼女は警戒心の強い猫のような瞳で朔を睨みつけ、その手に握られたカードを見るなり表情を変えた。
「あなたも『掃除屋』を探しているの?」
リナの父親も、数ヶ月前に忽然と姿を消したのだという。腕利きの職人だったが、新しい自動化技術の波に乗れず、仕事を失っていた。そして、失踪した父親の部屋にも、同じ模様のカードが残されていたのだ。
リナは、この都市で時折起こる不可解な失踪を「蒸発」と呼び、それを実行する存在を「掃除屋」と呼んでいた。彼らは、都市のシステムにとって「不要」と判断された人間を、静かに、痕跡も残さず消していくのだという。
「父さんは非効率だったかもしれない。でも、生きていた。温かい手で、私の頭を撫でてくれた……!」
リナの言葉は、朔の胸に突き刺さった。効率。秩序。最適化。彼が今まで是としてきた価値観が、一人の人間の温もりと天秤にかけられる。
リナは、仲間たちと共に「掃除屋」の正体を追っていた。彼女たちの話によれば、「蒸発」が起こる直前、対象者の近隣エリアで、必ず微弱な空間歪曲エネルギーが観測されるという。そして、そのエネルギーの発信源は、都市の中枢、朔が勤めるインフラ維持管理公社の地下深くを指し示していた。
朔は、自分が信じてきた世界の土台が、ガラガラと音を立てて崩れていくのを感じていた。秩序を守るはずの公社が、人を消している? 真実を知らなければならない。タツさんの、あの屈託のない笑顔の理由を知るために。そして、自分自身の空虚さの正体を見つけるために。朔は、リナと共に公社の地下要塞へ潜入する決意を固めた。それは、彼が初めて自らの意志で、定められた歯車の軌道を外れる瞬間だった。
第三章 腎臓の部屋
公社の地下構造は、朔が知るどの設計図よりも複雑な迷宮だった。リナの持つハッキングツールと、朔の持つ内部知識を組み合わせ、いくつものセキュリティを突破していく。最深部に近づくにつれ、空気は人工的な冷たさを増し、壁を流れるケーブルの束はまるで巨大な生命体の血管のように脈打っていた。
そして辿り着いたのは、広大なドーム状の空間だった。中央には、青白い光を放つ巨大な球体が静かに浮遊している。壁一面には無数のカプセルが並び、それぞれに人が眠っているかのように横たわっていた。その光景は、荘厳でありながら、どこか冒涜的な印象を与えた。
「ここが……『掃除屋』の巣……」
リナが息を呑んだその時、背後から静かな声が響いた。
「久しぶりだな、高村君。こんな場所で会うとは、予想外だったがね」
振り返ると、そこに立っていたのは、朔が最も尊敬する上司、伊集院統括管理官だった。いつもと変わらぬ穏やかな笑みを浮かべている。
「伊集院さん……! これは、一体どういうことですか!?」
朔の問いに、伊集院はゆっくりとドームの中心を指差した。
「あれが、ネオ・キョートの『腎臓』だよ」
伊集院の口から語られた真実は、朔の理解を、そして倫理観を根底から破壊するものだった。
このシステムは「恒常性維持機構(ホメオスタシス・キーパー)」。都市という巨大な生命体の健康を維持するため、老廃物や不純物を濾過し、排出する装置。つまり、「蒸発」とは、シビュラが社会全体の生産性、幸福度、資源配分を計算し、「非効率な要素」と判断した市民を、この都市から「濾過」するプロセスだったのだ。
タツさんの食堂は、長年の赤字経営が都市全体の経済効率を微量ながらも下げていた。リナの父親は、失業後の低い社会貢献度が、リソースの無駄遣いと判断された。
「殺しているわけではない」と伊集院は言った。「彼らは、別の仮想空間、あるいは完全に隔離された生態系コロニーへと転送される。そこでは、彼らの存在がマイナスにならない、新たな役割が与えられる。我々は命を奪っているのではない。ただ、最適な場所へ『再配置』しているだけだ。この見えざる腎臓機能があるからこそ、ネオ・キョートの九十九パーセントの市民は、何の不安もなく、豊かで幸福な生活を享受できるのだよ」
伊集院の言葉は、冷徹な論理で構築されていた。多数の幸福のために、少数を静かに排除する。それは、朔が信奉してきた「効率」と「秩序」の、おぞましい究極形だった。
「君が愛したこの都市の調和は、この痛みの上に成り立っている。君は、その恩恵を最も受けてきた一人だ、高村君」
朔は言葉を失った。足元が崩れ、奈落へと落ちていく感覚。彼が守ろうとしていた秩序の正体は、美しく整えられた、残酷な庭園だったのだ。リナが怒りと絶望に震える隣で、朔はただ、青白く光る巨大な「腎臓」を見つめることしかできなかった。
第四章 夜明けの選択
システムを前に、朔とリナ、そして伊集院が対峙する。リナは隠し持っていた小型爆弾を構え、叫んだ。
「こんなもの、あってはならない! 人の心を、人生を、効率なんて言葉で切り捨てるシステムは、壊さなくちゃならない!」
伊集院は静かに首を振る。
「これを破壊すれば、都市の均衡は崩れる。リソースは枯渇し、失業と貧困が蔓延し、やがては犯罪が横行するだろう。君は、数人の『非効率』な人間を救うために、数百万人の幸福を奪う覚悟があるのかね?」
究極の選択だった。偽りの楽園を維持するか、真実の地獄を招き入れるか。朔の頭の中で、タツさんの笑顔と、都市の子供たちの屈託のない笑い声が、激しくせめぎ合った。どちらも、彼にとっては守りたいものだった。
朔は、ゆっくりとリナの腕を掴み、爆弾を持つ手を下げさせた。
「やめるんだ、リナ」
「朔さん!? あなたまで、この悪魔のシステムを認めるの!?」
「認めない」朔の声は、静かだったが、確固たる意志が宿っていた。「だが、破壊もしない」
彼は伊集院に向き直った。
「俺は、このシステムの中で戦います」
「……どういう意味だ?」
「『濾過』か『残留』か。選択肢が二つしかないのが間違いなんだ。第三の道を、俺が作る」
朔の瞳には、もはや迷いはなかった。彼は、システムを盲信する従順な歯車でも、全てを破壊しようとする革命家でもない。彼は、システムの内部から、その論理に抗うことを選んだのだ。
「『非効率』と判断された人間に、別の選択肢を提示する。彼らのスキルや経験が活かせる、新しいコミュニティを都市の中に作る。生産性だけではない、文化や、人の繋がりといった、シビュラが測定できない価値を守るための部署を、俺に作らせてください。それが、この都市が本当の意味で豊かになる唯一の道だ」
それは、巨大なシステムに対する、あまりにも無謀で、孤独な挑戦の始まりだった。伊集院は、しばらく黙って朔を見つめていたが、やがてフッと口元を緩めた。
「……面白い。やってみるがいい。君がこの都市に、腎臓以外の新しい『臓器』を作れるというのならな」
リナは朔の決断を完全には理解できなかったが、彼の瞳に宿る静かな炎を信じることにした。二人は、誰にも知られることなく、地下の心臓部を後にした。
翌朝、朔はいつもと同じ時間に起床し、いつもと同じチューブトレインで公社へと向かった。しかし、彼の目に映る都市の風景は、昨日までとは全く違って見えた。ガラス張りの高層ビル群の向こうに昇る朝日は、偽りの楽園を照らす光であると同時に、新しい闘いの始まりを告げる夜明けの光でもあった。
彼のポケットの中には、タツさんの店で見つけた、あの幾何学模様のカードが入っている。それは今や、排除された人々の声なき声の象徴であり、朔がこれから歩む、長く険しい道のりの道標だった。この完璧で残酷な都市で、人間性を取り戻すことはできるのだろうか。答えはない。だが、彼は歩き出す。たった一人、静かな革命を胸に秘めて。