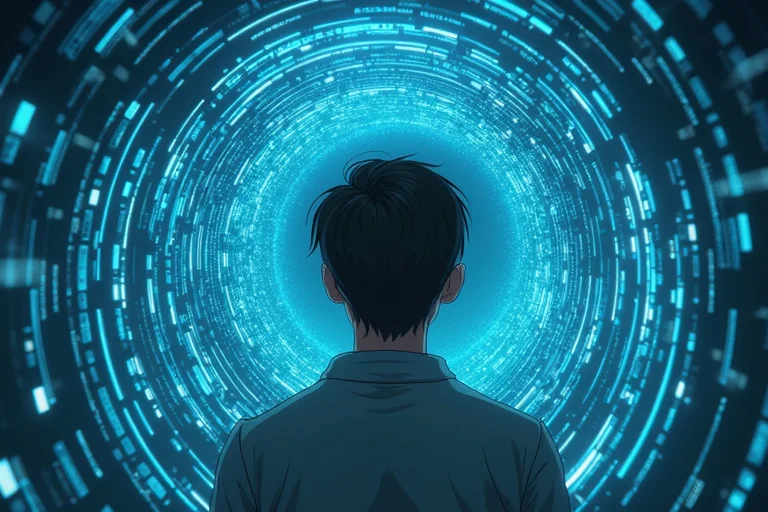第一章 欠けたパズル
柏木湊(かしわぎ みなと)の世界は、秩序とロジックで構築されていた。彼が勤める中央記憶取引監視機構のオフィスは、白い壁と磨き上げられたガラスで構成され、空気さえも濾過されているかのように無機質だ。彼の仕事は、国民の「記憶」の売買が、法規定の範囲内で公正に行われているかを監視すること。人々は生活苦から辛い記憶を売り、富裕層は退屈しのぎや経験の代行として他人の記憶を買う。このシステムが社会の歪みを吸収し、安定に貢献していると湊は固く信じていた。彼は、感情に流されず、データと規定のみを信じる優秀な審査官だった。
その日、湊のモニターに奇妙なアラートが点灯した。第7管区――通称「沈黙の街」と呼ばれる貧困地区で、極めて良質な「幸福記憶」が、この一ヶ月で三十七件も売却されている。しかも、すべて異なる人物からだ。子供の誕生、恋人との最初のキス、家族との温かい食卓。人が最も手放しがたいはずの、陽だまりのような記憶ばかり。
「妙だな」
湊は眉をひそめた。システムの脆弱性を突いた、新手のマネーロンダリングか、あるいは何者かが弱者を脅して記憶を搾取しているのか。データベースを深く掘り下げても、手続き上の不備は見当たらない。すべて合法的な取引として処理されている。しかし、彼の直感が警鐘を鳴らしていた。まるで、美しい蝶の標本がずらりと並べられているような、完璧すぎるがゆえの不気味さがあった。
彼は、自分のデスクに置かれた一枚だけの写真立てに目をやった。色褪せた写真には、幼い自分が、顔のよく見えない少女と手をつないでいる。妹だ。確か、病気で早くに亡くなったはずだ。だが、不思議なことに、彼女の声も、笑い方も、どんな顔をしていたかすら、霞がかかったように思い出せない。記憶のパズルから、最も重要なピースが抜け落ちているような感覚。その欠落感を振り払うように、湊は立ち上がった。
「第7管区の現地調査を申請します。コード・レッド案件の可能性あり」
彼の声は、静かなオフィスに確信を持って響いた。失われた他人の幸福の裏に潜む闇を暴くこと。それが、自分の内なる空虚を埋める唯一の方法であるかのように。
第二章 空っぽの温もり
第7管区は、湊が住むクリーンな都心とは別世界だった。空はいつも排気ガスのフィルターを一枚通したように色褪せ、建物は修復を諦めた傷跡を無数に晒している。路地裏に漂うのは、湿った埃と、安酒と、そして諦念の匂い。ここで人々は、魂を少しずつ切り売りして、その日を生き延びていた。記憶を売った者は「ブランク」と呼ばれ、時にその瞳から感情の光が消えているように見えた。
湊は身分を隠し、情報屋を通じて「幸福記憶」の売り主の一人を探し当てた。リナという名の、まだ二十歳を過ぎたばかりの女性だった。彼女は、錆びついたアパートの一室で、病気の幼い弟と二人で暮らしていた。部屋には生活必需品以外ほとんど何もなく、がらんとした空間が彼女たちの困窮を物語っていた。
「あなたが、家族旅行の記憶を売った方ですね」
湊が尋ねると、リナは一瞬、遠くを見るような目をした。
「……ええ。弟の薬代が必要だったから。もう、昔のことですから」
彼女の声には、諦めと、わずかな痛みが滲んでいた。湊は、彼女が売った記憶データを思い出す。海辺ではしゃぐ幼い弟、夕日を浴びて笑う両親、潮の香り、肌を撫でる温かい風。五感の全てが満たされる、完璧な幸福の記録。それを、彼女は自ら手放したのだ。
「後悔は?」
「後悔したって、弟のお腹は膨れない」
リナはそう言って、弟の寝ているベッドに目をやった。その横顔には、湊がこれまでデータ上でしか見たことのなかった「愛情」という感情が、ありありと刻まれていた。彼女は続ける。
「でも、不思議なんです。記憶を売って、データはもう私の中にないはずなのに……時々、胸のあたりが、ふっと温かくなることがある。空っぽのはずの場所に、温もりの感触だけが残っているみたいに」
その言葉は、湊の心を強く揺さぶった。彼はシステムを、記憶はデジタルデータであり、完全に移行・削除が可能だと理解していた。だが、彼女が語る「温もりの感触」は、そのロジックでは説明できない。それは、魂の残響のようなものだろうか。
湊は、リナの姿に、思い出せない妹の影を重ねていた。もし、自分があの時、彼女の側にいてやれたなら。もし、このシステムがなければ、彼女は大切な記憶を売らずに済んだのではないか。彼の信じてきた正義が、足元からぐらつき始めていた。この街で起きていることは、単なる犯罪ではない。もっと根源的な、人間の尊厳に関わる問題なのではないか。彼は、この取引の買い主――幸福を消費する側の正体を突き止めることを決意した。
第三章 共感の代償
調査は、湊の予想を遥かに超える、おぞましい真実へと繋がっていた。彼が追っていた「幸福記憶」の買い主は、犯罪組織などではなかった。最大の顧客は、彼が住む都心にそびえ立つ超高級エンターテイメント施設、「エデン・コア」だった。
湊は特権を使い、エデン・コアの内部データにアクセスした。そこで彼が見たのは、富裕層向けの最新サービス『リアル・エモーション・ダイブ』の企画書だった。それは、貧困層から買い取った純度の高い感情記憶を、VR技術と組み合わせ、他人の人生をリアルに「追体験」する、究極のエンターテイメント。彼らは、貧しい人々の幸福を、金を払って消費していたのだ。リナが売った家族旅行の記憶は、誰かの週末の娯楽になっていた。
愕然とする湊に、追い打ちをかけるように第二の衝撃が襲う。この非人道的なビジネスモデルを考案し、裏で推進していたのが、彼が所属する「中央記憶取引監視機構」の上層部そのものだったのだ。「社会の安定」という大義名分は、搾取構造を隠蔽するための欺瞞に過ぎなかった。機構は、貧困層から安く記憶を買い叩き、富裕層に高く売りつけることで、莫大な利益を上げていた。湊が信じてきた正義は、巨大な偽善のシステムを維持するための一つの歯車でしかなかった。
彼は震える手で、自身の個人ファイルへのアクセス権限をこじ開けた。何か、恐ろしい予感がしたからだ。そして、その最も深い階層に、厳重にロックされた一つのファイルを見つけた。それは彼の両親による、「記憶売却同意書」だった。
売却された記憶のタイトルは、『娘・沙耶(さや)の死の記憶、及び関連する全感情記録』。
――頭を殴られたような衝撃。湊はその場に崩れ落ちた。彼の妹は、病死ではなかった。不慮の事故だった。そして、当時まだ幼かった湊は、その現場に居合わせ、心に深い傷を負った。彼の両親は、息子の将来を案じ、彼の精神を守るという名目で、妹に関する全ての辛い記憶を売り払ったのだ。その売却で得た金が、彼の教育費となり、エリートとしての道を開いた。
彼が忘れていたのは、妹の顔だけではなかった。彼女の死の瞬間の絶望、自分の無力さ、そして悲しみという、人間として当然抱くべき感情そのものだった。彼の成功は、妹の存在そのものを対価とした、血塗られた犠牲の上に成り立っていた。彼が守ろうとしていた秩序は、彼自身から最も大切なものを奪った張本人だったのだ。
オフィスの白い壁が、ぐにゃりと歪む。自分が立っている場所が、信じてきた全てが、音を立てて崩壊していく。空っぽだったのは、パズルのピースだけではなかった。彼自身の魂の、中心そのものだった。
第四章 記憶の証人
機構を辞めた湊は、数週間、抜け殻のようになって自室に閉じこもった。彼を支えていた世界の全てが嘘だったという事実に、精神が耐えきれなかったのだ。しかし、リナが語った言葉が、暗闇の中で何度も響いた。
『空っぽのはずの場所に、温もりの感触だけが残っているみたいに』
失われたはずの記憶。だが、その残響は消えない。湊は、自分の胸に手を当てた。そこには確かに、形にならない温もりのようなものがあった。それは、忘却の彼方に追いやられた妹・沙耶への、消えない愛情の残滓なのかもしれなかった。
彼は立ち上がった。巨大なシステムを今すぐ破壊することはできない。だが、何もしないままではいられない。彼は再び第7管区へ向かった。以前のようなエリートのスーツではなく、着古した普段着で。
湊は、街の片隅にある閉鎖された小さな図書館を借り受け、一つの活動を始めた。『エコー・アーカイブ』と名付けたその場所で、彼は記憶を売った人々、ブランクたちの話を聞き、それをノートに書き留め始めた。データとしてではなく、言葉として。物語として。
「どんな些細なことでもいいんです。あなたが覚えている、その温もりの感触について教えてください」
最初は誰もが訝しんだ。だが、湊が一人一人の話に真摯に耳を傾けるうち、人々は少しずつ心を開き始めた。売ってしまった娘の運動会の記憶の断片。消したはずの故郷の祭りの音。彼らは、データ化できない「感触」や「匂い」や「音」の記憶を、ぽつりぽつりと語り出した。
ある日、リナが弟を連れてアーカイブを訪れた。
「私の記憶、まだどこかに残っていますか?」
湊は、静かに頷いた。
「ええ。あなたの話を聞かせてください。あなたの言葉で、あなたの物語を、ここに残しましょう。それは誰にも奪えない、あなただけのものです」
湊は、彼らの物語を記録し続けた。それは、巨大な搾取システムに対する、あまりにもささやかで、無力な抵抗かもしれない。だが、失われた記憶の残響に耳を澄まし、それを物語として紡ぎ直す行為は、人間の尊厳を取り戻すための、静かだが確かな戦いだった。
夕暮れ時、湊は図書館の窓から、沈黙の街を染める茜色の空を見上げた。それは、いつか妹と見た空の色に、少しだけ似ているような気がした。彼の瞳には、かつての冷徹な光はなく、痛みを知る者だけが持つ、深く、そして温かい光が宿っていた。本当の意味で、彼の人生が始まった瞬間だった。