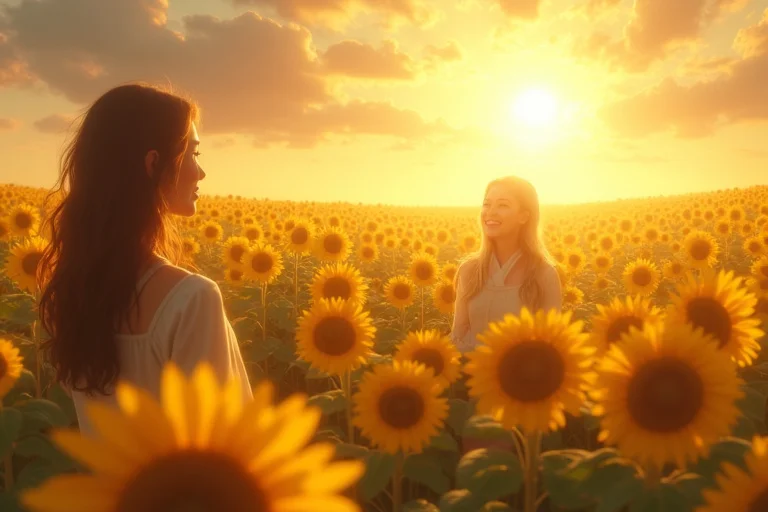第一章 空虚な軽さ
僕、柏木カイの指先は、少しばかり嘘がつけない。他人の肌に触れると、その人が抱える「過去への未練」が、ずしりとした物理的な重さとして伝わってくるのだ。それはまるで、湿った鉛の塊を直接心臓にねじ込まれるような、鈍い圧迫感だった。未練が深ければ深いほど、その人物の輪郭は現実から剥離するように霞み、存在そのものが曖昧な陽炎のように揺らめいて見える。
古物商という仕事は、そんな僕にとって天職でもあり、呪いでもあった。古い品々に残された、持ち主たちの重い記憶。それを手でなぞり、来歴を読み解く。だが、生きている人間との接触は、極力避けていた。誰もが、その背後に過去の自分の「影」を引きずって歩いている。手放した恋人、叶わなかった夢、帰れなくなった故郷。その半透明な幻影は、未練の象徴として、その人の傍らに寄り添い続けている。
だから、親友のリョウに再会した時、僕は息を呑んだ。彼の背後に、いつもいたはずの「影」が、忽然と消えていたからだ。彼の影は、三年前に事故で亡くなった恋人の姿をしていた。ヴァイオリンを奏でる、優美な横顔の影。それが、ない。
「カイ、久しぶりだな」
そう言って笑うリョウの肩に、僕は恐る恐る手を置いた。覚悟していた、ずっしりとした重さはない。代わりに指先を通り抜けていったのは、奇妙なほどに軽い、中身のない風船に触れているかのような、心許ない浮遊感だった。
「解放されたんだ。ようやく、あいつのことから」
リョウの声は晴れやかだったが、僕の目には、彼の存在がかつてないほど希薄に、今にも風に溶けて消えてしまいそうに霞んで見えた。それは解放の軽やかさではない。すべてを失った者の、空虚な軽さだった。
第二章 過去の侵食
リョウがおかしくなり始めたのは、それから一週間も経たないうちだった。
「オルゴールが、戻ってくるんだ」
電話口の声は、微かに震えていた。それは、亡くなった恋人が彼に贈った、最後のプレゼント。彼は影が消えた日に、思い出の品をすべて処分したはずだった。それなのに、捨てたはずのオルゴールが、翌朝には枕元に戻っていたという。
最初は気のせいだと思った。だが侵食は、静かに、しかし確実に彼の日常を蝕んでいった。彼女が編んだマフラーが、いつの間にかクローゼットに掛かっている。二人で撮った写真が、本棚の隙間から滑り落ちてくる。リョウが忘れたいと願った過去の遺物が、まるで意思を持ったかのように彼の前に現れ、その存在を主張し始めた。
彼の部屋を訪ねると、古い木の匂いに混じって、微かに彼女の使っていた香水の香りがした。リョウは痩せ、その輪郭はさらに曖昧になっている。彼に触れるたびに増していく「軽さ」は、僕を不安にさせた。まるで魂が少しずつ削り取られているかのように、彼の存在のテクスチャが失われていく。
「大丈夫だ」
彼はそう繰り返すばかりで、僕の差し伸べた手を弱々しく払いのけた。
第三章 影の欠片
この現象は、ただの幻覚ではない。僕は確信していた。リョウの身に起きていることは、僕の能力や、この世界の「影」の法則と深く関わっているはずだ。僕は店にある古文書を片っ端から読み漁った。そして、一つの記述にたどり着く。
――未練は質量を持つ。故に、極めて稀に、強い未練を吸い込み結晶化することがある。それを「影の欠片」と呼ぶ――
僕は、取引のある老齢の古物収集家を訪ねた。彼は僕の能力を知る、数少ない人物だ。事情を話すと、老人はため息をつき、桐の小箱から手のひらサイズの半透明な鉱石を取り出した。淡い乳白色の光を内包し、触れるとひんやりと冷たい。これが「影の欠片」だった。
「気をつけて使え。これは、魂の古傷を抉り出す石だ」
老人の忠告を背に、僕は石を握りしめた。途端に、脳裏に見知らぬ男女の断片的な記憶が流れ込む。戦地へ向かう息子を見送る母親の祈り。舞台の袖で、主役になれなかったバレリーナの涙。石に触れた者たちの、最も強い未練が幻影となって浮かび上がるのだ。
僕は、これをリョウの「過去の物」に触れさせるしかないと決意した。
第四章 転嫁された哀しみ
リョウからの連絡が途絶えた。僕は嫌な予感に駆られ、彼のマンションのドアを叩き続けた。返事はない。合鍵でドアを開けると、部屋は異様な光景に満ちていた。
オルゴールが、マフラーが、写真が、手紙が。無数の「過去の遺物」が部屋の至る所に散らばり、それぞれが微かに震え、囁くような音を立てている。まるで、物自体が生きているかのように。
部屋の隅で、リョウが蹲っていた。その姿は、ほとんど透けて見えそうなくらいに薄い。
「リョウ!」
僕は彼に駆け寄り、その冷たい手に「影の欠片」を無理やり握らせた。
瞬間、僕の意識は凄まจい奔流に飲み込まれた。
――それは、雨の降る夜のリョウの部屋だった。彼は恋人の「影」に向かって、何度も何度も叫んでいた。「もう、楽にしてくれ」「忘れたいんだ!」。彼は泣きながら、彼女の遺品を一つ一つ手に取った。オルゴールに、マフラーに、写真に。そして、祈るように、呪うように、囁き続けたのだ。
「僕の未練を、君が引き受けてくれ」
「この哀しみを、君に移す」
「僕の中から、消えてくれ」
彼の強い意志が、未練という名の重りを、恋人の影から物たちへと無理やり「転嫁」させていく。影は徐々に薄れ、やがて光の粒となって消滅した。解放されたリョウは笑った。だが、その足元では、未練の重みを受け継いだ物たちが、怨嗟のように微かな呻き声を上げていた。
幻影から覚めた僕の目の前で、リョウが泣き崩れていた。「解放なんかじゃなかった。これは…ただの置き換えだったんだ」
第五章 置き去りの自分
未練の器と化した物たちは、その重みに耐えきれず、半ば意思を持つ「過去の残滓」となってリョウを苛んでいたのだ。彼を過去に引きずり戻し、新しい未来へ進ませないために。
「救われるには、もう一度向き合うしかない」僕はリョウに言った。「今度こそ、正しく手放すために」
リョウは頷いた。彼は震える手で、まずオルゴールを拾い上げる。そして、それにまつわる幸せな記憶を語り、最後に「ありがとう。もう、行くよ」と告げた。すると、オルゴールの震えがぴたりと止み、ただの古い置物に戻った。
一つ、また一つと、彼は過去と対峙していく。マフラーに感謝し、写真に別れを告げ、手紙を燃やす。そのたびに、部屋を満たしていた不気味な気配が薄れ、リョウの輪郭が僅かずつ色を取り戻していくようだった。
その光景を静かに見守りながら、僕の心に一つの巨大な疑問が浮かび上がっていた。
なぜ、僕には「影」がないのだろう?
僕には、手放した過去も、叶わなかった夢も、何一つないというのか? そんなはずはない。
僕は衝動的に、ポケットに入れていた「影の欠片」を強く握りしめた。知りたい。僕自身の、感じることのできない「重さ」の正体を。
第六章 僕らのテクスチャ
脳裏に浮かび上がったのは、見知らぬ風景ではなかった。それは、僕自身の記憶。幼い僕が、両親が激しく罵り合う声が聞こえる部屋の隅で、耳を塞いで蹲っている。誰にも助けを求められず、ただひたすらに、この時間が過ぎ去るのを待っている、小さな僕の姿だった。
そうだ。僕は、あの時。
あの無力な自分を、どうしようもない哀しみを、心の奥底に封じ込めたのだ。
忘れるために。前に進むために。僕は、僕自身の最も重い未練を、「過去の自分自身」に転嫁して切り離した。リョウが物にしたように、僕は自分自身を器にした。だから僕には「影」が見えなかった。僕自身が、置き去りにした過去の「影」そのものだったから。僕がずっと感じていた微かな空虚さは、魂の半分を置き去りにしてきた証だったのだ。
はっと顔を上げると、リョウが心配そうに僕の顔を覗き込んでいた。彼はすべての作業を終え、その手はまだ頼りないほど軽かったが、確かな温もりを取り戻していた。僕の目から涙がこぼれるのを見て、彼は何も言わずに、僕の肩にそっと手を置いた。
その瞬間、僕の世界からノイズが消えた。今まで霞んで見えていたリョウの顔が、部屋の輪郭が、くっきりと像を結ぶ。
そして、背後に気配を感じた。おぼろげで、まだ形も定かでないが、確かに何かがいる。泣いている、幼い僕の「影」が。
過去と向き合うことは、その「重さ」を受け入れることだ。それはきっと、息が詰まるほど苦しい。けれど、魂の一部を失ったまま、空虚な軽さの中で生きていくより、ずっと温かい。
僕とリョウは、言葉を交わさなかった。ただ、互いの存在の、不確かで、それでいて確かなテクスチャを感じながら、夜が明けていく窓の外を、共に見つめていた。