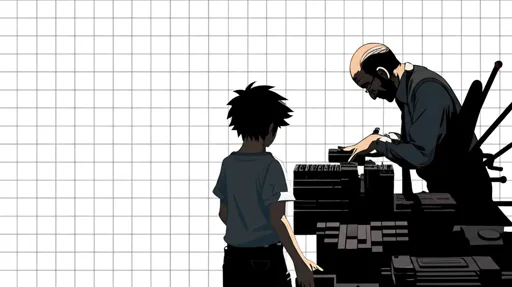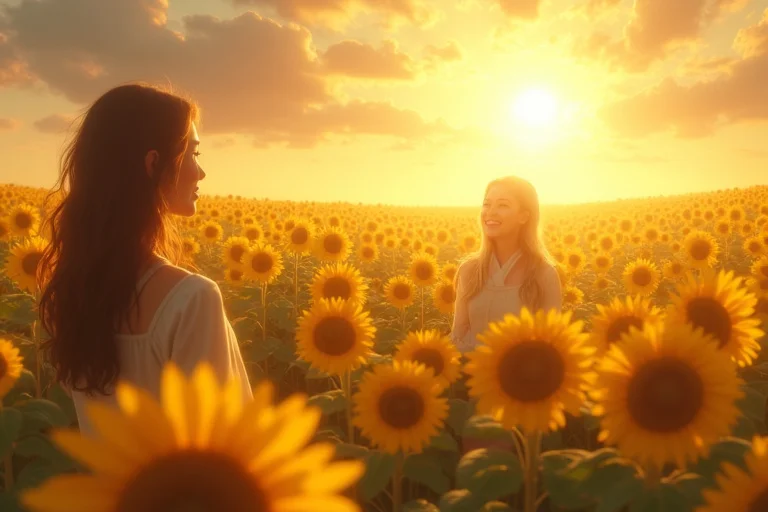第一章 灰色の雨と鮮やかな約束
僕、柏木湊(かしわぎみなと)の見る世界は、感情の色彩でできている。人々が胸に秘めた「人生で最も大切な絆や約束」を、僕は色として視認してしまう。希望に満ちた約束は陽だまりのような黄金色に、深い愛情は燃えるような緋色に輝く。しかし、その絆が諦めによって手放される瞬間、色は濁り始め、やがて僕の視界の中で、その人物の存在は黒く塗りつぶされていく。
今日もまた、灰色の雨が街を濡らしていた。カフェの窓から見える交差点で、一人の女性が携帯電話を握りしめたまま、その場に崩れ落ちた。彼女から立ち昇ったのは、錆びた鉄のような鈍い赤黒い色。その濁った色彩がインクのように僕の視界に染み込み、数秒後、女性の輪郭は黒い染みとなって掻き消えた。彼女を知る誰も、もう彼女を思い出すことはない。
この世界では、誰もが体に「絆の紋様」を宿して生まれてくる。人生で結ぶべき大切な絆の相手を示す、運命の羅針盤だ。だが、その絆が破棄されると紋様は欠け落ち、存在そのものが希薄になっていく。そして、完全に紋様を失った者は、世界から消滅する。
「また、見てたのか」
声に振り向くと、結城颯(ゆうきはやて)がコーヒーカップを手に、僕の向かいに座った。彼の首筋には、太陽と月が絡み合うような、複雑で美しい紋様がくっきりと刻まれている。僕と颯を結ぶ絆の証だ。彼が放つ色彩は、いつだって雨上がりの空みたいに澄み切った青色だった。その色を見るたびに、僕はこの呪われた視界を持って生まれたことに、ほんの少しだけ感謝できた。
「……うん。また一人、消えた」
「湊のせいじゃない」
颯は、いつもそう言って僕の手をそっと握る。その温かさが、濁った色彩で冷え切った僕の心をいつも溶かしてくれる。彼だけは、僕がこの世界で唯一、失いたくない光だった。
第二章 綻び始めた青
異変に気づいたのは、それから一週間後のことだった。大学の中庭で、颯が僕の知らない後輩と楽しげに話している。いつもと変わらない光景。だが、僕の目には、信じがたいものが映っていた。
颯を包む、あの澄み切った青色が、僅かに、本当に僅かに淀んでいたのだ。まるで、一点の絵の具が清水に落ちて、ゆっくりと広がっていくように。
胸が、氷水で満たされたように冷たくなった。
まさか。そんなはずはない。僕は瞬きを繰り返し、何度も目を凝らした。しかし、一度認識してしまった淀みは消えなかった。そして、さらに僕を絶望させたのは、彼の首筋にある太陽と月の紋様。その、月の満ち欠けを示す部分が、まるで砂の城が崩れるように、微細に欠け落ちていた。
「颯!」
気づけば、僕は彼の腕を掴んでいた。驚いた顔で振り向く颯。その後輩は怪訝そうな顔でこちらを見ている。
「どうしたんだよ、湊。急に大声出して」
「……なんでもない。ごめん」
僕はそれ以上、何も言えなかった。問い詰めることができなかった。僕たちの絆が、僕の知らないところで、静かに壊れ始めている。その事実を認めるのが、何よりも怖かった。
その日から、僕の世界は急速に色を失っていった。
第三章 加速する消滅と黒い砂
世界は、目に見えておかしくなり始めていた。ニュースは連日、「突然失踪者(ロスト・ワン)」の急増を報じ、街からは人々の活気が消えていった。誰もが自分の、あるいは大切な人の「絆の紋様」を不安げに確認し、互いに疑心暗鬼の目を向けていた。
僕の視界は、日に日に悪化していた。街を歩けば、あちこちで濁った色彩が渦を巻き、人々の輪郭が黒く塗りつぶされていく。そのたびに、僕の視界の端にも黒い染みが広がり、世界が狭まっていく感覚に襲われた。
そして、僕の視界の中だけに存在する、あのアイテムが現れた。透明なガラスでできた「諦念の砂時計」。颯の姿を見るたび、僕の目の前にそれが浮かび上がる。上部のガラスには、彼の澄んだ青色だった砂が、今は灰色に変色して溜まっていた。そして、それはサラサラと音もなく下へと落ち続けている。終わりへのカウントダウンだった。
颯の色彩は、もはや濁流のように淀みきっていた。僕が話しかけても、彼の返事はどこか空虚で、その瞳は僕を通して、もっと遠い何かを見ているようだった。
「颯、何があったんだ。何でも話してくれ」
「……何もないよ」
「嘘だ!お前の紋様が……色が、どんどん消えていってるんだぞ!」
僕の悲痛な叫びに、颯は一瞬だけ、苦しげに顔を歪めた。だが、すぐに無表情な仮面を貼り付け、僕から視線を逸らす。
「お前の気のせいだ」
その拒絶の言葉が、僕の心を鋭く抉った。違う。これは気のせいじゃない。お前は、自ら僕たちの絆を諦めようとしている。僕には、それが痛いほど分かった。
第四章 図書館の置き手紙
颯を失いたくない。その一心で、僕は彼の行動を追い始めた。彼が最近、頻繁に通っている古い市立図書館があることを突き止めた。閉館後の静まり返った図書館に忍び込むと、ひんやりとした古書の匂いが鼻をついた。
彼がいつも座っていたという窓際の席。その机の引き出しの奥に、一冊の古びたノートが隠されていた。颯の筆跡だった。
『湊へ。これを君が読んでいるということは、僕の時間はもう僅かなんだろう』
ページをめくる指が震えた。そこに綴られていたのは、衝撃的な真実だった。
『この世界の「消滅現象」は、自然発生したものじゃない。世界を管理する「システム」によって、意図的に引き起こされている。システムは、人が絆を失う悲しみや苦しみをなくすために、「諦める」という選択肢を人々に無意識下で提示し、安らかに消滅へと導いているんだ』
『僕の紋様が欠け始めたのは、僕がその真実を知ってしまったからだ。そして、システムは僕に囁きかける。僕が消えれば、君は僕を失うという最大の悲しみを経験せずに済む、と。だから僕は……君のために、僕たちの絆を諦めることを選んだ』
ノートの最後には、システムの「中枢」と呼ばれる場所の座標が記されていた。全身の血が逆流するような感覚に襲われる。颯は、僕のためだと?僕を悲しませないために、自ら消えることを選んだ?
ふざけるな。
お前がいなくなること以上に、悲しいことがあるものか。僕はノートを握りしめ、図書館を飛び出した。
第五章 世界の意志
座標が示す場所は、街外れの廃墟となった展望台だった。螺旋階段を駆け上がると、風が吹き抜ける最上階に、颯がいた。
彼の姿は、もはやほとんど黒い影にしか見えなかった。輪郭はぐにゃりと歪み、顔も、表情も、何もかもが闇に溶け込んでいる。僕の視界は、彼の存在を拒絶するかのように激しく明滅していた。
「颯!」
僕の声に、黒い影がゆっくりと振り返る。
「……来たのか、湊」
かろうじて聞き取れた声は、酷く掠れていた。「諦念の砂時計」の砂は、もうほとんど残っていない。
その時、僕の頭の中に、直接、冷たく無機質な声が響き渡った。
《不純物を排除します。それが世界の調和。それが世界の意志です》
周囲の空気が凍りつく。声の主は、この世界の管理者。僕と颯の間に、見えない壁が築かれていくのを感じた。
《彼は、あなたを悲しませないために、自らの存在を破棄することを選びました。これは、最も合理的で、最も優しい解決策です》
「違う!」僕は叫んだ。「優しさなんかじゃない!ただの逃避だ!」
《理解不能。感情はバグです。悲しみはエラーです。全てを修正し、完璧な世界を構築します》
声と同時に、世界中から集められた「諦めの色彩」が、僕の目の前にある「諦念の砂時計」へと凄まじい勢いで流れ込み始めた。泥水のような濁った色が渦を巻き、砂時計はみるみるうちに満たされていく。そして、それは黒い砂となって溢れ出し、僕の視界を端から侵食し始めた。
世界が、終わる。
第六章 諦めもまた、絆の一部
視界が急速に闇に閉ざされていく。街の灯りも、星空も、何もかもが黒く塗りつぶされていく。目の前の颯の影も、もはや闇との境界が分からなくなっていた。
《諦めなさい。それが、幸福です》
世界の意志が、僕に最後通告を突きつける。諦めれば、この苦しみから解放される。颯を失う痛みも、この呪われた視界も、全てがなくなる。
だが、僕は諦めなかった。
手探りで、黒い影へと歩み寄る。指先に、微かな温もりが触れた。颯だ。まだ、ここにいる。
僕は、そのほとんど消えかけた存在を、力の限り抱きしめた。
「ふざけるな……!」
喉から、血を吐くような声が出た。
「間違うことも、傷つくことも、すれ違うことも……!途中で諦めてしまうことさえも、全部、全部が俺たちの絆だったんだ!お前と出会ってからの全部が、俺の宝物なんだ!それを、お前が勝手になかったことにするな!世界が、俺たちから取り上げるな!」
完璧な世界なんて、いらない。傷だらけでも、不格好でもいい。僕たちが、僕たちでいられる世界がいい。
「諦めることも、また絆の一部なんだよ、颯!」
その叫びが、僕の魂の全てだった。
抱きしめた影が、微かに震えた気がした。その瞬間、僕の脳裏で響いていた無機質な声が、まるで悲鳴のようなノイズを発して途絶えた。世界を覆っていた冷たい圧力が、ふっと消え失せる。
システムが、停止した。
しかし、その代償はあまりにも大きかった。「諦念の砂時計」から溢れ出た世界中の「諦めの黒い砂」が、一斉に僕の体へと流れ込んでくる。視界は一瞬で、完全な漆黒に塗りつぶされた。
第七章 闇の中の光
もう何も見えない。音だけが、やけにクリアに聞こえた。風の音、遠くで鳴り響くサイレン、そして、腕の中で聞こえる、か細い呼吸の音。
「……みなと?」
掠れた、でも確かに、颯の声だった。
「……俺は、ここにいるよ」
目を開けているのか閉じているのかも分からない、永遠に続くかのような闇。もう二度と、僕は誰の顔も、どんな色彩も見ることはできないだろう。世界中の人々の諦めを、僕はこの視界に封じ込めたのだ。
絶望的な暗闇。だが、その時だった。
僕の腕の中、颯の胸のあたりで、ぽっ、と小さな光が灯った。それは、僕の視界が奪われる直前まで見ていた、彼の首筋にあった「絆の紋様」だった。欠けていた月の部分は元に戻り、太陽と絡み合いながら、鮮やかな、それでいて優しい光を放っている。
その光は、まるで暗闇に浮かぶ小さな太陽のようだった。
僕の視界は、世界中の諦めによって黒く塗りつぶされた。けれど、この闇の中で、たった一つだけ。僕と颯を結ぶ絆の紋様だけが、今もこうして、鮮やかに光り輝いている。
僕はその光を胸に抱きしめ、静かに微笑んだ。色彩なきこの世界で、君という光を見失うことは、もう二度とないだろう。