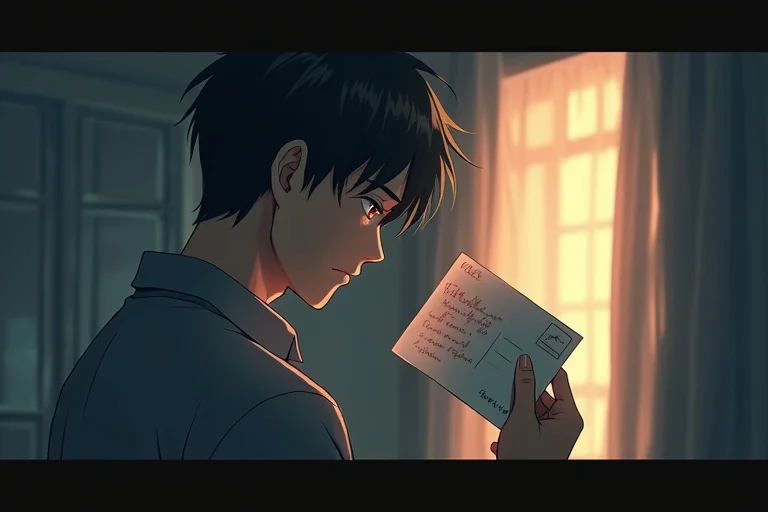第一章 黒インクの遺言
久保田健太のデスクは、寸分の狂いもなく整頓されていた。モニター、キーボード、書類の束、その全てが効率という名の定規で測られたかのように配置されている。都市計画コンサルタントとして、彼は常にロジックと数字で世界を捉えてきた。感情や感傷は、プロジェクトの遅延を招くノイズでしかない。そんな彼の価値観は、五年前に亡くなった父への複雑な感情とも繋がっていた。
父は、手作りの家具職人だった。時代遅れの道具で、非効率な手作業に固執し、一つの椅子に何週間もかけるような男。健太が語る未来都市のビジョンを、父はいつも黙って聞いていただけだった。二人の間には、分かり合えないという名の、厚く冷たいガラスが横たわっていた。
その日の午後、健太の元に見慣れない一通の封筒が届いた。会社の郵便物に紛れて、個人宛に。差出人の名はない。上質な和紙の封筒を開けると、中から現れた便箋に、健太は息を呑んだ。そこに並ぶインクの文字は、間違いなく、亡き父の筆跡だった。万年筆特有の、インクの濃淡が美しい、懐かしい文字。
『健太へ。
お前が本当に守りたいものを見つけたとき、この万年筆のインクが色を変えるだろう』
たった二行の、謎めいたメッセージ。そして便箋の隅には、父が愛用していた古い万年筆の絵が、稚拙ながらも丁寧に描かれていた。健太は混乱した。父は五年前、病室で静かに息を引き取ったはずだ。これは誰かの悪質な悪戯か? 父の古い知人だろうか。しかし、この筆跡は、あまりにも父そのものだった。
健太は自宅の書斎の引き出しの奥から、埃をかぶった桐の箱を取り出した。父の数少ない形見の一つ、例の万年筆だ。ずしりと重い黒檀の軸に、金のペン先。健太はカートリッジ式のインクを入れ、試しに白い紙に線を引いてみた。滑らかな書き心地と共に現れたのは、ごく当たり前の、漆黒のインク。当たり前だ。インクの色が変わるなど、まるで童話だ。
健太は便箋と万年筆をデスクの引き出しに仕舞い、思考を強制的に仕事へと切り替えた。だが、心の片隅に引っかかった小さな棘は、消えることなく鈍い存在感を放ち続けていた。まるで、父が遺した解けない宿題のように。黒いインクの遺言は、健太の合理的な日常に、静かな波紋を広げ始めていた。
第二章 取り壊される時間
数週間後、健太は新たなプロジェクトを担当することになった。市の中心部から少し離れた「ひだまり商店街」の再開発計画。彼の提案は、明快かつ効率的だった。古びた木造の店舗群をすべて解体し、ガラス張りの近代的なショッピングモールを建設する。地域経済の活性化、雇用の創出。彼の提示する数字は完璧で、クライアントの評価も高かった。
現地調査に赴いた健太は、その商店街が放つ独特の空気に眉をひそめた。醤油の香ばしい匂い、豆腐屋のラッパの音、軒先で日向ぼっこをする猫。そこには、彼の設計図から排除された、非効率で情緒的な時間が流れていた。
「こんにちは! 何かお探しですか?」
不意に声をかけられ、健太が振り向くと、セーラー服姿の少女が立っていた。古びた看板を掲げた「言の葉堂」という古書店の前だった。少女は、陽菜と名乗った。
「この商店街の調査をしています」
健太が素っ気なく答えると、陽菜の表情が曇った。
「……再開発の、ですか。このお店も、みんななくなっちゃうって本当ですか?」
その声には、抑えきれない不安が滲んでいた。陽菜にとって、祖母が営むこの古書店は、世界そのものだった。
「時代の流れです。より多くの人が利便性を享受できるようになる」
健太は、いつも通りの正論を口にした。だが、陽菜は真っ直ぐに健太を見つめて言った。
「数字だけじゃないです! ここには、おばあちゃんや、みんなの時間が詰まってるの! 取り壊していい時間なんて、ない!」
その言葉は、健太の胸に小さな石を投げ込んだ。非合理的だ。感傷的だ。そう頭では分かっているのに、陽菜の瞳に宿る真剣な光から、目が逸らせなかった。
その後も、健太は何度か商店街に足を運んだ。計画を進めるためだ。しかし、訪れるたびに、商店街の人々の暮らしが彼の目に焼き付いた。八百屋のおばちゃんが陽菜にオマケだと渡すトマトの赤。夕暮れの光を浴びて金色に輝く惣菜屋のコロッケ。それらは、健太のモノクロームの世界に、予期せぬ色彩を添えていった。
ある夜、健太は自宅で計画書の修正をしていた。ふと、父の万年筆が目に入る。気まぐれにそれを手に取り、設計図に線を引いた。その瞬間、脳裏に陽菜の悲しそうな顔が浮かんだ。
――その時だった。
万年筆が紙の上を滑った軌跡が、一瞬、黒から温かみのあるセピア色に滲んだように見えた。まるで古い写真のような、懐かしい色。健太はハッとして目を凝らしたが、そこにあるのは冷たい黒い線だけ。幻覚か。疲れているのだろう。しかし、心臓の鼓動は速まっていた。あの手紙の言葉が、脳内で不気味な信憑性を帯びて響いていた。
第三章 セピア色の幻
万年筆が見せた一瞬の幻。健太の合理的な精神はそれを否定しながらも、心はざわめきを止められなかった。あの手紙の謎を、そして父の真意を知らなければ、前に進めない。そう直感した健太は、週末、実家の物置にしまい込んでいた父の遺品を整理し始めた。
埃っぽい段ボール箱の中から、父が使っていた手帳やスケッチブックが出てくる。その中の一冊、古びた日記帳に手が止まった。ためらいながらページをめくると、そこには、健太の知らない父の姿が、朴訥な文字で綴られていた。
『健太が都市計画の道に進むと決めた。あいつは街を作る。俺は家具を作る。作るものは違えど、人の暮らしを豊かにしたいという想いは同じはずだ。あいつの作る街に、俺の作った椅子が置かれる日が来たら、どんなに素晴らしいだろう』
ページをめくる手が震えた。疎遠だったと思っていた。理解されていないと一方的に感じていた。だが、父は健太の仕事を、誰よりも理解し、応援してくれていたのだ。涙がこみ上げ、日記の文字が滲む。
そして、最後の方のページに、衝撃的な記述を見つけた。
『もう長くないらしい。健太に最後に何かを遺したい。あいつは賢いが、頭でっかちで不器用なところがある。いつか、数字だけでは割り切れない壁にぶつかるだろう。その時、道を見失わないためのおまじないを。ひだまり商店街の「言の葉堂」のご主人に、手紙を託した。あそこは、言葉の力を信じている場所だから。息子が本当に助けを必要とするときまで、預かってほしいと』
「言の葉堂」――陽菜の店だ。あの手紙は、父が死の直前に書き、陽菜の祖母に託したものだったのだ。全てのピースが、カチリと音を立ててはまった。
そして、万年筆の秘密も、そこに記されていた。
『インクの色が変わる、などとまじないのようなことを書いた。もちろん、そんな魔法はない。だが、人の心を本当に想うことができたなら、健太自身の見る世界の色が変わるはずだ。無機質な黒い線が、温かい物語を帯びたセピア色に見える日が来る。俺が家具の木目に、使う人の笑顔を見ていたように』
魔法などではなかった。特殊なインクでもなかった。健太が見たセピア色の幻は、彼自身の心の変化が映し出した景色だったのだ。父は、健太が軽んじていた「心」というものの価値を、最も詩的な方法で伝えようとしていた。健太が非効率だと切り捨ててきた父の生き方と、ひだまり商店街の人々の暮らしが、一本の線で繋がった。父が木に込めた想いと、商店街の人々が場所に込めた想いは、同じものだったのだ。
「親父……」
健太は声を上げて泣いた。父の深い愛情と、それに気づけなかった自分の愚かさに、涙が止まらなかった。価値観が、ガラガラと音を立てて崩れ落ち、その瓦礫の中から、温かく、そして確かなものが生まれようとしていた。
第四章 心が描く設計図
週明け、健太は役員たちが待つ会議室のドアを開けた。そして、深々と頭を下げた。
「ひだまり商店街の再開発計画ですが、白紙に戻させてください」
彼の言葉に、会議室は水を打ったように静まりかえった。健太は構わず、父の万年筆を手に、徹夜で作り上げた新しい計画案を広げた。それは、古い商店街の建物を活かし、耐震補強やバリアフリー化を施し、空き店舗を若者向けのシェアオフィスやカフェに改装するという、新旧が「共存」する計画だった。数字の上での利益は当初の計画に劣る。だが、そこには、健太が商店街で見た人々の笑顔と、未来への願いが詰まっていた。
「これは、ただのノスタルジーではない。街の歴史という資産を未来に繋ぐ、持続可能な計画です」
彼の言葉には、以前の冷徹な響きはなかった。そこには、人の心を信じる人間の、熱と誠意が宿っていた。激しい反対を、健太は一つ一つ丁寧に説得し、ついに承認を勝ち取った。
彼が万年筆で描く設計図の線は、もはや彼には冷たい黒には見えなかった。八百屋のおばちゃんの笑顔を思わせるトマトの赤。陽菜が愛する古書の紙のセピア色。未来への希望に満ちた、どこまでも続く空の色。彼の心は、黒いインクの向こうに、無数の色彩を見ていた。
数年後。再開発を終えたひだまり商店街は、昔ながらの温かさと新しい文化が融合した、活気あふれる場所へと生まれ変わっていた。観光客や若い家族連れで賑わい、かつてのシャッター通りが嘘のようだ。
健太は、新しくなった「言の葉堂」の前に立っていた。店の前では、大学生になった陽菜が、楽しそうに本の整理をしている。
「健太さん!」
陽菜が健太に気づき、花が咲くような笑顔で駆け寄ってきた。「見てください。この街、すごく素敵になりました。健太さんのおかげです」
「いや、僕だけの力じゃない。この街を愛するみんなの力だよ」
健太はそう言って、胸ポケットの万年筆にそっと触れた。
――父さん、見えますか。俺が本当に守りたかったものは、これだったみたいです。
彼は微笑みながら万年筆を取り出し、いつも持ち歩いている手帳に、何かを書き留めた。夕暮れの光を受けて、ペン先が鈍く輝く。そのインクは、誰の目にも、ごく普通の黒にしか見えない。
しかし、健太の目には、その一文字一文字が、人々の営みが織りなす物語のように、豊かで温かい色彩を放って見えていた。世界の色を変えるのは、魔法のインクではない。人の心を想う、自分の心なのだ。健太は手帳を閉じ、生まれ変わった街の優しい喧騒の中に、静かに溶け込んでいった。