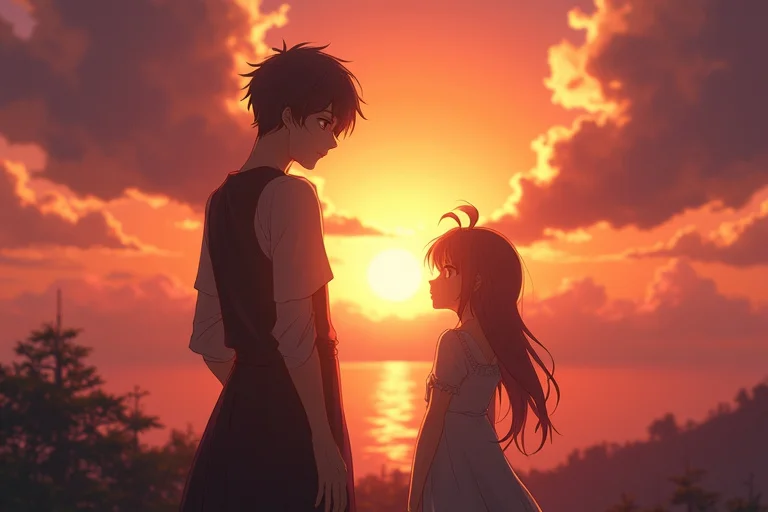第一章 揺れる羅針盤と二つの空
意識が浮上する。瞼の裏で明滅するのは、知らないはずの鮮やかな空。耳の奥で木霊するのは、聞いたことのない温かな笑い声。だが、目を開けたカイの目に映るのは、いつも通りの鉛色の空と、音もなく人々が往来する灰色の街並みだけだった。
「……また、か」
こめかみを押さえる。頭の中に、自分のものでありながら、自分のものではない記憶が渦を巻いている。空に浮かぶ珊瑚のような都市。風に乗って運ばれてくる花の香り。誰かと手を繋いだ時の、柔らかな温もり。それは、感情が豊かだったという古い時代の幻影。そして、今のカイが生きるこの現実は、感情が枯れ果て、世界から色が失われつつある時代。二つの意識が、予告もなく彼の精神を奪い合う。
ふと空を見上げると、そこには数人の「静止者」が浮かんでいた。感情を完全に失い、世界の重力から解き放たれてしまった人々。風に流されることもなく、ただ虚空に佇むその姿は、この世界の緩やかな死を象徴する墓標のようだった。
「カイ、大丈夫?」
背後からの声に振り返ると、幼馴染のリナが心配そうにこちらを見ていた。彼女の瞳にだけは、まだ微かな感情の揺らめきが残っている。
「最近のあなた、時々、すごく遠い場所にいるみたい。まるで別の人になったみたいに」
「……すまない」
カイは曖昧に微笑むことしかできない。どちらの自分が、本当の自分なのか。彼自身にも、もう分からなかった。
リナは小さな包みをカイの手に握らせた。古びた布を解くと、中から現れたのは手のひらサイズの真鍮製の羅針盤だった。針は定まらず、小刻みに震え続けている。
「お爺様の遺品なの。『共鳴針』って。世界で一番強い感情の源を指すって言い伝えだけど……今じゃ、この通り。でも、あなたなら、何かが分かるかもしれない」
カイがその冷たい金属に指で触れた、その瞬間だった。
視界が白く弾け、過去と未来の奔流が脳内で激突した。空に浮かぶ都市でリナと笑い合った日の記憶と、目の前で人々が静止者へと変わっていく絶望の光景が、モザイクのように重なり合い、彼を激しい眩暈へと引きずり込んだ。
第二章 欠けた記憶のモザイク
共鳴針を手にしてから、カイの中の混乱は一層深まった。しかし、それはただの無秩序な混沌ではなかった。二つの意識の境界線が曖昧になる瞬間、断片だった記憶と記憶が繋がり、微かな意味を帯び始めるのだ。彼はまるで、砕け散った鏡の破片を拾い集めるように、失われた世界の真実を辿り始めた。
「過去のカイ」の記憶は、色彩と音に満ちていた。人々の喜びや愛が街を空高く押し上げ、悲しみや祈りは豊かな雨となって大地を潤す。感情が世界の物理法則そのものであった時代。そこでは、彼はリナと共に風を読み、雲を渡り、歌うように生きていた。人々は感情を表現することを恐れず、そのエネルギーが世界を豊かに循環させていた。
対して、「未来のカイ」の記憶は、静寂と無彩色に支配されていた。原因不明の「無感情の病」が蔓延し始め、人々は表情を失っていった。感情を失った者は、まるで魂の重さを失ったかのようにふわりと浮き上がり、二度と地上に戻ることはない。人々は感染を恐れ、次第に感情を表に出すことをやめた。愛を囁く声は消え、街から音楽は途絶え、空に浮かんでいた都市は、推進力を失った船のようにゆっくりと高度を下げ始めていた。
カイは二つの意識を必死に集中させ、共鳴針を握りしめる。震えるばかりだった針が、ほんのわずかに、街の外れにある深い谷の方角を指し示そうとする。そこは「鎮魂の谷」と呼ばれる場所。最も多くの静止者が集う、世界の終着駅だった。
第三章 静止者たちの鎮魂歌
鎮魂の谷は、不気味なほどに静かだった。何百という「静止者」たちが、様々な高度で空中に浮かび、まるで時が止まった森のように佇んでいる。風が彼らの髪や衣服を揺らすことさえない。彼らは世界の物理法則から完全に逸脱した存在となっていた。カイとリナは、その異様な光景に息を呑み、ゆっくりと谷底へと歩を進めた。
「妹も……あそこにいるの」
リナが指さす先には、まだ幼さの残る少女が、目を閉じたまま静かに浮かんでいた。リナは声を振り絞って妹の名を呼ぶが、虚空に吸い込まれるだけで、何の応答もない。彼女の瞳から零れ落ちた一粒の涙が、地面に小さな染みを作る。その瞬間、カイは足元の地面が、ズシリ、とわずかに重みを増したのを感じた。リナの悲しみが、この場の重力を確かに増しているのだ。
カイは静止者たちに意識を向けた。注意深く感覚を研ぎ澄ますと、彼らの体から、陽炎のように揺らめく微かな「何か」が、谷の中心に向かってゆっくりと吸い上げられているのが分かった。それは感情の残り香だろうか。あるいは、生命そのものの残滓か。それは目に見えない川となり、谷底にある古びた石の祭壇へと注ぎ込んでいた。カイは本能的に悟った。あそこが、共鳴針が示そうとしていた場所だと。
第四章 感情の根源
カイはリナを谷の入り口に残し、一人で祭壇へと向かった。近づくにつれて、見えない流れは激しさを増し、まるで嵐の中心にいるかのような圧力を感じる。祭壇に辿り着いたカイは、震える手で共鳴針を握りしめ、その冷たい石に手を触れた。
その瞬間、世界が反転した。
過去と未来、二つの意識は完全に融合し、一つの奔流となってカイの魂を貫いた。そして、世界の真実が、膨大な情報となって彼の脳内になだれ込んできた。
これは、病などではなかった。
かつて、この世界は人々の過剰な感情によって滅びかけていたのだ。憎悪は大地を割り、狂喜は天を焼き、抑えきれない感情の津波が、幾度となく文明を飲み込んできた。感情重力の暴走。それこそが、この世界が常に抱える破壊の衝動だった。
「無感情の病」の正体は、古代の賢者たちが世界の崩壊を防ぐために作り出した、巨大な「調律システム」。この祭壇こそが、世界の核心に存在する『感情の根源』。それは、人々の過剰な感情エネルギーを吸収し、世界の重力を安定させるための、究極の安全装置だった。
しかし、永い時を経てシステムは暴走した。調整のためではなく、世界の存続に必要な感情までも無差別に吸収し始めたのだ。それが、この静かな世界の真実。静止者たちは、感情を根こそぎ吸い上げられ続けた、システムの犠牲者だった。そして、このまま感情の供給が完全に途絶えた時、重力バランスは完全に崩壊し、空に浮かぶ全ての都市は一斉に地上へと墜落する。古き予言は、システムの末路を指していたのだ。
第五章 二人で一つの決断
絶望的な真実を前に、カイは理解した。なぜ自分だけが、二つの時代の意識を持つのか。豊かな感情を知る「過去の自分」と、感情の喪失を知る「未来の自分」。彼の存在そのものが、暴走したシステムに介入できる唯一の鍵。感情の最大値と最小値をその内に宿す、完璧な「導管(コンジット)」。
カイの内で、二つの意識が静かに対話する。
『僕たちが、新しい調律者になるんだ』
それは過去の自分の声か、未来の自分の声か。もはや区別はつかなかった。ただ、揺るぎない一つの決意だけがあった。
カイはリナの元へ戻った。彼の顔つきは、先ほどまでとはまるで違っていた。迷いも混乱もなく、ただ静かな覚悟だけがそこにあった。
「リナ、僕は行かなくてはならない」
彼は全てを話した。世界の真実と、自らが果たさなければならない役割を。
「世界を救う。でも、その代わり……『カイ』という個人は、いなくなる」
リナは言葉を失い、ただ首を横に振った。涙が彼女の頬を伝う。しかし、彼女はカイの瞳の奥にある決意を前に、それ以上何も言うことができなかった。
「忘れない」
彼女は涙を堪え、カイの冷たくなった手を両手で包み込んだ。
「あなたが愛したこの世界も、あなたのことも、絶対に忘れない」
その言葉だけで十分だった。カイは微かに微笑むと、リナに背を向け、再び祭壇へと歩き出した。
第六章 空に融ける心音
祭壇の中央に立ったカイは、目を閉じ、自らの意識の全てを『感情の根源』へと接続した。過去の記憶、未来の記憶。リナと笑い合った日の喜び、静止者たちを見た日の絶望、愛、怒り、悲しみ、希望。彼が持つ感情の全てが、光の奔流となってシステムに注ぎ込まれていく。
彼の体は足元から光の粒子となって崩れ始め、祭壇に吸い込まれていった。個としての輪郭が失われ、意識は無限に拡散していく。彼はもうカイではなかった。彼は、世界全体の感情の流れを調整する、新しい「感情重力」の法則そのものへと変容していくのだ。
カイという存在が完全に世界に溶け合った瞬間、変化は起きた。
世界中を覆っていた重苦しい静寂が破られる。空に浮かんでいた静止者たちが、まるで長い眠りから覚めるように、ゆっくりと、穏やかに地上へと降りてきた。彼らの虚ろだった瞳に、微かな色の光が灯り始める。鎮魂の谷で、リナの妹がゆっくりと目を開け、かすれた声で姉の名を呼んだ。
世界に、感情が戻ってきたのだ。
人々は空を見上げ、理由も分からず涙を流し、そして笑い合った。街角からは、忘れられていたはずの音楽が流れ始める。墜落しかけていた空の都市は、人々の歓喜を力に変え、再びゆっくりと空高く浮かび上がっていった。
リナは、美しく蘇った世界を見渡した。空にも、地にも、カイの姿はどこにもない。けれど、彼女には分かった。頬を優しく撫でていく風の中に、街に響き渡る人々の笑い声の中に、世界を包む温かな光の中に、彼の存在が息づいているのを。まるで、世界そのものが、彼のかつての優しい心音を奏でているかのように。
彼女の手の中に残された共鳴針は、もうどこを指すこともなく、ただ静かに鎮まっていた。しかし、その針は時折、まるで挨拶をするかのように、彼女の鼓動に合わせて、優しく、優しく震えるのだった。