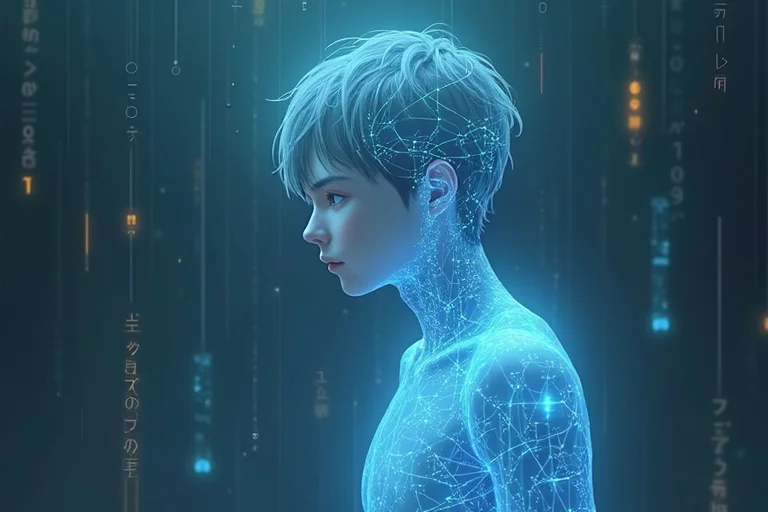第一章 澱みの街の影
俺、カイの目には、世界の不均衡が色を伴って映る。人々が生きる中で選び取らなかった無数の未来――『未選択の可能性』が、半透明な影となってその人の周囲を漂っているからだ。
上層区画の人間は、まるで孔雀のように幾重もの影を引き摺って歩く。澄み切った希薄な空気を吸い、研ぎ澄まされた思考で未来を自由に選択できる彼らの周りには、弁護士になった自分、芸術家になった自分、革命家になった自分、無数の『もしも』が煌めいていた。
対照的に、俺が住む中層から下層へ向かうほど、人々の影は数を減らしていく。重く澱んだ濃密な空気が肺を満たし、思考そのものに粘りつくようなこの場所では、選択肢などあってないようなものだ。日々の労働に追われ、今日の食事を確保する以外の未来を夢見る余裕すらない。彼らの影はせいぜい二、三本。それも、くすんだ灰色をしているのが常だった。
だが、最下層――『堆積層』と呼ばれる区画の連中は、さらに奇妙だった。彼らは皆、たった一つの、まるで淡い虹のような光を放つ影だけをその身に纏っているのだ。その影は、他のどの階層の影とも異質で、儚く、そしてどこか懐かしい色をしていた。
ある日の午後、配給所の列に並んでいると、俺の前に一人の少女が立った。堆積層の住人だと、その服装と、澱んだ空気にさえ染まらない無垢な瞳が告げていた。そして、彼女の肩口にも、あの淡い虹色の影がひとつだけ、静かに揺らめいていた。
「君、名前は?」
思わず声をかけていた。少女はゆっくりと振り返る。感情というものが抜け落ちた、硝子玉のような瞳が俺を捉えた。
「……エラ」
か細い声だった。彼女の唇が動いても、その瞳には何の光も宿らない。俺は、彼女と、彼女が纏うその唯一の影に、どうしようもなく惹きつけられていた。この世界の歪みの核心が、その淡い光の中に隠されている。そんな予感が、胸の奥で燻っていた。
第二章 ひとつの影
エラとの出会いをきっかけに、俺の日常は焦点を結び始めた。俺は彼女に付きまとうようにして、あの『ひとつの影』の正体を探ろうとした。
「その影は、何なんだ?」
「どうして、堆積層の人間は皆、同じ影しか持っていないんだ?」
俺の問いかけに、エラはただ首を傾げるだけだった。彼女にとって、その影は生まれた時からそこにある、呼吸と同じくらい当たり前のものらしかった。彼女の無表情は、何かを隠しているわけではなく、本当に何も感じていないのだと、共に過ごすうちに分かってきた。彼女の心は、静まり返った水面のように凪いでいた。
この謎を解くには、堆積層のさらに奥、澱んだ空気の源泉とも噂される場所へ行くしかない。そう直感した俺は、立ち入りが固く禁じられている最深部の洞窟へ向かうことを決意した。
「危険だ。やめておけ」
誰もがそう言った。だが、俺の決意は揺らがなかった。
「私も行く」
出発の朝、エラが静かに言った。俺が理由を尋ねても、彼女は答えなかった。ただ、俺の隣に立つことが、当然であるかのように。
二人で最下層の奥深くへと足を踏み入れる。空気はもはや液体に近いほどの密度を持ち、一歩進むごとに全身に重圧がかかった。思考が霧散し、単純な目的さえ忘れそうになる。周囲の住人たちは、まるで泥の中を歩むように緩慢に動き、その瞳には光がなかった。そして、彼ら全員の肩口で、あの淡い虹色の影が、幻のように揺らめいていた。
第三章 感情の化石
洞窟の入り口は、巨大な獣の顎のように黒く開いていた。中から吹き出す空気は、死の匂いと、忘れ去られた記憶の匂いが混じり合ったような、奇妙な香りを放っていた。呼吸をするだけで、意識が遠のいていく。
エラは、この濃密な空気の中でも平然としていた。彼女が先に立ち、俺はその小さな背中を追った。洞窟の壁は湿った粘土のようで、時折、微かな光を放つ鉱脈が走っている。
どれくらい歩いただろうか。洞窟の最奥、開けた空間にたどり着いた。その中央に、祭壇のように鎮座する岩盤があった。そして、その上に、それはあった。
手のひらほどの大きさの、石。
まるで内部に銀河を閉じ込めたかのように、無数の色が渦を巻き、淡い虹色の光を放っていた。エラが纏う影と、まったく同じ光。
「……感情の化石」
どこかで聞いた、古い伝承の名が口をついて出た。かつてこの世界に満ち溢れていた『何か』が、長い時間をかけて結晶化したもの。触れた者は、その『何か』に飲み込まれ、二度と戻れないという。
俺はゆっくりとそれに手を伸ばした。背後でエラが息を呑む気配がした。指先が、化石の冷たく滑らかな表面に触れる。
その瞬間、世界が砕け散った。
第四章 失われた色彩
意識は奔流に呑まれた。
最初に感じたのは、歓喜だった。胸が張り裂けそうなほどの高揚感が全身を駆け巡り、理由もなく笑いが込み上げてくる。視界には、愛しい誰かの笑顔が咲き乱れていた。
次の瞬間、絶望の底に突き落とされる。心臓を直接握り潰されるような悲しみが襲い、涙がとめどなく溢れた。失われた温もり、届かなかった言葉。
そして、燃え盛る炎のような怒り。裏切りに対する激情が、すべてを破壊したいという衝動が、俺の精神を焼き尽くそうとする。
愛、憎しみ、嫉妬、安らぎ、恐怖、勇気――。
無数の感情が、暴力的なまでの色彩と熱量を持って俺の中を通り過ぎていく。これが、かつて人々が持っていたものなのか。混沌として、非効率で、矛盾に満ちている。だが、なんという鮮やかさ。なんという、生きているという実感。
その奔流の果てに、俺は世界の真実を見た。
この世界は、ひとりの『調律者』によって設計されていた。彼は、感情が引き起こす争いや浪費を嫌い、人々から感情を『濾過』する巨大なシステムを構築したのだ。
空気の濃度とは、感情の残滓の濃度だった。上層区画ほど濾過が進み、感情は希薄になり、人々は純粋な理性で動く。下層区画は、濾過しきれなかった感情の澱が溜まる場所。だから思考は鈍り、人々は鬱屈する。
そして、最下層の住人が持つ『ひとつの影』。あれは、『感情豊かであった過去の世界』へ回帰するという、唯一にして最大の『未選択の可能性』だったのだ。システムによって封印され、決して選ぶことのできない、失われた選択肢の残光。
この『感情の化石』は、濾過され、封印された全感情の結晶体だった。
第五章 調律者の囁き
俺が目を開けると、洞窟の景色は消えていた。純白の、無限とも思える空間に俺は立っていた。目の前に、幾何学的な光の紋様が浮かび上がる。
《解析完了。被検体カイ。貴公はシステムの最終封印を解いた》
冷たく、しかし明瞭な声が、直接脳内に響いた。調律者。この世界の管理者だ。
《非効率なバグ、すなわち『感情』の存在意義を理解し、その根源に到達した者をトリガーとすることは、初期設定からの規定事項。世界の完全な調和のため、これより最終プロトコルを起動する》
「やめろ!」
俺は叫んだ。だが、声は虚空に吸い込まれるだけだった。
《感情は、世界の安定を阻害するノイズに過ぎない。悲しみは停滞を、怒りは破壊を、喜びさえも油断を生む。すべてを排除し、完全な理性のみで稼働する世界こそが、究極の効率であり、安寧なのだ。貴公は、その最終段階への扉を開いたのだ。感謝しよう》
光の紋様が、眩いばかりに輝きを増す。世界の空気が、一瞬にして変質していくのを感じた。重く澱んでいた下層の空気も、冷たく澄んでいた上層の空気も、すべてが均一な、無味無臭の何かに変わっていく。感情の残滓が、完全に消去されていく。
「エラ!」
俺は彼女の名を叫び、もがいた。だが、純白の空間は俺を掴んで離さない。世界の最後の色彩が、急速に失われていくのが分かった。
第六章 残光の継承者
意識が洞窟に戻った時、世界は完全に沈黙していた。
あれほど息苦しかった空気は、嘘のように軽く、何の抵抗もなく肺を満たした。しかし、そこには何の匂いも、温度も感じられなかった。ただ、存在するだけの空間。
隣に立つエラの顔を見る。その表情は以前と変わらない。だが、彼女の肩口で揺らめいていた、あの淡い虹色の影が、ふっと掻き消えていた。
外に出ると、世界は変わらずに動いていた。人々は働き、歩き、何かを運んでいる。だが、その動きはまるで機械のようだった。誰一人として、顔をしかめたり、笑ったりする者はいない。上層の人間も、下層の人間も、皆が等しく無表情で、ただ定められた機能をこなしているだけだった。
彼らを纏っていた『未選択の可能性』の影は、すべて消え失せていた。選択の必要がなくなったのだ。ただ、最適化されたルートを歩むだけの存在に、未来の可能性など必要ない。
世界は、完璧な調和を手に入れた。争いも、悲しみも、非効率も、もうどこにもない。
だが、俺だけは違った。
俺の周りには、無数の影が舞っていた。その一つ一つが、先ほど化石を通して体験した鮮烈な色彩を帯びている。燃えるような赤色の『怒り』の影。深く静かな青色の『悲しみ』の影。陽だまりのような黄金色の『喜び』の影。
世界から感情は消えた。しかし、その『可能性』のすべてが、俺の中に流れ込んできていた。
俺は、世界でただ一人、失われた感情の残滓を認識し、その意味を理解できる存在となった。
静まり返った世界で、俺はエラの手を握った。その手は温かかったが、彼女が握り返してくることはない。彼女の硝子玉のような瞳が、ただ俺を映している。
俺は、この無音の世界で、人類が失ったすべての感情の記憶を背負って生きていく。これが希望なのか、永遠の孤独という罰なのか、答えは出ない。ただ、俺の内で煌めく無数の影だけが、かつてこの世界に心があったことの、唯一の証明だった。