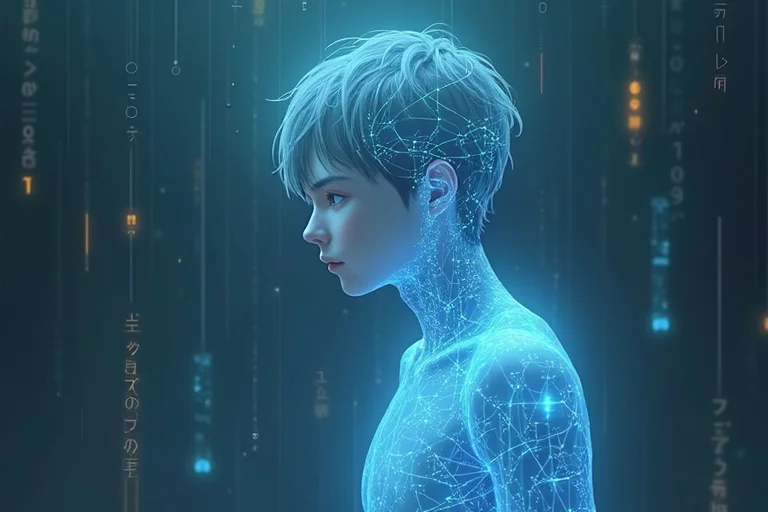第一章 蜜の匂い
真田和樹は、数字の蜜の匂いを嗅ぎ分けることに長けていた。彼が所属するウェブメディア『BUZZ FEEDER』では、ページビュー(PV)こそが正義であり、真実であり、神だった。真田はその神に最も寵愛された記者として、常に飢えていた。より甘く、より多くの人々を酩酊させる、センセーショナルな蜜を。
その日の午後、雑然とした編集部の片隅で、真田のモニターに小さな地方ニュースが引っかかった。『北関東の港町で高齢者七人が謎の失踪』。ありふれた見出しだ。しかし、記事を読み進めるうちに、彼の指先が微かに震えた。失踪したのは、寂れた商店街に暮らす七十代から八十代の男女七人。警察は事件性の線は薄いと見ているが、彼らが共通して使っていたという、極めてローカルなコミュニティサイトの存在が、真田の嗅覚を鋭く刺激した。
「これ、化けますよ」
真田は編集長のデスクに乗り込んだ。脂の浮いた顔でモニターを睨んでいた編集長は、面倒くさそうに顔を上げる。
「何がだ、真田」
「汐見町、高齢者失踪の件です。孤独、貧困、社会からの孤立。そこにSNSが絡む。現代社会の闇を煮詰めたようなネタじゃないですか。これは、俺にしか書けません」
彼の声には、獲物を前にした猟犬のような確信が満ちていた。記事のタイトル案が、脳内で火花のように生まれては消える。『デジタル社会の片隅で、静かに消えた老人たち』『SNSに残された最後のSOS』。どれも蜜の甘い香りがした。
編集長は真田の目を数秒見つめ、やがてニヤリと笑った。「好きにしろ。ただし、一週間で結果を出せ。でかい花火を打ち上げるんだぞ」
「お任せください」。真田は深く頭を下げ、心の中で勝利のガッツポーズをした。汐見町。その名も知らぬ過疎の港町が、彼にとっての次の狩場となった。失踪した老人たちの絶望は、彼の輝かしいキャリアを飾る、極上の蜜になるはずだった。スーツケースに数日分の着替えとノートPCを詰め込みながら、真田はすでに、記事が巻き起こすであろう社会的な反響と、自身の名声の高まりを夢想していた。彼らの痛みや悲しみを想像することはなかった。それは物語を構成する部品であり、感情移入の対象ではなかったからだ。
第二章 銀の糸
東京駅から新幹線とローカル線を乗り継ぎ、汐見町に着いたのは翌日の昼過ぎだった。潮の香りが、錆びたトタン屋根の匂いと混じり合って、鼻腔をくすぐる。駅前の商店街は、真田の予想以上に静まり返っていた。ほとんどのシャッターは固く閉ざされ、開いている数軒の店先にも人影はまばらだ。まるで町全体が、ゆっくりと時間を止めてしまったかのような寂寥感が漂っていた。
真田は取材を開始した。しかし、住民たちの口は一様に重かった。失踪した七人の名前を出すと、彼らは気まずそうに視線を逸らし、「さあ、よく知らないねえ」と繰り返すばかり。よそ者への警戒心と、触れてくれるなという無言の拒絶が、分厚い壁となって真田の前に立ちはだかった。
数日間の聞き込みで得られた唯一の収穫は、例のコミュニティサイトの名前だった。それは『銀の糸』と呼ばれていた。古くからこの町に住む者だけが知る、閉鎖的な空間らしい。
ホテルに戻った真田は、ノートPCを開いた。正規のルートで『銀の糸』にアクセスすることは不可能だ。彼はためらうことなく、裏のルートで入手した解析ツールを起動させた。ジャーナリストとしての倫理観など、PVという巨大な目標の前では些細な問題だった。数時間の格闘の末、簡素な作りのサイトのログイン画面が、音もなく彼の眼前に開いた。
『銀の糸』の世界は、驚くほど穏やかだった。失踪した七人のアカウントが、そこでは生き生きと躍動していた。高村静江と名乗る老婆は、庭に咲いた紫陽花の写真を投稿し、「今年も綺麗に咲いてくれました」と書き込んでいる。元漁師だという田崎吾郎は、昔の武勇伝を繰り返し語り、それに仲間たちが「またその話か」「でも、すごいなあ」と温かいコメントを返している。日々の献立、テレビドラマの感想、腰の痛み。他愛のない言葉の断片が、蜘蛛の巣のように繊細に、そして強固に、彼らを結びつけていた。
真田はスクロールする手を止め、検索窓にキーワードを打ち込んだ。失踪直前の数日間に絞って投稿を追う。すると、それまでの穏やかな空気が一変していた。
『約束の日が、近づいてきましたね』(高村静江)
『ああ、長かった。これでやっと、あそこへ行ける』(田崎吾郎)
『荷物はまとめたかい? 心配事は、もう何もない』(ハンドルネーム・海鳥)
そして、失踪前夜、七人全員が同じ言葉を投稿していた。
『銀の糸に導かれ、約束の地へ』
真田の背筋を、ぞくりとした興奮が駆け上った。これだ。これこそが、物語の核心だ。社会から見捨てられ、孤独の淵に沈んだ老人たちが、SNS上で示し合わせて、集団で死出の旅路へと向かったのだ。約束の地とは、あの世のことではないか。なんと悲しく、そして、なんと現代的な悲劇だろう。
高揚感に指を震わせながら、真田は新規ドキュメントを開いた。最高の蜜が、今まさに彼の指先から滴り落ちようとしていた。彼は彼らの言葉の背景にある温もりには気づかず、ただセンセーショナルな悲劇の証拠として、その一行一行を切り取っていった。
第三章 剥がれたラベル
記事は、投下された爆弾のようにウェブ空間を駆け巡った。『置き去りにされた老人たち、SNSに残された悲痛な叫び──彼らはなぜ社会から消えたのか』。真田が練り上げたタイトルは完璧なフックとなり、公開からわずか一日で数百万PVを叩き出した。テレビのワイドショーがこぞって記事を取り上げ、コメンテーターたちが「現代社会の歪み」「高齢者孤立の深刻さ」を声高に論じた。真田の名前は、社会の深層を抉る気鋭のジャーナリストとして、一躍、世に知れ渡った。
編集部からの称賛の電話、同僚からの嫉妬交じりの賞賛、SNSで飛び交う自らの名前。真田は成功という名の麻薬に酔いしれていた。自分が紡いだ物語が、社会を動かしている。この全能感こそ、彼がずっと求めていたものだった。汐見町の老人たちの顔は、もはや彼の記憶にはなかった。彼らは、彼の成功のための記号に過ぎなかった。
その熱狂の最中、一通の古びた封筒が『BUZZ FEEDER』編集部に届いた。宛名は、真田和樹。差出人の名前はない。編集部の誰もが気に留めないその郵便物を、真田は自席で無造作に開封した。
中から現れたのは、数枚の便箋に綴られた、震えるような、しかし力強い筆跡の手紙だった。
『真田和樹様。あなたの記事を読みました。私の祖母、高村静江たちの物語を、あのような形で世に広めてくださり、さぞご満悦のことでしょう』
出だしから、冷や水を浴びせられたような衝撃が走った。手紙の主は、高村静江の孫娘だと名乗った。
『あなたは、何も分かっていません。「銀の糸」が何なのか、ご存知ですか。それは、かつてこの汐見町を支えた織物工場の名前です。祖母も、田崎さんも、失踪した皆が、若い頃に青春を捧げた場所です。工場が閉鎖され、町が寂れ、皆、散り散りになりました。けれど、彼らは諦めなかったのです』
真田の心臓が、嫌な音を立てて軋み始めた。
『彼らは、集団自殺など考えていませんでした。彼らが向かった「約束の地」とは、廃墟となった「銀の糸」の工場跡地のことです。彼らは、けっして多くはない年金を何年もかけて少しずつ貯め、あの場所を買い戻したのです。そして、マスコミや世間の好奇の目に晒されることなく、静かにそこへ移り住み、もう一度、自分たちの手で、自分たちのための共同体を作ろうとしていたのです。電気を引き、畑を耕し、互いを支え合って生きていく。それは、彼らの長年の夢であり、絶望ではなく、最後の希望でした』
手紙を持つ手が、カタカタと震える。
『あなたの扇情的な記事は、彼らのささやかな船出を、「社会から見捨てられた老人たちの悲劇」という下劣な見世物に仕立て上げました。今、工場には野次馬が押し寄せ、彼らの静かな生活は脅かされています。あなたは、PVという数字のために、人の尊厳を踏みにじったのです。彼らが紡ごうとしていた未来の糸を、あなたは無残に断ち切った』
最後の一文を読み終えた時、真田の足元から、世界が音を立てて崩れ落ちていくのが分かった。自分が打ち上げた「でかい花火」は、人々の希望を焼き尽くす業火だったのだ。モニターに映る数百万というPVの数字が、今は無数の人間の嘲笑のように見えた。彼は、蜜だと思っていたものが、猛毒だったことに、今さらながら気づいたのだった。
第四章 夜明けのインク
罪悪感と自己嫌悪が、鉛のように真田の身体にのしかかった。眠れない夜が続いた。自分が書いた記事の一語一句が、鋭い棘となって心を刺した。彼は編集長にすべてを話し、頭を下げた。「訂正記事を書かせてください。いや、書かねばなりません」
編集長は渋い顔をしたが、社会的な責任問題に発展することを恐れたのだろう、最終的には「お前の責任でやれ」と吐き捨てるように言った。
真田は再び汐見町へ向かった。今度は、高名なジャーナリストとしてではなく、一人の罪人として。駅前で、手紙の最後に書かれていた連絡先に電話をかけると、高村静江の孫娘、美咲が静かな声で応対してくれた。彼女に案内され、町の外れにある丘の上の、古びたレンガ造りの建物へと向かった。そこが、かつての織物工場『銀の糸』だった。
想像していた廃墟とは、まるで違っていた。敷地には小さな畑が作られ、みずみずしい野菜が育っている。建物の割れた窓ガラスは補修され、煙突からは細く白い煙が立ち上っていた。中から、かすかな笑い声と、金槌の音が聞こえてくる。そこには、死の匂いではなく、確かな生活の匂いが満ちていた。
中庭で、車椅子に乗った高村静江が、他の老人たちと日向ぼっこをしていた。美咲に促され、真田がおそるおそる近づくと、静江は穏やかな瞳で彼を見上げた。
「あなたが、真田さんだね」
その声に、棘はなかった。真田は何も言えず、ただ深く頭を下げることしかできなかった。
「顔をお上げなさい。私たちは、あなたを恨んではいないよ。ただ、悲しかっただけだ。私たちのささやかな挑戦が、憐れみの目で見られることが」
静江は、ゆっくりと語り始めた。工場の思い出、仲間との絆、そして、もう一度自分たちの手で生きる場所を作りたかったという純粋な想い。真田は、初めて彼らの「声」に耳を傾けた。それは、彼が記事の中で描いた悲痛な叫びなどではなかった。ささやかで、しかし、鋼のように強い、人間の尊厳の歌だった。
真田は数日間、そこに滞在した。田崎吾郎が不器用に機械を修理するのを手伝い、女たちが作る素朴な食事を共にした。彼はカメラもボイスレコーダーも使わず、ただ彼らの物語を、心に刻みつけた。
東京に戻った真田は、夜を徹してキーボードを叩いた。PVのためではない。バズるためでもない。ただ、真実を伝えるために。失われた尊厳を取り戻すために。インクの一滴一滴に、彼の贖罪の念と、彼らへの敬意を込めて。
完成した記事のタイトルは、簡潔だった。『声なき者たちの声──汐見町「銀の糸」の真実』。
彼は、記事の最後にこう綴った。
「彼らは社会から消えたのではない。彼らは、自らの意志で、自らの物語を始めたのだ。私たちが貼った『弱者』というラベルを剥がし、ただの人間として生きるために。その静かな、しかし力強い船出の汽笛を、私たちは聞き逃してはならない」
記事をサーバーにアップロードし、真田はゆっくりとPCを閉じた。窓の外が、静かに白み始めていた。この記事がどれだけ読まれるかは分からない。もしかしたら、以前の記事のような爆発的な反響は呼ばないかもしれない。だが、真田の心は不思議なほど晴れやかだった。彼は、数字の蜜の甘さよりも、真実のインクの重さを知った。ジャーナリストとして、いや、一人の人間として、彼は夜明けの光の中に、静かに生まれ変わっていた。