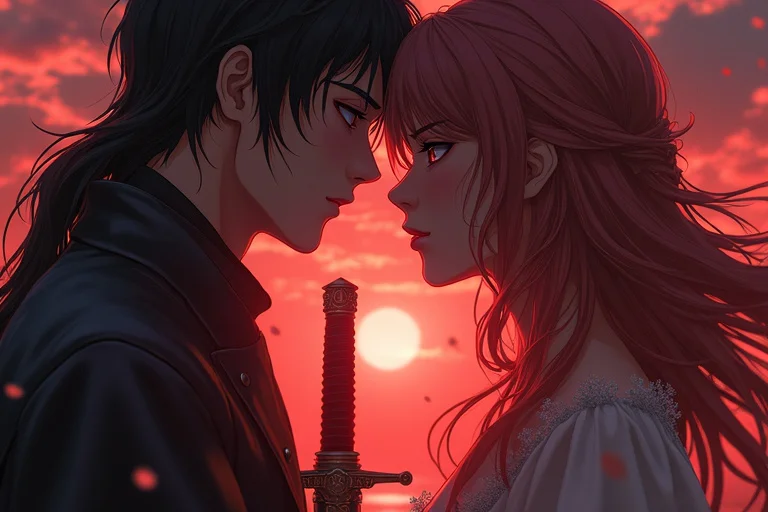第一章 鳴かぬ木鳥と盲目の娘
夕闇が藍色に溶け始める頃、江戸の片隅にある古道具屋「からくり堂」の戸口に、ちりん、と涼やかな鈴の音が響いた。店主の橘蒼馬は、油の染みた指先で手元の歯車を磨きながら、顔も上げずに応じる。
「うちは骨董屋じゃねえ。壊れたもんしか相手にしねえよ」
年の頃は二十代半ば。腕は確かだが、その口ぶりと眼差しには、世を達観したような冷めた光が宿っていた。客がたじろいで帰ることも少なくない。だが、鈴の音の主は、静かな声で言った。
「壊れております。だから、参りました」
ふと顔を上げた蒼馬は、息を呑んだ。そこに立っていたのは、白皙の肌を持つ、息をのむほど美しい娘だった。しかし、その澄んだ瞳は、どこか遠くを見つめるように、焦点を結んでいない。盲目なのだと、すぐに分かった。娘は大切そうに腕に抱えた桐の箱を、そっと蒼馬の前の作業台に置いた。
「父の形見なのです。どうか、これを治していただけませんか」
箱の中から現れたのは、掌に乗るほどの小さな木製の鳥だった。素材は山桜だろうか、使い込まれて滑らかな艶を帯びている。だが、翼の付け根には痛々しい亀裂が走り、内部の仕掛けがわずかに覗いていた。
「ただの木彫りの玩具じゃねえか。近所の子供にでも直させてやれ」
蒼馬が吐き捨てるように言うと、娘は悲しげに首を横に振った。
「いいえ、これはただの鳥ではございません。父は申しておりました。この鳥は昔、夜空を歌いながら飛んだ、と。もう一度……もう一度だけで良いのです。この鳥の歌声が聞きたいのです」
夜空を、飛んだ?
蒼馬は鼻で笑った。からくり仕掛けで鳥が鳴く、それくらいなら蒼馬にも作れる。だが、この大きさで空を飛ぶなど、天地がひっくり返ってもあり得ない。ただの親が娘に聞かせた与太話だろう。
「お嬢さん、夢物語は他所で語ってくれ。俺は忙しい」
冷たく突き放そうとした。だが、その時、蒼馬の目は木鳥の細工に釘付けになった。羽の一枚一枚に彫られた繊細な溝、極小の部品が噛み合う内部機構。それは、蒼馬がこれまで見たどんなからくりよりも、緻密で、そして温かみのある作りをしていた。作り手の魂が、この小さな木片に宿っているかのようだった。
そして何より、その鳥を見つめる娘の横顔が、あまりにも切実だった。
蒼馬は長い溜息をつき、無造作に鳥を手に取った。
「……飛ぶかどうかは請け負えねえ。鳴かせるだけだ。それでいいな?」
娘の顔が、ぱっと花が咲くように輝いた。
「はい。お願いいたします。私、小夜と申します」
蒼馬は名乗らなかった。ただ、からくり鳥の冷たい感触と、それを持ち込んだ盲目の娘・小夜の存在が、錆びついた彼の日常に、予期せぬ一滴の波紋を広げたことだけは確かだった。
第二章 からくりの心、人の心
翌日から、小夜は毎日からくり堂を訪れるようになった。修理の邪魔にならぬよう、戸口の隅にちょこんと座り、ただ静かに蒼馬の作業の音に耳を澄ませている。トントンと木を削る音、キリキリとぜんまいを巻く音。その一つ一つを、彼女は瞳の代わりに全身で聴いているようだった。
蒼馬は当初、その存在を疎ましく感じていた。かつて、彼は師と仰ぐ男にその腕を利用され、裏切られた過去があった。それ以来、人と深く関わることを避け、己の技術だけを信じて生きてきた。小夜の純粋すぎる眼差し(たとえそれが何も見ていなくとも)は、彼の心の古傷をちりちりと灼くようだった。
「茶でも飲むか」
ある雨の日、蒼馬は自分でも意外な言葉を口にしていた。小夜は驚いたように顔を上げ、小さく頷く。ぶっきらぼうに差し出された湯呑みを、彼女は両手で大切そうに包み込んだ。
「蒼馬さまの手は、魔法の手なのですね。いろんな音を生み出す」
「……ただの商売だ」
そう答えながらも、蒼馬の心には微かな温もりが広がっていた。
修理は難航を極めた。鳥の内部構造は、まるで知恵の輪のように複雑に絡み合っていた。音を出すための笛や鞴(ふいご)の仕組みは解明できたが、「飛翔」に繋がるような仕掛けはどこにも見当たらない。
「やはり、あんたの親父さんの大言壮語だったんだ」
夜更けに一人、呟きながらも、蒼馬の指は止まらなかった。なぜか、諦める気にはなれなかった。小夜の期待を裏切りたくないという気持ちが、知らず識らずのうちに蒼馬を突き動かしていた。
数日後、蒼馬は鳥の尾羽の付け根近く、内部の歯車に隠れるように刻まれた小さな紋様に気づいた。それは、三日月と星を組み合わせたような、不思議な印だった。設計者の銘だろうか。だが、どの流派の紋とも違う。蒼馬はこの紋様が、このからくりの核心を握る鍵だと直感した。
「小夜。この印に見覚えは?」
蒼馬が尋ねると、小夜はそっと鳥に触れ、指先でその紋様の場所を探り当てた。そして、静かに言った。
「父がよく、夜空を見上げておりました。『月と星が、道を示してくれる』と」
月と星。その言葉が、蒼馬の頭の中で何かの回路を繋いだ。彼は工房の奥から古びた天文書を持ち出し、紋様と星図を見比べ始めた。このからくりには、まだ自分の知らない、遥かに大きな秘密が隠されている。そんな予感が、彼の胸を高鳴らせていた。それは、人を遠ざけてきた彼が、久しく忘れていた感情だった。
第三章 夜空を渡る歌声
一月後、からくり鳥はついにその声を取り戻した。蒼馬が背中のぜんまいを巻くと、木鳥の喉から、澄み渡るような、しかしどこか物悲しい音色が流れ出した。それは単調な鳴き声ではなく、複雑な節回しを持つ、まるで短い歌のようだった。
「……鳴きはしたが、やはり飛ばねえ。これが限界だ」
蒼馬は、どこか申し訳ない気持ちで小夜に告げた。だが、小夜は穏やかに微笑むだけだった。
「いいえ。素晴らしい音色です。これこそ、父が聞かせてくれた歌声。本当に、ありがとうございます」
その時だった。店の戸が乱暴に蹴破られ、三人の男が押し入ってきた。人相の悪い、町のごろつきだ。彼らはぎらつく目で店内を見回し、小夜の姿を認めると卑しい笑みを浮かべた。
「見つけたぜ、小夜。お前の親父が隠した帳面はどこだ!」
帳面? 蒼馬が眉をひそめる。男の一人が小夜の腕を掴んだ。
「おとなしく渡せば、痛い目には遭わねえぜ」
小夜の父は、ただの職人ではなかった。彼は、町の裏側で私腹を肥やす悪徳商人・相模屋の不正を密かに記録していたのだ。そして、その不正に技術を悪用され、片棒を担がされていたのが、かつて蒼馬を裏切った師匠・源斎だった。
蒼馬の全身の血が、怒りで沸騰した。気づけば、彼は手にしていた鉄のやすりを握りしめ、ごろつきと小夜の間に立ちはだかっていた。
「その汚え手を離しやがれ」
乱闘になった。蒼馬は職人だが、腕っぷしは弱いわけではない。だが、相手は三人。じりじりと追い詰められたその時、壁際に倒れ込んだ小夜が、悲痛な声で叫んだ。
「蒼馬さま! 鳥を! 鳥を鳴らしてください!」
一瞬、蒼馬は意味が分からなかった。こんな時に、何を。だが、小夜の必死の形相に、彼はためらうことなく懐から木鳥を取り出し、ぜんまいを巻いた。
工房に、再びあの澄んだ歌声が響き渡る。
すると、信じられないことが起こった。店の天井裏、蒼馬も気づかなかった小さな窓が、からくり仕掛けでパカリと開いたのだ。そして、そこから一羽の鳩が、夜の闇へと飛び出していくではないか。その足には、小さな竹筒が結び付けられている。
ごろつきたちが呆然と空を見上げる。その瞬間、蒼馬は全てを理解した。
「夜空を歌いながら飛んだ鳥」。それは、この木製のからくり鳥ではなかった。この鳥の“歌声”を合図に、本当の空を飛ぶ伝書鳩。それこそが、小夜の父が娘に残した、最後の切り札だったのだ。
そして、蒼馬はもう一つの真実に気づき、戦慄した。小夜が、真っ直ぐに自分を見ていた。その瞳には、今までなかった確かな光が宿っている。
「あなたを、騙すつもりは……」
か細い声で呟く小夜。彼女は、盲目ではなかった。父が殺された後、追手の目から逃れるため、己の身を守るため、ずっと盲目を装い続けていたのだ。
第四章 翼なき飛翔
伝書鳩が運んだ報せは、的確に奉行所へと届いた。ほどなくして踏み込んできた役人たちによって、ごろつきどもはたちまち捕縛された。相模屋と、師匠であった源斎も、小夜の父が遺した帳面が決め手となり、その悪事が白日の下に晒された。
全てが終わった静かな夜、小夜は蒼馬の前に座り、深く頭を下げた。
「申し訳ございません。あなた様を、ずっと……」
「いいさ」
蒼馬は静かに遮った。怒りはなかった。むしろ、己の身一つで巨大な悪に立ち向かおうとした、このか細い娘の覚悟に胸を打たれていた。彼女は、蒼馬の腕を見込んで訪ねてきたのではなかった。その評判から人柄を探り、本当に信じるに足る人間か、己の目で見極めていたのだ。
「こいつは、大したからくりだ」
蒼馬は、修理を終えた木鳥を小夜の手にそっと置いた。「飛ばずとも、人の心を動かし、悪党どもを空の彼方へ吹き飛ばしちまった」
その顔には、いつもの皮肉な笑みはなかった。そこにあったのは、何年も忘れていた、穏やかで優しい微笑みだった。
やがて、小夜は証人として保護され、遠い親戚に引き取られることになった。江戸を発つ日、彼女は見送りに来た蒼馬に言った。
「いつか、本当に空を飛ぶ鳥を、あなた様が作る日を見てみたいです。翼で風を掴み、どこまでも高く飛んでいく鳥を」
その言葉は、蒼馬の心の奥深くに、確かな種を蒔いた。
一人、からくり堂に戻った蒼馬は、作業台に真新しい和紙を広げた。墨を含ませた筆で、彼が描き始めたのは、一つの設計図。それは、大きくしなやかな翼を持つ、美しい鳥の姿だった。それはもう、誰かを欺くための仕掛けでも、過去に縛られた復讐の道具でもない。未来へ、そしてまだ見ぬ空へと羽ばたくための、夢の設計図だった。
窓の外では、夜が明けようとしていた。蒼馬の耳の奥で、鳴かぬ木鳥が奏でたあの歌声が、いつまでも優しく響いていた。それは、閉ざされた心に翼をくれた少女への、感謝の音色のように聞こえた。