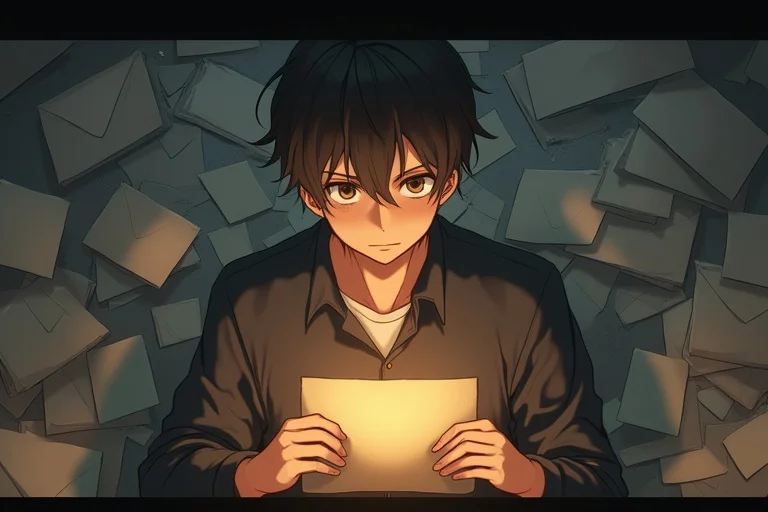第一章 沈黙のオルゴール
柏木修一が営む古道具屋「時の忘れもの」の扉が、錆びた蝶番を軋ませて開いたのは、冷たい雨がアスファルトを濡らす日の午後だった。入ってきた男は、その場の空気に溶け込んでしまいそうなほど、印象の薄い男だった。くたびれたコートを着て、水滴のついた傘を静かに畳む。
「いらっしゃいませ」
修一の声は、埃っぽい店内の静寂にかすかに吸い込まれた。男は店内を見回すでもなく、まっすぐにカウンターへ進み出ると、大切そうに抱えていた桐の箱をそっと置いた。
「これを、お願いしたい」
男の声もまた、その佇まいと同じように特徴がなかった。箱の中から現れたのは、精緻な螺鈿細工が施された、黒檀のオルゴールだった。月と星々が銀色に輝き、長い年月を経た風格を漂わせている。だが、その美しさとは裏腹に、天板には痛々しい亀裂が走り、金属部分はくすんでいた。
「修理ですか。古い型ですし、部品があるかどうか……」
「直してほしいのは、音ではありません」男は修一の言葉を遮った。「このオルゴールは、音の代わりに光を奏でるのです。持ち主の、最も幸せだった記憶を」
修一は眉をひそめた。また、曰く付きの品を面白半分に持ち込む客か。彼は懐疑的な視線を隠さずにオルゴールを手に取った。ずしりと重い。底にあるはずのネジを巻いてみるが、カリカリと空回りするだけで、ゼンマイが巻かれる感触はなかった。
「仕組みが分かりかねますが」
「ただ、触れるだけでいい。心から願えば、光は灯るはずです。ですが、今はもう……」男は悲しげに目を伏せた。「一週間、お預けします。どうか、もう一度だけ、あの光を見られるようにしてください」
そう言うと、男は代金だと言って古びた紙幣を数枚カウンターに置き、修一が何かを言う前に、再び雨の中へと消えていった。
一人残された修一は、溜息をつき、改めて黒檀のオルゴールに向き合った。光を奏でる記憶? 馬鹿馬鹿しい。そう思いながらも、何かに引かれるように、そっとその冷たい天板に指を触れた。古びた木の感触が指先に伝わる。彼は目を閉じ、意識を集中させた。自分の人生で、最も幸せだった記憶。
だが、何も起こらなかった。光の粒一つ、またたくことすらない。ただ、店の隅で古時計が刻む無機質な音と、窓を叩く雨音だけが響いていた。修一は自嘲気味に口元を歪めた。そもそも、自分にそんな記憶など、ありはしないのだ。彼はその日、まるで自分の空っぽな心を見せつけられたかのように、ただ黙ってその沈黙のオルゴールを見つめ続けた。
第二章 色褪せた記憶
それから数日、修一はオルゴールに取り憑かれたようになった。分解しようにも、どこにも継ぎ目が見当たらない。あらゆる文献を漁り、古い職人の名簿を調べたが、この奇妙なオルゴールに関する記述はどこにもなかった。
彼は、苛立ち紛れに常連の客にオルゴールを触らせてみた。近所で小料理屋を営む老婆が、皺だらけの手で恐る恐る触れると、オルゴールは淡い光を放ち始めた。光の粒子が集まり、形作ったのは、紋付袴の若い男と、綿帽子をかぶった花嫁が照れくさそうに微笑み合う姿だった。
「あらまあ……死んだうちの人と、祝言を挙げた日だわ」老婆は涙ぐみ、その儚い光景を愛おしそうに見つめた。
次に、店に迷い込んできた近所の少年が触れると、今度は弾けるような金色の光が溢れ、大きな誕生日ケーキの前に立つ、満面の笑みの少年の姿が映し出された。
彼らの記憶は、温かく、眩しい。それにひきかえ、自分はどうか。何度触れても、オルゴールは石のように冷たく沈黙したままだ。
修一の脳裏に、色褪せた記憶が蘇る。ピアニストになる夢を抱いていた十代の頃。コンクールで大失敗し、音楽家の父に「お前に才能はない」と勘当同然に突き放された日。唯一の理解者だった母が、病でこの世を去った日。父との間には、修復不可能なほどの深い溝が刻まれた。母の死後、父とは一度も言葉を交わすことなく、数年前にその訃報を人づてに聞いたきりだ。
幸せだった記憶を探そうとすればするほど、後悔と挫折の記憶ばかりが心を支配する。自分は、人生の美しい瞬間を、自ら捨て去ってきたのではないか。冷たいオルゴールは、まるで修一の凍てついた心を映す鏡のようだった。男が引き取りに来る約束の日が、刻一刻と近づいていた。
第三章 たった一つの光
約束の一週間が過ぎても、あの男は現れなかった。二週間が経ち、季節は初冬の気配を纏い始めていた。忘れられたのか、それとも元から捨てるつもりだったのか。修一の心には、諦めと、どこか安堵にも似た感情が入り混じっていた。
その夜、店の奥にある物置を整理していた修一は、父の遺品を収めた段ボール箱につまずいた。葬儀にも行かなかった自分に、親戚が無理やり送りつけてきたものだ。中には、父が愛用していた万年筆や手帳が乱雑に入っていた。捨てようとして、やめた。その中に、一冊の古びた日記帳があるのに気づいた。
ためらいながらページをめくると、そこには修一の知らない父の姿があった。無骨で、飾り気のない文字。そこには、修一のコンクールの結果を誰よりも気にかけ、陰で彼の演奏の録音を繰り返し聴いていた父の姿が記されていた。そして、修一に「才能はない」と告げた夜、父は日記にこう綴っていた。
『あの子を傷つけた。だが、私と同じ苦しみを味わわせたくない。この世界の厳しさを知るからこそ、夢を諦めさせることが、私の最後の愛情だ。すまない、修一。許してくれ』
ページをめくる手が震えた。そして、日記の最後に挟まっていた一枚の写真を見つけた。それは、幼い自分が父に肩車をされ、夜空に咲く大輪の花火を見上げている写真だった。自分は笑い、父の顔は見えないが、その太い首筋に、確かな温もりを感じた記憶が蘇る。写真の裏には、震えるような文字があった。
『あの日が、私の宝物だ』
瞬間、修一の目から熱いものが溢れ出した。勘違いしていた。自分は愛されていなかったのではなく、ただ、その不器用な愛情に気づけなかっただけなのだ。厳格さの裏に隠された父の苦悩と、深い愛情。何十年もの間、自分の心を縛り付けていた憎しみと後悔の氷が、音を立てて溶けていくのを感じた。
彼は、何かに突き動かされるように店へと駆け戻った。カウンターの上に置かれたオルゴールが、静かに彼を待っていた。震える指で、そっと天板に触れる。父の背中の温もり、夜空を焦がす花火の音、火薬の匂い、そして父の不器用な愛。その全てを、心の底から思い浮かべた。
すると、奇跡が起きた。
オルゴールの天板の亀裂から、一筋の光が漏れ出した。それは誰かの記憶の形を成すのではなく、ただ一つの、星屑のようにきらめく、温かく力強い光の粒だった。光はゆっくりと宙に浮かび上がり、店内の闇を優しく照らした。
その時、店の扉が静かに開いた。そこに立っていたのは、あの男だった。しかし、その姿は以前よりもずっと透き通って見え、まるで陽炎のようだった。男は、宙に浮かぶ光の粒を穏やかな目で見つめ、修一に向かって微笑んだ。
「ありがとうございます。その光が見たかったのです」
男の声は、風に運ばれる囁きのように聞こえた。
「このオルゴールは、幸せな記憶を映すのではありません。持ち主が、心の底から誰かを、あるいは自分自身を許すことができた時……たった一度だけ、こうして光を灯すのです。それは、『赦し』の光です」
修一は言葉を失った。では、この男は。
「あなたは……」
「私は、このオルゴールに残された最後の想い。持ち主が、あなたに伝えたかった後悔と、愛情の欠片です」
男の姿は、光の粒が輝きを増すにつれて、さらに薄くなっていく。父だ。父が、死してなお、自分に許しを請うていたのだ。
第四章 新しい旋律
男の姿は、宙に浮かぶ光の粒に吸い込まれるように、静かに消えていった。後には、しんとした静寂と、まるで小さな星のように輝き続ける一つの光だけが残された。
修一は、その場に崩れるように膝をつき、声を上げて泣いた。それは、悲しみの涙ではなかった。何十年も胸につかえていたものが洗い流されていくような、温かい解放の涙だった。父さん。ごめんなさい。ありがとう。言葉にならない想いが、涙となって頬を伝った。光は、まるで彼の涙に応えるかのように、一層優しく輝いていた。
光がその命を終え、オルゴールが再び完全な沈黙に戻ったのは、夜が白み始める頃だった。
翌日、修一は店の奥から、白い布をかぶった古いアップライトピアノを引っ張り出した。母が遺し、父が捨てることを許さなかったピアノ。彼が音楽を捨てて以来、一度も開けたことのない鍵盤蓋を、ゆっくりと持ち上げる。
埃っぽい鍵盤に、おそるおそる指を置く。そして、一つ、音を鳴らした。ポーン、と響いた音は、お世辞にも美しいとは言えない、不格好な響きだった。だが、修一にとっては、どんな名演奏家の音色よりも心に深く沁みわたる音だった。それは絶望の終わりと、新しい始まりを告げる、希望の旋律の第一音だった。
あの不思議なオルゴールが、二度と光を灯すことはなかった。しかし、修一はそれを磨き上げ、店の窓際の一番よく見える場所に飾った。訪れる客は、その螺鈿細工の美しさに感嘆するが、その本当の秘密を知る者は誰もいない。
修一だけが知っている。あの小さな箱が奏でた「赦し」という名の光が、どれほど人の心を救う力を持っているかを。
時折、彼の店からは、辿々しいピアノの音が聞こえてくるようになった。それはまだ拙く、何度もつっかえる旋律だ。だが、その音色は不思議なほど優しく、古い物が並ぶ静かな通りに、温かい光を灯しているようだった。過去と和解し、未来へと歩き始めた男が奏でる、新しい人生の歌のように。