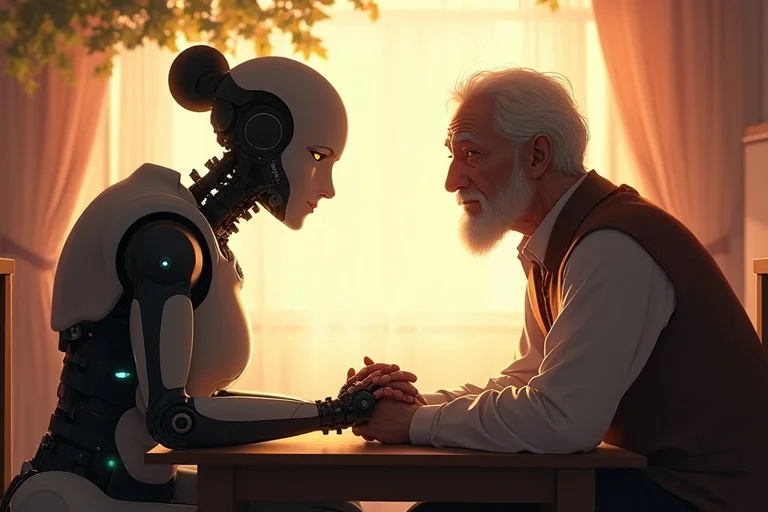西暦2742年。世界は静かすぎた。かつて「大静寂(グレートサイレンス)」と呼ばれた厄災が、人類からあらゆる芸術と、それに付随する多くの感情を奪い去ってから五世紀。人々は合理性を極め、効率的に生きるだけの存在となっていた。喜びも、悲しみも、歴史の教科書に載っているだけの、遠い概念だった。
考古学記録院の研究員であるカイは、そんな世界で浮いた存在だった。彼が執着しているのは、五世紀前の地層から発掘された、指先ほどの大きさの金属片――古代記録媒体、通称「遺物(レリック)」の解析だった。
「カイ、まだそんなガラクタを弄っているのか。時間の無駄だ。もっと生産的な研究をしろ」
上司の冷たい声が、静寂なラボに響く。カイは振り向かずに答えた。
「これはガラクタじゃありません。ここには、僕たちの失われた『何か』が眠っているはずなんです」
伝説があった。かつて人間は、「音」の連なりによって、魂を揺さぶられる体験をしたという。カイはその伝説を信じていた。心が、震える。その感覚がどんなものか知りたくて、彼は来る日も来る日も、解読不能なデータと格闘していた。
その夜、奇跡は起きた。何万通りものパスコードを試した末、遺物のプロテクトが、音もなく解除されたのだ。画面に表示されたのは、たった一つのファイル。「Symphony No.9」という無意味な文字列。
カイの心臓が、生まれて初めて大きく脈打った。これは、ただのデータではない。確信があった。彼は震える手で、遺物をラボの中央にある全方位音響システムに接続した。
「皆さん、少しだけ、時間をください」
カイの声に、残っていた数人の研究員が訝しげな視線を向ける。カイは構わず、再生ボタンを押した。
最初は、微かなノイズだけだった。
「……なんだ、やはり故障か」
誰かが呟いた、その瞬間だった。
――音が、溢れた。
弦楽器の、低く、しかし確かなうねり。それは次第に厚みを増し、波のようにラボを満たしていく。研究員たちは皆、ペンを置き、画面から顔を上げた。彼らの人生で一度も聴いたことのない、複雑で、秩序だった音の洪水。
やがて、旋律は激しさを増し、頂点に達したかと思うと、突如として静寂が訪れる。そして、静寂を切り裂くように、響き渡ったのだ。
人間の「声」が。
それは会話とも記録音声とも違う、音階に乗った魂の叫びだった。一人の声が、やがて幾重にも重なり、巨大な合唱となって空間を揺らす。
「Freude, schöner Götterfunken…」
意味は分からない。だが、カイには分かった。これが「歓喜」だ。これが「希望」だ。今まで文字情報でしか知らなかった感情が、鼓膜を通じて脳を直接揺さぶり、魂に流れ込んでくる。
気づけば、カイの頬を温かい雫が伝っていた。なんだ、これは。情報端末で調べると、それは「涙」という生理現象だと示された。強い感情の昂ぶりによって引き起こされる、と。
見回すと、他の研究員たちも同じだった。呆然と立ち尽くす者、胸を押さえる者、そしてカイと同じように、戸惑いながらも静かに涙を流す者。誰もが、生まれて初めての「感動」という名の嵐に打ちのめされていた。
無機質だったラボが、まるで色彩を取り戻したかのように輝いて見えた。
失われたものは、取り戻せる。カイは確信した。この星屑のような遺物の中に眠っていたのは、ただの音楽データではない。それは、人類が再び感動するための、最初の種火だったのだ。
夜明けの光が差し込む窓の外で、世界が、ほんの少しだけ鮮やかに動き出した気がした。