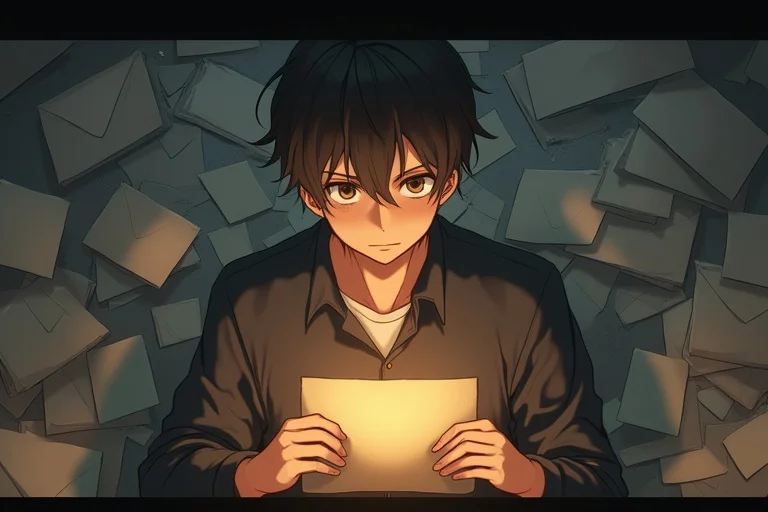第一章 開かれなかった手紙
都会のコンクリートジャングルに埋もれるようにして暮らす僕、相田健太の日常は、色の抜けた風景画のようだった。グラフィックデザイナーとして独立して五年。かつて抱いていた情熱は、クライアントの修正指示の波に洗われ、すっかり摩耗してしまっていた。人との深い関わりを避け、最小限のコミュニケーションで日々をやり過ごす。それが、僕がいつの間にか身につけてしまった処世術だった。
そんな灰色の日常に、一滴の鮮やかなインクが垂らされたのは、一本の電話からだった。故郷の叔母からで、内容は祖母の訃報。九十歳の大往生だった。悲しみよりも先に、どこか遠い世界の出来事のように感じてしまう自分に、嫌気がさした。
週末、僕は数年ぶりに新幹線に乗り、土の匂いがする田舎町へと戻った。葬儀が終わり、親戚たちが慌ただしく帰っていく中、僕は一人、祖母が遺した古い家の整理を任された。埃っぽい空気と、樟脳の懐かしい匂い。軋む床を歩きながら、祖母との他愛ない思い出が脳裏をよぎるが、そのどれもがセピア色の写真のように現実味がない。
問題の「それ」を見つけたのは、押し入れの奥深く、布団の山に隠されるように置かれていた桐の小箱だった。年代物らしく、表面は滑らかに黒光りしている。好奇心に駆られて蓋を開けると、中には古い便箋の束がぎっしりと詰まっていた。どれも祖母の震えるような、しかし丁寧な文字で書かれている。
宛名は、すべて同じ。「ミナト様」と。
僕はその名前に全く心当たりがなかった。親戚にも、祖母の友人にも、そんな名前の人間はいないはずだ。便箋を一枚手に取ると、日付は僕が小学校低学年だった頃のもの。内容は、季節の挨拶や、僕の成長の様子を伝える、ごく個人的なものだった。
『ミナト様。東京はもう秋の気配でしょうか。こちらの山々は、少しずつ化粧を始めています。健太は今日、初めて自転車に乗れました。あの子の笑い声が、あなたにも届けばよいのに』
奇妙なことに、手紙はどれも封筒に入れられてはいるものの、切手は貼られておらず、投函された形跡が一切ない。何十通、いや、百通はあろうかという未投函の手紙。祖母は一体誰に、何を伝えたかったのか。そして、なぜこの手紙を送らなかったのか。
桐の箱から漂う古い紙の匂いが、僕の無気力な心を静かに掻き乱し始める。忘れ去られていたはずの過去の扉が、ゆっくりと、しかし確かに軋み始めた音だった。
第二章 色褪せた記憶の町
東京に戻った僕は、仕事の合間に祖母の手紙を少しずつ読み進めていた。無機質なモニターの光に照らされた手紙は、まるで別世界の遺物のようだ。そこには、僕の知らない祖母の姿と、僕が忘れてしまった僕自身の姿があった。
手紙には頻繁に「約束」という言葉が出てきた。『あの丘の桜が咲く頃に、また二人で笑いましょう』『あなたとの約束を、健太も私も、一日たりとも忘れたことはありません』。
「ミナト」という少年は、どうやら僕が子供の頃に親しくしていた、少し年上の存在らしかった。夏祭りの夜店、川での魚捕り、神社の裏にあった秘密基地。手紙に綴られる情景は、朧げながら僕の記憶の片隅にも引っかかった。だが、肝心のミナトの顔も声も、どうしても思い出せない。まるで、パズルの重要なピースだけが、ごっそりと抜き取られてしまったかのように。
なぜ忘れてしまったのだろう。あんなに親しかったのなら、覚えているはずなのに。手紙を読めば読むほど、僕の頭の中は靄がかかったように混乱した。
「このままじゃ、何も分からない」
いてもたってもいられなくなり、僕は再び故郷へ向かうことにした。クライアントに無理を言って数日の休みを取り、僕は半ば衝動的に車を走らせた。目的は、手紙に出てくる「あの丘の桜」を見つけること。そして、自分の記憶の空白を埋めること。それは、停滞した日常からの逃避行でもあった。
実家に着き、今度は書斎を漁ってみる。すると、本棚の隅に、祖母がつけていた数冊の古い日記が見つかった。手紙と日記を照らし合わせれば、何か分かるかもしれない。僕は藁にもすがる思いで、インクが滲んだページを一枚一枚、丁寧にめくっていった。最初は他愛ない日々の記録だった。しかし、ある夏の日付のページで、僕は息を呑んだ。祖母の文字が、そこだけひどく乱れていたのだ。
第三章 罪と沈黙の理由
『八月十六日。ああ、神様。なぜ、あのようなことに。私の、私たちの、取り返しのつかない過ちだ』
日記のその一文から、僕の知らない過去が、津波のように押し寄せてきた。
ミナト君――湊という苗字のその少年は、隣家に住んでいた僕の唯一の親友だった。両親が共働きだった僕にとって、三歳年上の彼は兄のような存在だった。日記と、乱れた文字で書かれた数通の手紙の断片を繋ぎ合わせ、僕はついに、記憶の蓋の奥底に封じ込めていた真実に行き着いた。
あの日、僕たちは二人で裏山の川へ遊びに行った。前日の夕立で増水していることも知らずに。僕は浅瀬で足を滑らせ、あっという間に激しい流れに足を取られた。パニックに陥り、溺れかけた僕を、湊君は必死に岸へ引き上げてくれた。僕はかすり傷だけで済んだ。だが、湊君は僕を庇った際に、川底の岩に強く足を打ちつけていた。
彼の怪我は、当初考えられていたよりもずっと深刻だった。複雑骨折と神経の損傷。度重なる手術も及ばず、彼の右足には生涯癒えることのない後遺症が残った。未来ある少年の夢を、僕が奪ってしまった。
僕の両親は何度も湊君の家に頭を下げた。けれど、小さな田舎町だ。噂はあっという間に広がり、同情の視線は、いつしか湊君の家族を追い詰める棘へと変わっていった。いたたまれなくなった湊君の一家は、事故から一年も経たないうちに、町を去っていった。
幼い僕は、その全てを理解するにはあまりに無力だった。自分のせいで親友が歩けなくなったという凄まじい罪悪感と、彼を失った喪失感。僕の心は、その重みに耐えきれず、自己防衛のために湊君に関する一切の記憶に固く蓋をしてしまったのだ。
祖母は、引っ越した湊君に手紙を書き続けていた。僕の成長を伝え、いつか再会できる日を願いながら。しかし、彼女はその手紙を送ることができなかった。僕がこの事実を知れば、どれほど傷つくか。罪の意識に苛まれる孫の姿を見たくなかったのだ。未投函の手紙は、僕を守るための、苦渋に満ちた沈黙の証だった。
「だからか…」
僕は無意識に呟いていた。僕がずっと、他人と深く関わることを恐れていた理由。心のどこかで、「自分が誰かを不幸にしてしまう」という呪いを、ずっと抱えて生きてきたのだ。
全てのピースが繋がった瞬間、涙が溢れて止まらなかった。それは、湊君への申し訳なさ、祖母の深い愛、そして何も知らずに生きてきた自分への不甲斐なさがないまぜになった、しょっぱい涙だった。僕は桐の箱を抱きしめ、子供のように声を上げて泣いた。
第四章 桜の丘で、もう一度
涙が乾いた頃、僕は一つの決意を固めていた。湊君に会って、謝らなければならない。何十年分の「ごめんなさい」と「ありがとう」を伝えなければ、僕は未来へ一歩も進めない。
僕は叔母や古い知人を頼り、必死に湊君の消息を探した。そして数日後、彼が隣県の小さな市で、車椅子に乗りながら、子供向けの絵画教室を開いていることを突き止めた。
僕は祖母が遺した百通以上の手紙を、大きな鞄に詰め込んだ。まるで、祖母の想いと僕の後悔の重さを、その両腕で抱えているかのようだった。
絵画教室のドアを開けると、絵の具の匂いと子供たちの明るい笑い声が僕を迎えた。その中心に、彼はいた。窓からの柔らかな光を受け、穏やかな表情で子供たちに筆の使い方を教えている。車椅子に乗っていることを除けば、面影は記憶の奥底にある少年のままだった。
僕に気づいた彼――湊君は、少し驚いたように目を見開いたが、すぐに静かに微笑んだ。
「健太…か?大きくなったな」
その声を聞いた瞬間、僕の記憶のダムは完全に決壊した。夏の日差し、水の冷たさ、彼の叫び声。全てが鮮明に蘇る。僕は彼の前に進み出ると、震える声で、鞄から手紙の束を取り出した。
「湊君…ごめん。本当に、ごめんなさい。俺、ずっと忘れてた。君のこと、全部…」
言葉が続かない。ただ、嗚咽が漏れるだけだった。
湊君は静かに僕の話を聞いていた。そして、手紙の束にそっと手を伸ばすと、優しい声で言った。
「ばあちゃん、書いてくれてたんだな…。嬉しいよ」
彼は空を見つめ、懐かしむように目を細めた。
「ずっと待ってたわけじゃないけど、いつかこうして会える日が来るんじゃないかって、どこかで思ってた。謝るなよ、健太。あれは事故だ。俺が、お前を助けたいって思った。それだけのことだよ」
彼の言葉は、僕の心を縛り付けていた何十年もの重い鎖を、いとも容易く解き放ってくれた。赦された安堵と、彼の変わらぬ優しさへの感謝で、僕は再び涙を流した。それは、罪悪感を洗い流す、温かい涙だった。
僕たちは、子供の頃に戻ったかのように、たくさんの話をした。彼が絵を描くことで救われたこと。僕がデザイナーになったこと。空白の時間は、あっという間に埋まっていった。
東京に戻った僕の世界は、色を取り戻していた。モニターに向かう目には、以前のような澱んだ光はなく、確かな意志が宿っていた。僕は新しいプロジェクトの企画書を書き始めた。テーマは「再会」。
数週間後、僕の元に一通の封筒が届いた。差出人は、藤川湊。中には、一枚の水彩画が入っていた。そこに描かれていたのは、満開の一本桜が咲き誇る丘の上で、二人の少年が肩を組んで笑い合っている姿だった。あの丘の、あの桜だ。
絵の裏には、短いメッセージが添えられていた。
『また、あの丘で』
窓の外には、都会の喧騒が広がっている。だが、今の僕には、その風景が少しだけ温かく、優しく見えた。過去は消せない。後悔が完全になくなることもないだろう。だけど、過去と向き合い、赦し合うことで、未来はこんなにも豊かに色づき始める。
僕はその絵を机の一番見える場所に飾り、静かに微笑んだ。いつかまた、桜の咲く季節に、あの丘で彼に会おう。今度は、胸を張って。