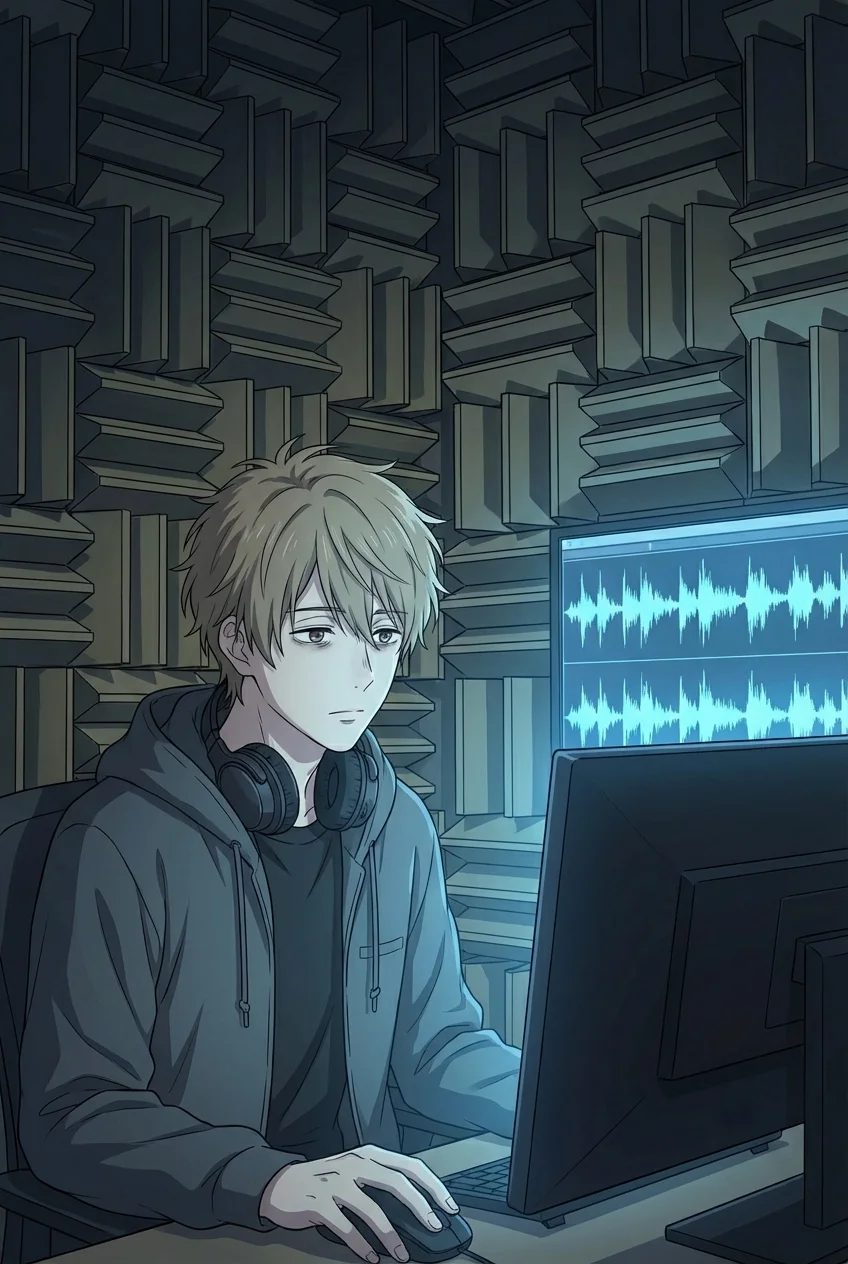第一章 色褪せた軌跡
僕の眼には、世界が光の軌跡で満ちている。人々が繰り返す日常の行動パターンが、固有の色と形を持つ光の粒子となって空間に編み込まれているのだ。毎朝七時八分に同じ車両に乗るサラリーマンの軌跡は、焦燥感を滲ませた青い直線。公園のベンチで、午後三時から決まって文庫本を読む老人のそれは、穏やかな陽だまりのような金色の円。
この能力は、物心ついた頃からの僕だけの秘密だった。人々は、自分たちの日常がどれほど強固なパターンに縛られているかを知らない。そして、その反復が世界の物理法則に微細な亀裂を入れていることにも、誰も気づいていない。
時折、街のあちこちで奇妙な現象が起こる。カフェの砂糖壺がふわりと数秒浮き上がったり、踏切の警報音がまるで水中から聞こえるように歪んだり。人々は「貧血かな」「耳鳴りがひどい」と首を傾げるだけ。だが僕にはわかる。それは、誰かの『日常』が極限まで繰り返されたことで生じる、時空の些細な悲鳴なのだ。
古びたアパートの自室で、僕はポケットから使い古したサイコロを取り出した。片側だけが奇妙に磨耗した、象牙色の立方体。テーブルの上で転がすと、カラン、と乾いた音を立てて止まる。出た目は「1」。もう一度振る。今度は「6」。何度試しても、このサイコロは1か6しか示さない。まるで、選択肢の少ない僕自身の日常を嘲笑っているかのようだった。
第二章 白き輝きの前兆
異変の兆しは、公園の老人から始まった。彼の金色の光は、僕にとって一種の安らぎだった。毎日同じ時間に、同じベンチで、同じページを開く。その完璧な反復が、彼の光を誰よりも安定させていた。
しかし、ある日の午後、彼の光は常ならぬ輝きを放ち始めた。金色の中に純白の閃光が混じり、まるで内側から発光しているかのようだった。僕は息を呑んで見つめる。すると、老人の周囲だけ、空気がゼリーのように固まった。木の葉のざわめきが消え、子供たちの歓声が遠のき、世界から音が奪われる。数秒の完全な静寂。
やがて世界が色と音を取り戻した時、老人はただ満足げに目を細め、空を仰いでいた。その表情は、長い旅を終えた旅人のように安らかだった。それが、僕が彼を見た最後になった。翌日から、あのベンチに彼の姿はなかった。彼の金色の軌跡も、綺麗に消え失せていた。
その頃からだ。僕は、街のあちこちで奇妙な痕跡に気づき始めた。誰かの光が白く輝いて消えた場所の近くに、どのパターンにも属さない、淡く漂う光の粒子が残されているのだ。それはまるで、誰かが歩いた後に残る、目に見えない足跡のようだった。僕はそれを『不可視の日常』と名付けた。
第三章 琥珀色のワルツ
僕には、密かに心惹かれている光があった。駅前の小さな喫茶店『豆灯』で働く、日向栞さんの軌跡だ。彼女の動きは、まるで精緻なワルツのようだった。カウンターに立ち、豆を挽き、湯を注ぐ。その一連の動作が描き出す光は、温かい琥珀色をしていた。
「いつもの、でよろしいですか?」
僕が席に着くと、彼女は柔らかな声で尋ねる。僕がいつも同じブレンドコーヒーを頼むことを、彼女は知っている。僕の日常のパターンは、彼女の日常の一部に組み込まれていた。
その日、彼女の琥珀色の光が、いつもより強く、そして白く揺らめいていることに気づいてしまった。公園の老人と同じ、あの白光化の前兆だった。胸がざわつく。失いたくない、と強く思った。
「栞さん、最近、何か変わったこと、ありましたか?」
思わず口から出た言葉に、自分でも驚いた。彼女は少しだけ目を丸くしてから、ふわりと微笑んだ。
「変わったこと、ですか?……そうですね。最近、よく昔のことを思い出すんです。子供の頃、父が入れてくれたココアの味とか。一番、幸せだった頃の記憶、みたいな」
その言葉が、僕の心の深い場所に小さな石を投げ込んだ。店を出て、震える手でサイコロをポケットから取り出す。衝動的に、路地裏でそれを振った。
カラン。
サイコロはアスファルトの上で転がり、止まった。
出た目は、「2」だった。
初めて見るその目に、僕は世界の法則が根底から覆るような、途方もない予感を覚えていた。
第四章 零れたインクと歪む世界
数日後の午後、その時は訪れた。僕が『豆灯』の扉を開けると、店内の空気が奇妙に張り詰めていた。カウンターに立つ栞さんの身体から、眩いばかりの純白の光が放たれている。琥珀色の軌跡は完全にその輝きに飲み込まれていた。
「……っ、栞さん!」
僕の声は、誰にも届かなかった。次の瞬間、世界が壊れた。
店内にあったカップというカップが、一斉に宙へと浮かび上がる。スプーンがぐにゃりと意思を持ったように曲がり、壁の時計の針が逆回転を始めた。窓の外の喧騒が、分厚いガラスの向こう側のように完全に遮断される。客たちが声にならない悲鳴を上げるが、その声すらも歪んで聞こえない。
時空が悲鳴を上げている。だが、その中心にいる栞さんだけは、穏やかな表情をしていた。彼女はカウンターに両手をつき、まるで大切な何かを慈しむように、ゆっくりと目を閉じる。そして、その身体が、まるで水に零れたインクのように、輪郭から滲み始めた。
僕は手を伸ばす。だが、指先が彼女に触れる寸前、その姿は淡い光の粒子となって霧散した。後には、彼女がいつも使っていたマグカップと、あの優しいコーヒーの香り、そして無数の『不可視の日常』の粒子だけが、きらきらと舞っていた。
一瞬の後、浮いていたカップは床に落ちて砕け、世界の音も元に戻った。何事もなかったかのように。だが、僕の世界は、もう元には戻らなかった。
第五章 サイコロが紡ぐ真実
栞さんが消えてから、街の白光化は加速した。あちこちで人々が光の中に溶け、その度に『不可視の日常』の粒子が世界を満たしていく。僕は狂ったようにその痕跡を追い続けた。これは破滅だ。世界が終わるのだ。そう信じていた。
だが、気づいた。人々が消えた場所には、必ずその人が最も愛した『日常の記憶』が色濃く残されていることに。公園のベンチには陽だまりの温もりが。交差点には、恋人を待ち続けた青年の焦燥と期待が入り混じった空気の匂いが。そして『豆灯』には、栞さんのコーヒーの香りが、以前よりもずっと深く、満ちていた。
これは、喪失ではない。消失でもない。
――これは、刻印だ。
ポケットの中で、サイコロが熱を持っていることに気づく。取り出して、祈るように手のひらで転がした。
「3」
もう一度。
「5」
さらに、もう一度。
「4」
かつて1と6しか示さなかったサイコロは、今や僕に応えるように、全ての可能性を指し示していた。日常のパターンが崩れ、世界が変容していく。その中で、僕の認識もまた、新たな形へと変わっていく。
白光化は、世界の終焉を前にした、最後の儀式だったのだ。この世界に生きた全ての人々が、自らの最も幸福だった日常の記憶を、次の世界の礎として時空に刻みつけている。物理法則の不安定化は、その膨大な記憶が刻まれる際に生じる、幸福な副作用に過ぎなかった。僕が今まで見ていたのは、世界の終わりへと向かう、人々の祝福の軌跡だったのだ。
第六章 僕の日常、世界の夜明け
空を見上げると、街中から立ち上った『不可視の日常』の光が、巨大なオーロラとなって夜空を覆っていた。それは、数えきれない人々の愛おしい記憶のタペストリー。世界は、荘厳なほどの静寂に包まれている。
ふと、自分の手のひらを見下ろす。僕の日常を描いていた光の軌跡が、ゆっくりと白く輝き始めているのを、僕は静かに受け入れた。
僕の、最も幸福な日常。
それは、何か特別な出来事ではない。古書店の埃っぽい匂い。インクと古紙が混じり合った香りの中で、静かにページをめくる時間。そして、カウンター越しに見た、栞さんの穏やかな笑顔。彼女が入れてくれたコーヒーの、あの琥珀色。
「……また、どこかの日常で」
誰に言うでもなく呟き、最後のひと振りのためにサイコロを握りしめる。僕の記憶が、これから生まれる新しい世界のどこかで、誰かの心を少しだけ温めるのなら。
サイコロは宙を舞い、僕の手のひらに落ちた。その目が何を示したのか、僕は確かめなかった。
身体が内側から光で満たされていく。意識が薄れる中、僕の視界の端に、地平線の向こうから昇る、新しい世界の朝焼けが見えた気がした。それは、僕が遺した琥珀色によく似ていた。