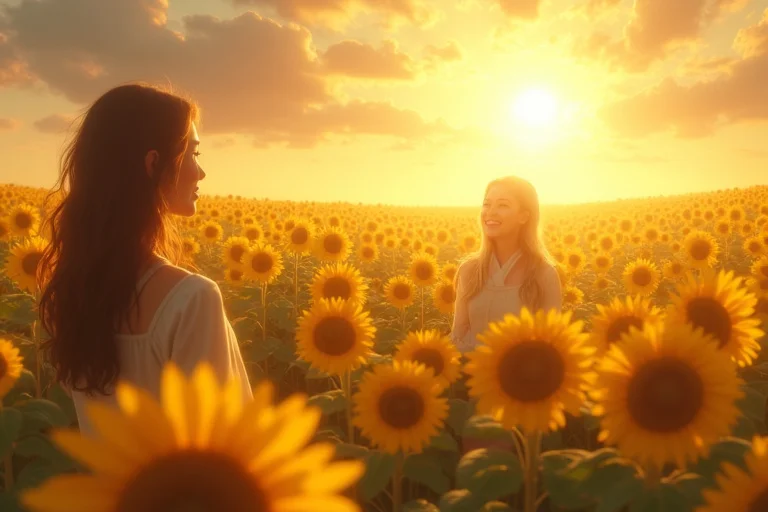第一章 刻まれた痛み
俺、カイの身体は、他人の心の帳面だ。誰かの胸に燻る「未練」は、俺の皮膚の上に物理的な傷跡となって浮かび上がる。それは時に細い掻き傷のように、また時には鈍い痣のように現れ、その持ち主の心が晴れるまで決して消えることはない。
今日もそうだ。路地裏で膝を抱える少年の傍らを通り過ぎた瞬間、左腕にすっと冷たい線が走った。見れば、真新しい一本の切り傷。少年の心に触れるまでもない。その瞳に映る悔恨の色を見れば、親友と交わした些細な口論が原因だとすぐに分かった。
「謝れば、その痛みも消えるさ」
俺が呟くと、少年はびくりと肩を震わせ、やがてこくりと頷いて駆け去っていった。数時間もすれば、この傷も跡形もなく消えるだろう。それが俺の日常だった。
だが、この街の日常は少しずつ歪み始めていた。人々が生涯で一度だけ交わす、最も重い「約束」。それを守る証である「契りの小石」を誰もが持ち、その約束が破られた時、人は徐々に透明になり、やがて世界から完全に消滅する。それが、この世界の絶対的な法則のはずだった。
しかし、近頃は奇妙な噂が乾いた風に乗って囁かれていた。約束を破ったわけでもない人々が、次々と透明になって消えている、と。その噂は、まるで街全体を覆う薄墨色の靄のように、人々の顔から確かな色彩を奪っていくようだった。
その夜、事件は起きた。眠りについていた俺を叩き起こしたのは、胸を内側から抉られるような、未だかつて経験したことのない灼熱の激痛だった。
「ぐっ……ぁあ!」
シーツを握りしめ、体をくの字に折り曲げる。シャツを乱暴に引き裂くと、鏡に映った自分の姿に息を呑んだ。心臓の真上から、まるで巨木が雷に打たれたかのように、巨大な傷跡が赤黒く刻み込まれていたのだ。それは誰かの未練にしては、あまりにも深く、あまりにも広大だった。まるで、世界そのものが悲鳴を上げているかのような、絶望的な傷跡だった。
第二章 透明な影
翌日から、俺は傷の持ち主を探して街を彷徨った。誰かの肩に触れ、誰かの瞳を覗き込む。だが、俺の胸で脈打つこの巨大な痛みに共鳴する魂は、どこにも見当たらなかった。傷は日増しに深くなり、時折襲う激痛は俺の意識を朦朧とさせた。
そんな折、広場の中心で人々の悲鳴が上がった。駆けつけると、人垣の中心で一人の男がゆっくりと透けていくところだった。彼の妻らしき女性がその腕に縋りついているが、指は頼りなく彼の体をすり抜けていく。
「どうして……あなたは約束を破ったりしないのに!」
男の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちる。彼の掌で輝いていたはずの「契りの小石」は、濁った灰色に変色し、ひび割れていた。
「俺は……ただ、幸せに……」
その言葉を最後に、男の姿は陽炎のように揺らめき、光の粒子となって風に溶けた。ぱりん、と乾いた音が響き、砕け散った小石の欠片が地面に散らばる。その瞬間、俺の胸の傷がズキンと疼き、さらに深く抉られたような気がした。
消滅は連鎖した。約束を守り、誠実に生きてきた人々が、次々と透明な影となって消えていく。街は静かなパニックに包まれ、人々は互いの顔に疑念と恐怖の色を浮かべ始めた。誰を信じればいいのか。何が正しいのか。その不信感が蔓延するたびに、俺の傷は叫び声を上げた。この痛みは、消えていく人々の最後の未練なのだろうか。だとすれば、なぜ彼らは消えねばならないのか。謎は深まるばかりだった。
第三章 契りの小石
「カイ、また顔色が悪くなってる」
幼馴染のリナが、心配そうに俺の顔を覗き込む。彼女だけが、俺のこの特異な体質を知り、静かに寄り添ってくれる存在だった。彼女の掌から伝わる温もりが、少しだけ傷の痛みを和らげてくれた。
俺たちの指には、揃いの指輪に通した小さな「契りの小石」が揺れている。幼い頃、二人で交わした約束。「どんな時も、互いを信じ、一人にしない」。他の小石が輝きを失っていく街の中で、俺たちの石だけは、変わらず澄んだ光を放ち続けていた。
「このままじゃ、街の皆が消えてしまう」
俺は書庫に籠もり、古文書の山に答えを探した。埃っぽい紙の匂いと、ページをめくる乾いた音だけが、俺の焦燥感を宥めてくれる。そして、一冊の古びた年代記の中に、一つの記述を見つけたのだ。
『世界の始まりに、大いなる約束あり。その記憶を守る賢者は、霧深き丘の麓に今も息づく』
霧深き丘。街の外れにある、誰も近づかない場所だ。そこに、この謎を解く鍵があるのかもしれない。俺はリナに「必ず戻る」とだけ告げ、痛む胸を押さえながら、霧の中へと歩みを進めた。
第四章 最初の約束
霧の丘の麓には、苔むした石造りの小さな家がひっそりと佇んでいた。扉を開けると、無数の書物に囲まれた一人の老人が、静かに俺を迎えた。皺だらけの顔に浮かぶ瞳だけが、星空のような深い叡智を湛えている。
「その傷……ついに現れたか。世界の嘆きが」
老人は俺の胸の傷を一瞥するなり、全てを悟ったように呟いた。彼は、この世界の成り立ちについて語り始めた。それは、神話ともお伽話ともつかない、途方もない物語だった。
「我々の祖先は、この世界が生まれた時、世界そのものと一つの約束を交わしたのだ。『互いを信じ、支え合い、共に生きる』と。それが、全ての約束の源となった『最初の約束』じゃ」
老人の言葉が、雷のように俺の脳を撃ち抜いた。
「人々はいつしか、その大いなる約束を忘れた。目先の小さな約束に固執し、隣人への不信を募らせ、他人の痛みに目を閉じた。無関心と利己主義が、見えざる刃となって『最初の約束』を少しずつ切り刻んでいったのじゃ。人々が消滅しているのは、その綻びが限界に達した証拠。世界の土台そのものが、崩れ始めているのよ」
そして老人は、俺の傷を真っ直ぐに見据えた。
「お主のその傷は、特定の誰かの未練ではない。この世界に生きる全ての人々が、『最初の約束』を忘れ、破り続けていることへの、世界そのものの『未練』であり『痛み』なのだ」
その言葉が真実だと告げるかのように、俺の胸の傷跡の中心が、内側から弾けるような激しい光を放った。皮膚を突き破り、目の前に現れたのは、人の頭ほどもある巨大な「契りの小石」だった。それは鈍く、悲しげに明滅しながら、俺の心臓と共鳴するように脈打っていた。
第五章 選択の刻
巨大な小石は、俺の生命力を貪欲に吸い上げ始めた。指先からゆっくりと、自分の体が透明になっていくのが分かる。このままでは、俺自身が世界より先に消滅してしまう。
「その傷を癒やす方法は、ただ一つ」と、老人は静かに告げた。「お主が新たな『柱』となり、この砕け散った世界と、もう一度『最初の約束』を結び直すことだ。それは……お主自身の消滅を意味する」
自己犠牲。その言葉が重くのしかかる。俺一人が消えることで、この街が、リナが救われるのなら……。
その時、家の扉が勢いよく開かれ、リナが息を切らして飛び込んできた。俺の透け始めた体を見て、彼女の顔が絶望に歪む。
「いや……!カイ、行かないで!」
彼女は俺の体に縋りつくが、その手は虚しく俺をすり抜ける。「一人にしないって約束したじゃない!」と泣き叫ぶ彼女の声が、薄れゆく意識の中で痛いほど響いた。
俺が消えれば、彼女との約束も破ることになる。世界を救うために、たった一つの大切な約束を裏切るのか? それは、この連鎖を断ち切ることになるのか、それとも新たな悲劇を生むだけではないのか? 答えは、出なかった。
第六章 傷跡という名の希望
俺は、ゆっくりと首を横に振った。
消滅は、選ばない。
残された力を振り絞り、リナに支えられながら街の中央広場へと向かう。人々は、透け始めた俺の姿と、その胸で禍々しくも神々しく脈打つ巨大な小石を見て、息を呑んだ。
俺は声を張り上げた。それは、俺自身の声であり、世界の嘆きの声でもあった。
「この傷を見ろ! これは、俺たち自身が刻んだ傷だ! 我々が忘れていた痛みの記憶だ! 誰かを信じる心を失い、隣人の苦しみに目を閉じた、我々自身の未練なんだ!」
俺は胸の小石に手を当てる。不思議と、痛みは感じなかった。
「犠牲は何も生まない! 消える必要などないんだ! 俺たちがすべきことは、ただ一つ……思い出すことだ! もう一度、隣人の手を握ること。互いを信じ、支え合うと誓った、あの『最初の約束』を!」
俺の言葉は、人々の凍てついた心に染み渡っていった。人々は恐る恐る顔を上げ、互いの目を見つめ合う。そこには、忘れかけていた温かい光が灯り始めていた。一人が、そっと隣の男の肩に手を置いた。それをきっかけに、人々は手を取り合い、抱きしめ合った。彼らの胸元で曇っていた小さな「契りの小石」が、一つ、また一つと、柔らかな輝きを取り戻していく。
その光景に呼応するように、俺の体の透明化がぴたりと止まった。しかし、胸の巨大な傷跡と小石は消えなかった。それはもう、呪いではない。人類が犯した過ちの「戒め」として、そして、これから歩むべき道を示す「希望の象徴」として、俺の体に永遠に刻まれたのだ。
街から消滅の影は消え去り、穏やかな光が全てを包んでいた。俺はリナの手を強く握る。彼女の小石と俺の小石が触れ合い、澄んだ音を立てた。胸の傷はまだそこにある。だが、もはやそれは痛みだけを伝えるものではなかった。人々の温かな想いを受け、まるで心臓がもう一つ増えたかのように、確かな希望の光を帯びて、静かに脈打っていた。