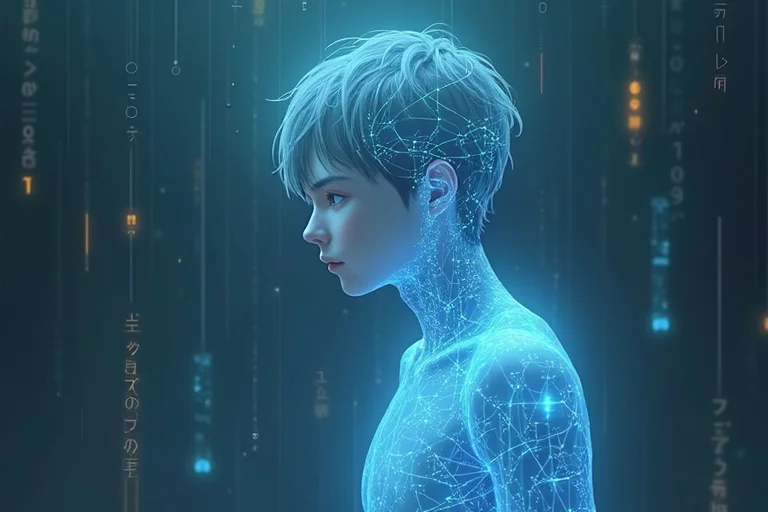第一章 加速する街
アスファルトの隙間から立ち上る陽炎のように、この街の時間は歪んでいた。俺、カイの目には、それが人々の体に刻まれた無数の『傷』として映る。ガラスの破片が皮膚の下に埋め込まれたような、光の角度で明滅する細い線。それは社会から見過ごされた不利益が、物理的な形をとって現れたものだった。
「カイ、ぼうっとしてないで、手を動かせ!」
背後から怒声が飛ぶ。ここは「急速区」。富める者が住まう「悠久区」とは隔絶された、時間に追われる者たちの街だ。ここでは誰もが早足で、息を切らし、短い生涯を駆け抜けていく。俺は解体現場の瓦礫を運びながら、向かいの歩道で背を丸める老婆に目をやった。彼女の頬には、深い皺に沿うように幾筋もの傷が走っている。それは年金制度の不備によって奪われた、穏やかな老後の象徴だった。
そっと老婆に近づき、震えるその手に自分の手を重ねる。指先が傷に触れた瞬間、氷の針を刺されたような冷たい痛みと、何十年も無視され続けた心の軋みが、奔流となって俺の中に流れ込んできた。息が詰まる。これが、彼らの時間。これが、彼らの痛みだ。老婆は虚ろな目で俺を見上げ、何かを呟いたが、その言葉は加速した時間の風にかき消された。
俺たちの時間は、なぜこうも速く過ぎ去るのか。そして、なぜ俺だけが、その代償である傷を見ることができるのか。空を見上げると、街の真ん中にそびえ立つ白亜の塔が、すべてを見下ろしていた。
第二章 時間結晶の輝き
危険を冒して「悠久区」に足を踏み入れると、世界の速度が変わった。空気はねっとりと肌に絡みつき、人々の動きは優雅な舞踏のようだ。ここでは鳥のさえずりさえもスローモーションで聞こえる。急速区の喧騒が嘘のようだった。
悠久区の住人たちは、皆一様に宝飾品を身につけていた。ネックレスやピアスの石は、内側から淡い光を放ち、持ち主のゆったりとした心拍と共鳴するように明滅している。あれが『時間結晶』。富の象徴であり、彼らの悠久を保証する石。
カフェのテラスで談笑する貴婦人の耳元で、結晶がひときわ強く輝いた。その瞬間、俺の目の奥が疼く。貴婦人の滑らかな肌の下に、一瞬だけ、急速区の老婆と同じ『傷』が、糸くずのように明滅して見えた。錯覚ではない。結晶の輝きと、俺たちに刻まれる傷は、間違いなく繋がっている。
「あなた、急速区の人間ね」
不意に声をかけられた。振り返ると、ウェイトレスの制服を着た女が立っていた。リナと名乗る彼女の瞳には、俺と同じ、世界への疑念と怒りの色が宿っていた。
「あなたにも、見えるの? 時間のひび割れが」
リナの腕には、制服の袖で隠された無数の傷が、うっすらと浮かんでいた。
第三章 システムの心臓
リナは、この世界の時間の流れを制御する巨大なシステム――『クロノスの天秤』の存在を教えてくれた。街の中央にそびえるあの白亜の塔こそが、システムの心臓部だという。
「天秤は、富める者から時間を奪い、貧しい者に与える……そう教えられてきたわ。でも、真実は逆。私たちの時間を奪い、彼らに捧げているのよ」
リナは地下の隠れ家で、壁に貼られた塔の設計図を指さした。彼女は仲間たちと、この不平等を終わらせるためにシステムの破壊を計画していた。俺の『傷』が見える能力は、計画の切り札になるかもしれないと彼女は言った。
塔への潜入を決意した夜、俺は自分の腕に浮かんだ新しい傷に気づいた。それは細く、まだ淡い光しか放っていなかったが、確かにそこにあった。システムの謎に近づくほど、俺自身もまた、世界の歪みに蝕まれていくようだった。胸騒ぎが、冷たい霧のように心を覆っていく。それでも、もう引き返すことはできなかった。急速区で生きる人々の顔、その体に刻まれた無数の痛みが、俺の背中を押していた。
第四章 零時の囁き
白亜の塔の内部は、静寂に満ちていた。外の世界とは隔絶された、時間の概念さえ存在しないかのような空間。リナの案内で警備を抜け、俺たちはついに中枢部へとたどり着いた。
そこに広がっていたのは、想像を絶する光景だった。
巨大な洞窟ほどの広さがあるドームの中央に、脈動する巨大な時間結晶が鎮座していた。心臓のように明滅する結晶からは、無数の光のパイプが伸び、ドームの壁面へと繋がっている。パイプの一つ一つが、急速区に住む一人一人の人間から奪った時間、そのものなのだと直感した。そして、そのパイプの所々がひび割れ、漏れ出した光が、俺の目にだけ見える『傷』となって現れていたのだ。
「よく来たね、綻びの子よ」
声は、巨大結晶の前に立つ、古びたアンドロイドから発せられた。彼が『クロノスの天秤』の管理者だった。
「このシステムを破壊しに来たのだろう。だが、真実を知っても、君にその引き金を引けるかな?」
管理者は静かに語り始めた。この世界はかつて、誰もが平等な時間の中、緩やかに滅びへと向かっていたのだと。原因不明の疫病のように、人類全体の生命力が希薄になっていた。クロノスの天秤は、その滅びを回避するための最後の手段だった。
「これは延命措置なのだよ。人類という種を存続させるために、生命力を特定の層に集中させる。貧しき者から時間を、つまり生命力を徴収し、富める者に供給する。そうして、人類の『種としての記憶と文化』を、彼らに託して未来へ繋ぐのだ。君に見える傷は、その生命供給パイプに生じる歪み。そして君の能力は、システムが生み出した最も大きなバグ……歪みを修復するために生まれた抗体のようなものだ」
管理者の言葉が、重い楔となって胸に突き刺さる。不平等は、種の存続のための苦渋の選択だったというのか。
第五章 選択の代償
「それでも、こんなのは間違ってる!」
リナが叫んだ。彼女の目には涙が浮かんでいた。加速する時間の中で、病気の母をあっけなく喪った彼女にとって、その理屈はあまりにも残酷な欺瞞だった。
俺も同じだった。老婆の手から伝わってきた、あの冷たい絶望を思い出す。未来のために現在を犠牲にするというのなら、その現在を生きる俺たちは何なのだ。偽りの延命か、それとも残酷な平等か。
「俺たちは……家畜じゃない」
俺は呟き、中枢の制御装置に手を伸ばした。管理者は止めようとしない。ただ静かに、俺たちの選択を見つめている。
「偽りの楽園より、真実の荒野を」
リナが俺の手を握った。二人で、システムの停止スイッチを押し込む。
世界が、一瞬だけ光に包まれた。巨大な結晶の脈動が止まり、塔が大きく揺れる。窓の外では、急速区のせわしなかった街の動きが、嘘のように緩やかになっていくのが見えた。人々が空を見上げ、困惑しながらも、その顔に安堵の色が広がっていく。
やったんだ。俺たちは、時間を取り戻したんだ。
だが、安堵は束の間だった。リナがふと、自分の手の甲を見た。そこに、蜘蛛の巣のような細かい皺が、みるみるうちに広がっていく。彼女の黒かった髪に、白いものが混じり始める。
「カイ……? なんだか、頭が……」
リナだけではない。窓の外で喜んでいた人々も、次々と自分の体に起こる異変に気づき、悲鳴を上げ始めていた。富裕層も、貧困層も、関係なく。平等に。
第六章 等しき黄昏
塔を降りて、俺は変わり果てた街を歩いた。誰もが等しく老い、記憶を失っていく世界。システムの破壊は、堰き止められていた生命力という名のダムを決壊させたのだ。集中管理されていた生命力は霧散し、全人類が等しく、本来の滅びの運命へと回帰し始めた。
かつて俺の目にだけ見えていた、あのきらめく『傷』は、もう誰の体にもなかった。その代わりに、誰もが「死」という、巨大で、決して癒えることのない傷を、平等にその身に刻みつけていた。
公園のベンチに座るリナを見つける。彼女は、まるで初めて会う人間を見るような目で俺を見つめ、小さく微笑んだ。彼女はもう、俺の名前さえ覚えていない。
俺は彼女の隣に座り、夕日を見た。空は、血を流すように燃えている。俺がもたらしたこの皮肉な平等は、果たして正しかったのだろうか。答えは出ない。ただ、急速に失われていく世界の記憶の中で、老婆の手に触れた時の、あの冷たい痛みの感触だけが、永遠の傷のように、俺の掌に焼き付いていた。