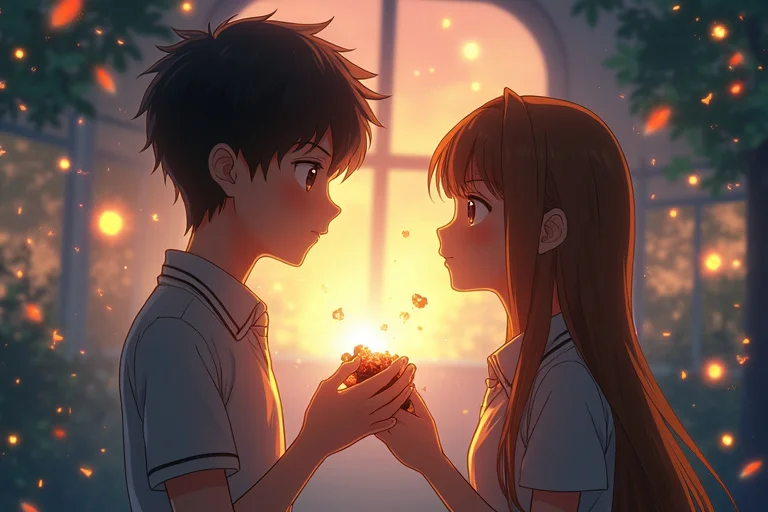第一章 腐敗する光
判定が下された瞬間、エレナの美しい若草色のオーラが、見るも無惨に「腐り」始めた。
まるで生肉が急速に時間を早回しで朽ちていくように、鮮やかな緑がドス黒く変色し、ボタボタと粘着質の雫となって足元の石畳を汚していく。
「あ……あぁ……」
彼女の悲鳴は、喉の奥で凍りついていた。
可憐な指先が痙攣し、虚空を掻く。
僕、天沢悠の視界には、そのグロテスクな変貌がありありと映っていた。
吐き気がこみ上げる。胃の腑が裏返るような強烈な拒絶反応。
ここは学園の中央広場。
肌を刺すような冷たい風が吹き抜ける中、一千人の生徒が死刑宣告を待つ囚人のように整列している。
今日は『選定の日』。
広場の中央には、絶対的な支配者として「クロノスの砂時計」が鎮座していた。
高さ二十メートル。水晶の巨塔。
内部を流れる黄金の砂が、ザァァ、ザァァと、僕たちの寿命を削り取るような重苦しい駆動音を響かせている。
壇上に立つ男、ヴァルデス教官が静かに手元の端末を操作した。
彼の背後には、凍てつくような金属質の黄金色のオーラが立ち昇っている。かつて僕が憧れた、温かな色ではない。鋭利な刃物の輝きだ。
「エレナ・フォスター。適性判定、『重工学兵器開発』」
ヴァルデス教官の声は、厳冬の湖面のように波がない。
「ま、待ってください教官!」
エレナが泣きそうな声で訴える。
彼女の足元で、腐敗した黒いオーラがさらに広がっていく。僕にはその悪臭さえ感じられるようだ。
「私は植物の育成や、医療の勉強をしてきました。兵器なんて……誰かを傷つけるなんて、できません」
「個人の感傷など、砂の一粒ほどの価値もない」
教官はエレナを見下ろした。その瞳には、慈悲ではなく、狂信的なまでの「理」が宿っていた。
「君の潜在的な空間認識能力と、対象を微細に分解する思考プロセス。それは治癒よりも、破壊において数千倍の効率を叩き出す。システムがそう結論づけた」
「そんな……」
「効率こそが正義だ。君の『優しさ』は、この過酷な世界では弱点にしかならない。私がその弱点を、鋼鉄の強さへと鍛え直してやる」
反論を許さない圧力が、広場の空気を押しつぶす。
違う。
それは彼女の魂を殺すことだ。
「次。カイ・アルディン」
僕の親友が呼ばれた。
カイの体からは、緻密な設計図を思わせる、透き通った幾何学模様の「青」が溢れている。
「判定、『前線突撃歩兵』」
カイが息を呑む音が聞こえた。
パリン、と何かが割れる幻聴。
あの美しい幾何学の青が、一瞬にして砕け散り、恐怖に染まった泥のような灰色へと濁っていく。
僕の奥歯がギリと鳴った。
このシステムは異常だ。
適材適所ですらない。まるで、あえてその人間が最も苦しむ場所へ配置し、心を摩耗させることを目的としているかのように。
僕は自分の掌を見つめる。
そこにあるのは、色褪せたアスファルトのような「灰色」。
美しくもなく、醜くもない。
ただのノイズ。
判定不能(エラー)の烙印を押された落ちこぼれの色。
だが、この濁った瞳だけが捉えている。
クロノスの砂時計の根元に渦巻く、どす黒い怨嗟のエネルギーを。
ヴァルデス教官。あなたは一体、僕たちを何「燃料」にして、何を動かそうとしているんだ?
第二章 砂礫の演算
深夜、寮を抜け出した僕は、吸い寄せられるように広場へ戻っていた。
砂時計の駆動音が、昼間よりも大きく、耳障りに響いている。
ザァァ……ザァァ……。
「眠れんか、天沢悠」
闇の中から現れたヴァルデス教官に、僕は驚かなかった。
彼の黄金のオーラは、夜の闇の中でより一層、冷たく輝いている。
「……あの判定には納得できません」
僕は単刀直入に切り出した。
「エレナもカイも、心が壊れてしまう。教官は、生徒を愛していたはずだ。それが、こんな残酷な配置を?」
「愛しているからこそだ」
教官は砂時計のガラス面に手を触れた。
その横顔には、昼間は見せなかった深い苦悶の影が落ちている。
「悠。君には『色』が見えているのだろう?」
「……知っていたんですか」
「君のその『灰色』は、ただの無色ではない。……まあいい。見ろ」
教官が端末を操作すると、砂時計の砂が逆流を始めた。
黄金の粒子が空中にホログラムを描き出す。
そこ映し出されたのは、燃え盛る大地だった。
逃げ惑う人々。
皮膚を溶かす酸の雨。
枯渇した資源を巡り、骨肉の争いを繰り広げる人類の末路。
「これは……」
「シミュレーションNo.1048。『大崩壊』だ」
教官の声が震えた。
それは恐怖ではない。確定した未来に対する、重すぎる責任感の震えだ。
「人類が今のまま『自由』を謳歌し、好きな道を歩めば、わずか三十年でこの結末に至る。確率は99.9%だ」
「だからって……」
「回避するには、個人の『幸福』を捨て、種としての『生存』に特化するしかないのだ!」
教官が叫んだ。
いつも冷静な彼の、悲痛な叫びだった。
「エレナの才能を兵器転用し、カイを弾除けにしてでも、防衛ラインを維持しなければならない。非情な計算だけが、我々を延命させる唯一の道標なのだよ」
黄金のオーラが揺らめく。
彼の正義は、あまりにも巨大で、あまりにも悲しい。
数億の命を救うために、目の前の千人を犠牲にする。その罪を、彼は一人で背負おうとしている。
「君の灰色は『半端者』の証だ。システムに組み込む価値すらない。……部屋へ戻れ。運命はもう、計算し尽くされている」
教官は背を向けた。
その背中は、拒絶の壁そのものだった。
圧倒的な論理。
生存という大義名分。
足が竦む。
でも、僕の網膜には焼き付いている。
腐り落ちたエレナの緑。砕け散ったカイの青。
「……嫌だ」
僕は、震える足を一歩前へ踏み出した。
「計算し尽くされている? ふざけるな」
「何?」
「未来を勝手に諦めるなよ。……僕たちは、数字じゃない!」
第三章 飽和するノイズ
「何をする気だ!」
教官の制止を振り切り、僕はクロノスの砂時計へと疾走した。
巨大なクリスタルガラス。
その表面には、複雑怪奇な幾何学模様の回路が走っている。
「やめろ! 生身で接触すれば、脳が焼き切れるぞ!」
僕は構わず、両手をガラスに叩きつけた。
ジジジジッ!!
指先から脳髄へ、焼きごてを当てられたような激痛が走る。
膨大な演算データが、津波となって僕の意識に流れ込んでくる。
『生存確率ノ低下ヲ検知』
『排除シマス』
『排除シマス』
無慈悲な警告音が脳内で鳴り響く。
このシステムは、特定の色(波長)しか受け入れない。
赤は赤の、青は青の回路へ。
純粋な色だけが「効率的」に処理される。
だから、混じり気のある僕の灰色は弾かれる。
「ぐ、あぁああああッ!」
「離れろ、悠! 死ぬぞ!」
教官が僕の肩を掴もうとする。
だが、その手は僕の体から噴き出した衝撃波に弾かれた。
「違う……この色は、弾かれるんじゃない……」
歯を食いしばり、血の味が口いっぱいに広がる。
激痛の中で、僕は自分の「灰色」の本質を理解した。
絵の具を全部混ぜれば黒になる。
だが、光は?
すべての色の波長を重ね合わせれば、それは白へ、そして無限のスペクトルを含んだ灰色へと至る。
僕の灰色は、空っぽなんかじゃない。
すべての可能性(カラー)を内包した、混沌(カオス)そのものだ。
「受け取れ……これが、人間の『雑音』だッ!!」
僕は意識の奥底にある灰色の門を、全開にした。
ドォォォォンッ!!
砂時計が唸りを上げる。
僕の手から流し込まれた「全色の波長」が、システムの処理能力を飽和させていく。
「な、なんだこの数値は……!? システムが、オーバーフローしている!?」
教官が狼狽する声が聞こえる。
認証システムは、僕のオーラを「赤」とも「青」とも「緑」とも認識し、同時にそのすべてを否定する。
矛盾。
葛藤。
迷い。
システムが排除してきた「非効率な感情」のすべてが、計算式を食い荒らすウイルスとなって駆け巡る。
『演算不能』
『未来予測、分岐、無限大』
ガラスの中の黄金の砂が、重力を無視して暴れ狂う。
下に落ちるはずの砂が、横へ、上へと舞い踊る。
「教官……見えますか……!」
僕は叫んだ。鼻から血が滴り落ちるのも構わない。
「砂の動きは、一つじゃない! エレナが兵器を作らずに、その分析力で土壌汚染を解決する未来も! カイがシェルター建築で人を守る未来も!」
「だが、その確率は0.01%以下だ!」
「ゼロじゃないなら、賭ける価値はあるだろうッ!!」
バキィッ!!
硬質な破砕音が響いた。
クロノスの砂時計に、巨大な亀裂が走る。
システムが描いていた「たった一つの絶望的な未来」という名の牢獄が、僕の灰色によって塗りつぶされていく。
「僕たちが選ぶんだ……。効率じゃなく、意志で!」
視界が真っ白に染まる。
最後に見たのは、呆然と立ち尽くす教官の顔と、砕け散りながら七色に輝き始めた砂の粒子だった。
第四章 プリズムの夜明け
鳥のさえずりが聞こえる。
頬を撫でる風は、昨日までの刺すような冷たさを失っていた。
「……悠!」
カイの声。
目を開けると、心配そうに覗き込むカイとエレナの顔があった。
二人とも泣いているようだったが、その瞳にはもう絶望の色はない。
僕はゆっくりと上半身を起こした。
広場の中央、あの威圧的だった砂時計は活動を停止し、美しいオブジェのように静まり返っている。
「……目が覚めたか」
瓦礫に腰を下ろしていたヴァルデス教官が、静かに口を開いた。
彼の纏っていた鋭利な黄金のオーラは消え失せ、今は温かみのある夕陽のような色が漂っている。
「システムは破壊された。いや……再構築されたと言うべきか」
教官が空中にホログラムを展開する。
『推奨ルート:環境再生学(適性A)。※ただし、本人の意志を最優先とする』
『推奨ルート:防衛建築学(適性A)。※ただし、本人の意志を最優先とする』
命令形が消え、選択肢が増えていた。
確定していた未来図は白紙になり、無数の分岐線が網の目のように広がっている。
「君が砂に干渉し、不確定性原理を組み込んだのだ。おかげで未来は見えなくなった」
教官はふっと自嘲気味に笑った。
「大崩壊が来るかもしれない。人類は滅びるかもしれない。……だが、不思議だな。以前よりも、恐怖を感じない」
「自分たちで選んだ道なら、足掻けるからです」
僕が答えると、教官は小さく頷き、僕の手を取って立たせてくれた。
「行け、天沢悠。君たちが作る『予測不能』な未来を、私も見届けるとしよう」
「はい」
歩き出そうとした僕の背中に、カイが驚いた声を上げた。
「おい、悠。お前のオーラ……すごいことになってるぞ」
「え?」
「灰色じゃない。……キラキラしてて、まるでプリズムだ」
僕は自分の手をかざした。
朝日に透かしたその手からは、見る角度によって無限に色を変える、透明な光が溢れていた。
何色にも染まらない色。
けれど、世界中のどんな色にもなれる光。
アカデミアの鐘が鳴り響く。
それは新しい時代の幕開けを告げる、祝福の音色だった。
僕はカイとエレナの背中を押して、光の満ちる方へと駆け出した。