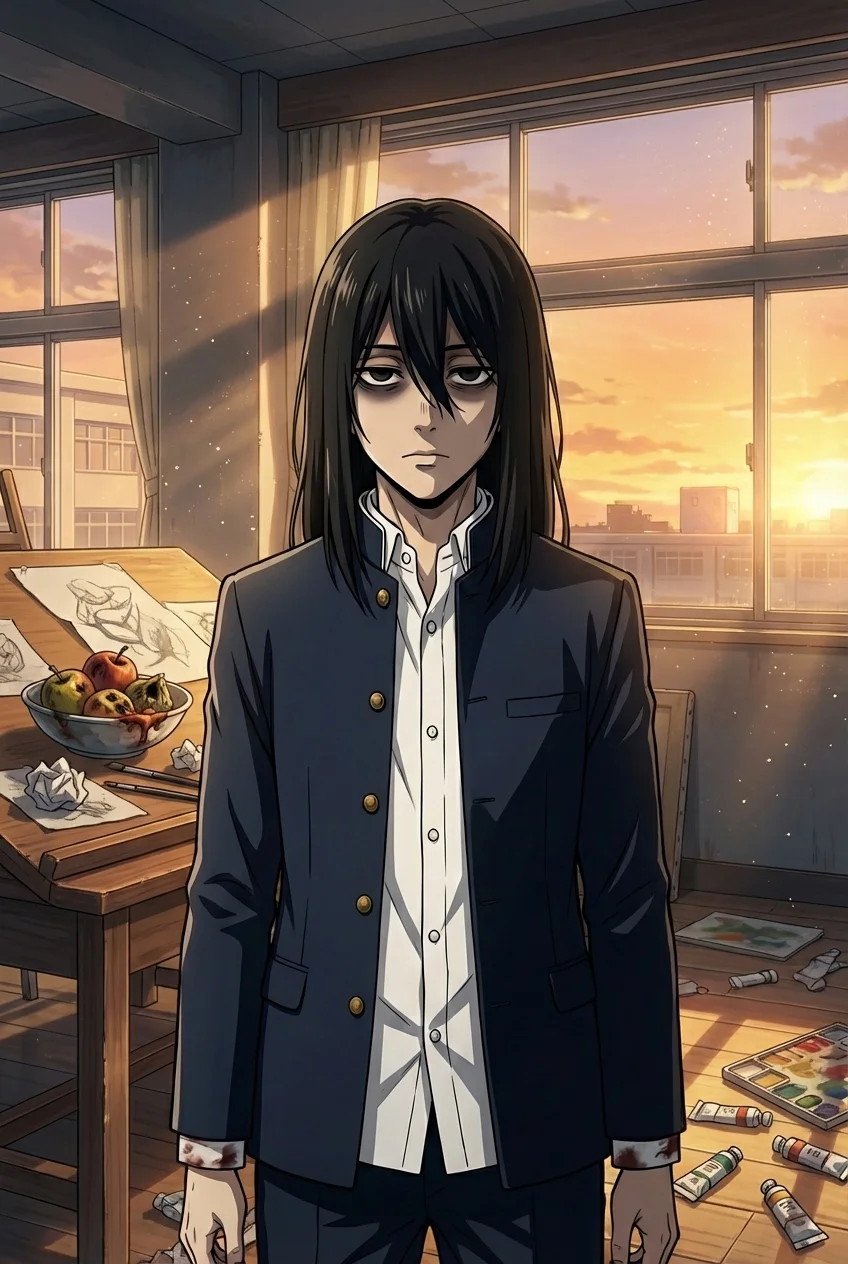第一章 色彩の牢獄
僕の視界は、常に他人の才能で飽和していた。
ここ、エウレカ学園の生徒たちは、誰もが生まれつき特定の学問分野における「才能」を授かっている。それは学習の進捗に応じて、オーラのような「学習マップ」として脳内に形成される。僕の特異体質は、そのマップを色の塊として視覚化できることだった。
物理学講義室の硬い椅子に身を沈めながら、僕は隣の席のアカリを盗み見る。彼女の頭の周りには、深海のサファイアを溶かしたような、鮮烈な青が渦巻いていた。あれが物理学の才能。一つ一つの数式を理解するたびに、青は星屑のようにきらめき、その輝きを増す。教室は、数学の緻密なエメラルド、歴史学の重厚なセピア、化学の変幻自在なバイオレットといった色彩で満たされ、まるで万華鏡の中にいるようだった。
だが、僕自身の内側は、どこまでも空虚な白だった。完全な、無垢な、そして絶望的な白。どれだけ教科書をめくり、数式をなぞっても、僕の学習マップに色が灯ることはない。理解しているという実感も、進んでいるという手応えもない。黒板に連なるチョークの文字は、ただの無機質な記号の羅列に過ぎなかった。
講義が終わると、喧騒が僕の肌を撫でて通り過ぎていく。僕は一人、学園の心臓部である大図書館へと向かった。古書のインクと乾燥した紙の匂いが満ちる静寂の中だけが、僕が唯一安らげる場所だった。高い天井から差し込む午後の光が、舞い上がる埃を黄金の粒子に変えている。
その時だった。書架の影に、半透明の人影が立っているのに気づいたのは。陽光に透けるその姿は、まるで古いフィルムの残像のようだ。他の誰も、その存在に気づいていない。人影は音もなく移動し、一冊の本を手に取ると、静かにページをめくっていた。やがて、彼はふっと姿を消し、その場には一冊のノートだけが残されていた。
僕は吸い寄せられるようにそれに近づく。生徒が使うノートは、才能の科目に応じて縁が色付けされているはずだ。だが、そのノートは違った。縁取りのない、真っ白な表紙。僕自身の内側と同じ、無色のノートだった。
第二章 消費される才能
「ねえ、レン。私のこの青、前より少しだけ、薄くなってないかな」
放課後のカフェテラスで、アカリが不安げに呟いた。彼女の指先が、空のカップの縁を神経質になぞっている。僕は彼女の学習マップに視線を向けた。確かに、数週間前に見たあの燃えるようなサファイアの輝きは、少しだけ落ち着き、透明度を増しているように見えた。
この学園の法則は残酷だ。才能は、学習によって輝きを増すと同時に、「消費」されていく。知識という果実をもぎ取るたびに、才能という名の幹が細っていくのだ。そして、完全に才能を使い果たした時、その生徒はその科目に関する一切の記憶と能力を失う。
「気のせいだよ。今日の講義だって、誰より深く理解してたじゃないか」
僕の慰めが、どれほど空虚なものか自覚していた。進捗を感じられない僕には、失う恐怖もまた、理解できなかったからだ。アカリは力なく微笑むと、夕日に染まる窓の外へ視線を向けた。その横顔に落ちる影が、彼女の焦りを雄弁に物語っていた。
自室に戻った僕は、図書館で拾った無色のノートを机に広げた。ざらついた表紙を撫で、ゆっくりと最初のページを開く。そこには、特定の科目に属さない、根源的な問いが震えるような筆跡で記されていた。
『なぜ星は輝きを失うのか?』
『記憶とは、脳に刻まれた傷跡なのか?』
『無限とは、終わりがないことか、始まりがないことか?』
それは、テストの点数や単位のためではない、純粋な知的好奇心の結晶だった。才能の枠を超えた、普遍的な問い。ページをめくるたびに、僕の白い内側に、かすかな波紋が広がるのを感じた。このノートの持ち主は、一体誰なのだろう。そして、なぜ僕だけが、彼らの存在を認識できるのだろう。
第三章 無限者の影
その日から、僕は「無限者(インフィニット)」と仮に名付けた彼らの影を追うようになった。
彼らはいつも、誰にも気づかれずにそこにいた。講義室の隅で、最も熱心な生徒の学習マップが放つ輝きを静かに見つめ、図書館の片隅で、難解な論文に没頭する学生の傍らに佇む。まるで、他人の知性の輝きを浴びて、自らの存在を保っているかのようだ。
僕は何度も彼らに話しかけようとした。
「君は、誰なんだ?」
だが、僕の声は彼らの体を通り抜け、冷たい壁に吸い込まれるだけだった。彼らは僕の存在に気づいているのかいないのか、何の反応も示さない。システムに認識されない彼らは、この世界のバグなのだろうか。それとも――。
焦燥感が募る一方で、アカリの才能の消耗は、誰の目にも明らかになっていった。彼女は失う恐怖に抗うように、無茶な学習にのめり込んでいった。夜を徹して論文を読み漁り、食事も疎かにして実験室に籠もる。彼女の周りを舞う青色のオーラは、最後の輝きを振り絞る線香花火のように、激しく明滅を繰り返していた。
「やめるんだ、アカリ!そんなことをしたら……!」
僕の制止の声は、彼女の耳には届かなかった。彼女の瞳には、才能の限界という崖の縁だけが映っていた。
第四章 青の消失
その瞬間は、あまりにも唐突に、そして静かに訪れた。
実験室の床に、アカリが倒れていると聞き、僕は駆けつけた。ガラス器具の破片が散らばる中、彼女は呆然と座り込んでいた。そして、僕は見てしまった。彼女の周りを常に彩っていた、あの美しいサファイアの光が、跡形もなく消え失せているのを。
「アカリ……?」
僕が声をかけると、彼女はゆっくりと顔を上げた。その瞳は、僕を映してはいるが、僕を認識してはいなかった。まるで、初めて見る異物でも観察するような、空虚な視線。
「……あなた、だれ?」
その言葉が、僕の心を氷の杭で打ち抜いた。彼女は物理学のすべてを、そして、物理学を通じて僕と共有した時間の記憶さえも、失ってしまったのだ。
絶望が空間を支配する。その時、僕はアカリの背後に、静かに佇む無限者の姿を捉えた。いつもと同じ、半透明の影。だが、一つだけ違う点があった。
彼の胸元が、ほんのりと青く色づいていたのだ。
まるで、アカリが失った才能の最後の輝きを、その身に宿したかのように。彼らは、他人の才能を奪う存在なのか? 怒りがこみ上げた瞬間、僕の頭にガラスが砕けるような激痛が走った。
――なぜ星は輝きを失うのか?――
脳内に、誰かの声が響く。忘れていたはずの記憶。無色のノートに記されていたあの筆跡が、自分のものだったような、強烈なデジャヴ。視界が白く染まり、僕は意識を失った。
第五章 白地図の真実
目覚めた時、僕は見慣れない白い部屋にいた。目の前には、何人もの無限者たちが僕を取り囲むように立っていた。彼らは語りかけない。だが、その思念が直接、僕の意識に流れ込んでくる。
『我々は、かつて君と同じ生徒だった者たちだ』
その声は、僕自身の内側から響いているようだった。
『才能を消費し尽くし、すべてを失った者たちの、学習意欲の残滓。それが我々、無限者だ。肉体を失い、純粋な知的好奇心という思念だけが、この学園に留まっている』
彼らは奪う存在ではなかった。失われた才能の輝きを見つめ、それを自らの内に再構築することで、永遠に学び続ける純粋な探求者だったのだ。アカリの才能の輝きは、彼らの中で新たな知として生き続ける。
そして、最も衝撃的な真実が告げられた。
『君も、我々と同じだ。レン』
僕もまた、かつて才能を消費し尽くした無限者の一人だった。この世界は、すべてを失った僕たちが、もう一度『学ぶ喜びと苦しみ』を体験するために用意された、精巧なシミュレーション。僕の学習マップが白一色だったのは、それが始まりも終わりもない、無限の可能性を秘めた原初の状態――『白地図』だったからだ。苦悩を感じなかったのは、一度その絶望を通り過ぎていたから。
すべての記憶が蘇る。僕が失った才能は、あらゆる学問の根源を問う「哲学」だった。
意識が現実世界に戻ると、僕はアカリの病室にいた。彼女は窓の外を、何も映さない瞳で眺めている。記憶を失った彼女の世界もまた、今は白紙なのだろう。
僕は彼女の隣に静かに腰を下ろし、鞄から一冊のノートを取り出した。縁取りのない、無色のノート。そこに、新しいペンで最初の文字を記す。
「僕の名前は、レン。君の友達だ。これから、もう一度一緒に学んでいかないか」
才能を消費する呪われたプロセスではない。ただ純粋に、知ることを楽しむために。
アカリはゆっくりと僕の方を向き、その瞳に、ほんのかすかな光が宿った。
僕の学習マップは、今も変わらず白一色のままだ。だがもう、それは虚無の色ではない。これからどんな色彩をも受け入れることができる、無限の可能性を秘めたカンバスの色だ。失われた記憶の代わりに得たこの真実を胸に、僕とアカリの、そして無限者たちの、新たな探求が始まる。白地図の上に、最初の道を描くために。