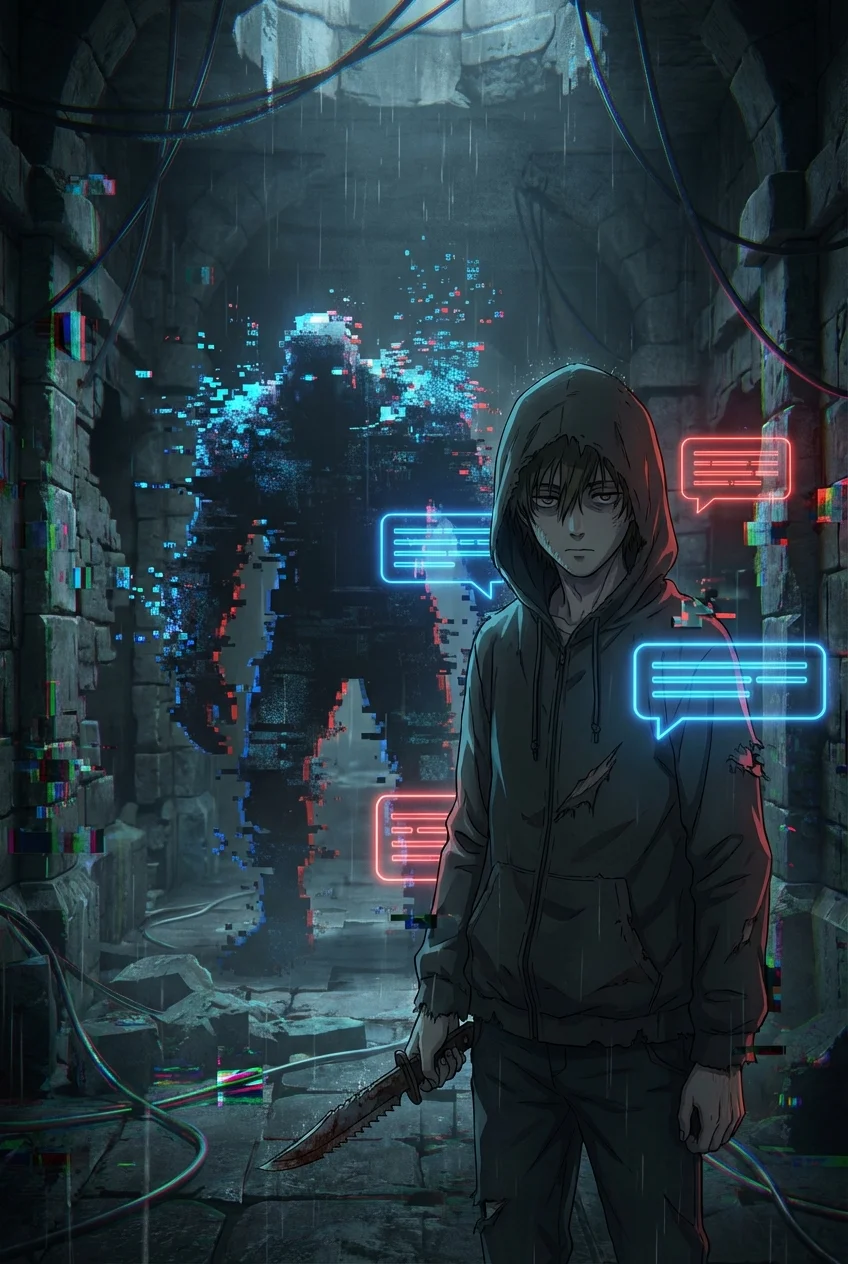第一章 婚約破棄とバイオハザード
「エララ・フォン・ローゼンバーグ! 貴様との婚約を、今ここで破棄する!」
王宮の舞踏会場。クリスタルガラスのシャンデリアが煌めく下で、王太子の絶叫が響き渡った。
周囲の貴族たちが息を呑み、扇子で口元を隠してさざめき合う。
私は、ゆっくりと瞬きをした。
目の前には、顔を真っ赤にして唾を飛ばす王太子フレデリック。そして、その腕にしなだれかかる「聖女」リリア。
(……唾液飛沫。距離2メートル。感染リスク大)
私の脳内では、もはや婚約破棄のショックなど微塵もなかった。
前世、国立感染症研究所の病理医だった記憶が、アラートを鳴らしているのだ。
「私の愛しいリリアを階段から突き落とそうとしたな? その腐った性根、もはや王妃にふさわしくない!」
フレデリックが吠える。
私は絹の手袋を嵌めた手で、そっとドレスの裾をつまみ、一歩下がった。
「殿下。一つ訂正を」
「言い訳など聞かん!」
「いいえ。リリア様の肌……ご覧になりましたか? その首元の紅斑」
リリアがビクリとして首元を押さえる。
薄化粧で隠しているが、私には見える。血管に沿って走る微細な紫斑。特有の皮膚壊死の初期症状。
「何を……! これは、エララ、貴様がいじめたストレスで!」
「『赤死病(レッド・デス)』の初期症状ですわ」
会場が凍りついた。
赤死病。かつて大陸の人口の三割を奪ったとされる、伝説の疫病。
「なっ……不吉なことを! 衛兵! この女を連れ出せ!」
私は抵抗しなかった。
むしろ好都合だ。この「培養皿」のような不衛生な王都から脱出できるのだから。
「謹んでお受けいたします、殿下。……ああ、それと」
去り際、私はリリアに向かって冷ややかに微笑んだ。
「貴女、自分が『無症状キャリア』である可能性を考えたことはなくて?」
第二章 領地改革という名の大掃除
王都を追放され、辺境のローゼンバーグ領へ戻った私を待っていたのは、絶望的な光景だった。
「……臭い」
馬車を降りた瞬間、鼻をつく汚臭。
道端には排泄物が垂れ流され、井戸のそばで家畜が洗濯水に口をつけている。
「お嬢様、長旅お疲れ様で……」
「執事長! 直ちに領民を広場に集めなさい!」
私はドレスの裾を破り捨て、叫んだ。
「これより、ローゼンバーグ領は戒厳令を敷く! 敵は隣国ではない。目に見えぬ『菌』だ!」
そこからの私は、領民たちから『潔癖の暴君』と恐れられることになった。
まず、上下水道の完全分離。
前世の知識を総動員し、ローマン・コンクリートを再現。河川への垂れ流しを死罪とし、浄化槽の設置を義務付けた。
「水は必ず煮沸しろと言ったはずです! 生水を飲んだ者は鞭打ち十回!」
広場で、私は自ら煮沸のデモンストレーションを行った。
顕微鏡などないこの世界で、彼らに「菌」を理解させるには、恐怖と結果で示すしかない。
「石鹸工場を建設します。原料は余った獣脂と木灰。これを『聖なる石』として安価で配給しなさい」
領民たちは当初、反発した。
「魔女の仕業だ」「水を煮るなど薪の無駄だ」と。
しかし、一ヶ月が過ぎた頃。
「……おい、今年の夏は、赤ん坊が死なねぇぞ」
「腹を下す奴が減った」
事実は、いかなる演説よりも雄弁だ。
清潔な水。整備された下水。石鹸による手洗い。
劇的に低下した乳児死亡率が、私を「暴君」から「奇跡の領主」へと変えていった。
だが、私は知っていた。
これはまだ、来るべきパンデミックへの予行演習に過ぎないことを。
第三章 聖女の来訪、あるいは病原体
領地改革から半年。
私の元に、不吉な知らせが届いた。
「聖女リリア様が、王太子殿下と共に『視察』にいらっしゃるそうです」
執事の声が震えている。
表向きは、追放された私への温情ある見舞い。だが実態は、私の改革を「魔法を否定する異端」として弾圧するための査察団だ。
「……来たか」
私は白衣(特注の厚手のリネン製)を翻し、城壁の上に立った。
眼下には、王家の紋章を掲げた煌びやかな馬車。
そして、その後ろに続く、咳き込む兵士たちの列。
(馬鹿な……。隔離もせずに行軍してきたの?)
王都ですでに感染爆発(アウトブレイク)が起きている。
彼らは視察に来たのではない。汚染された王都から逃げてきたのだ。
「門を開けろ! 王太子フレデリックである!」
城門の前でフレデリックが叫ぶ。その顔色は土気色で、脂汗が浮いている。
隣のリリアは、相変わらず透き通るように白い肌で、不安そうに彼に寄り添っていた。
「お断りします」
私は拡声器(風魔法を応用した魔道具)ごしに告げた。
「エララ! 貴様、王命に逆らう気か!」
「逆らっているのではありません。防疫です。貴方たちは汚染されている」
「ひどいです、エララ様!」
リリアが涙ながらに叫ぶ。
「私は聖女です! 祈りの力で、病など……」
「その『祈り』が、接触感染を拡大させていることに気づきなさい!」
私は指差した。
リリアが触れた兵士たちが、次々と倒れ伏していく様を。
「貴女は発症しない。けれど、貴女の呼気、皮膚、汗、その全てが死を撒き散らす。貴女こそが『歩く感染源(タイフォイド・メアリー)』なのよ!」
第四章 硝子の壁越しの愛
「入れてくれ! 頼む、エララ!」
フレデリックが門を叩く。
かつて私を断罪した傲慢な王太子の姿はどこにもない。
城壁の内側、ローゼンバーグ領の民は、静まり返ってその様子を見ていた。
彼らは知っている。
壁の外では「赤死病」が猛威を振るい、死体が山を築いていることを。
そして、この壁の内側だけが、清潔で、安全な聖域であることを。
「……条件があります」
私は冷酷に告げた。
「武装解除。そして、二週間の完全隔離。リリア様に関しては、地下牢……いえ、特別隔離室へ入っていただきます」
「リリアを牢屋だと!?」
「彼女を生かしておけば、国が滅びます。選んでください、殿下。愛か、生存か」
フレデリックは、膝から崩れ落ちた。
彼の手が、リリアの手を離す。
それが、答えだった。
第五章 クリーン・ニュー・ワールド
数年後。
ローゼンバーグ領は、独立国家としての地位を確立していた。
徹底された公衆衛生。上下水道完備。そして、顕微鏡を用いた「医療革命」。
周辺国が疫病で疲弊する中、唯一、人口を増やし続けた我が国は、圧倒的な経済力と軍事力(生物兵器ではない、純粋な国力)を持つに至った。
私は今、王城の最上階にある研究室にいる。
「陛下、本日の報告書です」
元王太子であり、現在は私の秘書官を務めるフレデリックが、分厚い書類を置いていく。
彼は王位継承権を剥奪され、一市民として私の元で働いている。
その顔には、かつての愚かさはなく、科学者としての実直な瞳があった。
「ありがとう。……例の『患者』の容態は?」
「……変わりありません。地下の無菌室で、祈りを捧げ続けています」
リリア。
彼女はまだ生きている。
私の研究対象として。そして、永遠に外の世界へ出ることを許されない「聖女」として。
私はガラス越しに、眼下に広がる白亜の街を見下ろした。
煙突からは白い蒸気が上がり、人々は清潔な服を着て笑っている。
愛も、情熱も、ロマンスもない。
あるのは、徹底管理された衛生と、数値化された幸福だけ。
「美しいわ」
私は呟き、アルコールで指先を消毒した。
この清潔で冷たい世界こそが、私の望んだハッピーエンドなのだから。