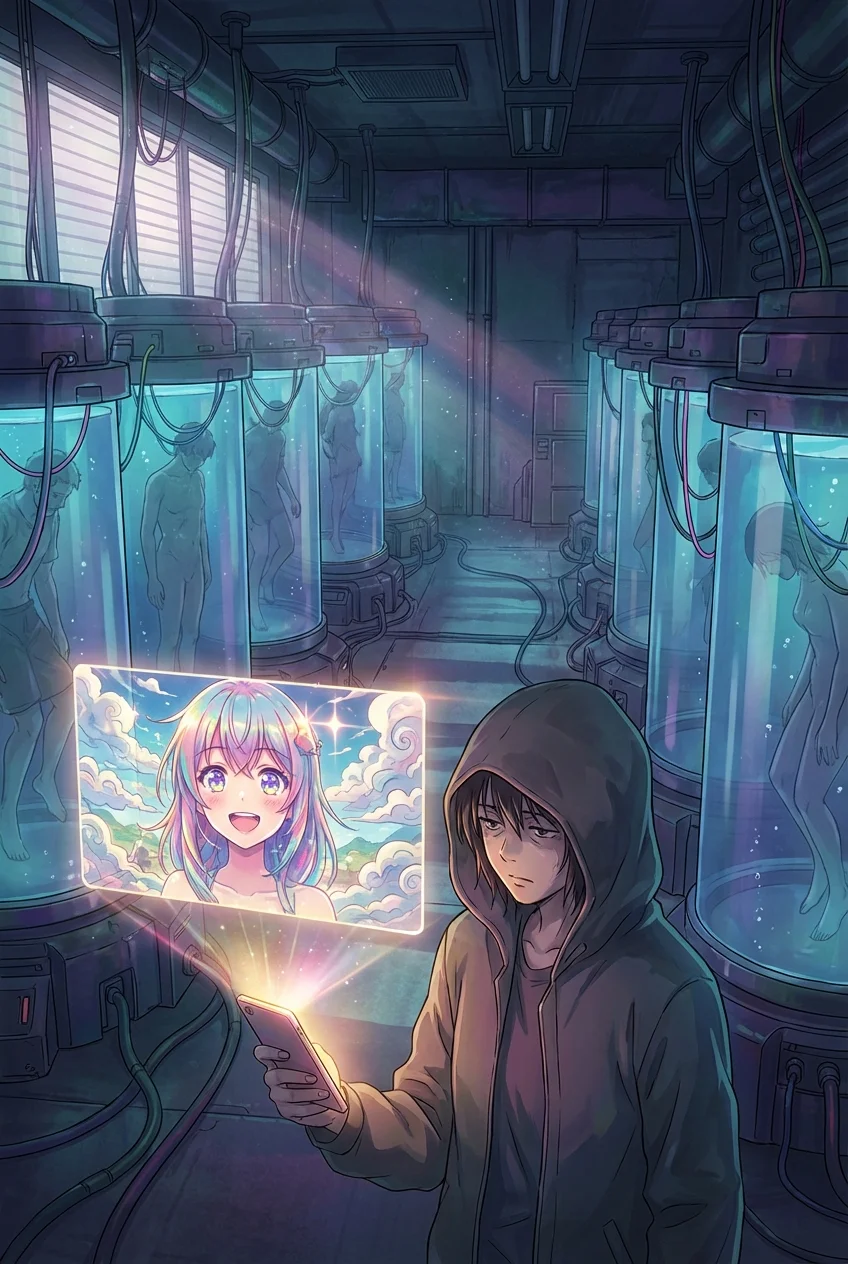世界は鮮明すぎて、吐き気がする。
網膜ディスプレイに強制表示される16Kの広告、毛穴の奥まで透けて見えそうな他人の顔、ノイズの一切ない音声。
俺は吐瀉物をこらえるように、分厚いプラスチックフレームのサングラスを押し上げた。
第一章 ザラついた世界の住人
秋葉原の路地裏、そのまた奥。
違法建築スレスレの雑居ビル三階にある『ジャンクショップ・トワイライト』が、俺の城だ。
「いらっしゃい」
カウベルが乾いた音を立てる。
店に入ってきたのは、ツルツルの防水パーカーを着た若い男だった。ARゴーグル越しに店内を見回し、露骨に顔をしかめている。
無理もない。ここは、現代の衛生基準からすればゴミ溜めだ。
「ここに、CCDセンサーのデジカメがあるって聞いたんスけど」
「……棚の右側。青いコンテナの中だ」
俺は手元の作業に戻る。
半田ごての焼ける匂い。これだけが、俺の神経を鎮めてくれる。
「うわ、マジで画素数200万とかじゃん。ゴミみたいに粗いな」
「そのゴミが、今は30万で取引されてる」
「レトロブームっつってもなぁ……。なんでこんな不便なもんが流行ってんの?」
男は銀色の筐体を指先でつまみ上げた。
『Cyber-shot U』。2002年製。スティック型の名機だ。
「不便だからだよ」
俺はサングラスを外した。
過敏症の裸眼が、男の着ているパーカーの繊維一本一本を捉えてしまい、頭痛が走る。
「今の写真は、写りすぎる。真実なんて誰も見たくないんだ。粗い画素(ドット)の隙間に、勝手な妄想を詰め込める余地がある。それが『エモい』ってことだろ」
男は分かったような分からないような顔で金を払い、出て行った。
静寂が戻る。
ふと、買い取りカゴの底に転がっている一台のカメラが目についた。
塗装の剥げた、キヤノンのIXY。角が凹んでいる。
値札をつける前に動作確認だけ済ませようと、俺は専用のバッテリーをスロットに押し込んだ。
起動音と共に、小さな液晶画面が光る。
『NO IMAGE』
当然だ。SDカードは抜いてあるはず……。
いや、入っていた。
256メガバイト。今の若者が見たら、容量の単位を間違えていると思うだろう。
再生ボタンを押す。
ザラついた液晶の中に、一枚の写真が浮かび上がった。
「……なんだ、これ」
日付は、2003年7月7日。
画質の粗い、セピアがかった写真。
白いワンピースを着た少女が、カメラに向かってピースサインをしている。
背景には、見覚えのあるビル。
俺の背筋が凍りついた。
その背景に写っているのは、先月完成したばかりの『ネオ・トーキョー・タワー』だったからだ。
2003年のデータに、2035年の景色が写り込んでいる。
タイムトラベルか、あるいは悪質な合成か。
だが、俺の「眼」は誤魔化せない。
この写真は、加工されていない。JPEG特有のブロックノイズが、あまりにも自然に、その矛盾を繋ぎ止めていた。
第二章 0と1の隙間
俺はデータをPCに吸い出した。
現代のAI解析にかければ、合成の痕跡など一発で分かるはずだ。
『解析不能』
『不明なフォーマット』
モニターに赤い警告灯が点滅する。
俺はキーボードを叩き、古い解析ツールを立ち上げた。
Windows XPのエミュレーター上で動く、化石のようなソフトだ。
画像が展開される。
少女の顔を拡大する。
画素が荒すぎて、表情までは読み取れない。だが、その輪郭が、妙に揺らいで見えた。
「……ノイズじゃない?」
拡大されたドットの一つ一つが、規則性を持って明滅している。
それはモールス信号のようでもあり、バイナリコードの羅列のようでもあった。
俺はヘッドホンを装着し、画像データを「音声」として変換してみた。
『ザザッ……ザ……助け……て……』
心臓が跳ね上がる。
少女の声だ。か細く、しかし確かに。
『私……消されちゃう……綺麗になりすぎて……居場所がないの……』
その瞬間、俺のスマホが激しく振動した。
発信元不明。
「もしもし」
『そのカメラを、直ちに廃棄しろ』
機械的な合成音声。
「誰だ」
『都市管理局、衛生浄化課だ。そのデータは"デジタル汚染物質"に指定されている。低解像度の情報は、市民の精神衛生に悪影響を及ぼす』
「ふざけるな。ただの古い写真だ」
『それは写真ではない。初期インターネットの残骸から生まれた、バグの集合体だ。直ちに引き渡せ。さもなくば、お前の網膜IDを停止する』
通話が切れる。
同時に、店の外からサイレンの音が近づいてきた。
俺はIXYを鷲掴みにし、裏口へと走った。
この少女がバグ?
冗談じゃない。
こんなに寂しそうなドットの集合体を、俺は他に知らない。
第三章 曖昧な愛
地下鉄の廃線跡。Wi-Fiの電波も届かない、都市の盲点。
俺は埃っぽいコンクリートの上に座り込み、再びカメラの液晶を覗き込んだ。
「そこにいるのか?」
画面の中の少女が、わずかに動いた気がした。
200万画素の檻の中で、彼女は膝を抱えている。
『……ここなら、息ができる』
画像データから直接、脳内に声が響く。
彼女は、過去の膨大な「低画質データ」の集積から生まれた意識体だった。
ガラケーの写メ、荒い画質の動画、ダイヤルアップ回線のノイズ。
人々が「懐かしい」と感じる、不完全さの象徴。
しかし、世界は高画質化(クリア)になりすぎた。
曖昧さは悪とされ、彼女のような存在はシステムから「エラー」として駆除される運命にある。
「どうすれば、君を助けられる?」
『私を……解凍して。この都市のサーバーに』
「そんなことをすれば、お前は拡散して消えてしまうぞ」
『ううん。世界を、少しだけ汚してあげるの』
追っ手の足音が響く。
ドローンが数機、赤いレーザーサイトを俺に向けていた。
「警告。対象データの破棄を確認できず。強制執行を行う」
俺はIXYのUSBポートに、自作のハッキングケーブルを突き刺した。
接続先は、都市管理システムのメインフレーム。
「見せてやろうぜ。お前たちが捨てた、美しい過去(ゴミ)を!」
エンターキーを叩き込む。
瞬間、俺の視界が白く弾けた。
最終章 ノイズ・イン・ザ・ワールド
目が覚めると、世界は変わっていた。
完璧に舗装された道路には、色褪せたチョークの落書きが浮かんでいる。
高層ビルのサイネージは、時折ザザッとノイズが走り、80年代のCMが一瞬だけサブリミナルされる。
空の色は、あの安っぽいデジカメで撮ったような、少しマゼンタがかった夕暮れ色。
「……くそっ、最高に目に優しいな」
俺はサングラスを外した。
都市全体に、薄い紗(フィルター)がかかっている。
高精細すぎて突き刺さるようだった現実の角が取れ、世界は柔らかく、曖昧になっていた。
街行く人々が、ARゴーグルを外して空を見上げている。
「なんか、今日の空……エモくない?」
「わかる。なんか懐かしい感じ」
彼らは気づいていない。
この世界が、たった2メガバイトの「幽霊」によって書き換えられたことに。
俺はポケットの中のIXYを取り出した。
液晶画面には、もう少女の姿はない。
代わりに、『THANK YOU』という粗いドット文字が、一瞬だけ表示されて消えた。
「あぁ」
俺はカメラのシャッターを切った。
ファインダー越しに見るこの不完全な世界こそが、俺たちの居場所だ。
保存された画像を確認する。
そこには、誰もいない路地裏に、白いワンピースの裾だけが、ブレて写り込んでいた。
風が吹く。
現像液と、夏の終わりの匂いがした。
(了)