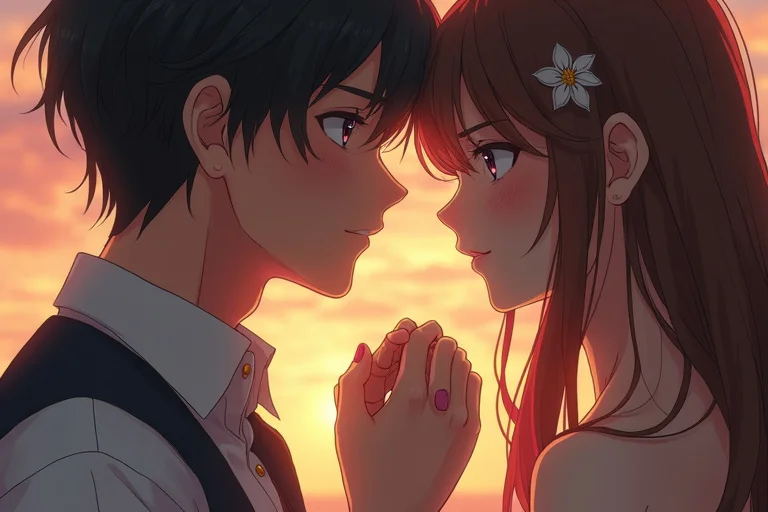第一章 墓掘りたちの歌
「痛いか?」
俺はレンチの先で、ひしゃげたチタン合金の板を軽く叩いた。
コツン、と振動がグローブ越しに骨へ伝わる。
音はない。
ここは静寂の海。
本当の意味での静寂が支配する場所だ。
だが、俺には聞こえる。
金属の悲鳴が。
『カイト、またブツブツ言ってるの? 酸素の無駄よ』
ヘルメット内のスピーカーから、エララの呆れた声が響く。
ノイズ混じりのその声は、この荒涼とした月面で唯一の「色」だ。
「こいつが泣いてるんだよ。まだ使えるってな」
「はいはい。さっさとその旧世紀の遺物を回収して。AEGIS社のパトロールが回ってくるまであと二十分」
俺、カイト・レンは「スカベンジャー(回収屋)」だ。
かつてのエリート宇宙飛行士候補生?
そんな肩書きは、大気圏突入時に燃え尽きたゴミと同じ。
今の俺は、企業が見捨てたデブリを拾い、日銭を稼ぐ月面のハイエナに過ぎない。
目の前にあるのは、二十年前に墜落した無人探査機の残骸だ。
レゴリス(月面の砂)に半分埋もれている。
通常のセンサーなら見落とすだろう。
だが、俺の「耳」は誤魔化せない。
俺には、素材にかかる微細な応力(ストレス)が、まるで不協和音のように聞こえる。
特異体質?
いや、医者は「共感覚の一種」と言った。
おかげで、どんなガラクタの中からでも、まだ生きているパーツを見つけ出せる。
「……待てよ」
残骸の腹をこじ開けた瞬間、俺の手が止まった。
「どうしたの? 金目のもの?」
「いや……変だ」
聞こえない。
何も。
このパーツだけ、金属の「悲鳴」が全くない。
まるで、生まれたての赤ん坊のように無垢で、完璧な均衡を保っている。
俺は埃を払い、その黒いカプセルを引き抜いた。
表面には、どこの企業のロゴもない。
ただ、奇妙な幾何学模様が刻印されているだけだ。
ズズッ。
突然、HUD(ヘッドアップディスプレイ)にノイズが走った。
『カイト! レーダーに反応! パトロールじゃないわ、これ……』
エララの声が緊迫する。
『軍用機よ。しかも三機』
「マジかよ。ただのゴミ拾いに軍がお出ましか?」
「ゴミじゃない」
俺は直感した。
俺が手にしているこれは、ただのジャンクじゃない。
パンドラの箱だ。
「エララ、ローバーを出せ! ずらかるぞ!」
俺はカプセルを腰のマグネットホルダーに叩きつけ、低重力の荒野を蹴った。
背後で、音もなくレゴリスが吹き飛ぶ。
着弾。
静寂の海が、にわかに騒がしくなってきた。
第二章 緑色の悪夢
地下三階層、廃棄された溶岩洞窟を利用した俺たちの隠れ家。
気密ハッチが閉まる重たい音が、ようやく生きた心地を取り戻させた。
「あんた、一体何を拾ってきたのよ」
エララがヘルメットを脱ぎ捨てながら詰め寄ってくる。
赤毛のショートカットが汗で額に張り付いている。
彼女の瞳には、怒りよりも恐怖が滲んでいた。
「俺にも分からん。ただ……」
俺は作業台の上に例のカプセルを置いた。
黒い表面は、作業灯の光を吸い込むように鈍く輝いている。
「こいつからは、音がしないんだ」
「音がしない?」
「ああ。金属疲労も、歪みも、原子レベルの振動さえも感じない。完全な静寂だ」
俺はレーザーカッターを構えた。
普通ならこんな正体不明の物体を開封するのは自殺行為だ。
だが、好奇心が恐怖を上回る。
それが、俺が宇宙飛行士失格の烙印を押された理由でもあった。
ジュッ。
極細のレーザーがカプセルの継ぎ目をなぞる。
意外なほどあっけなく、外殻がスライドして開いた。
中に入っていたのは、宝石でも、新型のチップでもない。
ガラス質のシリンダー。
その中で、エメラルドグリーンの液体が揺らめいている。
「……液体? 燃料?」
エララが覗き込む。
その時だ。
ピシッ。
シリンダーに微かな亀裂が入った。
俺が触れてもいないのに。
「危ない!」
俺はとっさにエララを突き飛ばした。
シリンダーが砕け散る。
緑色の液体が作業台にこぼれ落ちた。
「クソッ、汚染警報は!?」
俺は慌ててモニターを見る。
だが、アラートは鳴らない。
代わりに、信じられない光景が目の前で展開された。
こぼれた液体が、作業台の鋼鉄を「食べて」いる。
いや、違う。
鋼鉄が、錆びるような速度で変質し、その表面からモコモコと緑色の何かが芽吹いていく。
「嘘……これ、植物?」
エララが呟く。
「苔……か?」
無機物が、有機物に置換されている。
金属を栄養源にして、猛烈なスピードで増殖する植物。
俺は震える手で分析スキャナーをかざした。
『酸素濃度上昇』
『湿度上昇』
HUDに表示される数値が跳ね上がる。
こいつは、ただの苔じゃない。
金属や岩石を分解し、水と酸素、そして有機土壌を作り出す、究極のテラフォーミング・ナノマシン……いや、人工生命体だ。
「おいおい……こいつがあれば」
俺は乾いた笑い声を漏らした。
「月で酸素を買う必要がなくなるぞ」
現在、月面都市の生命維持システムは、AEGIS社が独占している。
水一リットルが血よりも高いこの世界で、この「緑」は革命だ。
あるいは、既存の経済システムを崩壊させる核爆弾だ。
「カイト、見て」
エララが指差す。
緑の浸食は止まらない。
作業台の脚を伝い、床のコンクリートへ、そして壁の配管へと広がっていく。
「聞こえる……」
俺は耳を澄ませた。
今まで聞いたことのない音。
金属の悲鳴じゃない。
何かが芽吹き、呼吸し、歌うような音。
『警告。外部アクセスにより、セキュリティが突破されました』
無機質なAIのアナウンスが、希望の歌を遮った。
「見つかったか」
俺たちは顔を見合わせた。
AEGIS社は、これを知っていたんだ。
知っていて、葬り去ろうとしていた。
自分たちの「水商売」を守るために。
第三章 星を継ぐ選択
隠れ家は包囲された。
振動センサーが、頭上で複数の重機が動いていることを伝えてくる。
「どうする? データを渡して命乞いする?」
エララが震える手で銃を握りしめている。
彼女の夢は、地球に帰って海を見ることだ。
この発見を売れば、ファーストクラスで帰還できる。
だが、AEGIS社は生かしておかないだろう。
「選択肢は二つだ」
俺は増殖し続ける緑の塊――今や部屋の半分を埋め尽くしている――を見つめた。
「ここでこいつと心中するか、それとも……」
俺の視線は、壁の太いパイプに向けられた。
メイン・ベンチレーション。
月面都市全域に空気を送る、主要換気ダクトだ。
「まさか、カイト。あんた正気?」
エララが目を見開く。
「これを流せば、都市中の金属が腐食するわ! ドームが崩壊するかもしれないのよ!」
「逆だ、エララ。こいつの強度は計算済みだ」
俺の「耳」が教えてくれている。
この植物が形成するセルロースのような構造体は、チタン合金よりも遥かにしなやかで強靭だ。
「こいつは金属を食い荒らすんじゃない。金属をベースに、より強固な『生きた外殻』を作り出してるんだ」
俺はパイプに手を触れた。
都市の鼓動が聞こえる。
苦しそうだ。
継ぎ接ぎだらけの拡張工事、疲弊したリサイクルシステム。
月面都市は、限界を迎えている。
「AEGIS社はこの技術を隠蔽した。なぜなら、メンテナンスフリーで永遠に酸素を生み出す都市なんて、金にならないからだ」
ズドン!
入り口のハッチが爆破された。
武装したドローンが雪崩れ込んでくる。
「時間がない!」
俺はレンチを振り上げた。
「エララ、お前は裏口から逃げろ。俺が囮になる」
「ふざけないで! 一人でかっこつけないでよ!」
彼女は叫びながら、ドローンに向けて発砲した。
「海が見たいんだろ! ここが新しい海になるんだよ!」
俺は叫び返し、渾身の力で換気ダクトのボルトを叩いた。
俺の才能。
物質の「急所」がわかる力。
ここだ。
この一点を砕けば、気圧差で中身がすべて吸い出される。
「頼む、咲いてくれ……!」
ガキンッ!
ボルトが弾け飛ぶ。
轟音と共に、緑色の胞子と粘液がダクトの中へ吸い込まれていった。
それは、都市の肺へと直結している。
直後、スタングレネードの閃光が俺の視界を白く染めた。
第四章 静寂のラプソディ
意識が戻ったとき、俺は拘束されていた。
場所はAEGIS社の尋問室だろうか。
いや、窓の外に見える景色が違う。
俺は身を起こそうとして、拘束具がないことに気づいた。
「目が覚めたかね、スカベンジャー」
老人が一人、窓際に立っていた。
AEGIS社のロゴが入ったスーツを着ているが、その表情は敗北者のそれだった。
「外を見てみろ」
俺はふらつく足で窓に歩み寄った。
言葉を失った。
灰色だった月面都市が、緑に覆われていた。
ドームのフレームには蔦のような植物が絡みつき、強化ガラスの向こう側では、巨大な樹木のような構造体がビルを支えている。
そして何より驚くべきは、ドームの外だ。
レゴリスの荒野が、うっすらと緑色に発光している。
あのアリゾナの砂漠のような荒野が、草原へと変わりつつあるのだ。
「君がばら撒いた『種』は、想定以上の速度で適応した。金属を苗床にし、太陽光と放射線をエネルギーに変え、酸素と水を噴き出す」
老人は苦笑した。
「株価は大暴落だ。我々の酸素プラントは無用の長物と化したよ」
「……俺を殺さないのか?」
「殺して何になる? もう止まらんよ。それに……」
老人は空を指差した。
「地球からの通信だ。『美しい』とさ」
俺は窓ガラスに手を当てた。
かつて聞こえていた、都市の軋むような悲鳴はもう聞こえない。
代わりに聞こえるのは、穏やかな律動。
葉擦れのような、波のような音。
月が、歌っている。
ドアが開いた。
「カイト!」
エララが飛び込んでくる。
彼女の手には、小さな花が握られていた。
配管の隙間に咲いていたという、金属光沢を持つ不思議な白い花だ。
「海は見られなかったけど」
彼女は涙目で笑った。
「ここも悪くないかもね」
俺は彼女の肩を抱き寄せ、変わり果てた――いや、生まれ変わった世界を見つめた。
月はもう、冷たい墓場じゃない。
人類にとっての、二番目の故郷(ゆりかご)になったんだ。
俺の「耳」には、芽吹く命の産声が、最高のラプソディとして響いていた。
(了)