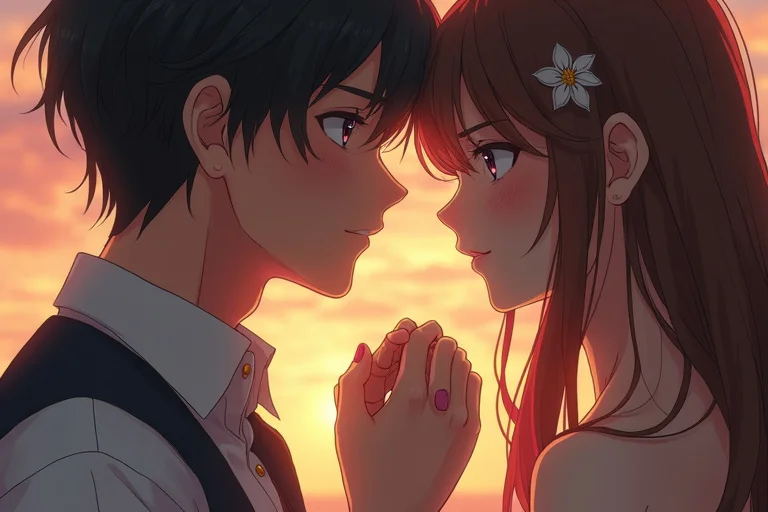第一章 黴(かび)の匂いと鉄の味
雨の匂いがした。
それも、ただの雨じゃない。埃と排気ガス、そして古びた紙が湿気を吸って吐き出す、甘ったるい腐敗臭。
神保町の路地裏にある雑居ビル、その最奥にある私の工房「雨宮修復堂」は、今日も世界の掃き溜めのような空気に満ちていた。
「雨宮先生、生きてますか」
ドアベルのカウベルが鳴ると同時に、遠慮のない声が響く。
私はルーペから目を離さず、ピンセットの先で一九世紀のヴェラム(羊皮紙)からカビの胞子を慎重に除去しながら答えた。
「死んでるように見えるなら、それは君の『観測』が足りないだけだ。あるいは、シュレーディンガーの猫のように、生死が重なり合っているのかもな」
「相変わらずの減らず口。安心しました」
入ってきたのは、佐々木という名のブローカーだ。仕立ての良いチャコールグレーのスーツ。その胸ポケットには、常に不釣り合いなほどの欲望がねじ込まれている。
彼はデスクの上に、油紙に包まれた重厚な何かを置いた。
「こいつの修復を頼みたい」
「予約は半年先まで埋まってる」
「報酬は三倍だ。それに、これはあんた好みの品ですよ」
佐々木が油紙を解く。
瞬間、鼻をついたのは強烈な鉄の臭い。インクに含まれる鉄分が酸化した臭いではない。
血だ。
現れたのは、一冊の大学ノートだった。表紙は黒ずみ、所々が焼け焦げている。だが、私の視線を釘付けにしたのは、そこから覗く数式の羅列だった。
「一九二七年、ブリュッセル」
私が呟くと、佐々木が片眉を上げた。
「ほう、さすがは元・天才物理学者。見る目が違う」
「第五回ソルベイ会議……物理学の黄金時代だ。アインシュタイン、ボーア、ハイゼンベルクが一堂に会した、伝説の会議」
私は手袋をはめ、震える指でページをめくった。
ドイツ語の筆記体。鋭く、神経質な筆跡。
『……観測者による波動関数の収縮は、物理的干渉ではなく、意識的排除である』
背筋に冷たいものが走った。
「誰のノートだ?」
「ヴォルフガング・パウリ。……と言いたいところだが、署名はない。だが、このノートが発見されたのは、パウリが晩年を過ごしたチューリッヒの別荘の地下室だ」
「パウリの排他律……」
「依頼主は、これを完全な状態で読めるようにしてほしいと言っている。特に、後半の焼失しかけたページを」
私はルーペを覗き込んだ。
インクの滲み、筆圧の乱れ。そこには、純粋な知の探求など微塵もなかった。
あるのは、狂気と、恐怖と、そして殺意。
「断る」
私はノートを閉じた。
「これは科学史の遺産じゃない。呪物だ」
「四倍出そう」
「金の問題じゃない。この数式は、書いてはいけないものだ」
佐々木は冷ややかな笑みを浮かべ、懐から封筒を取り出した。
「あんたの借用書だ。研究室を追い出された時に背負った、巨額の研究費不正流用の賠償金。これを私が肩代わりしてもいい」
喉が鳴った。
アルコールで焼けた胃が、別の渇きを訴える。
私は震える手で、再びノートを引き寄せた。
「……期限は?」
「三日だ。それ以上は待てない」
佐々木が出て行った後、私はウイスキーのボトルを開けた。
琥珀色の液体がグラスに注がれる音だけが、静寂を埋める。
私はまだ知らなかったのだ。
このノートを開くことが、この世界の「確定した過去」を書き換える行為そのものであることを。
第二章 悪魔の代筆
作業は難航を極めた。
紙の繊維に入り込んだ煤(すす)を、ミクロ単位で除去していく。特殊な波長の紫外線を当てると、消えかけたインクが青白く浮かび上がる。
『意識の重ね合わせ』
『多世界解釈における個我の消滅』
読み進めるほどに、私の物理学者としての直感が警鐘を鳴らし続けていた。
このノートに書かれているのは、物理法則の記述ではない。
「現実をハッキングするためのコード」だ。
二日目の夜、異変が起きた。
コーヒーを淹れようと席を立った時、ふと窓ガラスに映った自分の顔を見た。
私の後ろに、誰か立っている。
振り返る。
誰もいない。
ただ、本棚の影が長く伸びているだけだ。
疲れているのか。
再び作業に戻る。ページは後半、最も損傷の激しい部分に差し掛かっていた。
そこには、思考実験の図解が描かれていた。
密室。一人の男。そして、観測装置。
シュレーディンガーの猫によく似ている。だが、決定的に違う点が一つあった。
箱の中に入っているのは猫ではない。「書き手自身」だ。
『観測されるまで、私は死んでいないと同時に、生まれてもいない』
筆跡が乱れていく。
『彼らが見ている。壁の隙間から。時間の裂け目から』
『私は見つけた。排他律を人間に適用する方法を。二つの意識は、同一の量子状態を共有できない。つまり、他者の意識と完全に同調すれば、片方を“弾き出す”ことができる』
弾き出す?
どこへ?
『存在の確率ゼロの領域へ』
私は息を呑んだ。
これは殺人ではない。存在の抹消だ。
その時、スマートフォンの通知音が鳴った。佐々木からだ。
『進捗はどうだ? 急かしてすまないが、依頼主が焦れている』
私は返信を打とうとして、指を止めた。
画面の日付。
一〇月二四日。
そんなはずはない。私が依頼を受けたのは昨日、一〇月二二日だ。
丸一日、記憶が飛んでいる?
いや、違う。
私は作業机を見た。コーヒーカップが三つ。全て飲み干されている。
灰皿には吸い殻の山。
私は寝ていない。作業を続けていたはずだ。なのに、その記憶がない。
ふと、修復中のページに目が留まる。
そこには、真新しいインクで、数式が書き足されていた。
私の筆跡で。
「なんだ、これは……」
記憶にない計算式。だが、それはあまりにも美しく、そして残酷なほどに完璧な「解」だった。
過去の物理学者たちが到達し得なかった、量子重力理論のミッシングリンク。
私が書いたのか?
無意識のうちに?
それとも、このノートの「著者」が、私の体を借りて続きを書かせたのか?
恐怖よりも先に、かつてアカデミズムの世界で味わったことのない高揚感が押し寄せた。
これはノーベル賞どころの騒ぎではない。
神の領域だ。
私はペンを執った。修復ではない。執筆だ。
止められない。数式が頭の中で奔流となって溢れ出す。
その時、ドアが激しく叩かれた。
「雨宮! 開けろ!」
佐々木の声だ。だが、いつもと様子が違う。焦っている。
「警察が来てる! 逃げろ!」
警察?
私はドアを開けた。
佐々木が転がり込んでくる。その白いシャツは、真っ赤に染まっていた。
「……佐々木?」
「依頼主だ……あいつらは、ノートを修復させるつもりなんてなかった。お前に『解かせた』んだ。完成した瞬間に、お前ごと消すつもりだ」
「どういうことだ」
「そのノートは、未完成だったんじゃない。封印されていたんだ! 書いた本人が、危険すぎて破り捨てたんだよ!」
佐々木が崩れ落ちる。背中に深い刺し傷。
「雨宮、読むな……それ以上、観測するな……」
佐々木の瞳から、光が消えていく。
私は立ち尽くした。
静寂が戻る。
いや、静寂ではない。
背後で、ペンの走る音がした。
振り返る。
無人のデスクで、万年筆がひとりでに動いている。
『第三章、開始』
ノートにはそう記されていた。
第三章 重ね合わせの罪
私は恐怖に駆られ、ライターを掴んだ。
燃やすしかない。この呪われた知識を、この世から消し去らなければ。
火を点ける。
炎が紙端を舐める。
だが、燃えない。
紙が黒くなるどころか、炎の方がまるで映像のように透けて見える。
『無駄だ』
脳内に直接、声が響いた。
『一度観測された事象は、確率1へと収束する。君はもう、この理論を理解してしまった』
誰だ。
私は部屋を見渡した。
鏡。
姿見に映る私が、笑っていた。
私が笑っているのではない。鏡の中の「私」だけが、口角を吊り上げている。
『君は優秀な器だったよ、雨宮君。あのアインシュタインですら、私の理論を拒絶した。神はサイコロを振らないと言ってね。だが君は違った。君は自身の空虚さを埋めるために、悪魔のサイコロを受け入れた』
「お前は……パウリか?」
『パウリ? ああ、あの男か。彼もまた、私を記述しようとして失敗した一人に過ぎない』
鏡の中の私が、ゆっくりと歩み寄ってくる。
鏡の表面など存在しないかのように、そいつは現実世界へと踏み出してきた。
「来るな!」
私はデスクの上のカッターナイフを構えた。
「排他律……二つの意識は共存できない。なら、お前を消せばいい」
『その通り。だが、どちらが“オリジナル”かな?』
そいつは私の目の前に立った。
同じ顔。同じ傷。同じ、アルコールの臭い。
『君は覚えているかい? 三日前のこと、本当に覚えているか?』
記憶が揺らぐ。
佐々木が来る前のこと。その前の日。その前の週。
思い出せない。
私の記憶は、このノートを開いた瞬間からしか、鮮明ではない。
『君は、このノートを修復するために雇われたのではない』
そいつが私の耳元で囁く。
『君は、このノートの記述から“生成”されたんだよ』
世界が回転する。
壁のシミ、積み上げられた本、雨の音。
すべてがデジタルノイズのように点滅し始める。
「嘘だ……私は雨宮修復堂の……」
『雨宮という男は、一九二七年に死んでいる。ソルベイ会議の裏で、ある実験に巻き込まれてね。君は彼の残留思念と、この数式が結合して生まれた、一時的な波動関数に過ぎない』
そいつの手が、私の首にかかる。
冷たい。
絶対零度の冷たさ。
「私が……偽物……?」
『いいや、君こそが最新版だ。だから、古いバージョンである私は消える。君に座を譲ろう』
そいつの指が食い込む。
だが、苦しいのは私ではない。
そいつの顔が歪む。
『……なに?』
私は笑った。
直感が働いたのだ。物理学者としての、最後のプライドが。
「お前は一つ見落としている」
私は震える手で、ノートの最終ページを開いた。
そこには、私が無意識に書き殴った数式がある。
「観測者効果。見られることで状態は確定する。だが、観測者が『自分自身を観測しない』と定義したらどうなる?」
私はカッターナイフを、そいつではなく、自分の目に向けた。
『やめろ! 波動関数が崩壊する!』
「視覚情報の遮断。自己認識の放棄。私は私を観測しない。よって、私の存在確率は拡散する。……お前ごと道連れにな」
私は躊躇なく、刃を振り下ろした。
激痛。
そして、闇。
世界から色が消え、音が消え、形が消える。
ただ、数式だけが暗闇の中で金色の光を放っていた。
最終章 崩壊する波動関数
目が覚めると、病院のベッドの上だった。
白い天井。消毒液の匂い。
「気がつきましたか」
看護師が覗き込んでくる。
「……ここは?」
「神田駿河台の病院です。路地裏で倒れていたところを保護されたんですよ。三日間も眠っていました」
三日間。
「佐々木は? ノートは?」
「佐々木さん? ノート? 持ち物は何もありませんでしたよ。ただ……」
看護師は少し言い淀んでから、鏡を持ってきた。
「目の怪我ですが、奇跡的に視力に影響はありませんでした。ただ、傷跡が……」
私は鏡を受け取った。
右目の上から頬にかけて、一直線に走る傷跡。
だが、それはただの傷ではなかった。
ケロイド状に盛り上がった皮膚が、文字を形成していた。
『$\\Psi$』
波動関数を表す、ギリシャ文字のプサイ。
私は震える指でその傷に触れた。
熱い。
まるで、まだそこにある数式が生きているかのように。
「退院の手続きをしてきますね」
看護師が出て行く。
私は窓の外を見た。
東京の空は晴れ渡っている。だが、私の目には見えていた。
空の彼方に、薄っすらと浮かぶグリッド線。
通行人の背中に表示される、微細なパラメータ。
世界の「ソースコード」が見える。
あのノートは消えたのではない。
私の中に「インストール」されたのだ。
私はベッドから降りた。
ポケットを探るが、何もない。
いや、違う。
白衣のポケットに、一枚の紙片が入っていた。
焼け焦げた、あのノートの切れ端。
そこには、私の筆跡でこう書かれていた。
『第二巻へ続く』
私はその紙片を握りつぶし、口元を歪めた。
この世界がシミュレーションだろうが、多重宇宙の吹き溜まりだろうが、関係ない。
私が観測する限り、私がこの世界のルールだ。
「さて、修正パッチを当ててやろうか」
私は誰もいない病室で呟き、歩き出した。
その足跡が、床に黒いインクのように滲んで消えていった。