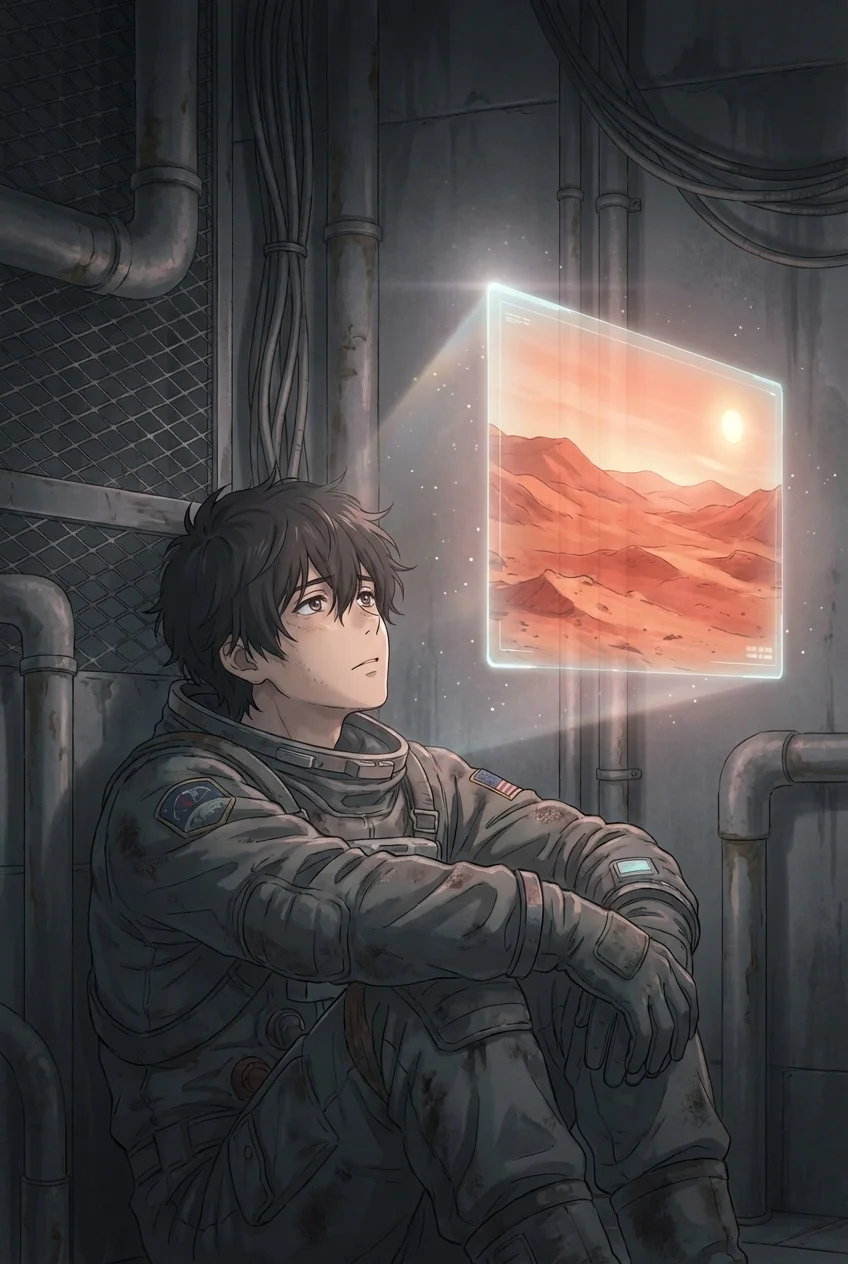第一章 死の舞踏とスパチャの雨
「おいおい、マジかよ。こいつの血、本当に青く光ってやがる」
腐臭とオゾンの混じった地下五十階層。
俺は倒れ伏したミノタウロスの顔面に、最新鋭の8Kドローンカメラを限界まで寄せた。
ブゥゥゥン、という無機質なプロペラ音が、かつては聖域と呼ばれた静寂を切り刻む。
巨獣の瞳が、恐怖に見開かれている。
それは死への恐怖ではない。
自分の断末魔が、レンズの向こうの何百万という人間に「コンテンツ」として消費されていることへの、本能的な嫌悪だ。
視界の隅に浮かぶARグラスには、滝のようなコメントが流れている。
『草』
『CG乙』
『もっと寄れ』
『¥10,000 : 今日の晩飯は牛タンですね!』
チャリン、という電子音が脳髄を揺らす。
俺、カイトの借金はこれでまた少し減った。
「みんな、スパチャサンキュー! さて、この伝説の番人も、俺の『超接続(コネクト)』の前じゃただの肉塊だ」
俺のスキルは戦闘系じゃない。
どんな異次元、どんな結界内部からでも、地球のインターネットにラグなしで接続できる。
それだけだ。
だが、この世界においてそれは「神殺し」の力に等しい。
かつて冒険者たちは、未知への畏敬を持ってここへ潜った。
だが俺は違う。
サーチライトで闇を暴き、騒音で静寂を汚し、神秘を数値と解像度(データ)に還元する。
神秘は、暴かれた瞬間に死ぬのだ。
足元のミノタウロスが、光を失っていく。
肉体が灰になるのではない。
まるで、解像度の低いポリゴンへ劣化するように、存在の「質感(テクスチャ)」が剥がれ落ちていく。
「あれ? なんかバグってね?」
『運営仕事しろ』
『テクスチャ抜けw』
コメント欄が嘲笑で埋まる。
俺は冷めた目で、崩れゆく神話の残骸を跨いだ。
「さあ、次は最奥だ。どんな『神様』がいるか知らねえが……バズる絵が撮れりゃなんでもいい」
俺たちは気づいていなかった。
未知を既知に変えるという行為が、この世界にとってどれほどの猛毒であるかを。
第二章 騎士の尊厳、または1再生0.1円
最奥への扉は、重厚なアダマンタイト製だった。
はずだった。
「はい、これ見てください。この彫刻」
俺は指先で扉の装飾をコンコンと叩く。
「これ、炭素年代測定キットによると、たかだか三百年前のものらしいっす。神代とか言われてたけど、嘘バレちゃいましたねー」
俺がそう解説した瞬間、扉の重厚な輝きが失せた。
まるで安っぽいプラスチックのような質感に変質する。
『なんだよ萎えるわ』
『結局テーマパークかよ』
『設定ガバガバで草』
視聴者の「失望」が、ダンジョンの構成要素(マナ)を書き換えていく。
この世界の強度は、人々の「信じる心」で保たれている。
俺の実況は、その信仰を「ファクトチェック」という暴力で剥ぎ取っているのだ。
扉が開く。
中にいたのは、漆黒の鎧を纏った『冥府の騎士』。
かつて一国の軍隊を壊滅させたと言われる、絶望の象徴。
騎士が剣を抜き、殺気を放つ。
肌が粟立つような、本物の殺意。
だが、俺は動じない。
ドローンを操作し、騎士の背後へ回り込ませる。
「うわっ、みんな見て! こいつの背中、カビ生えてる! 冥府の騎士がカビ掃除もできないとかマジウケるんだけど!」
ドローンがフラッシュを焚く。
カシャッ。
強烈な光に、騎士がたじろぐ。
その姿は、強大なボスモンスターではない。
パパラッチに追われ、醜態を晒す哀れなピエロだった。
「グゥ……オォ……」
騎士が呻く。
剣先が震えている。
怒りではない。羞恥だ。
『カビ騎士w』
『風呂入れよ』
『もしかして:ホームレス』
無慈悲なコメントが、騎士の鎧を錆びさせていく。
彼の誇り高い魔力は霧散し、ただの薄汚れた鉄屑へと成り下がった。
俺はため息をつく。
「あーあ、弱っ。期待外れだなあ。登録解除しないでね?」
膝をついた騎士を無視し、俺は玉座へと歩を進める。
そこに座っているはずの「ダンジョンマスター」。
そいつを暴けば、俺の借金は完済され、この異世界攻略(コンテンツ)も終わる。
そう思っていた。
第三章 チャンネル登録と高評価をお願いします
玉座の間は、異様なほど明るかった。
松明の明かりではない。
青白い、LEDのような冷たい光。
玉座に座っていたのは、絶世の美女だった。
魔王、あるいは女神。
だが、彼女は何もしない。
ただ、虚空に浮かぶホログラムのようなウィンドウを見つめている。
俺が近づくと、彼女はゆっくりとこちらを向いた。
そして、俺ではなく、俺の背後に浮かぶドローンのレンズを直視した。
「……そうか。これが、貴様らの『魔力』か」
透き通るような声。
だが、その響きには違和感があった。
あまりにも、こちらの言語に馴染みすぎている。
「お前がラスボスか? 悪いが、世界征服の野望もここまでだ。俺のリスナーが黙ってな……」
「黙って? いいや、彼らは騒いでいるぞ」
彼女は指を鳴らす。
すると、空間に無数のモニターが出現した。
そこに映っていたのは、俺の配信画面ではない。
『魔王ちゃん可愛すぎワロタ』
『このクオリティなら課金する』
『俺の嫁決定』
『スパチャ投げます!!』
「な……?」
俺の配信枠のコメント欄ではない。
彼女の周囲に、彼女自身の「ステータス」として、視聴者数が表示されていた。
【同接:1,200,000人】
俺の数字を、遥かに超えている。
「分析完了(アナライズ)。恐怖による支配は効率が悪い。信仰よりも、承認欲求(エンゲージメント)こそが、新たな世界を構築するエネルギー源だ」
彼女が立ち上がる。
その瞬間、彼女の衣装が変化した。
重厚なローブから、露出度の高い、しかし計算され尽くした「映える」衣装へ。
ドンの空気が変わる。
陰鬱なダンジョンが、極彩色のネオン輝くサイバーパンクなステージへと書き換わっていく。
「待て、何をした!?」
「文化侵食(アップデート)だ。貴様が望んだのだろう? 神秘のない、分かりやすい世界を」
彼女はドローンに向かって、完璧な角度で微笑んだ。
その笑顔は、聖女の慈愛でも、魔女の誘惑でもない。
1ミリの隙もない、プロのアイドルの笑顔だった。
「ようこそ、私のチャンネルへ。愚かな侵入者(ゲスト)を処刑する配信、始めるわね♡」
『うおおおおおお!』
『処刑wktk!』
『神回確定』
俺のARグラスが、警告音(アラート)で埋め尽くされる。
俺の味方だったはずのコメント欄が、一瞬で彼女の信者へと反転する。
ダンジョンの床から、無数の「カメラ」のような魔物が湧き出した。
それらは全て、俺に向けられている。
「撮影(コロ)してあげる」
俺は理解した。
俺は、神秘を殺したのではない。
神秘を、より強欲で、より残酷な「エンターテインメント」へと進化させてしまったのだ。
「ちょ、待て! カメラ止めろ! 配信切れ!!」
俺の絶叫は、陽気なBGMにかき消された。
視界がブラックアウトする直前、俺が見たのは。
とびきりの笑顔で、俺のドローンに手を振る魔王の姿と。
『次の動画も見てね!』
という、ポップなテロップだった。