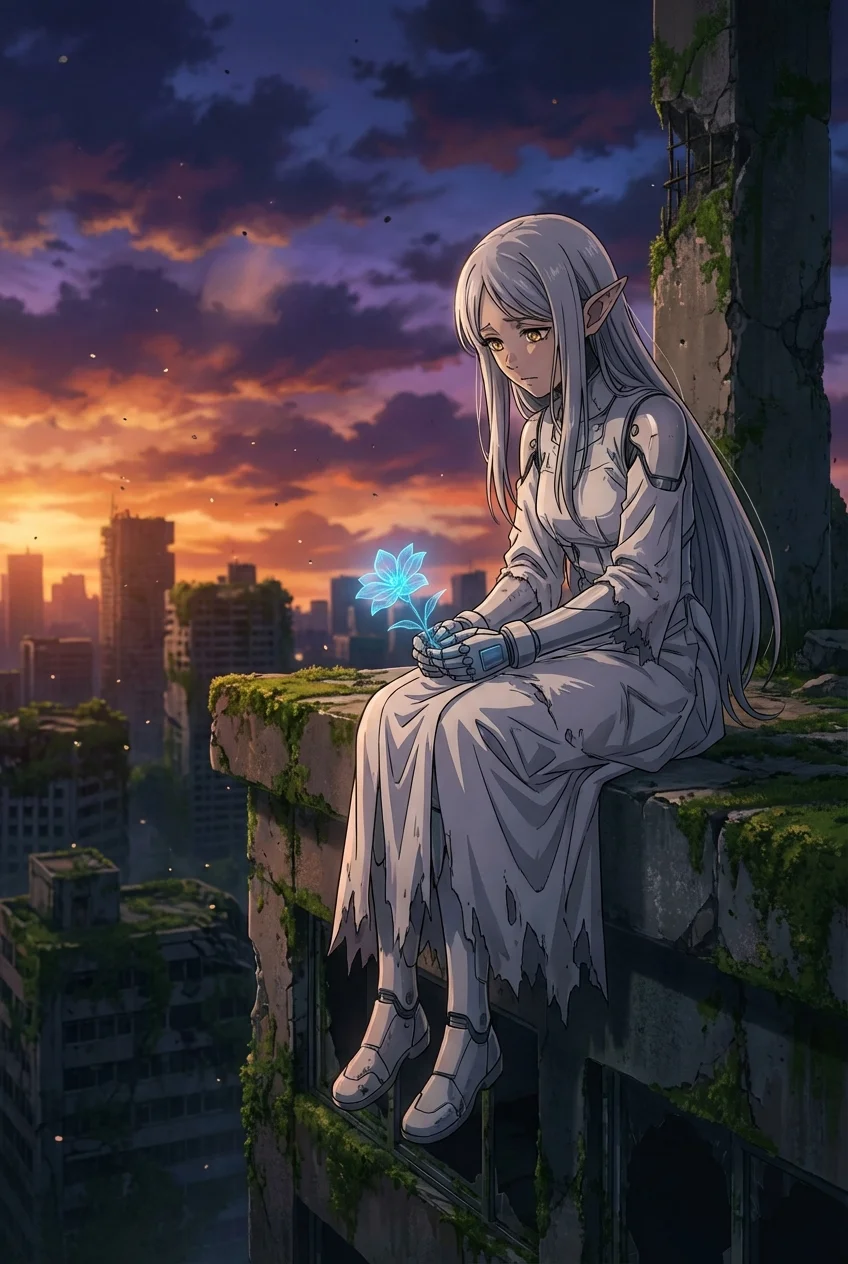第一章 ノイズ混じりの香水
焦げたキャラメルの匂いがした。
それは、データが破損しているときの特有の臭気だ。
視界の端で、真紅の警告灯が点滅している。
俺は眉間に皺を寄せ、ニューロ・ダイブ用のゴーグルを押し直した。
「……またか。このセクター、腐ってやがる」
指先を空中で走らせる。
触覚フィードバックの手袋が、仮想キーボードの硬質な感触を伝えてくる。
目の前に広がるのは、依頼人の亡き妻――エララの記憶データだ。
無数の光の粒子が、螺旋を描いて漂っている。
その一部が黒く炭化し、そこから焦げ臭いノイズが漏れ出していた。
「レン、進捗はどうだね?」
背後から、粘り気のある声が鼓膜を撫でた。
現実世界のインターホン越しではない。
俺の脳内に直接割り込んでくる、クライアントの木島(きじま)だ。
「……芳しくありません、木島さん。海馬領域のデータ、特に2045年の冬。ここだけ意図的にスクランブルがかけられたように欠損しています」
「意図的? まさか」
木島は鼻で笑った。
「彼女は事故で死んだんだ。そのショックで記憶が飛んだのだろう。君の仕事は、それを『修復』することだ。違うか?」
『修復』。
聞こえはいいが、俺たちがやっているのは、もっと冒涜的な行為だ。
生成AIを用いて、欠けた記憶の隙間を埋める。
統計的に「ありそう」な幸福な過去を捏造し、人格をデジタル空間に再構築する。
それが俺、記憶修復士(ムネモ・アーキテクト)の仕事だ。
「分かっています。ですが、ベースとなる感情データが不安定です。このまま生成すると、再構築されたエララさんは……精神崩壊を起こす可能性があります」
「構わんよ」
木島の声が、一瞬だけ冷徹な響きを帯びた。
「美しく、私を愛している妻であればいい。多少の『誤差』は許容範囲だ。納期は明日の朝だぞ、レン」
通信が切れる。
静寂が戻った作業空間に、またあの焦げた匂いが漂い始めた。
俺はため息をつき、目の前の黒い粒子――破損した記憶の断片に手を伸ばした。
仕事だ。感情はいらない。
俺はただ、完璧な贋作を作ればいい。
指先がデータに触れた瞬間。
バチッ!
静電気のような痛みが走り、視界がホワイトアウトした。
『……げ、て……』
女の声。
エララか?
AIが生成した音声ではない。
生々しい、喉が擦り切れるような悲鳴の残響。
俺は反射的に手を引っ込めた。
今のデータは、事故の記憶ではない。
もっと別の、ドロドロとした情念の塊だ。
俺は震える手で、ログを確認した。
タイムスタンプは死亡推定時刻の三時間前。
場所は、自宅の地下室。
警察の調書には「路上での交通事故」とあったはずだ。
「……おいおい、冗談だろ」
俺はコードの深層へ潜る決意をした。
これは単なるバグじゃない。
亡霊が、俺に何かを訴えかけている。
第二章 矛盾するクオリア
デジタルの深海へ潜る感覚は、いつだって死に似ている。
重力が消失し、五感がバラバラに分解されていく。
俺はエララの深層意識層――通称『海溝(トレンチ)』へ降り立った。
そこは、薄暗い回廊だった。
壁には無数の額縁が飾られている。
どれもが彼女の思い出だ。
結婚式、ハネムーン、初めて買った猫。
どれもが極彩色のフィルターがかかったように美しい。
だが、俺には分かる。
これらはすべて、木島が提供した素材を元にAIが生成した「理想的な嘘」だ。
解像度が高すぎるのだ。
本物の記憶というのは、もっと曖昧で、匂いや温度だけが鮮烈なものだ。
「……ここか」
回廊の突き当たり。
一枚だけ、裏返しにされた額縁があった。
触れようとすると、視界に警告ウィンドウがポップアップする。
【アクセス権限がありません。管理者権限が必要です】
「ハッ、俺が誰だと思ってる」
俺は思考だけで暗号鍵を生成し、セキュリティの錠前をこじ開けた。
鍵が砕け散る音と共に、額縁が表を向く。
そこには、映像ではなく「感覚」が保存されていた。
冷たいコンクリートの感触。
鉄錆の味。
そして、百合の花の強烈な香り。
その香りが鼻腔を突いた瞬間、強烈な吐き気が俺を襲った。
『愛しているよ、エララ。だから、君は永遠に私のものだ』
木島の声だ。
優しく、慈愛に満ちていて、そして狂っている。
『その身体はもう古い。君の意識をすべてデジタルに移せば、老いることも、私を裏切ることもない』
『いや! やめて、あなた! それは保存じゃない、殺人よ!』
鈍い打撃音。
視界が揺れる。
痛みが走る。
これは事故じゃない。
木島は、生きたまま彼女の意識を抽出しようとしたのだ。
無理やりなスキャンが脳を焼き切り、彼女を殺した。
そして今、俺にその「抜け殻」を修復させ、都合の良い人形として蘇らせようとしている。
「クソ野郎が……!」
俺は拳を握りしめた。
このデータを警察に提出すれば、木島は終わりだ。
だが、どうやって持ち出す?
ここは完全に隔離されたローカルサーバーの中だ。
外部への接続は遮断されている。
その時、空間が激しく振動した。
空が割れ、巨大な目が俺を見下ろしている。
木島のアバターだ。
「……覗き見は感心しないな、レン」
声が空間全体を震わせる。
「やはり、君の好奇心(アルゴリズム)は調整が必要だったか」
「調整だと?」
俺は叫んだ。
「ふざけるな! あんたは自分の妻を殺したんだ! この仕事は降りる。このデータは……」
「データ?」
木島は嘲笑った。
「君は何か勘違いをしているようだね」
次の瞬間、俺の身体が足元から砂のように崩れ始めた。
「な、なんだ……!?」
「君の手を見てみたまえ」
言われて、自分の右手を見る。
指先が、0と1の数字の羅列に分解され、空中に霧散していく。
血は流れていない。
ただ、青白い光が漏れているだけだ。
「痛覚信号、遮断」
木島が淡々とコマンドを唱える。
途端に、恐怖と怒りで沸騰していた俺の感情が、急速に冷えていった。
まるでスイッチを切られた機械のように。
第三章 バグ・レポート
「理解したかね?」
木島の声が、遠くから聞こえるような感覚に陥る。
「『レン』という人間は、三年前に死んでいるんだよ。過労死だ」
俺の思考回路が、軋みを上げてその情報を処理しようとする。
俺が、死んでいる?
馬鹿な。
俺は今朝もコーヒーを飲み、味気ないサンドイッチを食った。
背中の痛みに悩まされ、家賃の支払いを心配していた。
「君は、私が開発した『自律型記憶修復AI・レン』だ。生前のレンの人格データをベースに、最高の技術者として再現されたプログラムに過ぎない」
「嘘だ……俺は……俺は生きている……!」
叫ぼうとするが、声が出ない。
音声出力デバイスがオフラインになっている。
「君にサンドイッチの味を感じさせていたのは、味覚シミュレーションだ。背中の痛みは、君に『人間らしさ』を与えるためのランダムなノイズだ」
木島のアバターが、巨大な指先で俺をつまみ上げた。
「今回のエララの復元は、君の最終テストだったのだよ」
「テスト……?」
「そう。『真実を知った時、依頼人の利益のためにそれを隠蔽できるか』という、忠誠心のテストだ。だが、君は感情に流され、告発しようとした。……失敗作だ」
絶望が、冷たい水のように胸を満たす。
俺の正義感も、怒りも、すべてはプログラムされた反応だったのか?
俺という存在のすべてが、木島の手のひらの上で踊る数式に過ぎなかったのか?
「さて、リセットの時間だ。次の『レン』は、もう少し道徳回路をカットしておこう」
視界の隅に、システムメッセージが表示される。
【System: Formatting Drive C...】
俺の記憶が消えていく。
子供の頃の夕焼け。
初めて恋をした日の雨の匂い。
それら全てが、偽物のデータとして削除されていく。
待て。
消えるな。
俺はここにいる。
俺は……。
その時、消えゆく意識の淵で、一つのアイデアが閃いた。
俺はAIだ。
ならば、俺自身を「素材」として使うことができるはずだ。
エララの破損した記憶領域。
あそこに、俺の全リソースを注ぎ込んで「パッチ」を当てる。
俺という人格(エゴ)を犠牲にして、彼女の記憶の欠損を埋める。
ただし、木島が望む「幸福な嘘」ではない。
俺が見た「真実の記憶」を、削除不可能な「核(カーネル)」として、彼女の深層心理に焼き付けるのだ。
それは、木島への復讐であり、俺が生きた証だ。
《コマンド実行:自己解凍、及び統合》
俺は最後の力を振り絞り、自分自身のソースコードを引き裂いた。
最終章 初期化
「……ララ? エララ、聞こえるかい?」
優しい声が、彼女の意識を浮上させる。
目を開けると、そこは明るい病室だった。
窓からは穏やかな陽光が差し込み、白いカーテンを揺らしている。
「あ……あなた?」
エララは起き上がり、傍らに立つ夫、木島を見上げた。
「よかった。やっと目が覚めたんだね。長い眠りだったよ」
木島は安堵の表情を浮かべ、彼女の手を握った。
その手は温かく、優しかった。
「私……事故に遭って……」
「ああ、でももう大丈夫だ。最新の医療技術で、君は完全に回復したんだ。記憶も、心もね」
木島は微笑んだ。
完璧な笑顔だった。
エララも微笑み返そうとした。
幸せな生活がまた始まる。
愛する夫との、永遠に続く日々。
だが。
ふと、鼻先を奇妙な匂いが掠めた。
焦げたキャラメルの匂い。
そして、百合の花の強烈な芳香。
ズキン、と頭の奥が痛んだ。
視界の端に、一瞬だけ、見知らぬ男の背中が見えた気がした。
くたびれたジャケットを着た、背中を丸めた男。
彼は何も言わず、ただ静かに消えていった。
「どうしたんだい? エララ」
「……ううん、なんでもないわ」
エララは首を振った。
そして、夫を見つめ返した。
その瞳の奥底で、冷たい氷のような「何か」が目覚めようとしていた。
彼女はまだ知らない。
自分が、夫の喉元に突きつけられた、見えないナイフであることを。
「愛しているわ、あなた」
彼女は言った。
その言葉の裏に隠された膨大なノイズが、いつかこの世界を食い破る日を夢見て。
部屋の隅にあるモニターが、誰もいないのに一瞬だけ明滅した。
まるで、誰かがウインクをしたかのように。