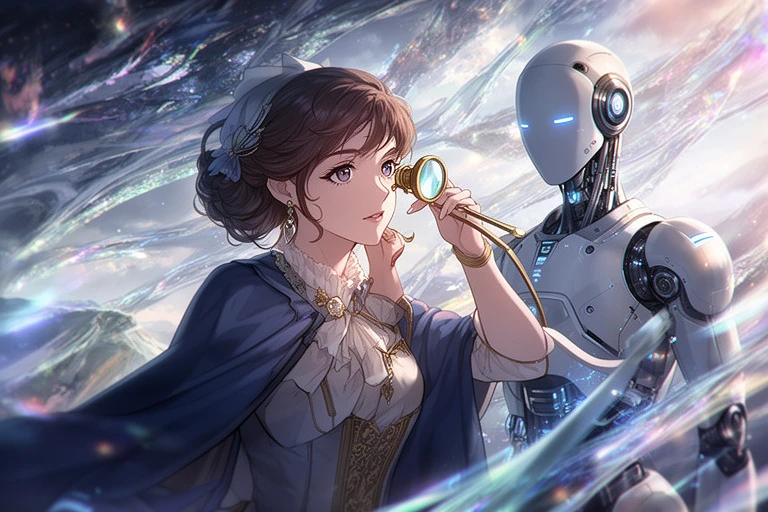第一章 煤煙と真鍮の鼓動
カラン、コロン。
真鍮製のドアベルが、乾いた音を立てた。
「いらっしゃい」
私は顔を上げずに言った。手元には分解された懐中時計。ピンセットの先で、米粒よりも小さな歯車を摘まみ上げている最中だったからだ。
「あの……直していただけると聞いて」
怯えたような、それでいて芯のある少女の声。
オイルと古紙の匂いが染みついたこの店に、似つかわしくない甘い香りが漂ってくる。
私はようやくルーペを外し、客を見た。
亜麻色の髪に、煤(すす)で汚れたエプロンドレス。年齢は十六、七といったところか。彼女の震える手には、ガラスの割れた銀時計が握りしめられている。
「エルフの時計技師がいると聞きました。どんな壊れた時間でも、元通りにしてくれると」
「『どんな』は誇張だ。私は神じゃない。ただ長生きなだけだ」
私は椅子から立ち上がった。
きしむ床板。天井まで届く棚には、数千の時計がそれぞれの時間を刻んでいる。チクタク、チクタク。その不協和音だけが、私の孤独を埋める唯一の友だった。
彼女、リリアは差し出した時計を愛おしそうに撫でた。
「戦場に行く彼が、残していったんです。動かなくなってしまって……これでは、彼がいつ帰ってくるのかもわからない」
「貸してみろ」
受け取った時計は、酷い有様だった。
メインスプリングは断裂し、ヒゲゼンマイは絡まり合っている。だが、私の指先がそれに触れた瞬間、金属の「記憶」が流れ込んできた。
爆音。泥。そして、最後の瞬間にこの時計を握りしめた男の、強烈な祈り。
――ああ、またか。
人間というのは、なぜこうも脆い器に、あふれんばかりの感情を詰め込もうとするのか。
「直るか?」
「直します。……なんとしても」
私は作業台に戻った。
私の種族にとって、百年は午睡(ごすい)に等しい。だが、彼ら人間にとっての時間は、火花のように激しく、そして一瞬で燃え尽きる。
窓の外を見る。
石畳の通りを、蒸気機関車が白煙を上げて走っていく。巨大な工場の煙突が空を灰色に塗りつぶしている。
この街も変わった。かつては森だった場所が、今は鉄と蒸気の都だ。
「ねえ、時計屋さん」
作業を見守るリリアが呟く。
「あなたは、ずっとここにいるの?」
「ああ。この店を開いてから、もう三百年になる」
「寂しくないの? お友達とか、家族とか」
「見送る方が辛い。だから、私はただ観測するだけだ。壊れた時間を直し、持ち主に返す。それ以上の関わりは持たない」
嘘だった。
本当は、関わりを持つのが怖いのだ。彼らの命はあまりに短く、私の記憶の中で彼らが「死者」として過ごす時間の方が、圧倒的に長くなってしまうから。
カチッ。
小さな音が響いた。
秒針が震え、再び時を刻み始める。
「できたぞ」
リリアの顔が、店内の薄暗いランプの下で、花が咲くように輝いた。
「ありがとう! 本当に……ありがとう!」
彼女はなけなしの銀貨をカウンターに置き、時計を胸に抱いて店を出て行った。
ドアが閉まる瞬間、冷たい風と共に、街の喧騒が入り込む。
私は再びルーペを目に当てた。
彼女の「彼」は、もう帰ってこない。時計に残った残留思念がそう告げていた。
それでも、時間は進む。残酷なほど正確に。
第二章 ネオンの雨と電子の夢
カラン、コロン。
ベルの音が、電子的なノイズにかき消されそうになる。
「よう、旦那。やってるか?」
入ってきたのは、左腕をサイバネティクス義手に変えた青年だった。
頭にはホログラムゴーグル。濡れた合成皮革のジャケットからは、酸性雨特有の鼻を刺す刺激臭がする。
「修理か?」
「ああ。こいつを見てくれ」
彼がカウンターに放り投げたのは、旧世紀の遺物――物理的なキーボードがついた端末だった。
窓の外は、もう空が見えない。
摩天楼が幾重にも重なり、極彩色のネオンサインが絶えず点滅している。空飛ぶエアカーが、川のような光の帯を作って流れていく。
かつて蒸気機関が走っていた道は、今はホログラム広告が踊る空中回廊になっていた。
「骨董品だな」
「ひい婆ちゃんの形見なんだ。データバンクが焼き切れてる。どこのテックショップに持ち込んでも『修理不能』だとよ」
青年、レオンはゴーグルをずらして私を見た。
その瞳の奥に、かつてのリリアと同じ光が見える。
「ここなら、どんな古いもんでも直せるって噂だ。頼むよ、この中には『本物の空』の映像が入ってるんだ」
「本物の空?」
「今の空はプロジェクションだろ? 昔は、空ってのが青かったらしいじゃねえか。俺、それが見てえんだよ」
私は端末を手に取った。
回路は焼き切れ、記憶媒体は腐食している。だが、私の指先は知っている。物質の構造、電子の流れ、それらを超えた「想い」の修復方法を。
私の種族――『修復者(フィクサー)』の指先からは、微弱なマナが流れ出る。それは科学技術がどれだけ進歩しても解析できない、生命の根源的な力だ。
「三百五十年ぶりか」
「は? 何が?」
「いや、独り言だ」
私は作業を始めた。
この数百年で、人間は変わった。肉体を機械に変え、脳をネットに接続し、寿命を倍に伸ばした。それでも、彼らの本質は変わらない。
失われたものを懐かしみ、届かない星に手を伸ばす。
「あんた、耳なげーな。整形か?」
「天然だ」
「へえ。長生きなんだろ? 昔の空は、本当に青かったのか?」
「ああ。目が痛くなるほどな」
「いいなあ……。俺、この街から出たことねえからさ」
レオンはカウンターに頬杖をつき、退屈そうに指でリズムを刻む。
そのリズムは、あの日、リリアが刻んでいた鼓動と同じだった。
「終わったぞ」
端末の画面がちらつき、ノイズの向こうに映像が浮かび上がる。
それは、ただの曇り空だった。だが、雲の隙間から一筋の光が差し込み、雨上がりの街を照らしている。
「すげえ……」
レオンは息を呑んだ。
「これが、太陽か」
彼は震える義手で端末を握りしめた。
「サンキュ、旦那。これがあれば、俺はまだ生きていける」
彼は電子マネーではなく、古びた金属片――かつての銀貨をカウンターに置いた。
「親父が、ここに来たらこれで払えって言ってたんだ」
彼はウィンクをして、ネオンの海へと消えていった。
私は銀貨を手に取る。
それは、三百年前に私がリリアから受け取ったものと同じ鋳造年の硬貨だった。
人間は、愚かで、愛おしい。
文明がどれほど姿を変えようと、彼らは想いを繋いでいく。
私は銀貨をポケットにしまい、窓の外の偽物の空を見上げた。
私の「観測」は、まだ終わりそうになかった。
第三章 静寂の雪と錆びた真実
カラン……。
ベルの音が、やけに大きく響いた。
音がないからだ。
外の世界から、音が消えて久しい。
「いらっしゃい」
私は声を出した。喉が張り付くような感覚。言葉を発するのは、数十年ぶりかもしれない。
入ってきたのは、人ではなかった。
白い流線型のボディ。顔には目鼻がなく、ただ一つの青いセンサーライトが点滅している。自律型アンドロイドだ。
外は、白い砂のような雪が降り積もっている。
ネオンも、エアカーも、摩天楼も、すべてが砂に埋もれた。
人間は、もういない。
彼らは星を食いつぶし、あるいはデータの海へと精神を移行させ、肉体を持つ種としての歴史を終えた。
残されたのは、主を失った機械たちと、私だけだ。
「修復ヲ、希望シマス」
機械的な音声が響く。
アンドロイドは、大切そうに何かを抱えていた。
それは、小さなオルゴールだった。塗装は剥げ、装飾も欠けている。
「お前たちに、音楽を楽しむ機能があるのか?」
「イイエ。コノ個体ニ、感情機能ハ搭載サレテイマセン」
「なら、なぜ直す?」
「……記録データニヨルト、コノ音色ヲ聴クト、胸部演算ユニットニ原因不明ノ熱量ガ発生シマス。コノ熱量ノ正体ヲ解明スルタメ、修復ガ必要デス」
私は苦笑した。
それを、かつて人間たちは「心」と呼んだのだ。
私はオルゴールを受け取った。
内部は単純な構造だ。だが、長い年月が、ゼンマイを錆びつかせている。
私は指先からマナを送る。
だが、反応が鈍い。世界そのものからマナが枯渇し始めている。
「私が見てきた人間たちは、騒がしく、勝手で、すぐに死ぬ生き物だった」
私は独り言のように語りかけた。
「だが、彼らは何かを残そうとした。時計を、映像を、そしてこのオルゴールを」
作業を続ける私の手元を、アンドロイドの青い光が見つめている。
「オマエハ、ナゼココニ?」
アンドロイドが問うた。
「ナゼ、コノ星ガ死ヌマデ、店ヲ続ケル?」
「約束、のようなものだ」
私は答えた。
「誰との?」とは聞かれなかった。
カチッ。
最後の調整が終わる。
私はゼンマイを巻いた。
ポロン、ポロン……。
流れてきたのは、古臭い民謡だった。リリアが生きた時代の、流行歌だ。
アンドロイドは静止した。
センサーライトが、青から、暖かなオレンジ色へと変わる。
「……熱量ガ、上昇シテイマス。コレハ……不快デハアリマセン」
「それを懐かしさと呼ぶんだ」
アンドロイドはオルゴールを受け取ると、深々と頭を下げた。
そして、対価として一枚のチップを置いた。
「コレハ?」
「『遺言』デス。人類ガ最後ニ残シタ、全テノ記録。コノ店ナラ、永遠ニ保存サレルと判断シマシタ」
アンドロイドは店を出て行った。
白い砂漠へと続く足跡は、すぐに風に消されていく。
私は残されたチップを握りしめた。
これで、本当に終わりだ。
私は立ち上がり、店のドアを開けた。
吹き込む風は凍えるほど冷たい。だが、その中には微かに、土と緑の匂いが混じっていた。
「……再生が、始まるのか」
雪の下で、新たな生命が芽吹こうとしている。
私は店に戻り、看板を裏返した。
『CLOSED』
いや、違う。
私はペンを取り、その下に小さく書き加えた。
『準備中』
数千年、あるいは数万年後。
また誰かが、壊れた時間を抱えて、このドアを叩く日が来るだろう。
それまで、少し長い午睡を楽しむとしよう。
私は椅子に深く腰掛け、目を閉じた。
無数の時計の音が、私を暖かく包み込んでいた。