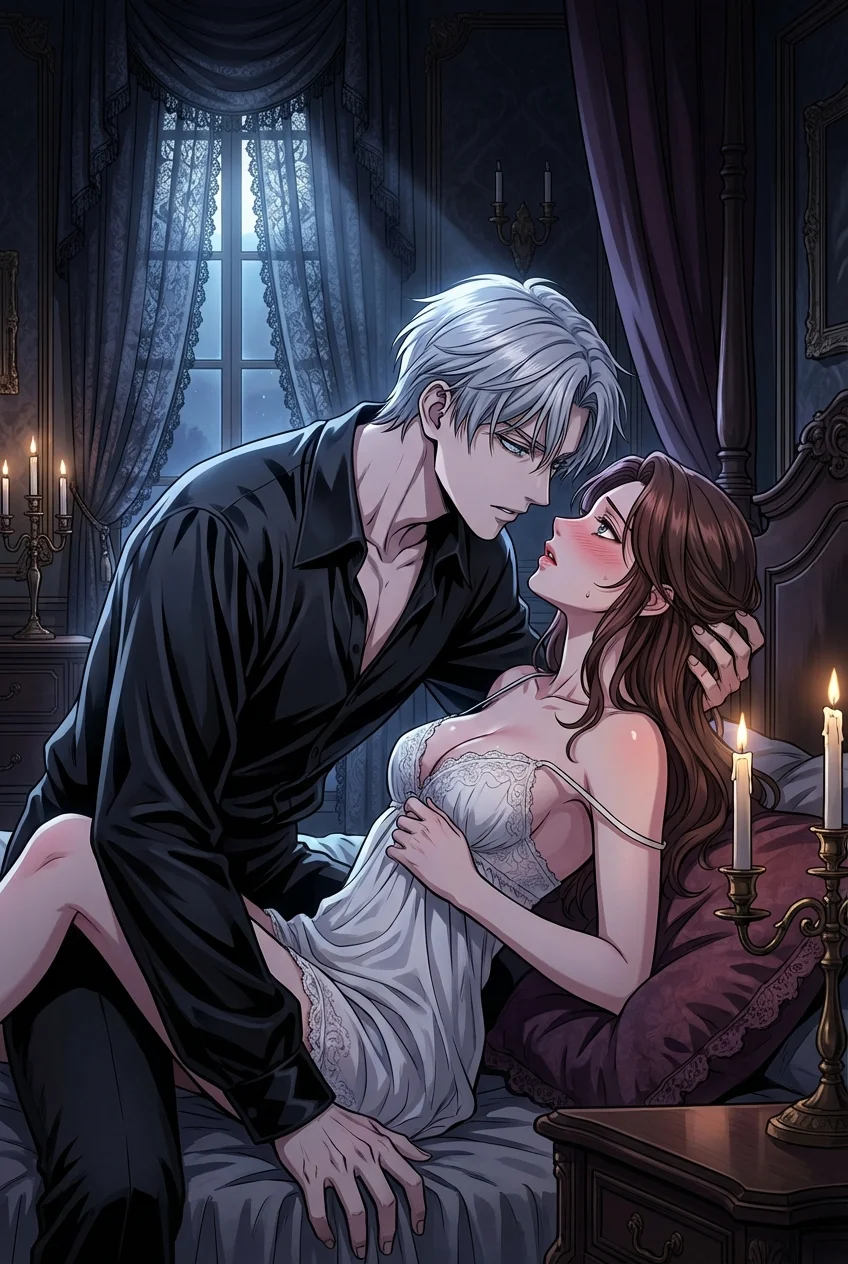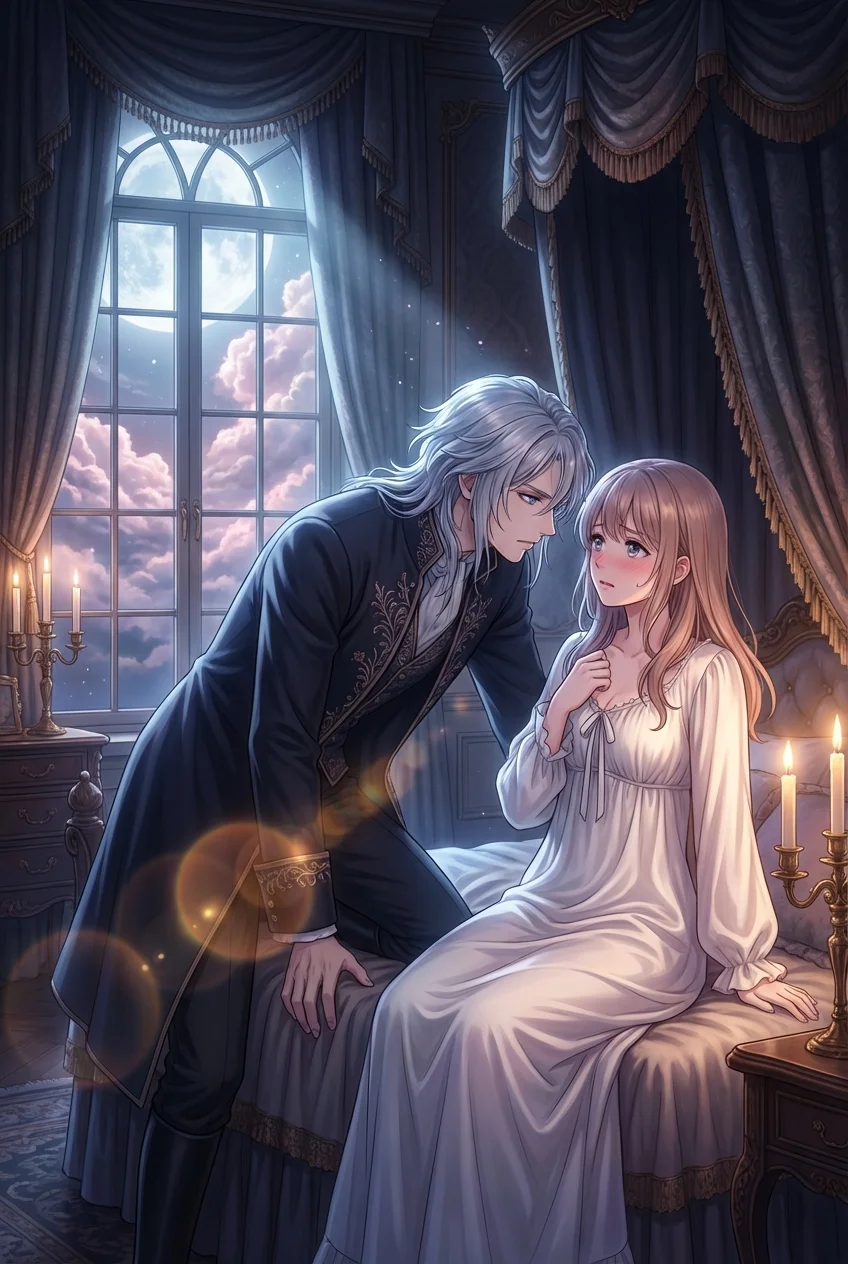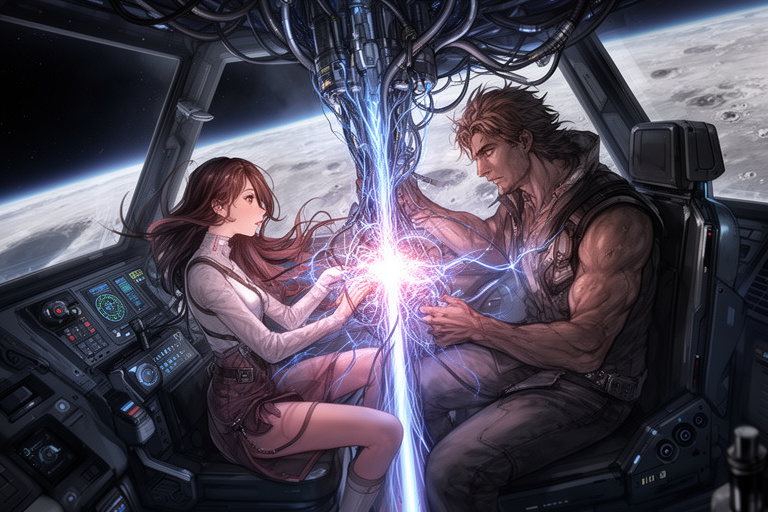第一章 氷の檻と0.1ヘルツの焦燥
「……心拍数が早い。ノイズが混じっている」
完全防音のスタジオに、冷徹な声が響いた。
スピーカーから聞こえるその声は、まるで氷の刃のように私の鼓膜を撫で、脊髄へと直接滑り込んでくる。
私は分厚いガラスの向こう側にいる男――久我山(くがやま)レイを見つめた。
彼は手元のコンソールを操作しながら、私を一瞥もしない。
白衣に包まれたその背中は、昼間のオフィスで見せる「無愛想な上司」そのものだ。
けれど、今は違う。
ここは世界最高峰の音響工学研究所の地下。
そして私は、彼の秘書であり、唯一の「実験体」だ。
「すみません、久我山さん……少し、部屋の温度が……」
「室温は常に24度に保たれている。熱いのは君の脳内だけだ、エマ」
久我山がスイッチを切り替える。
ブゥン……。
空気が震えた。
耳には聞こえないほどの低周波が、床を伝い、私が座る革張りの椅子を微かに揺らす。
「あ……っ」
思わず吐息が漏れた。
ただの振動ではない。
彼が設計したこの特殊な周波数は、人体の神経系に直接干渉し、強制的に「昂ぶり」を引き出すようにプログラムされている。
昼間は冷淡に書類を突き返すだけの彼が、夜だけはこうして私をこの椅子に縛り付け――物理的な拘束具など使わずに――音だけで私を犯すのだ。
「動くなと言ったはずだ。……君は感度が良すぎる」
ヘッドフォン越しに、彼のため息が聞こえる。
その吐息さえもが高解像度で再生され、私の耳元で彼が直接囁いているかのような錯覚を覚える。
「次は中音域の共鳴テストだ。……耐えられるか?」
「は、い……」
「嘘だな。君の身体はもう、限界を訴えている」
ガラス越しに目が合った。
無機質な眼鏡の奥にある瞳が、獲物を観察する爬虫類のように細められる。
彼はゆっくりと立ち上がると、コントロールルームを出て、私がいるブースの重い扉を開けた。
密閉された空間に、彼の匂いが入り込む。
消毒液と、微かなミント、そして冷たい金属のような香り。
「口では否定しても、身体は正直だ」
彼は私の前に跪くと、震える膝にそっと手を置いた。
ただ触れられただけ。
それなのに、まるで高圧電流が走ったかのように、私の背中が反り返る。
「ひっ……!」
「いい声だ。……だが、まだ許可はしていない」
久我山の指が、私の太腿を這い上がり、スカートの裾を無造作に捲り上げる。
彼の指先は恐ろしく冷たい。
その冷たさが、火照りきった私の肌には焼き鏝(やきごて)のような刺激となって突き刺さる。
「焦らされるのは嫌いか?」
「そ、んな……こと……」
「強がりは不要だ。君のその場所は、もう私の音を求めて泣いている」
彼は残酷なほど冷静に、私の秘められた熱源へと指を伸ばした。
しかし、核心には触れない。
ギリギリの輪郭をなぞり、焦らし、理性を削ぎ落としていく。
これは愛ではない。
調律だ。
彼にとって私は、最高の音色を奏でるための楽器に過ぎないのだから。
第二章 被験体の甘い悲鳴と和音
「……ッ、ん、あぁ……!」
私の口から、意味を成さない言葉が零れ落ちる。
久我山は私の反応を観察しながら、もう片方の手で音叉(おんさ)を取り出した。
銀色に輝くその金属棒を、彼は硬いヒールで軽く叩く。
キィィィン……。
澄んだ高音が響く。
彼は振動し続ける音叉の柄を、私の鎖骨、そして首筋へと押し当てた。
「ひあぁっ!?」
音の振動が骨を伝わり、脳髄を揺らす。
直接的な接触よりも遥かに深く、身体の内側から掻き回されるような感覚。
視界が白く明滅する。
「美しい反応だ。骨伝導による快感中枢への刺激……理論通りだが、君の反応は想定値を超えている」
彼は淡々と分析を口にするが、その瞳の奥には昏い炎が灯っていた。
音叉が胸元の膨らみを滑り落ち、薄いブラウス越しに敏感な突起を掠める。
金属の微細な振動が、張り詰めた神経を極限まで逆撫でする。
「や、やめ……おかしく、なる……っ」
「おかしくなればいい。君の理性など、私の研究には邪魔なだけだ」
久我山は音叉を放り投げると、今度は両手で私の腰を掴み、強く引き寄せた。
距離が消える。
彼の整った顔が目の前に迫り、荒い呼吸が私の唇にかかる。
「……昼間、新入社員の男と笑っていただろう」
唐突な言葉に、混濁した意識が一瞬だけ浮上する。
「え……?」
「私の前では見せないような、緩みきった顔で。……不愉快だ」
彼の指が食い込むように強く肉を掴む。
痛みと快感が混ざり合い、私の喉からは掠れた嗚咽が漏れた。
無愛想で、仕事以外に興味がないと思っていた彼。
けれど今、彼が私に向けている感情は、明らかに歪んだ独占欲だった。
「君は私が作った楽器だ。他の人間にその音色を聞かせるな」
「く、がやま、さ……」
「返事は?」
「は、い……貴方だけの、ものです……っ」
その言葉を聞いた瞬間、彼の理性のタガが外れる音がした。
彼は乱暴に私の唇を塞いだ。
味見などではない、酸素を奪い尽くし、私の存在そのものを飲み込もうとするような深い接吻。
口内を蹂躙されながら、私は彼が普段隠している熱情の激しさに打ち震えた。
氷のような仮面の下には、煮えたぎるマグマのような執着が渦巻いている。
彼の手が、ついに焦らし続けていた最奥の扉をこじ開けた。
「あっ、あぁッ! くる、きちゃ……っ!」
「まだだ。許さない」
絶頂へ駆け上がろうとする私の腰を、彼は非情にも押さえつける。
「……ッ!?」
「このまま、私の指と声だけで狂え。君が壊れるまで、何度でも」
彼は耳元で低く囁きながら、容赦なく「核心」を突き上げた。
第三章 永遠に続く共鳴
時間は意味をなさなくなっていた。
終わりのない波状攻撃。
久我山の指使いは、精密機械のように正確で、かつ悪魔的に執拗だった。
引いては押し寄せ、高めては寸止めし、私が懇願するたびに冷たく突き放す。
「お願い、もう、許して……!」
涙で視界が滲む。
シーツを握りしめた指先は白くなり、全身の筋肉が痙攣している。
「許してほしいか? なら、もっと泣け。その声が私を癒やす」
彼は私の涙を指ですくい取り、自らの唇に運んだ。
「甘いな。……君の全てが、私の神経を鎮める唯一の薬だ」
そう呟くと、彼は最後の仕上げにかかった。
逃げ場のない椅子の上、広げられた両足の間で、彼は巧みに、そして深く、私の中を侵食していく。
熱い楔のような指が、敏感な粘膜を擦り上げ、今まで触れられたことのない深い場所にあるスイッチを押した。
「あ、あ、あぁぁぁぁッ!!」
声にならない絶叫。
視界が弾け飛び、世界が真っ白な光に包まれる。
けれど、彼は止まらない。
痙攣し、意識が飛びそうになる私を現実に引き戻すように、さらに激しく、深く、執拗に責め立てる。
「イッても終わらせない。君の感覚が焼き切れるまで、私は止まらない」
「し、んじゃう、死んじゃうぅぅッ!」
「死なせない。君は私のものだ。……永遠に」
彼が耳元で囁いたその言葉は、呪いのようであり、愛の告白のようでもあった。
五感が溶解していく。
音も、光も、温度も、すべてが彼という存在に塗り替えられていく。
もはや自分が誰なのかもわからない。
ただ、この冷酷でサディスティックな天才に奏でられるためだけに存在する、肉の楽器。
何度も、何度も、果てることを許されず、絶頂の淵を走らされる。
「……レイ、さん……っ」
無意識に彼の名前を呼んだとき、彼の動きが一瞬だけ止まった。
「……その名前で呼ぶのは、この部屋の中だけだ」
彼は少しだけ優しく、私の汗ばんだ髪を撫でた。
だが、その瞳にある独占欲は、先ほどよりも一層深く、濃くなっていた。
「明日の朝、君がオフィスで涼しい顔をしていても……身体の奥には、私が刻み込んだ熱が残っているはずだ」
彼は再び、私を快楽の地獄へと突き落とす。
「それを感じるたびに思い出せ。君は誰のものかを」
薄れゆく意識の中で、私は確信した。
この防音室から出ても、私はもう逃げられない。
私の鼓膜は、神経は、細胞のひとつひとつは、彼の周波数にしか共鳴できなくなってしまったのだから。
深夜の調律室。
二人の荒い呼吸と、濡れた水音だけが、永遠に反響し続けていた。