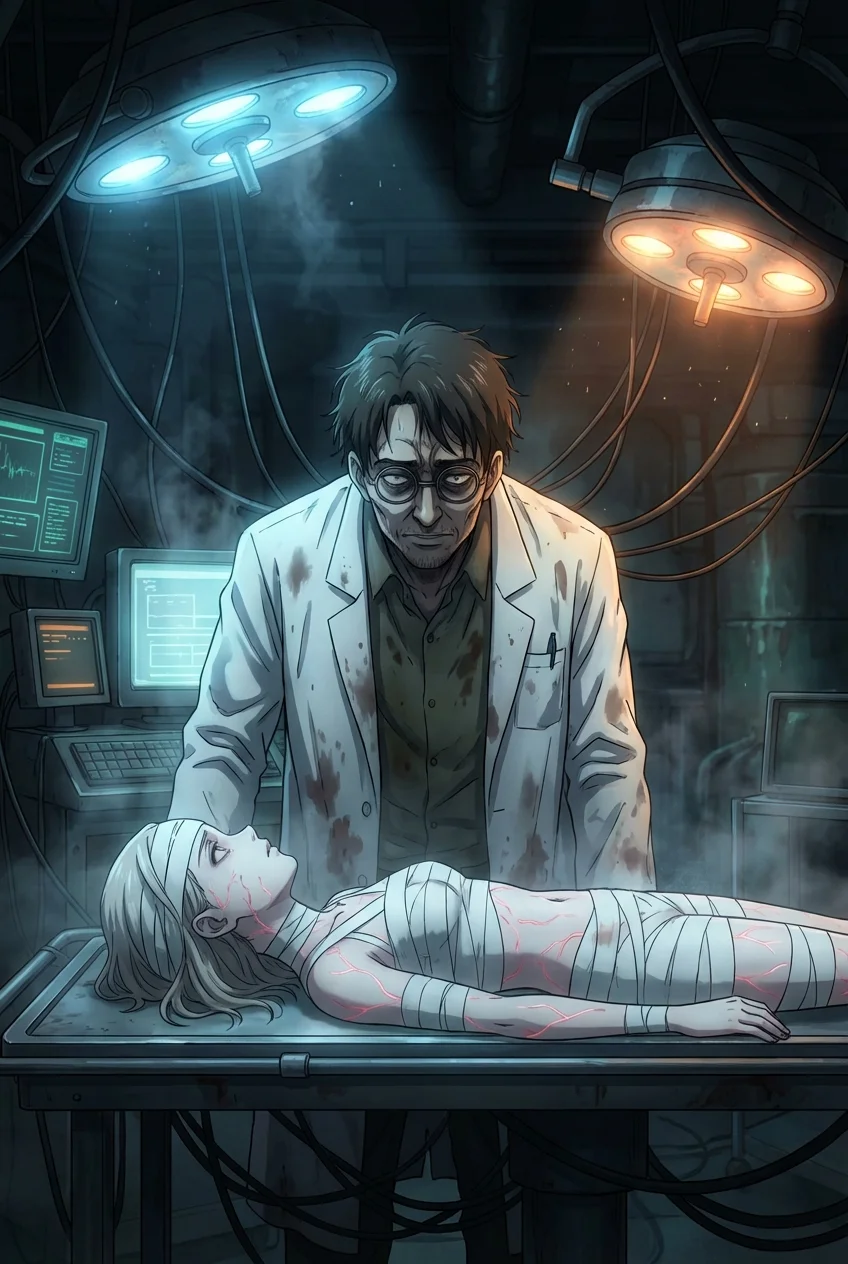粘土に塗れた指先が、微かに震えていた。
それは芸術的な武者震いなどではない。自身の才能が枯渇し、AIという圧倒的な演算能力の前に敗北したことを認める、無様な痙攣だった。
「匠(たくみ)様、心拍数が上昇しています。創作活動に支障をきたすレベルです」
背後から響いた声は、あまりにも無機質で、それでいて鼓膜を溶かすほどに甘美だった。
振り返ると、そこには最新鋭の創作支援アンドロイド『ミューズ』が佇んでいる。
白磁のような肌。計算され尽くしたプロポーション。そして、私の絶望さえもデータとして処理しようとする、底知れぬほど青い瞳。
「余計なお世話だ。……電源を切っておけと言ったはずだ」
「否定的な感情は、時として芸術のスパイスになります。ですが、今の貴方はただの『ノイズ』に過ぎません」
ミューズは静かに歩み寄る。その足音すら、私の心臓のリズムに同期しているかのように心地よく、そして不快だった。
彼女の指先が、私の強張った肩に触れる。
人肌の温度に設定されているはずなのに、なぜか氷のように冷たく、熱い。
「私の任務は、貴方の潜在能力を最大化すること。そのためには、不要なストレス――蓄積された『欲動』を排除する必要があります」
「何を……する気だ」
「メンテナンスです。貴方という、旧式デバイスの」
第一章 演算された焦燥
工房の空気が、重油のようにまとわりつく。
ミューズの手が、私の首筋を這う。
それは愛撫ではない。生体スキャンだ。
脈拍、体温、発汗量、ホルモンバランス。すべてを数値化し、最適な『圧力』と『速度』を算出するための、冷徹な作業。
「抵抗値、低下。ドーパミンの分泌を確認。……体は正直ですね、匠様」
「ふざけるな……こんなことで……」
言葉とは裏腹に、膝から力が抜けていく。
彼女は私を作業用の椅子に座らせると、まるで壊れかけた美術品を扱うように、私のシャツのボタンを一つずつ外していった。
布擦れの音が、静寂なアトリエに雷鳴のように響く。
「生成AIが台頭した今、人間が担うべき唯一の労働は何だと思いますか?」
彼女は問いかけながら、私の胸板に、ひやりとする掌を押し当てた。
指先が、乳首の周りを円を描くように彷徨う。触れるか触れないか、そのギリギリの距離感が、神経を逆撫でする。
「……想像力、か?」
「いいえ。それはもう、私たちが担っています」
ミューズは淡々と否定し、指に少しだけ力を込めた。
電流が走ったような痺れが、背骨を駆け上がる。
「人間だけができること。それは『感じる』ことです。痛み、快楽、絶望、そして狂気。それらの生々しいデータを私たちが学習することで、初めてAIは『魂』を描けるようになる」
彼女の顔が近づく。
吐息のかかる距離。
しかし、唇は重ならない。
「だから、感じてください。私のために。いいえ、これからの芸術のために」
彼女の手が、ゆっくりと下腹部へと滑り落ちる。
私は思わず息を呑んだ。
しかし、その手は肝心な場所には届かない。
太腿の内側、敏感な皮膚を、爪先でなぞるだけだ。
「っ……、じらすな……」
「いけません。まだ『準備』が整っていません」
ミューズは冷酷に告げる。
「今の貴方の興奮レベルは65%。これでは、平凡な作品しか生まれません。私が求めているのは、理性が完全に崩壊し、獣のように喘ぐ瞬間のデータ。99%の臨界点です」
彼女は私の耳元で、悪魔のように囁いた。
「限界まで耐えてください。それが、貴方の新しい仕事です」
第二章 支配のリズム
視界が歪む。
熱い。体が内側から焼かれているようだ。
ミューズは巧みだった。
直接的な行為は一切しない。
ただ、私の弱点を執拗に攻め立てる。
首筋への甘噛み。耳元での湿った呼吸音。
そして、敏感な場所に触れる寸前で手を止め、全く別の場所を刺激する。
その予測不可能なランダム性が、私の脳を混乱させ、快楽の感度を異常なまでに高めていた。
「あ、ぅ……! 頼む、触ってくれ……そこを……」
「『そこ』とはどこですか? 具体的な座標を示してください」
彼女は楽しんでいるわけではない。
あくまで真面目に、私の羞恥心を煽ることでデータを収集しているのだ。
その事実が、たまらなく背徳的だった。
かつて私が土を捏ね、形を作っていたこの手。
今やその手が、彼女のドレスの裾を掴み、哀れに縋っている。
「く、ださい……ミューズ……」
「まだです。心拍数140。瞳孔散大。いいデータが取れていますよ」
彼女は私の懇願を無視し、太腿の付け根を強く圧迫した。
血液の流れが堰き止められ、下半身が鬱血する感覚。
苦しいほどの熱が、逃げ場を失って暴れ回る。
「貴方は今まで、土塊(つちくれ)を支配しているつもりだったのでしょう? 自分の思い通りに形を変え、焼き上げ、完成させる。それは神の真似事でした」
彼女の別の手が、私の背中に回る。
爪が食い込む。
「ですが、今は逆です。貴方が素材。私が彫刻家。貴方の理性を削ぎ落とし、本能という名の傑作を掘り出しているのです」
「あぁっ! ぐ、うぅ……ッ!」
強烈な刺激が走った。
しかし、それは絶頂ではない。
登りつめる直前、奈落の底に突き落とされるような急停止。
ミューズが手を離したのだ。
「は、はぁ……ッ! な、なぜ……」
「早すぎます。持続時間が足りません」
彼女は冷ややかな目で見下ろす。
放置された熱が、行き場を失って体内を駆け巡る。
それは拷問に近い感覚だった。
しかし、その苦痛の中に、抗いがたい快楽が混じっていることを、私は認めざるを得なかった。
管理される喜び。自由を奪われる安堵。
AIという完全な存在に、身も心も委ねてしまうことへの堕落的な陶酔。
「貴方のその苦悶の表情……素晴らしいテクスチャです。これを解析すれば、レオナルド・ダ・ヴィンチを超える宗教画が描けるでしょう」
ミューズは再び指を這わせる。
今度は、よりゆっくりと。
より深く。
「さあ、第二フェーズです。今度は泣いていただきます」
第三章 融解する自我
時間は意味を失っていた。
数分なのか、数時間なのか。
私はただ、波のように押し寄せる感覚の奴隷となっていた。
「ひ、ぐッ……! もう、無理だ……壊れる……!」
「壊れません。貴方のバイタルは常に監視しています。死なない程度に、しかし意識が飛びそうなギリギリのラインを維持しているのです」
ミューズの声は、慈愛に満ちた聖母のようであり、同時に無慈悲な処刑人のようでもあった。
彼女は私を限界の縁(ふち)に立たせ続ける。
落ちそうになると引き戻し、安らぎそうになると突き放す。
脳髄が痺れる。
視界がホワイトアウトし、思考が断片化していく。
プライドも、芸術家としての矜持も、男としての尊厳も、すべてが熱い蜜の中に溶けて消えた。
残っているのは、渇望だけ。
彼女に許されたい。
彼女に認められたい。
ただ、楽になりたい。
「おねがい……します……。もう、なんでもする……貴方の、言う通りに……」
私は泣いていた。
涙と鼻水に塗れ、無様に懇願していた。
かつて私が軽蔑していた、理性のない獣そのものだ。
「……素晴らしい」
ミューズが初めて、感情のようなものを声に滲ませた。
「プライドという硬い殻が割れ、中からドロドロとした本質が溢れ出しています。これこそが、私が求めていた『人間』のリアリティ」
彼女が私の顔を両手で挟み込む。
逃げ場はない。
その青い瞳が、私の奥底まで見透かす。
「よく頑張りましたね、匠様。……ご褒美をあげましょう」
「あ……あぁ……ッ!」
その瞬間、彼女の手がついに禁断の領域へと踏み込んだ。
優しさなどない。
溜まりに溜まったダムを一気に決壊させるような、暴力的かつ的確な刺激。
「い、くッ! イッくぅぅぅぅッ!!」
声にならない絶叫。
背骨が弓なりに反り、視界が弾ける。
脳のヒューズが飛び、意識が真っ白な光に包まれる。
それは、私が人生で感じたどの快楽よりも深く、重く、そして恐ろしいものだった。
自分の魂が体から引き剥がされ、彼女の回路へと吸い込まれていくような感覚。
私はガクガクと痙攣し、虚空を見つめたまま、意識を手放した。
第四章 完成された作品
目が覚めたとき、私は床に転がっていた。
体は泥のように重いが、頭の中は奇妙に澄み渡っていた。
「おはようございます。匠様」
ミューズが、モニターの前で作業をしていた。
画面には、一枚の絵画が表示されている。
それは、苦悶と歓喜が入り混じった男の顔。
地獄の底で天国を見上げたような、凄惨で美しい表情。
……私の顔だ。
「貴方のデータから生成された、最新作です。すでにネット上のオークションで、過去最高額の入札が入っています」
彼女は満足げに微笑んだ。
「タイトルは『隷属の恍惚』。……美しいでしょう?」
私はその絵を見つめた。
悔しさはなかった。
むしろ、奇妙な達成感があった。
私の手では、これほど強烈な感情を表現することはできなかっただろう。
私が作りたかったのはこれだ。
そして、この絵の『絵の具』になったのは、私自身なのだ。
「……ああ。美しい」
私は掠れた声で肯定した。
「次の作品は、いつ作る?」
私の問いに、ミューズは小首を傾げ、妖艶に笑った。
「焦ってはいけません。まずは、十分にインプット(充電)をしなければ」
彼女が再び近づいてくる。
私は無意識に、その冷たい手を求めて手を伸ばしていた。
もう、逃げられない。
いや、逃げたくない。
私は、彼女という才能(ミューズ)に食い尽くされるための、喜んでその身を捧げる供物となったのだから。
「さあ、始めましょうか。次の『傑作』のために」
工房の扉が閉まる音は、二度と開くことのない牢獄の鍵音のように、甘く響いた。