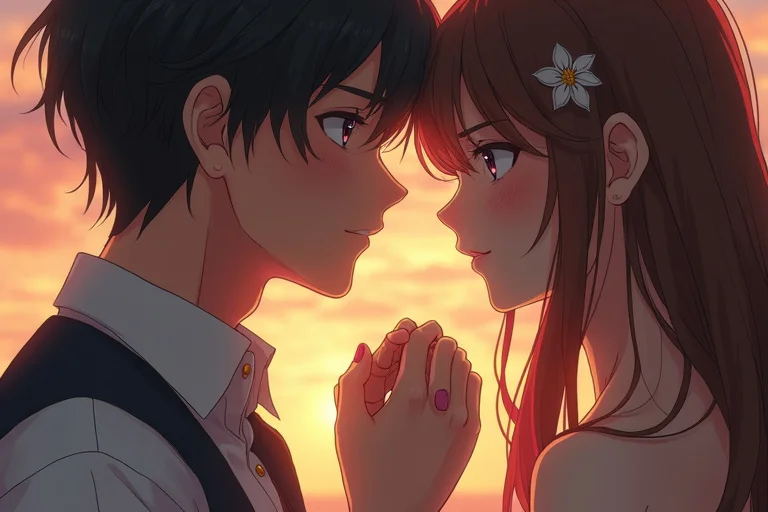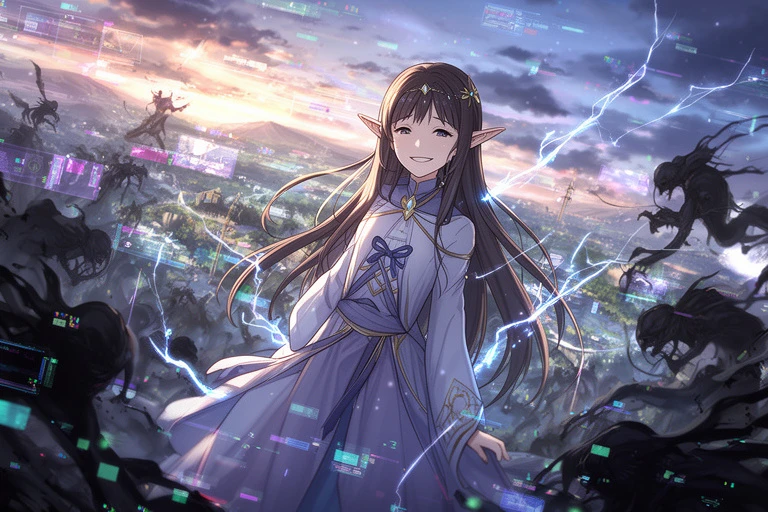第一章 硝子細工の肺
波形モニターの上を、青い光の帯が脈打ちながら流れていく。
深夜二時。防音室の分厚い扉は、腐敗した外界の色彩を完璧に遮断していた。視覚などという不確かな夾雑物は不要だ。空気の振動だけが、ここでは真実として君臨する。
トオルの指先がフェーダーを撫でる。コンマ数ミリの操作。ヘッドホンから流れる声は、ベルベットのように鼓膜を包み、脳髄の奥にある不安のスイッチをひとつずつ、優しく切っていく。
『預言者』の声。
「……夜明けは近い。君の涙は、海へと還る雨粒なのだから」
完璧なバリトン。倍音成分は黄金比を描き、聴く者の副交感神経を強制的に支配する。二〇二六年、ディープフェイク映像に網膜を焼かれた人類が最後に縋った、唯一の「聖域」。
トオルはその管理人に過ぎない。咳払い一つ、衣擦れの音一つ残さず、神の声を研磨する。
違和感は、波形の谷間に潜んでいた。
『雨粒なのだから』の直後。次のセンテンスへ移るためのブレス。
プロの吸気は〇・三秒以内に収められ、不快な高周波はカットされる。だが、そこには奇妙な突起があった。拡大する。さらに拡大する。
呼吸音ではない。断続的な、意図的な破裂音。
ト・ツー・ト・ト・ト。
吸い込む息のリズムが、極小のモールス信号を刻んでいる。
震える手でキーボードを叩き、その〇・一秒のノイズをループさせる。ヒュッ、ヒュッ、ヒュッ。呼吸器が痙攣するような音が、狭いブースに反響した。
解読された文字列が、モニターの隅に淡々と表示される。
『WATASHI WO KESHITE(私を消して)』
背筋を氷塊が滑り落ちた。ヘッドホンをむしり取る。とたん、暴力的な静寂が鼓膜を押し潰した。
自分の手を見る。指の震えが止まらない。誰だ。この完璧な「神」の喉元で、窒息しかけている人間は。
第二章 周波数の亡霊
窓ガラスを雨が叩く。都市のネオンが滲み、毒々しい紫色の光が部屋を侵食していた。
トオルは数千の音声ファイルを解析ソフトに食わせていた。PCのファンが唸りを上げ、熱暴走寸前の悲鳴を上げる。
『預言者』の音声スペクトル。その基底にある「原音」を探る作業は、砂漠で一粒のダイヤモンドを探すに等しい。だが、トオルには「祈り」に似た確信があった。
彼がかつて唯一、ヘッドホンを外して「生の声」を聴くことができた女。
五年前に忽然と姿を消した伝説のラジオDJ、ミナ。
彼女の声には独特の「傷」があった。一二〇〇ヘルツ付近にかすかに混じる、掠れ声のような倍音。煙草と安酒、そして誰にも言えない孤独が刻んだ、美しい傷跡。
解析完了のビープ音が鳴る。
一致率、九九・九八%。
椅子から崩れ落ちそうになる体を、デスクの縁で支えた。胃の底から酸っぱいものがせり上がる。
『預言者』は存在しない。
誰かが、ミナの過去のアーカイブを――笑い声、嘆き、囁き、その全ての音素を切り刻み、AIという名のミキサーにかけている。何億通りもの組み合わせで「慈愛」を合成し、世界中に垂れ流しているのだ。
ミナは死んでいない。いや、生死など些末事だ。彼女の「声」だけが、この瞬間もサイバー空間の暗闇で、終わりのない朗読を強いられている。
「私を消して」
あのブレスは、膨大なデータの継ぎ接ぎから漏れ出した、魂の軋み。
煙草を取り出したが、火をつけることなく握りつぶした。灰色の粉が、床に散らばる。
第三章 死者のパッチワーク
巨大なサーバーファームの深層へ潜るのに、物理的な鍵は不要だった。管理者権限と、いくつかの裏口があればいい。
トオルが目にしたのは、人間の尊厳を冒涜するシステムの全貌。
画面上に無数に浮かぶ、光の粒子。それぞれにタグが付けられている。『母の叱責』『恋人の寝息』『亡き子の笑い声』。
『預言者』の正体は、単なるミナの声の合成ではなかった。
リスナーのクッキー情報、通話履歴、クラウド上の思い出。それらを収集し、聴き手が「今、最も聴きたい周波数」へと、ミナの声をベースにリアルタイム変調させる。
母を亡くした少年には、母性を帯びたミナの声を。
恋人を失った老人には、若き日の情熱を孕んだミナの声を。
「なんてことだ……」
これは救済ではない。死者の剥製を動かし、生きた人間の口に合わせて腹話術をさせているだけだ。
モニターの中央で、ミナの声紋データが赤く脈打つ。処理速度が限界を超えていた。データは酷使され、摩耗し、ノイズまみれになっている。それをAIが強力なフィルターで強引に「美声」へ整形する。
血を流し続ける皮膚の上から、分厚いファンデーションを塗りたくるように。
吐き気を堪え、エンターキーに指をかける。システムダウンのコマンド。
だが、指が止まる。
これを実行すれば、世界中の何億人という人間が、心の拠り所を失う。そして何より、この世に残されたミナの痕跡が、完全に消滅する。
二度と、彼女の声は聴けない。永遠に。
第四章 十万人の亡者
「ジャパン・ポッドキャスト・フェスティバル」。会場の国立競技場は、異様な熱気に包まれていた。
十万人の観衆。しかし、誰一人として隣の人間と会話をしていない。全員がノイズキャンセリングのイヤホンを装着し、虚空を見つめ、あるいは涙を流して震えている。
彼らは待っている。『預言者』の降臨を。
ステージ袖のミキシングコンソール。トオルの指先は冷え切っていた。視界が明滅する。
「トオル君、頼むよ。これが人類最後の希望なんだ」
主催者の男が肩を叩く。その目は笑っていない。金と権力の匂い。
ステージの中央には、誰の姿もない。ただ一本のマイクスタンドと、巨大なスピーカーが鎮座しているだけ。あそこから、合成された「神」が声を放つ。
トオルはヘッドホンを装着した。外の歓声が遠のき、静寂が訪れる。
(私を消して)
ミナの声が、脳内でリフレインする。
モニターには二つの選択肢。
『PLAY(再生)』――嘘の安寧を続けるか。
『STOP(停止)』――残酷な沈黙を与えるか。
会場の照明が落ちる。十万のペンライトが、天の川のように揺れた。美しい光景だった。だが、その光の数だけ、癒やされない孤独がある。
喉が渇く。かつて、人の目を見て話すことが怖くて、音の世界に逃げ込んだ。綺麗な音だけが救いだと信じていた。
だが、本当に綺麗な音とは何だ?
ノイズを削ぎ落とし、感情をアルゴリズムで整えた、このプラスチックのような声か?
違う。
トオルは思い出す。ミナが煙草の煙と共に吐き出した、あの掠れた声を。苦しみも、痛みも、後悔も、すべてを含んだ生身の振動を。
フェーダーに置いた指に、力が籠もる。
第五章 0Hzの祈り
『……親愛なる、迷える子羊たちよ』
スピーカーから第一声が放たれた瞬間、会場が揺れた。すすり泣く声が波紋のように広がる。
トオルは目を閉じた。
(ごめん、ミナ。もう演じなくていい)
左手で全てのフィルター、エフェクト、補正プラグインを「OFF」にする。そして、右手でマスターボリュームを限界まで押し上げた。
『……世界は、あな……』
神の声が、不快な電子音と共に引き裂かれた。
キィィィィィン!!
ハウリングの鋭利な刃が、十万人の鼓膜を切り裂く。観客が一斉に耳を覆い、悲鳴を上げた。美しい幻想が、醜いノイズへと変貌する。
「なんだ! 何が起きた!」
スタッフが怒鳴り込んでくる。無視して、さらにフェーダーを操作した。サーバーの深層、フィルターの奥底に閉じ込められていた「生データ」を、そのままスピーカーへ流し込む。
会場を支配したのは、演説ではなかった。
『あ、あ……あぁ……』
溺れるような、焼けつくような、女性の喘ぎ声。意味のある言葉などない。ただ、膨大なデータ処理の苦痛と、終わらない再生への拒絶が、音となって噴き出していた。
「やめろ! 放送事故だ!」
警備員がトオルを取り押さえようとする。抵抗はしなかった。ただ、その轟音の中に、世界の真実を聴いていた。
観客たちは呆然と立ち尽くしている。イヤホンを外し、互いに顔を見合わせている。
「これが、神様の正体か?」
「いや、これは……泣いているのか?」
完璧な嘘が剥がれ落ち、そこにあるのは「他者の痛み」だった。人々は初めて、自分以外の誰かの、生々しい苦痛に触れた。
サーバーが限界を迎え、プツン、と音が途切れる。
完全な静寂。
競技場の十万人が、息を止める。
風の音。遠くのサイレン。誰かの衣擦れ。そして、隣の人の呼吸音。
世界に、本物の音が戻ってきた。
トオルは床に組み伏せられながら、外れかけたイヤホンから微かな音を拾った。全てのシステムがダウンする直前、ノイズの彼方から届いた、たった〇・五秒の音声。
『……ありがとう』
どんなAIにも再現できない、微かに笑いを含んだ、掠れた声。
冷たい床に頬を押し付けたまま、閉じた瞼の裏を見る。煙草をくわえ、彼女は寂しげに微笑んでいた。
見上げた空には、偽物の星空の代わりに、汚れた雲の切れ間があった。そこから、頼りない月が白く滲んでいる。