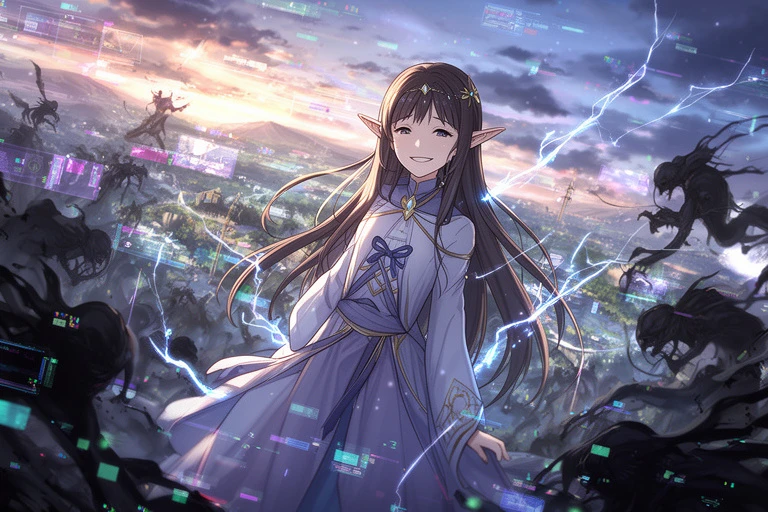第一章 画素数(ピクセル)の欠けた森
「はーい、みんな元気? 今日も『エモシオーネ』の朝は最高にキラキラしてるよっ! ふわりんだよ〜!」
私は口角を限界まで引き上げ、一オクターブ高い声を喉から絞り出した。
目の前には、薄青く発光する水晶――『想念石』が浮いている。
作り込んだ笑顔。
完璧な角度の首の傾げ方。
前世、ブラック企業で身につけ、配信者として磨き上げた「愛想笑い」の仮面は、異世界に転生しても顔にへばりついたままだ。
「見て見て、この朝露! まるで宝石みたいでしょ?」
指差したのは、巨大なシダ植物の葉。
その先端で震える水滴は、確かに美しかった。
――ザザッ。
一瞬、視界の端が歪んだ。
シダの葉の輪郭がブレる。まるで、画質の悪い動画が読み込み不良を起こしたときのように、緑色が四角いブロック状に崩れて明滅した。
奥歯のあたりで、キーという耳鳴りが響く。
(……まただ。最近、頻度が増えてる)
私は笑顔を貼り付けたまま、吐き気を飲み込む。
この世界『エモシオーネ』は、美しすぎるがゆえに脆い。
「ルルリアお姉ちゃん、何してるの?」
背後から、遠慮がちな声がした。
村の少年、ティムだ。
振り返った瞬間、私の網膜に色彩が飛び込んでくる。
ティムの心臓のあたりに、柔らかなオレンジ色の光が灯っていた。
それは、焚き火のような温かさを帯びた『好意』の色。
言葉よりも雄弁なその光を見て、私は反射的に目を細める。
「あ、ティムくん! 今はね、遠くのお友達にこの綺麗な景色を送ろうと思って」
私は「ふわりん」のまま、鈴を転がすような声で嘘をついた。
途端に、ティムの胸元のオレンジ色が、泥を垂らしたように濁った灰色へと変色した。
ザラついた、不信の色。
「……お姉ちゃん、なんか変だよ? 笑ってるのに、顔が泣いてるみたい」
心臓が早鐘を打つ。
子供の直感は、鋭すぎて痛い。
その時だ。
私の手の中にある『想念石』が、ブブブ、と不快に振動し始めた。
石の表面から黒いタールのような液体が滲み出し、私の指を汚していく。
「きゃっ!」
焼き付くような熱さに、思わず石を取り落とす。
地面に落ちた石は、どろりと溶け、触れた草花を一瞬で茶色く枯死させてしまった。
「あーあ……また『バグ』っちゃった」
私は冷めた目で、色を失っていく花を見つめた。
この世界は、純粋な感情を魔力とする。だから、私が嘘という異物を混ぜ込むたびに、世界は消化不良を起こして壊れていくのだ。
第二章 ノイズ混じりの魔物
キィィィィン――。
不快な高周波音が鼓膜を突き刺した。
鳥のさえずりが途絶え、風がピタリと止む。
森の奥の闇が、不自然に膨れ上がった。
木々の隙間から這い出してきたのは、獣ではない。
空間そのものが抉り取られたような、真っ黒な穴。
その輪郭は絶えずギザギザと波打ち、視界に入れるだけで平衡感覚が狂いそうになる。
『感情の澱(オリ)』。
この世界が生み出した、エラーの塊。
「う、うわぁぁん!」
ティムが悲鳴を上げて私の腰にしがみつく。
彼の胸元から発せられる光が、恐怖を示す真っ青な冷気となって私の肌を刺した。
(守らなきゃ)
そう思うのに、足がすくむ。
歪みながら迫りくる黒い塊が、前世の記憶とオーバーラップしたからだ。
深夜のオフィス。
鳴り止まない通知音。
『君、もっと上手く笑えないの?』と見下ろす上司の目。
澱の表面に浮かぶ歪んだ模様が、私を嘲笑う無数の顔に見える。
あれは、私が飲み込み続け、腹の底に溜め込んできた「言葉にならなかった叫び」の集合体だ。
「……嫌だ、来ないで」
後ずさりする私の首元で、ネックレスにしていた『ウェブカメラ』が熱を持った。
前世からの唯一の持ち物。壊れて動かないはずのレンズが、今は私の命綱のように思えた。
「ルルリア、癒やしの魔法を!」
「聖女様、お願いだ!」
村人たちの声が遠くで聞こえる。
彼らは私に期待している。「ふわりん」という完璧な聖女の奇跡を。
そうだ、私はこの世界でも演じ続けなきゃいけない。
期待に応えなきゃ、居場所なんてないんだから。
「き、綺麗な光よ……悪戯っ子を叱って!」
震える手で杖を構え、いつもの配信のように叫ぶ。
けれど、杖の先から放たれたのは、美しい光ではなかった。
バチバチッ! ギャリギャリ!
ガラスを爪で引っ掻いたような音が響き、杖から紫色の稲妻が奔る。
それは魔物を傷つけるどころか、周囲の空間をさらに狂わせた。
空の色が、毒々しい蛍光グリーンへと変色していく。
「嘘……どうして」
黒い塊が、ドクンと脈打った。
私の「嘘」が、敵にエサを与えてしまったのだ。
不協和音が大きくなる。世界が、崩壊していく。
第三章 仮面を割る音
魔物が、鎌首をもたげるように頭上へ覆いかぶさる。
逃げ場はない。
「ごめんなさい、ごめんなさい……!」
私はティムを抱きしめ、地面にうずくまった。
死ぬ。また、私は何もできずに、誰かの期待を裏切って終わるんだ。
その時。
首元のウェブカメラが、カチリと音を立てた。
レンズカバーが開き、黒い瞳のようなレンズが私を至近距離で捉える。
そこに映っていたのは、もはや「ふわりん」ではなかった。
恐怖で目を見開き、鼻水を垂らし、顔をくしゃくしゃに歪めた、ただの天道花咲。
(撮らないで……こんな、情けない顔)
誰にも見せたくない。
幻滅されたくない。
でも――。
レンズに映るその顔は、今までで一番、生々しく「私」だった。
『……これが、私だ』
ふと、心の奥底で張り詰めていた糸が、プツンと切れる音がした。
他人の顔色を伺い、評価を気にし、完璧を演じてきた糸。
それが切れた瞬間、腹の底から熱い塊がせり上がってきた。
「……うるさいんだよ、バカ野郎ッ!!!」
私は叫んだ。
作られたアニメ声じゃない。喉が裂けそうなほど低く、しゃがれた、本音の咆哮。
「私は聖女じゃない! スローライフなんてクソくらえだ! 虫は怖いし、トイレはないし、毎日不安で、寂しくて、本当は誰かに『よく頑張ったね』って頭を撫でて欲しかっただけなんだよ!!」
涙がボロボロと溢れ出し、化粧が汚く崩れていく。
もう、どう思われたっていい。止められない。
「仕事も、配信も、転生しても……ずっとずっと、演じてばっかりで……疲れたんだよぉぉッ!」
その瞬間。
私の首元のウェブカメラが、まばゆい光を炸裂させた。
それは魔法の光ではない。
私の内側から溢れ出した感情が、カメラという触媒を通して質量を持ったのだ。
光の色は、虹色。
喜びも、悲しみも、怒りも、全てが混ざり合った「真実」の色。
衝撃波となって広がったその光は、迫りくる黒い靄を真正面から飲み込んだ。
ギザギザの輪郭が溶け、不快なノイズが優しい風の音へとかき消されていく。
世界が、深呼吸をするように正常な色を取り戻していく。
蛍光グリーンの空が、本来の澄み渡るような青空へと塗り替えられる。
バグっていたシダの葉が、鮮明な緑を取り戻し、瑞々しい香りを放ち始めた。
魔物だった黒い塊は、光の中でほどけ、無数の白い蝶となって空へ昇っていく。
それはまるで、私がずっと抱え込んでいたストレスが、ようやく成仏したかのようだった。
「……え?」
私は呆然と、自分の手を見つめた。
そこには、泥のように濁っていたはずの『想念石』が、透き通るような輝きを取り戻し、静かに脈打っていた。
最終章 ただいま、私
あれから、私の生活は一変した。
「ルルリア、今日のスープ、ちょっと焦げてないか?」
「文句あるなら自分で作りなよ、ティム。これでも苦労したんだから」
「へへ、でもなんか、母ちゃんの味に似てて美味いよ!」
村の広場で、私は大鍋をかき混ぜている。
かつてのような「映える」料理じゃない。野菜は不揃いだし、盛り付けも適当だ。
服だって、ドレスじゃなくて動きやすい麻の服。
でも、鍋を囲む村人たちの胸には、揺るぎない温かなオレンジ色の光が灯っている。
私の胸の奥も、もう冷たくない。
世界のバグは消えた。
私が「完璧」を演じるのをやめたから、世界も「完璧な楽園」である必要がなくなったのだ。
私はエプロンで手を拭き、首元のウェブカメラを手に取った。
もう、これはただのアクセサリーだ。
でも、私にとっては大切なお守り。
私はカメラを夕焼けの空にかざした。
ここには、私の汚い部分も、弱い部分も知った上で、名前を呼んでくれる人たちがいる。
「ふわりん」はいなくなったけれど、私はここにいる。
「……聞こえるかな」
私は空の向こう、遠い記憶の中にある故郷へ向かって、小さく呟いた。
「ただいま。やっと、本当の自分になれたよ」
風が吹き抜け、木々がざわめく。
その音は、まるで「おかえり」と答えてくれているようだった。
***
地球。
とある深夜のワンルームマンション。
疲れ果てて眠りについた元ファンのスマートフォンの画面が、一瞬だけノイズ交じりに発光した。
画面には何も映っていない。
けれど、彼は夢の中で確かに聞いた気がした。
泥だらけで、くしゃくしゃの笑顔で笑う少女の、「幸せだよ」という声を。
彼は寝言で小さく「よかった」と呟き、その夜は久しぶりに深く安らかな眠りについた。