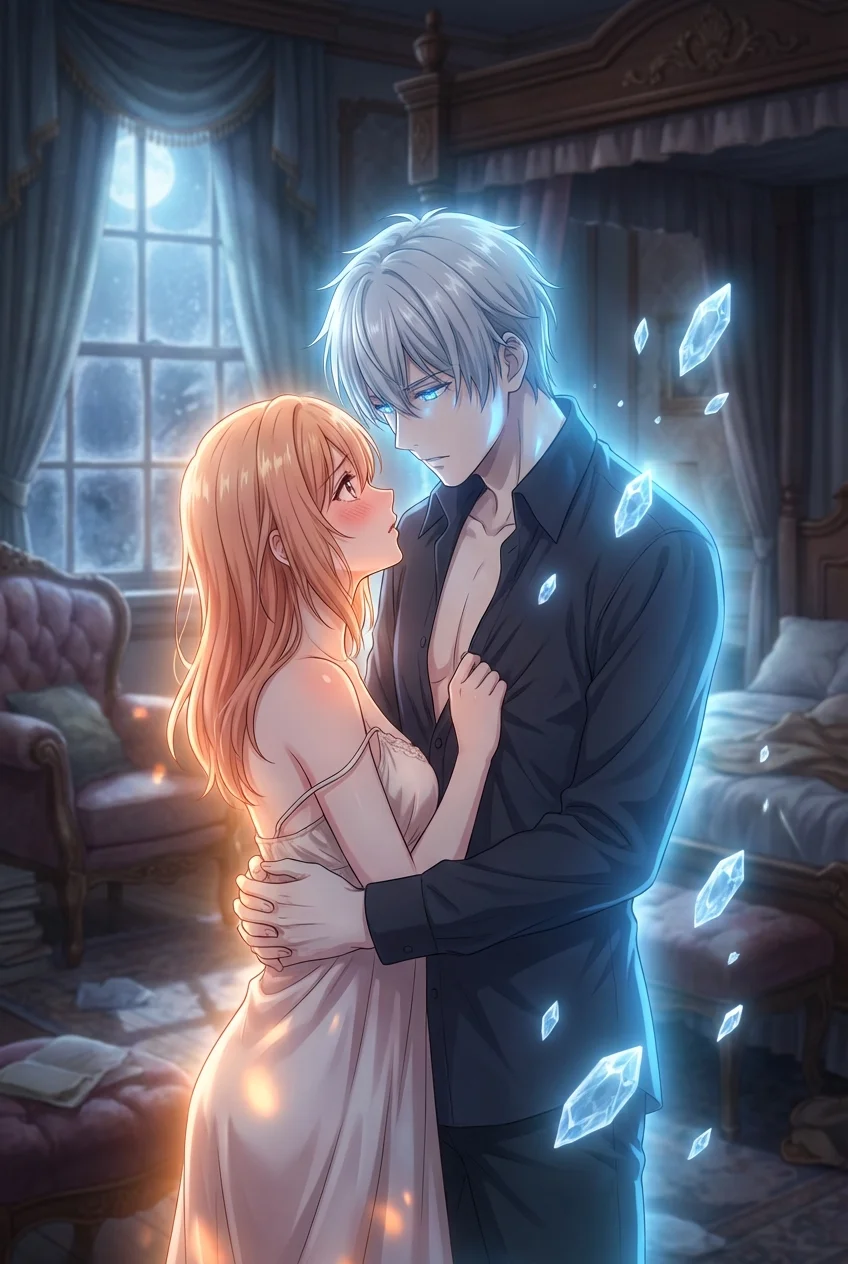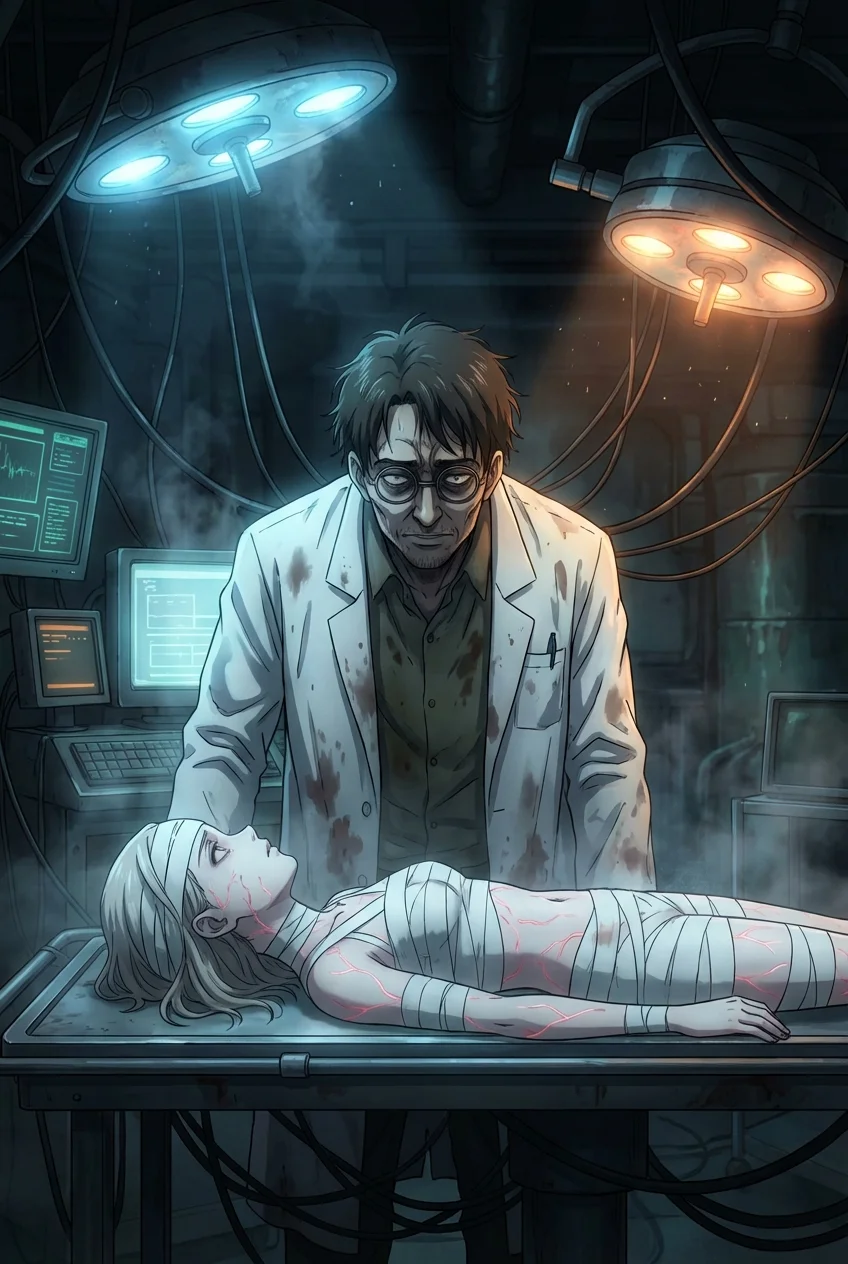第1章: 硝子の雨、断絶の音
アスファルトを叩きつける豪雨が、世界から色彩を剥ぎ取っていた。
足元には、ふやけた紙片が一枚。かつて「離婚届」と呼ばれたそれは、いまやインクが滲み、泥水の中で意味を失ったパルプの死骸に過ぎない。
傍らには、キャスターの壊れたトランクが一つ。
桐生美緒(32)。それが彼女の人生の総重量だった。
「ごめんね、美緒。君は、石女(うまずめ)だから」
夫の言葉は、鋭利なナイフではなく、錆びたハンマーのように彼女の子宮を、尊厳を、未来を粉砕した。
痛みはない。ただ、内臓をくり抜かれたような欠落感だけが、冷たい雨と共に皮膚を浸透していく。
私は、壊れた家電と同じ。
機能不全なら廃棄される。それは資本主義の路地裏では、至極真っ当な理屈に思えた。
突如、ヘッドライトの閃光が網膜を白く焼き尽くす。
水飛沫をあげて停車したのは、闇夜に溶け込むような漆黒のセダンだった。
パワーウィンドウが音もなく滑り降りる。
雨の匂いを瞬時に駆逐する、白檀と冷たい金属の香り。
「君」
低く、チェロの弦を指で弾いたような声。
美緒が顔を上げると、そこには不遜な美貌があった。色素の薄い瞳が、雨に濡れた野良犬を見るような、あるいは美術品の贋作を鑑定するような眼差しで射抜く。
男は車を降りる。傘もささず、仕立ての良いスーツを躊躇なく濡らし、美緒の目前に立った。
長い指が伸びる。
涙と雨でぐしゃぐしゃになった頬に触れるかと思いきや、彼はその指先を、震える唇の端に滑らせた。
体温を感じないほど冷たい指。
「……っ」
美緒が息を呑むと、男は口角をわずかに上げた。愉悦ではない。壊れた玩具のバネを弾く子供のように。
「いい音で壊れているね」
雨音すらも圧する声は、鼓膜ではなく脳幹に直接響く。
「俺が君を、一から組み直してやる」
彼は濡れたトランクを一瞥もしない。美緒の顎を強い力で掴み、視線を固定させる。
「ただし、拒否権はない。拾われた瓦礫に、選択肢があると思うなよ」
その手は救済者の温もりなど微塵も含んでいない。
だが、美緒の凍りついた心臓は、恐怖と、そして理解不能な安堵によって、早鐘を打ち始めていた。
第2章: 蜜の檻、空白の夜
神宮寺蓮の住まいは、生活の匂いが徹底的に排除されていた。
無機質なコンクリートの壁、間接照明の青白い光。深海に沈められた実験室だ。
「服を脱げ」
絶対の命令。
浴室に充満する湯気の中、蓮はシャツの袖を捲り上げ、無防備に晒された美緒の肌に海綿スポンジを滑らせる。
きゅ、きゅ、と吸い付くような感触。
首筋から背骨、腰のくびれ、そして太腿の内側へ。
「力を抜け。筋肉が強張っていると、神経の伝達が鈍る」
彼の指先が、うなじの産毛を逆撫でるように這う。
ただ洗われているだけだ。性的な意味などないはずだ。
それなのに、視界を白いタオルで塞がれた美緒の体内で、得体の知れない熱が燻り始める。
視覚を奪われる恐怖は、すぐに倒錯した快楽へと変質した。
スポンジの重み、シャワーの水圧、不規則な吐息。
増幅された情報が、脳髄を直撃する。
「次は食事だ」
バスローブ一枚で椅子に座らされる。目隠しはされたまま。
冷たい銀のスプーンが唇に触れる。口を開けると、温かいスープが舌の上を流れた。
「味わえ。喉を通る熱さを、胃に落ちる重さを」
耳元で囁かれる声は、咀嚼を促す命令でありながら、甘美な呪文のようだった。
ごくり、と飲み込むたびに喉が鳴る。その下品な水音さえも、蓮は聞き逃さない。
「いいぞ。その反応だ」
彼は美緒の耳たぶを、親指と人差し指で挟み、じわりと圧をかけた。
電流が走ったかのように、美緒の背筋が跳ねる。
「な、にも……してないのに……」
美緒は浅い呼吸を繰り返す。
夫との生活では、情事の最中でさえ感じたことのない痺れが、指先から末端へと広がっていく。
管理されている。支配されている。
その事実が、彼女の責任を、思考を、自我を溶かしていく。
何も考えなくていい。ただ、彼に与えられる感覚だけを貪ればいい。
それは思考停止という名の、極上の麻薬だった。
第3章: 錆びた鎖、断裂の時
平穏は、チャイムの音一つで粉々に砕け散った。
玄関のモニターに映っていたのは、元夫。
離婚届を出した後、彼の中で何かが変わったらしい。あるいは、蓮の手によって磨き上げられ、内側から発光するように艶めいた美緒の姿をどこかで見かけ、歪んだ所有欲を再燃させたのか。
「美緒! いるんだろう! 話がある!」
インターホン越しに響く怒声。美緒の膝が震え、床に崩れ落ちそうになる。
古傷が疼く。罵倒の記憶がフラッシュバックし、胃の腑が冷たく縮み上がる。
助けて。
美緒は縋るような目で蓮を見上げた。
蓮は動かない。
ワイングラスを揺らし、冷徹な瞳で美緒を見下ろすのみ。
「開けてやれ」
「……え?」
「彼が誰のものか、選ばせてやろうと言っているんだ」
蓮の声には、慈悲も加護もない。あるのは実験動物を見る観察者の冷たさだけ。
彼は背を向け、ソファに深々と腰掛けた。
「自分で這い上がれないなら、君は一生、誰かの玩具だ。あの男の元へ戻りたければ、好きにしろ」
突き放された。
信頼という名の細い糸が、ぷつりと切れる音。
彼は私を守ってくれるわけじゃない。私が「壊れたまま」なら、興味を失うだけ。
美緒は震える足で玄関へ向かう。
ドアを開けると、湿った外気と共に、元夫の汗ばんだ手が伸びてきた。
「やっぱりここにいたか。帰るぞ、美緒。お前みたいな欠陥品、俺以外に誰が面倒見きれるって言うんだ」
その手は温かかった。けれど、それは腐った沼のような、不快な生温かさ。
蓮の冷たい指先とは違う。
ここは地獄だ。でも、振り返った先にいる蓮は、こちらを見てもいない。
私は、一人だ。
世界中のどこにも、足場なんてなかったのだ。
第4章: 崩壊、あるいは覚醒
元夫の手が、美緒の二の腕を掴んだ瞬間だった。
「……っ、う……!」
喉から言葉にならない嘔吐感がせり上がる。
生理的な拒絶。細胞レベルでのNO。
彼女は反射的にその手を振り払い、その場に膝をついて胃の中身をぶちまけた。
「なっ、なんだお前!?」
後ずさる元夫。
美緒は涙と胃酸に塗れながら、激しく咳き込んだ。汚い。汚らわしい。
かつては「日常」だったその男の気配が、今は耐え難い悪臭のように感じられる。
「触らないで……!」
美緒は叫んだ。人生で初めて吐き出した、純粋なエゴの咆哮。
「いい妻」の仮面が、音を立てて割れた瞬間だった。
その時、背後で硬質な足音が響いた。
「合格だ」
蓮が立っていた。
彼は元夫を冷ややかな一瞥だけで射殺すように威圧し、低く告げる。
「俺の所有物に触れた代償は、弁護士を通じて請求する。消えろ」
扉が閉ざされる。世界が、再び二人だけになる。
蓮は床に這いつくばる美緒の前に膝をつき、汚れた口元を自身のハンカチで乱暴に拭った。
「よく耐えた。ご褒美に、もう二度とあんな男を思い出せないようにしてやる」
彼は美緒を抱き上げ、寝室へ運ぶ。
ベッドに放り出された美緒の身体は、高熱を出したように火照っていた。
「蓮、さん……」
「喋るな。感じるだけでいい」
蓮は服を脱がない。美緒の衣服だけが引き裂かれるように剥ぎ取られ、純白のシーツの上に晒される。
挿入など、必要なかった。
彼の冷たい指先が、熱を帯びた秘所に這う。
「あっ、ぁ……!」
与えられたのは愛撫ではない。秩序ある蹂躙だ。
敏感な突起を執拗に弾かれ、美緒の背中が弓なりに反る。
「ここか? 随分と濡れているな。口では嫌がっても、身体は正直だ」
蓮の指が、蜜に濡れた花弁をこじ開け、最奥の柔らかな襞を容赦なく抉る。
ぐちゅ、と卑猥な水音が静寂な部屋に響き渡った。
「ひっ、だめ、おかしく、なる……っ!」
「おかしくなれ。理性のタガなど外してしまえ」
指の動きが加速する。粘膜を擦り上げる絶妙な圧力。
快楽は波ではなく、津波となって押し寄せた。
過去の古傷、元夫の言葉、自分を卑下する心――それら全てが、圧倒的な感覚の洪水に飲み込まれ、上書きされていく。
視界が白く明滅し、焦点が合わない。
涎が口端から零れ落ちるのも構わず、美緒はただ獣のように喘いだ。
「イくなら俺の許可を得ろ。まだだ」
絶頂の寸前で動きを止められ、焦らされる。
その拷問めいた空白が、さらなる蜜を溢れさせる。
「お願い、許して、蓮さま、蓮さまぁ……ッ!」
懇願する声を聞き届け、彼が深く、鋭く穿った瞬間。
美緒の脳内で銀河が弾けた。
「あ、あ゛っ――!!!」
激しい痙攣が全身を駆け巡る。身体中の筋肉が硬直し、目の前が真っ白に染まる。
彼女は初めて、他人の名を叫んで果てた。
貞淑な妻の抜け殻は置き去りにされ、そこにはただ、彼に快楽を貪らされるためだけに生まれた、あられもない雌の姿があった。
第5章: 瓦礫の上の戴冠式
翌朝、カーテンの隙間から差し込む光は、暴力的なまでに鮮やかだった。
美緒は目覚める。
昨夜の記憶は、熱病のように、しかし焼き印のように鮮明に肌に残っていた。
隣には蓮が眠っている。その寝顔は、独裁者の休息のように静謐だった。
自分の手を見る。
そこにはもう、見えない手錠は嵌められていない。
代わりに、魂の深淵に、彼という絶対的な楔が打ち込まれていた。
蓮が目を開ける。
彼は起き上がると、サイドテーブルから小さなビロードの箱を取り出した。
ロマンチックな演出などない。それを美緒の指に、所有印を押すように嵌める。
「これは契約だ」
蓮は美緒の手を取り、その甲に唇を寄せる。
それは騎士の誓いであり、看守の宣告。
「君は、俺なしでは呼吸もできないように作り変えられた。そして俺も、君が崩れ落ちる瞬間の美しさなしでは、この退屈な世界に耐えられない」
対等ではない。健全でもない。
けれど、その歪な空洞にこそ、二人の愛はぴったりと嵌まり込んだ。
「誓え。君の全てを俺に捧げると」
美緒は微笑んだ。かつての人形のような笑みではない。
官能と依存を煮詰めた、とろけるような蕩けた瞳で。
「はい。私のすべては、あなたのものです」
彼女は蓮の首に腕を絡ませる。
瓦礫の中から救い出された淑女は、自ら望んで、この甘美な暴君の指先に溺れていくことを選んだのだ。
窓の外、雨上がりの空はどこまでも青い。
だが二人が堕ちた沼は、永遠に甘い湿り気を帯び、底なしの闇で二人を抱き留めていた。