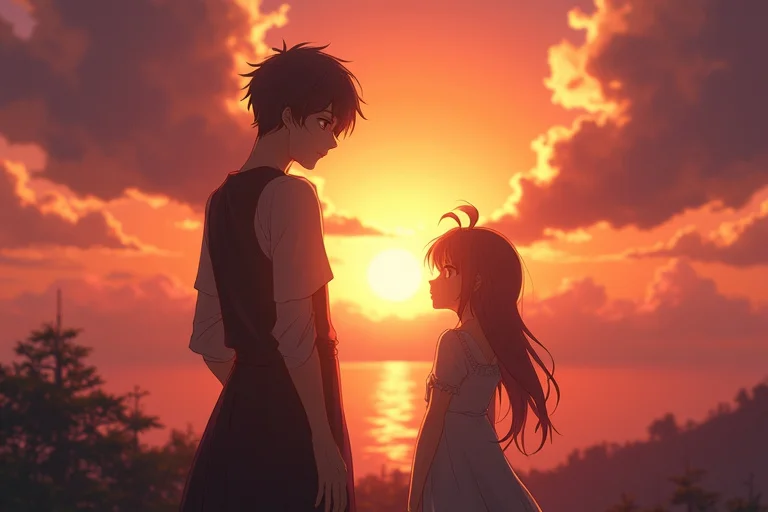第一章 硝子の欠片と無気力な日々
その街では、時折、空から記憶が降ってきた。
人々が忘れた記憶は、硝子のように透き通った結晶となり、はらはらと舞い落ちるのだ。それは雪のようにも、桜の花びらのようにも見えたが、地面に触れても溶けることも朽ちることもない。人々はそれを「記憶結晶」と呼んだ。
俺の仕事は、その結晶を掃除することだ。夜明け前、まだ街が深い眠りについている時間に、特殊な箒と塵取りを手に、石畳の道を巡回する。人々が踏み砕いてしまわぬように。そして、誰かがうっかり他人の記憶に触れてしまわぬように。
結晶に触れると、持ち主が忘れた記憶が奔流となって流れ込んでくる。大抵は、どうでもいい記憶だ。「昨日の夕食の献立」や「買い忘れた石鹸の種類」。そういった些細な日常の欠片は、淡い光を放ち、拾い上げるとすぐに塵となって消える。
だから俺は、この仕事を気に入っていた。誰とも深く関わらず、ただ静かに、消えゆくものを処理する。感情の波風が立たない、凪いだ水面のような日々。それこそが、俺の望む全てだった。過去に何を失ったのかさえ思い出せない俺にとって、他人の記憶など、ただのゴミでしかなかったからだ。
その日も、俺はいつも通り、薄紫色の夜空の下で作業をしていた。街灯がぼんやりと照らす石畳の上に、いくつもの結晶が煌めいている。箒でそっと掃き集め、塵取りで掬い上げる。その、単調で心地よいリズム。
不意に、路地の奥でひときわ強い光が明滅するのが見えた。それは、今まで見たこともないような輝きだった。普段目にする結晶の、白や水色の淡い光ではない。まるで、溶かした琥珀に夕陽を閉じ込めたかのような、深く、温かい橙色。
好奇心という、久しく忘れていた感情に突き動かされ、俺は路地へと足を踏み入れた。光は、古びた噴水の縁で、まるで主を待つかのように静かに佇んでいた。大きさは小指の先ほど。複雑な幾何学模様が内部で明滅し、微かに、鈴を鳴らすような心地よい音色を響かせている。
俺は、自分が手袋を嵌めているのも忘れ、思わずその結晶に手を伸ばしていた。こんなに強く、鮮やかな記憶は、きっと持ち主にとって、かけがえのない宝物だったに違いない。なぜ、こんなものが忘れられてしまったのか。
指先が触れる、その瞬間。俺は自分の過ちに気づいたが、もう遅かった。
第二章 温かい光の在り処
指先から脳髄へと、灼熱の奔流が駆け巡った。それは暴力的な侵入ではなく、むしろ、凍てついた心臓を優しく解かすような温もりだった。
――視界に広がったのは、柔らかな陽光が差し込む部屋。テーブルには湯気の立つシチューが並び、数人の男女が笑い合っている。暖炉の火がぱちぱちと音を立て、壁に掛けられた古時計が穏やかに時を刻んでいた。その光景の中心には、栗色の髪をした一人の少女がいた。彼女は満面の笑みで、向かいに座る父親らしき男の頬に、シチューのソースを悪戯っぽくつけている。母親らしき女が、呆れたように、けれど慈愛に満ちた眼差しでそれを見守っている。笑い声。食器の触れ合う音。シチューの芳しい香り。幸福という概念をそのまま形にしたような、完璧な時間。
「…っ!」
俺は弾かれたように手を引いた。心臓が激しく鼓動し、呼吸が乱れる。額には汗が滲んでいた。あの温もり、あの光景は、俺がとうの昔に失くしてしまった何かを、容赦なく突きつけてくる。
俺は慌てて結晶を特製のポーチにしまい込むと、その場を逃げるように走り去った。頭の中で、あの家族の笑い声が木霊する。忘れなければ。これは俺の記憶じゃない。他人の幸福を覗き見て、感傷に浸るなど、最も愚かしい行為だ。
だが、その日から、俺の世界は静かに変容し始めた。街を歩けば、あの記憶の持ち主を探してしまう自分がいた。あの栗色の髪の少女は、今、どうしているのだろうか。なぜ、あんなにも温かい記憶を失くしてしまったのだろう。
数日後、俺は彼女を見つけた。広場で鳩に餌をやっていた少女。記憶の中で見たよりも少しだけ大人びていたが、あの屈託のない笑顔は変わらなかった。彼女の名前はリナというらしく、花屋で働いていることを知った。
俺は客を装って、何度も彼女の店に通った。他愛もない会話を交わすうち、彼女が明るく、誰にでも優しい少女であることが分かった。だが、その完璧な明るさの裏に、時折、ふっと表情が抜け落ちたような、深い空虚が見え隠れするのに気づいてしまった。まるで、心の最も大切な部分に、ぽっかりと穴が空いているかのように。
ある雨の日、店先で雨宿りをしていると、リナが温かいハーブティーを差し出してくれた。
「いつもありがとうございます、掃除屋さん」
彼女はにこりと笑った。俺の正体を知っていたのだ。
「…なぜ、俺が」
「あなたの手、いつも綺麗だから。街を綺麗にしてくれる手ですもの」
その言葉に、胸の奥が微かに痛んだ。彼女の優しさが、俺の頑なな心を少しずつ侵食していく。
俺は、彼女にあの結晶を返すべきか、迷っていた。あれは彼女の記憶だ。しかし、あれを返せば、彼女はなぜそれを忘れていたのかを知りたがるだろう。その先に、何が待っているのか。俺には、それがひどく恐ろしいことのように思えたのだ。
第三章 偽りの平穏と盗まれた真実
リナと関わるうちに、俺は街の奇妙な点に気づき始めた。この街には、強い感情の起伏を持つ者がほとんどいない。誰もが穏やかで、親切だが、深い悲しみや、燃え上がるような怒り、そして、あの結晶が放っていたような熱い喜びを見せることは滅多にないのだ。まるで、街全体が薄い膜に覆われ、感情が平準化されているかのようだった。
俺は、この街の成り立ちについて調べ始めた。図書館の古文書や、年寄りたちの断片的な話を繋ぎ合わせるうち、戦慄すべき仮説にたどり着く。
――この街の「記憶結晶」は、自然現象などではなかった。
かつて、この街は絶え間ない争いと憎しみに満ちていた。それを憂いた初代の街長は、古代の魔術を用いて、巨大な「調律の塔」を建設した。その塔は、人々の精神に干渉し、争いの火種となる「強い感情を伴う記憶」を強制的に抽出し、無害な結晶へと変えるシステムだったのだ。人々は悲しみも怒りも、そして強すぎる喜びさえも忘れることで、偽りの平和を手に入れた。
俺たちが日々掃除している結晶は、ゴミなどではなかった。それは、人々から盗まれた魂の欠片そのものだった。
愕然とする俺の脳裏に、リナの顔が浮かんだ。彼女のあの空虚な表情。彼女が失ったのは、ただの幸福な家族の記憶だけではないはずだ。あれほど強い輝きを持つ記憶には、同等の強い感情が伴っているはずだ。喜びだけではない。おそらくは、深い悲しみや怒りも。
俺は禁書庫に忍び込み、調律の塔の設計図と、過去の「処理記録」を発見した。そして、リナの両親の名前を見つけた時、全身の血が凍りついた。
記録によれば、彼女の両親は、この記憶管理システムに気づき、反抗を試みた「危険分子」として、塔に記憶を根こそぎ奪われ、「処分」されていた。リナが失ったのは、両親との幸せな日々の記憶であると同時に、両親が目の前で連れ去られ、消されていくという、あまりにも過酷な記憶でもあったのだ。あの琥珀色の結晶は、幸福と絶望という、相反する感情が極限で混ざり合った末に生まれた、奇跡のような代物だった。
街は、彼女を守るために、彼女から真実を奪った。悲劇を忘れさせることが、唯一の救済だと信じて。
震える手で記録をめくっていた俺は、自分の名前を見つけて、息を呑んだ。カイ。俺の名前の横にもまた、両親の名前が記されていた。罪状は、リナの両親と同じ、「システムへの反抗」。
そうだ。思い出した。俺にも、温かい家族がいた。父がいて、母がいた。彼らは、奪われた記憶を取り戻そうと、塔に挑んだ。そして、俺の目の前で…。
「やめろ…やめてくれ…!」
忘却の海の底から、引き裂かれるような絶叫が蘇る。炎。悲鳴。絶望の色。俺が無気力に生きてきたのは、性格などではなかった。俺もまた、この街のシステムによって、最も大切な記憶と、生きる意志そのものを奪われていたのだ。
手の中のポーチが、まるで俺の怒りに呼応するかのように、熱く、脈打ち始めた。
第四章 夜明けへの第一歩
俺は、夜が明けるのを待って、リナの花屋を訪れた。その手には、あの琥珀色の記憶結晶を握りしめている。
店に入ると、リナは不思議そうな顔で俺を見つめた。俺は何も言わず、ただ、結晶を彼女の前に差し出した。
「これは…?」
「君の記憶だ。君が失くした、一番大切なものだ」
リナは戸惑いながらも、その結晶にそっと触れた。彼女の瞳が見開かれ、みるみるうちに涙が溢れ出す。幸福な食卓の光景。そして、その後に続く、両親との永遠の別れ。歓喜と絶望の濁流が、彼女の魂を洗い流していく。
「あ…あぁ…お父さん、お母さん…!」
膝から崩れ落ち、嗚咽するリナ。俺は、その小さな肩を、ただ黙って支えることしかできなかった。偽りの平穏の中で生きるか、痛みを伴う真実と共に生きるか。その選択を、彼女自身に委ねなければならなかった。
どれくらいの時間が経っただろうか。やがて顔を上げたリナの瞳には、涙の奥に、今まで見たこともないほど強く、澄んだ光が宿っていた。それは、悲しみを乗り越えた者だけが持つ、覚悟の光だった。
「ありがとう、カイ。思い出させてくれて」
彼女は震える声で言った。
「辛いよ。胸が張り裂けそう。でも…でも、これは、私が私であるための記憶だもの。忘れちゃいけなかった」
その言葉は、俺自身の心にも深く突き刺さった。俺たちは、この街に記憶を盗まれ、空っぽのまま生かされてきた。だが、もう終わりだ。
俺たちは顔を見合わせ、静かに頷いた。言葉はなかったが、やるべきことは分かっていた。
俺とリナは、花屋を出た。夜明けの光が、街の石畳を黄金色に染め始めている。人々が目覚め、また「穏やかな一日」を始める前に、俺たちは行かなければならない。
街の中心に聳え立つ、巨大な「調律の塔」へ。
俺の手には、かつて俺が失った記憶の在処を示す、古びたコンパスが握られていた。父が、最後の抵抗として俺に遺してくれたものだ。そして、リナの手には、両親の愛と悲しみが詰まった琥珀色の結晶が。それはもはや、ただの記憶の欠片ではない。偽りの平和を打ち砕き、人々の魂を解放するための、俺たちの道標だった。
空からは、今日も無数の記憶結晶が、きらきらと舞い落ちてくる。それは、この街で生きる全ての人々が失くした、笑いと、涙と、怒りと、愛の欠片だ。
俺たちは、それらを取り戻す。
この戦いの先に何が待っているのか、俺には分からない。世界は再び、混沌に満ちるのかもしれない。それでも、俺たちは進む。作られた幸福ではなく、痛みさえも抱きしめられる、本物の人生を取り戻すために。
俺たちの夜明けは、今、始まったばかりだ。