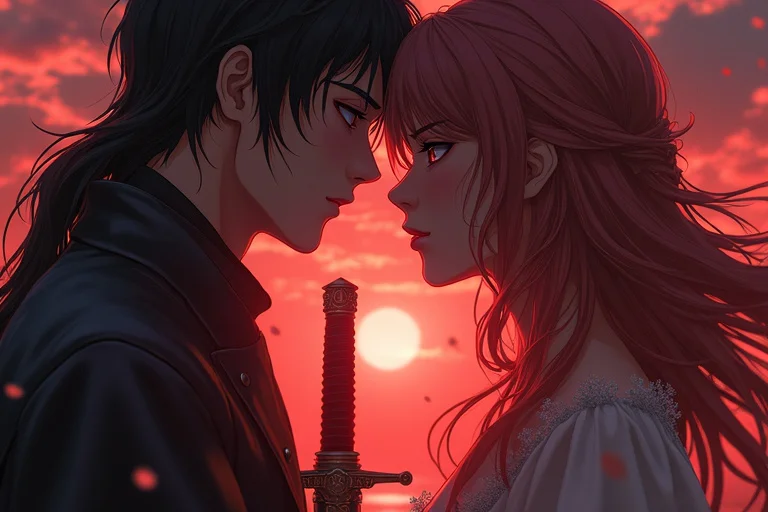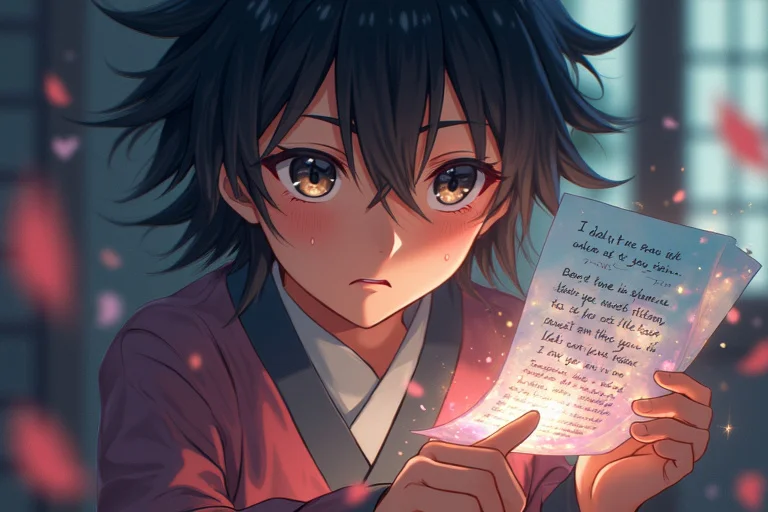第一章 緋色の残像
江戸の夕暮れは、いつも俺の眼を焼く。屋根瓦を濡らす茜色とは違う。人の心から滲み出す、どす黒い欲望の色が、埃っぽい空気と混じり合って街全体を覆うのだ。
俺、相馬弦之助には、生まれついての奇妙な癖があった。人の感情が、その者の周りに漂う「色」として見えるのだ。怒りは血を煮詰めたような緋色に、喜びは陽だまりのような淡い黄色に、そして嫉妬は腐った沼のような淀んだ緑色に見える。この呪われた眼のせいで、俺は誰も信じられなくなった。言葉と心が放つ色は、あまりにも違う。
今はしがない浪人暮らしだが、かつては北の小藩で父と兄を持つ武家の次男だった。しかし、五年前のあの日、全てを失った。家老の黒部道玄が謀反を企て、父と兄は無念の死を遂げた。俺だけが、家臣の手引きで辛くも城を落ち延びた。以来、俺の世界は、黒部への復讐を誓う「緋色」の残像に塗り込められていた。
その黒部が、失脚したはずの藩で再び権勢を握ったという知らせが届いたのは、三月前のことだ。俺は草鞋の紐を締め直し、この煤けた江戸の裏長屋に潜み、復讐の機を窺っている。
ある月夜の晩だった。いつものように黒部の屋敷近くを見張っていた帰り道、橋のたもとで、か細い琵琶の音色が聞こえてきた。音の主は、年の頃十五、六ほどの盲目の少女だった。汚れた小袖を纏い、一心に弦を弾いている。通行人たちは、物乞いかと眉をひそめ、足早に通り過ぎていく。
だが、俺の足は縫い付けられたように動けなかった。彼女から立ち上る色に、息を呑んだからだ。それは、俺がこれまで一度も見たことのない色だった。あらゆる感情が混濁した人の世の色ではない。ただひたすらに澄み切った、夜明け前の湖面のような「水色」。そこには、偽りも、淀みも、一片たりともなかった。
少女がふと顔を上げる。白く濁った瞳は何も映していないはずなのに、俺の存在を正確に捉えているようだった。
「お侍様。何か、とても重たい色を背負っておいでですね」
その声もまた、琵琶の音のように凛と澄んでいた。俺は言葉を失った。この眼のことは誰にも話したことがない。まさか、この少女にまで見えているというのか。
「……人違いだ」
絞り出した声は、自分でも驚くほどにかすれていた。俺は背を向け、逃げるようにその場を立ち去った。しかし、背中に突き刺さるような、あの静謐な水色の感覚は、いつまでも消えなかった。復讐の緋色に染まった俺の世界に、予期せぬ一滴の雫が落ちた瞬間だった。
第二章 水色の旋律
それからというもの、俺は毎夜のように橋のたもとへ足を運んだ。少女は静(しず)と名乗った。彼女との短い会話は、ささくれ立った俺の心を奇妙に慰撫した。静は俺の素性を尋ねず、俺も彼女の過去を問わなかった。ただ、琵琶の音に耳を傾け、彼女から発せられる「水色」のオーラを浴びる時間が、俺にとって唯一の安らぎとなっていた。
「弦之助様の心は、まるで固く凍てついた冬の土のようです。でも、その下には、春を待つ若草の芽が眠っている気がします」
ある日、静がぽつりと言った。俺はぎょっとして彼女を見た。盲目の少女が、なぜ俺の心の内を見通せるのか。
「お前は……一体何者だ」
「私はただの琵琶法師です。目が見えぬ代わりに、音や、人の気配が少しだけ分かるのです。あなたの纏う空気は、とても冷たくて、悲しい音がします」
その言葉に嘘はなかった。彼女の周りの水色は、微動だにしない。俺はこの時初めて、自分の呪われた眼とは違う理で世界を捉える者がいることを知った。
静との交流は、俺の復讐心を鈍らせた。黒部を斬ることだけが生きる意味だったはずなのに、今は静の弾く琵琶の音を明日も聞きたい、と思ってしまう自分がいる。緋色の憎悪と、水色の安らぎ。二つの色が俺の中でせめぎ合い、心をかき乱した。
一方で、黒部道玄の周辺を探る動きも続けていた。だが、調べれば調べるほど、不可解な点が浮かび上がってくる。巷で聞く黒部は、冷酷非情な権力者のはずだ。しかし、俺が遠目に見る黒部の周りには、憎悪や権勢欲を示す「どす黒い赤」や「濁った金色」は微塵もなかった。
彼の周りを常に漂っているのは、深い、深い「藍色」だった。それは、己の行いを悔いるかのような、底なしの悲しみの色。そして、その藍色を包むように、時折、強い意志を示す「黄金色」の光が迸るのが見えた。まるで、何かを、誰かを、命を懸けて守ろうとしているかのような色だった。
仇の色ではない。俺の知る謀反人の色では、断じてなかった。
まさか。俺の眼が狂ったのか? それとも、俺が信じてきた五年間の全てが、幻だったというのか。混乱と疑念が、墨汁のように心を蝕んでいく。決着をつけねばならない。真実が何であれ、この手で確かめるしかない。俺は錆びついた刀の柄を、強く、強く握りしめた。
第三章 藍と黄金の真実
決行は、雨のそぼ降る闇夜だった。俺は手練れの忍びではない。だが、五年間の執念が俺の五感を研ぎ澄ましていた。屋敷の警備の薄い場所を見つけ、息を殺して塀を乗り越える。雨音と風の音が、俺の気配をかき消してくれた。
目指すは奥にある書院。黒部道玄は、そこで一人、夜更けまで書状を認めているという。濡れた草を踏み、音もなく縁側に上がる。障子に映る人影は一つ。間違いない。俺は静かに障子を開け放ち、室内に躍り込んだ。
「黒部道玄、覚悟!」
蝋燭の灯りに照らされた黒部は、俺の姿を認めると、驚きもせず、ただ静かに筆を置いた。五十代半ばだろうか。皺の刻まれた顔には、疲労と、そして諦念のようなものが浮かんでいた。
「……やはり、来たか。相馬の若君」
その落ち着き払った態度に、俺の怒りは頂点に達した。
「貴様のせいで、父上と兄上は……! 今日こそ、その命、貰い受ける!」
俺が刀を振りかぶった、その瞬間。黒部の体から放たれる色を見て、俺は動きを止めた。
それは、やはり「どす黒い赤」ではなかった。深い、深い「藍色」の悲しみが嵐のように吹き荒れ、その中心で、全てを焼き尽くすほどの強烈な「黄金色」の光が輝いていた。それは、忠誠の色。命を懸けた、約束の色だった。
「待て、若君。斬るのは、話を聞いてからにしていただきたい」
黒部は静かに語り始めた。
「五年前のあの日、御家を滅ぼしたのは、この私ではない。藩主の座を簒奪せんとした、叔父君の一派の仕業だ」
衝撃的な言葉だった。
「何を……戯言を」
「私は、先代藩主である君の父上から、密命を受けていた。万一の時は、家名よりも血筋を、相馬の血だけは絶やすな、と。そして、まだ幼い君だけは、何としても生かせ、と」
黒部の話は、俺の知らない陰謀の全貌を明らかにした。敵は、藩内に深く根を張っていた。黒部は、弦之助を城から逃がすため、そして敵の目を欺くために、自ら謀反人の汚名を被ったのだ。藩を追われたのも、全ては敵の油断を誘い、力を蓄え、そして今、復讐の機を窺うための芝居だった。彼が権力の座に戻ったのも、一族の無念を晴らすための最終段階に入ったからだった。
「父上が……そんなことを……」
「若君、君が生きていることだけが、我らに残された最後の希望だった。この五年間、遠くからずっとお主を見守ってきた。辛い思いをさせたことは、万死に値する」
黒部は深く頭を下げた。彼の周りには、後悔の「藍色」と、亡き主君への忠誠の「黄金色」が、悲しいほどに美しく渦巻いていた。俺の信じてきた五年間の全てが、音を立てて崩れ落ちていく。
呆然と立ち尽くす俺に、黒部は最後の、そして最大の真実を告げた。
「そして……もう一つ、詫びねばならぬことがある。あの騒動の折、混乱の中で、私の娘が……敵方の凶刃に倒れ、視力を失った」
俺の心臓が、氷の塊になったように冷たくなる。
「その娘の名は……」
「静、と申す」
頭を殴られたような衝撃。静。あの水色の少女。彼女の琵琶の音、澄んだ声、そして俺の心を見透かすような言葉が、脳裏に蘇る。あの純粋な水色は、全てを失い、それでもなお世界を信じようとする、彼女の魂の色だったのだ。
俺は、仇の娘に救われていた。そして、その仇は、俺の最大の恩人だった。
第四章 灰色の夜明け、若草の兆し
俺は、刀を取り落とした。カラン、と乾いた音が、静まり返った書院に響く。復讐という緋色の炎が消え去った俺の世界は、何の色彩も持たない、冷たい「灰色」に変わっていた。目的を失った魂は、抜け殻も同然だった。
「……どうすれば、よかったのだ」
絞り出した声は、雨音に溶けて消えそうだった。俺はいったい、何を憎み、何のために生きてきたのか。
黒部は、静かに立ち上がると、一枚の書状を俺に差し出した。
「これは、敵方の悪事の全てを記した証拠だ。近々、我らは決起する。若君、君の力を貸してはくれまいか。父君の無念を晴らすために」
だが、俺は首を横に振った。もはや、俺に戦う意味はなかった。憎しみは消え、残ったのは空虚さと、静に対するどうしようもない罪悪感だけだった。俺は何も答えず、よろめくように屋敷を後にした。夜明け前の空は、俺の心と同じ、重たい鉛色をしていた。
数日後。俺は、いつもの橋のたもとを訪れた。静は、変わらずそこに座り、琵琶を爪弾いていた。彼女の周りには、あの美しい「水色」が穏やかに広がっている。
俺は、彼女の前に無言で座った。
「弦之助様」
静が顔を上げる。
「もう、重たい色は消えたのですね。でも、今はとても寂しい色をしています。……まるで、生まれたての赤子のように、何色にも染まっていない」
その言葉に、俺の目から涙が溢れた。この少女は、俺が何をしたのかも知らず、ただ俺の魂のありようだけを感じ取っている。
俺は、自分の眼が見せる色の世界のことも、彼女の父とのことも、何も話さなかった。ただ、嗚咽を堪え、彼女の弾く琵琶の音に、魂ごと耳を傾けた。
一曲、また一曲と、旋律が夜の静寂に溶けていく。どれくらいの時が経っただろうか。ふと、俺は自分の内側から、ある変化が起きていることに気づいた。
冷たい灰色だった俺の心の中から、ほんのりと、小さな光が灯り始めていた。それは、まだ弱々しいが、確かな温かみを持つ光。
春を待つ土の下で、固い殻を破って芽吹こうとする、生命の色。
「若草色」だった。
復讐は終わった。だが、俺の人生が終わったわけではない。この呪われた眼で、俺はこれから、何を見ていけばいいのだろう。
答えはまだ見つからない。だが、今はただ、目の前の水色の旋律と、胸に灯ったばかりの若草の兆しだけを信じようと思った。
俺は、静かに立ち上がった。
「また、来る」
短く告げると、静はにっこりと微笑んだ。その笑顔は、どんな色彩よりも鮮やかに、俺の灰色の世界を照らした。
色彩に満ちたこの世界で、俺は初めて、本当に美しいものを見た気がした。